金融危機以降、苦境に立ってきたスウェーデン自動車業界の展開については、ボルボ乗用車部門(Volvo Cars)とサーブ(SAAB)の売却交渉を中心に何度か書いてきましたが、最近少し怠けていました。
――――――――――
サーブのほうは、今年に入ってから事実上の経営破綻に陥り、会社更生法の適用を受けながら新生サーブへと生まれ変わる努力を続けてきた。同時に、サーブを傘下に収めてきたGMがサーブ売却の意向を示してきたため、GMに代わる新しい所有者を見つけるための作業が続けられてきた。
買収候補者の中から選ばれたのは、スウェーデンのスポーツカー・メーカー、ケーニッグセグだったが、問題は完全買収に必要な資金が足りない、ということだった。スウェーデン政府にお伺いを立ててみたものの「支援はしない」との冷たい返事。
穴埋めの一つの方法は、ヨーロッパ投資銀行(EIB)からの融資を受けることだった。ただし、融資審査には厳しい条件がある上、スウェーデン政府からの信用保証がなければお金は貸さない、と言ってきた。度重なるやり取りの末に、やっとのことでこの条件をすべて満たすことに成功し、EIBから融資が受けられることになった!
しかし、それでも30億クローナ(4億3000万ドル)が足りない! この穴埋めをすることになったのは北京汽車(BAIC)だった。この中国企業はケーニッグセグに出資する見返りに、サーブの技術の一部を手にする目論見だったようだ。こうしてケーニッグセグは買収に必要な資金がやっと揃えたかと思いきや・・・
2009年11月25日 「ケーニッグゼグ、サーブ買収交渉打ち切り」との報道!
[デトロイト 24日 ロイター] 米自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)[GM.UL] は24日、傘下サーブの売却を中止すると発表した。売却先のスウェーデンの高級自動車メーカー、ケーニッグゼグが買収を取りやめた。
サーブは来月末までをメドに、中国の北京汽車工業の出資を得てケーニッグゼグに売却される予定だった。
ケーニッグゼグは声明で、売却手続きから撤退したと表明。「会社に新たな命を吹き込む戦略上、時間的要因が常に重要だった」と述べた。(以下省略)
ロイターの記事
せっかく狭い難関を何度も乗り越えて、やっと新生サーブが誕生するかと思った矢先だった。これで売却プロセスは一からやり直しだ。しかし、GM側としては年内に売却を済ませたい、と言ってきたため、残り時間は非常に短い。売却が無理なら、サーブの廃業・解体ということになる。しかし一方では、サーブ買収に名乗りを上げる企業がいくつかあるという報道もあり、サーブの社長は「希望はまだまだある」と相変わらずの楽観的なコメントを述べていた(日刊紙のある解説者はそれ以前から「彼はどんなひどい目にあってもへこたれない人だ」と賞賛していた)。
しかし、先週末に一つのニュースが入ってきた。北京汽車(BAIC)がサーブの技術と生産設備の一部を購入する契約を結んだ、というのだ。サーブという企業の事実上の解体がついに始まったか!?と思わせる見出しだったが、よく聞いてみるとそうではなかった。
北京汽車(BAIC)が購入することになったのは、9-3モデル(旧型)と9-5モデル(旧型)の生産技術と生産設備だ。設備については、解体して中国へ運び、設置するのだそうだ。両モデルは開発から既に10年以上が経っており、サーブや欧米の自動車メーカーにとっては既に一世代遅れの技術となっている。それを北京汽車が買い取り、自社の新型モデルに融合するのだという。(自動車業界では、一つのモデルの“寿命”は6年ほどだとか)
だから、スウェーデン各紙は「Win-Win situation」だと報じていた。つまり、北京汽車はのどから手が出るほど欲しがっていた技術が、たとえ一世代遅れのものであろうと手に入る。他方で、サーブは今となっては重要ではない古い技術を売ることで資金が手に入る、ということなのだ。しかも、技術移転を行ってその技術を北京汽車が自社の新型モデルに融合していくためには、大掛かりなサポートがサーブ側で必要になり、おそらく今後数年はサーブの本拠地における技術部門の活動も盛んになるだろう、とある新聞は予測している。
ロイターの日本語記事
ちなみに、9-3モデルや9-5モデルについては、サーブはリニューアルした新型バージョンを開発しており、それが現在生産されている。そして、こちらの技術は今後もサーブ内に留めておくのだという。
――――――――――
歴史は繰り返すという。戦後、スウェーデンはヨーロッパ最大の造船国だと呼ばれた時代がかつてあった。しかし、日本や韓国などの新興国に追い上げられ、競争力を失っていき、70年代から80年代に造船工場が相次いで閉鎖されていった。ヨーテボリやマルメなどにあった造船設備や大型クレーンの一部は、その頃に解体され韓国に輸出されて、再び使われることになった。今では造船業といえば、スウェーデン海軍の軍用艦艇を細々と作っている程度だ。

それと同じことが今、自動車産業で起きているのだろうか? 自動車産業は造船業と違って、スウェーデンや欧米は新技術の開発を続けていくことで新興国の追い上げをかわしていくことができるのだろうか・・・?
――――――――――
話をサーブに戻そう。サーブ買収に関心を示した企業の中で、現在唯一残っている企業は、オランダのスポーツカー・メーカーのSpyker(スパイカー)だ。そう、またもやスポーツカー・メーカーなのだ。この企業も買収を断念したケーニッグセグと同様、高級車を年間数十台作っている程度の企業だ。サーブの将来は、今この企業にかかっているといっても良いだろう。
この書き込みをしている15日深夜、主要日刊紙のサイトを見ていると「スパイカーによる買収交渉がうまく行かなければ、サーブは廃業するだろう」という見出しが掲げられていた。

日本のサイトによると、サーブが廃業したあとのシナリオもすでに描かれている、という情報もある。
日経新聞2009年12月12日「上海汽車、サーブ買収か 中国紙」
【上海=下原口徹】中国紙、経済観察報(電子版)は11日、中国自動車最大手の上海汽車集団が米ゼネラル・モーターズ(GM)のスウェーデン子会社のサーブを破産後に低価格で買収することで、GMと水面下で合意していると報じた。(以下省略)
日経の記事
ただし、これはあくまで中国の情報筋によるところであって、スウェーデンでは報じられていない。しかし、そのような準備が着々と進んでいてもおかしくはないだろう。
サーブのほうは、今年に入ってから事実上の経営破綻に陥り、会社更生法の適用を受けながら新生サーブへと生まれ変わる努力を続けてきた。同時に、サーブを傘下に収めてきたGMがサーブ売却の意向を示してきたため、GMに代わる新しい所有者を見つけるための作業が続けられてきた。
買収候補者の中から選ばれたのは、スウェーデンのスポーツカー・メーカー、ケーニッグセグだったが、問題は完全買収に必要な資金が足りない、ということだった。スウェーデン政府にお伺いを立ててみたものの「支援はしない」との冷たい返事。
穴埋めの一つの方法は、ヨーロッパ投資銀行(EIB)からの融資を受けることだった。ただし、融資審査には厳しい条件がある上、スウェーデン政府からの信用保証がなければお金は貸さない、と言ってきた。度重なるやり取りの末に、やっとのことでこの条件をすべて満たすことに成功し、EIBから融資が受けられることになった!
しかし、それでも30億クローナ(4億3000万ドル)が足りない! この穴埋めをすることになったのは北京汽車(BAIC)だった。この中国企業はケーニッグセグに出資する見返りに、サーブの技術の一部を手にする目論見だったようだ。こうしてケーニッグセグは買収に必要な資金がやっと揃えたかと思いきや・・・
2009年11月25日 「ケーニッグゼグ、サーブ買収交渉打ち切り」との報道!
[デトロイト 24日 ロイター] 米自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)[GM.UL] は24日、傘下サーブの売却を中止すると発表した。売却先のスウェーデンの高級自動車メーカー、ケーニッグゼグが買収を取りやめた。
サーブは来月末までをメドに、中国の北京汽車工業の出資を得てケーニッグゼグに売却される予定だった。
ケーニッグゼグは声明で、売却手続きから撤退したと表明。「会社に新たな命を吹き込む戦略上、時間的要因が常に重要だった」と述べた。(以下省略)
ロイターの記事
せっかく狭い難関を何度も乗り越えて、やっと新生サーブが誕生するかと思った矢先だった。これで売却プロセスは一からやり直しだ。しかし、GM側としては年内に売却を済ませたい、と言ってきたため、残り時間は非常に短い。売却が無理なら、サーブの廃業・解体ということになる。しかし一方では、サーブ買収に名乗りを上げる企業がいくつかあるという報道もあり、サーブの社長は「希望はまだまだある」と相変わらずの楽観的なコメントを述べていた(日刊紙のある解説者はそれ以前から「彼はどんなひどい目にあってもへこたれない人だ」と賞賛していた)。
しかし、先週末に一つのニュースが入ってきた。北京汽車(BAIC)がサーブの技術と生産設備の一部を購入する契約を結んだ、というのだ。サーブという企業の事実上の解体がついに始まったか!?と思わせる見出しだったが、よく聞いてみるとそうではなかった。
北京汽車(BAIC)が購入することになったのは、9-3モデル(旧型)と9-5モデル(旧型)の生産技術と生産設備だ。設備については、解体して中国へ運び、設置するのだそうだ。両モデルは開発から既に10年以上が経っており、サーブや欧米の自動車メーカーにとっては既に一世代遅れの技術となっている。それを北京汽車が買い取り、自社の新型モデルに融合するのだという。(自動車業界では、一つのモデルの“寿命”は6年ほどだとか)
だから、スウェーデン各紙は「Win-Win situation」だと報じていた。つまり、北京汽車はのどから手が出るほど欲しがっていた技術が、たとえ一世代遅れのものであろうと手に入る。他方で、サーブは今となっては重要ではない古い技術を売ることで資金が手に入る、ということなのだ。しかも、技術移転を行ってその技術を北京汽車が自社の新型モデルに融合していくためには、大掛かりなサポートがサーブ側で必要になり、おそらく今後数年はサーブの本拠地における技術部門の活動も盛んになるだろう、とある新聞は予測している。
ロイターの日本語記事
ちなみに、9-3モデルや9-5モデルについては、サーブはリニューアルした新型バージョンを開発しており、それが現在生産されている。そして、こちらの技術は今後もサーブ内に留めておくのだという。
歴史は繰り返すという。戦後、スウェーデンはヨーロッパ最大の造船国だと呼ばれた時代がかつてあった。しかし、日本や韓国などの新興国に追い上げられ、競争力を失っていき、70年代から80年代に造船工場が相次いで閉鎖されていった。ヨーテボリやマルメなどにあった造船設備や大型クレーンの一部は、その頃に解体され韓国に輸出されて、再び使われることになった。今では造船業といえば、スウェーデン海軍の軍用艦艇を細々と作っている程度だ。

それと同じことが今、自動車産業で起きているのだろうか? 自動車産業は造船業と違って、スウェーデンや欧米は新技術の開発を続けていくことで新興国の追い上げをかわしていくことができるのだろうか・・・?
話をサーブに戻そう。サーブ買収に関心を示した企業の中で、現在唯一残っている企業は、オランダのスポーツカー・メーカーのSpyker(スパイカー)だ。そう、またもやスポーツカー・メーカーなのだ。この企業も買収を断念したケーニッグセグと同様、高級車を年間数十台作っている程度の企業だ。サーブの将来は、今この企業にかかっているといっても良いだろう。
この書き込みをしている15日深夜、主要日刊紙のサイトを見ていると「スパイカーによる買収交渉がうまく行かなければ、サーブは廃業するだろう」という見出しが掲げられていた。

日本のサイトによると、サーブが廃業したあとのシナリオもすでに描かれている、という情報もある。
日経新聞2009年12月12日「上海汽車、サーブ買収か 中国紙」
【上海=下原口徹】中国紙、経済観察報(電子版)は11日、中国自動車最大手の上海汽車集団が米ゼネラル・モーターズ(GM)のスウェーデン子会社のサーブを破産後に低価格で買収することで、GMと水面下で合意していると報じた。(以下省略)
日経の記事
ただし、これはあくまで中国の情報筋によるところであって、スウェーデンでは報じられていない。しかし、そのような準備が着々と進んでいてもおかしくはないだろう。










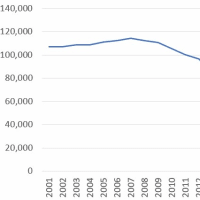
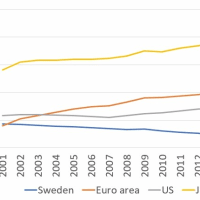
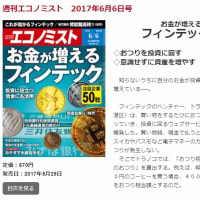
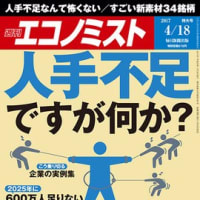






解体されてしまいました。
しかし昔大造船所があったというランドマーク的価値があると思いますが。いつもデンマークから船でマルメ入りするとCockumsの名が入ったあのクレーンを見ると遠くからも見えるし懐かしく思ったものですが。カーニヴァルクルーズのHoliday('85)Celebration('87),ス海軍の潜水艦Naeckenが船台に載っているのが見えたものです。
ランドマーク的価値といえば、ヨーテボリが造船業が栄えた時代の名残としてクレーンを残していますよね。
保存されていました。ですから函館もそのようにすべきだと思ったのでした。此処に載っている写真は解体をして韓国に運ぶ写真だと思ったのですが。ヨータヴェルケンは有名な造船所でした。今では仕事はしていないのですか、旅行者の写真で浮きドックに文字が見られたのでまだやっているのかと思っていました。クレーンが残されているのは知りませんでした。去年行った時は気が付きませんでした。
英語のブログで書きました:
http://martinjapan.blogspot.com/2007/08/recycling-kockumskranen.html
H.Usuiさん、私の間違いでした。Martinさんのリンクを御覧ください。