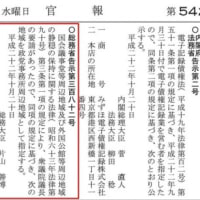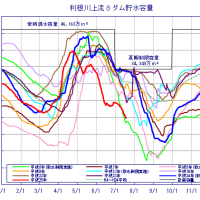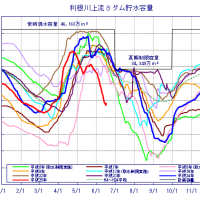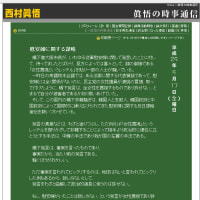NHK
とは思わない。1.7%は確率として容認できるレベルではない。
売り上げが年300億円だそうだから、単価700円として、約4300万皿。1.7%の確率なら、約70万皿にO157が含まれている可能性があることになる。仮にその1/10としても、7万皿。それでも一皿を数人でつつくから、年間のべ20万客くらいは、O157と接した可能性があることになる。1.7%基準で考えれば、年間200万~300万客。
#温度管理で繁殖させないとか、客のお腹の調子がよければラッキーといったこともあろう。
実際の事件としては、2009年ペッパーランチで11人。2011年焼肉酒家えびすで24人(うち2名死亡)。2012年炭火焼き肉ホルモン美貴亭で16人。ただしこの中で生レバーはえびすだけのようだ。一般に野菜など生の料理に混入する例が多いようだが、感染経路は不明。基本的にO157は牛の腸にいるわけで、どこかで生肉等から混入ないし感染したと推定するしかなかろう。
300億円の売り上げがあって、実際の被害はこんなものであろうか。だとしたら、実際の感染確率は 1.7%よりは低そうである。食中毒事件の報告通り、仮に年間20人としたら、感染確率は1.7%の10万分の1のオーダーである。こんなものは、事実上ゼロではないのか。違うのか。それで、1.7%は正しいのか。だとしたら、なぜこれほど実際の食中毒が少ないのか。
まあよく分からん話である。
ざっくり書く。目の前に出された皿の生レバーを食うと、100万分の1の確率で食中毒になります、といわれたら、どう考えるかである。それはリスクなのか? おそらく、実際は空気である。
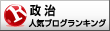
去年、全国16か所の食肉衛生検査所で173頭の牛のレバーを調べたところ、3頭のレバーの内部からO157などが検出(中略)これまで食中毒を引き起こす細菌「カンピロバクター」は確認されていましたが、僅かな菌でも重症化するおそれがあるO157が検出されたのは初めてでした。(中略)レバー内部の殺菌についても有効な方法はなかった(中略)全国食肉事業協同組合連合会は、「何を食べるかは自己責任で、法律で規制すべきではない。(中略)多くの消費者から、規制はおかしいという声が上がってきている。(中略)提供が禁止されると年間で300億円以上の売り上げが失われる(中略)研究会では、高い濃度の塩素系の消毒薬をレバーに注入し、いったん凍結したうえで解凍する方法で、検出される病原性大腸菌O157を大幅に減らすことができた(中略)消毒や凍結などによる味への影響は少ない(中略)「甘みもあり、処理されていたことによる差はまったく感じない」たしか、放送では「リスクゼロはない」という表現をしていた。ならば、原発と生レバーを同じ基準、つまり確率論をベースに考察すべきだ。3/173なら、確率は1.7%である。内部にO157がある確率が1.7%なら、そう表示すればよい。2011年の調査でこうでした、と。それで客が食うかどうか、判断させればよい...
とは思わない。1.7%は確率として容認できるレベルではない。
売り上げが年300億円だそうだから、単価700円として、約4300万皿。1.7%の確率なら、約70万皿にO157が含まれている可能性があることになる。仮にその1/10としても、7万皿。それでも一皿を数人でつつくから、年間のべ20万客くらいは、O157と接した可能性があることになる。1.7%基準で考えれば、年間200万~300万客。
#温度管理で繁殖させないとか、客のお腹の調子がよければラッキーといったこともあろう。
実際の事件としては、2009年ペッパーランチで11人。2011年焼肉酒家えびすで24人(うち2名死亡)。2012年炭火焼き肉ホルモン美貴亭で16人。ただしこの中で生レバーはえびすだけのようだ。一般に野菜など生の料理に混入する例が多いようだが、感染経路は不明。基本的にO157は牛の腸にいるわけで、どこかで生肉等から混入ないし感染したと推定するしかなかろう。
300億円の売り上げがあって、実際の被害はこんなものであろうか。だとしたら、実際の感染確率は 1.7%よりは低そうである。食中毒事件の報告通り、仮に年間20人としたら、感染確率は1.7%の10万分の1のオーダーである。こんなものは、事実上ゼロではないのか。違うのか。それで、1.7%は正しいのか。だとしたら、なぜこれほど実際の食中毒が少ないのか。
まあよく分からん話である。
ざっくり書く。目の前に出された皿の生レバーを食うと、100万分の1の確率で食中毒になります、といわれたら、どう考えるかである。それはリスクなのか? おそらく、実際は空気である。