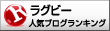今でこそ南米音楽のリズムとエッセンスでスウィングする「サウス・アメリカン・ジャズ」に夢中になっている私。「ラテンジャズ」の枠で一括りにされている感のあるジャズではあるが、1940年代頃にアメリカで生まれたアフロ・キューバン・ジャズとはかなり毛色が違っている。しかし、そんなことが言えるのも今だからこそ。ラテンジャズの世界は実に奥が深いということを知ることができたのも、ほぼリアルタイムで追いかけ続けることになるポンチョ・サンチェスの音楽にFENのジャズ番組で出逢ったからに他ならない。
今はAFN(American Forces Network)と名を変えているFEN(Far East Network)は、アメリカ合衆国の成り立ちを反映するかのような多様な音楽を流し、日本の音楽ファンにも貴重な情報を提供してくれた放送局だった。アメリカンロックやカントリー&ウェスタンが流れる傍らで、ヒスパニック系の人々を対象とした『VIVA』という番組があった。もちろんスウィングジャズやイージーリスニングを流している時間帯もあったし、ソウルやディスコで盛り上がる時間帯ももちろんあった。
とくにスペイン語と英語のちゃんぽんでプログラムが組まれていた『VIVA』はいわばラテン音楽てんこ盛り、いやごった煮番組の面白さがあった。プエルトリコ系のサルサからコロンビアのクンビア、メキシコのマリアッチにドミニカのメレンゲとバラエティに富んでいる。「ヒスパニック」と一括りにされている人達でさえ、多種多様なバックグラウンドがあり、そんな人達が合衆国で生活している。時間帯ははっきりしなかったが、ラテン音楽にもいろいろあるんだなぁと感心しながら耳を傾けていた記憶がある。

しかし、FENの中で一番熱心に耳を傾け、そして深く印象に残っている番組は、夜の9時半から30分間ジャズを流している『ジャズ・ビート』。ローラ・リーという名前の女性がDJを務めていた、その名もズバリ!ジャズを聴かせてくれる番組だった。トークはどちらかというと倫理的なもので音楽の話は殆どなかったが、コンテンポラリージャズを含むセレクションが素晴らしくてカセットテープに録音して楽しんだりしていた。
中でも強く心を惹かれたのがマンボやボレーロ(これは絶品!)などのラテンリズムに乗ったポンチョ・サンチェスの演奏するジャズだった。当時(1980年代前半)のアメリカで話題になっていたのかどうかは不明だが、ポンチョはおそらくDJ女史のお気に入りでもあったのだと思う。イヴァン・リンスやジャヴァンといったブラジルMPBのファンにはつとにお馴染みのトランペット奏者、マルシオ・モントロヨスの音楽とともに何度もオンエアされていたから。
ポンチョ・サンチェスの音楽をじっくり聴きたいという思いは募る一方となり、そんなときに池袋のレコードショップ(たぶんHMV)で見つけたのが『ビエン・サブローソ』(日本語訳:「とっても美味しい!」)だった。ポンチョ・サンチェスがコンコード・ピカンテ・レーベルからリリースした2作目(1984年発売)にあたり、グラミー賞のラテンジャズ部門にもノミネートされた作品(であったことは後で知る)。レコードに針を下ろした瞬間、ホーンアンサンブル(トランペット、トロンボーン、サックスの3管)による哀愁感の漂うサウンドに意表を突かれるとともに強く引きつけられた。
ポンチョ・サンチェスは名前からラテン系であることは察しがついていたが、LA近郊で生まれたメキシコ系アメリカ人だとは知らなかった。道理で(緊迫感のあるNYではなく)カリフォルニアの青い空を感じさせるようなサウンドが飛び出してきたわけだ。FENで流れていたのはこのLPに収められた曲であり、そのレコードが日本にも入ってきていたことに感謝したい気持ちになった。このレコードには何度も何度も針を下ろし、そして、そのときからポンチョ・サンチェスはずっとアイドルであり続けて現在に至っている。

2枚目に手に入れたポンチョのアルバムは実質的なデビュー作に当たる『ソナンド』。この作品はポンチョが偉大な師として仰いだカル・ジェイダーの突然の死を乗り越えて作り上げた感動作でもある。「チュニジアの夜」に始まり、ダンソンの名曲「ソナンド」や「アルメンドラ」からボサノバタッチで演奏されるミシェル・ルグランの「夏の想い出」まで。ただし、編成はコンガ、ボンゴ、ティンバレスの3人の打楽器奏者、ピアノ、ベースにトランペット、バルブ・トロンボーン、サックス2本という9人編成でドラムを含まないアフロ・キューバン・スタイル。「本格派」の枠組みの中にウェストコースト風味が乗っかった(アフロ・キューバン・ジャズとは少し違った)ユニークなサウンドがポンチョ・サンチェスの魅力だと言うことを知る。(その後、ディスカバリーから出た本当のデビュー作も手に入れた。)
ヴァイブラフォン奏者で1950年代からずっと西海岸でラテンジャズを演奏してきたカル・ジェイダー。ポンチョ・サンチェスのプロミュージシャン(コンガ奏者)としてのキャリアは、1975年にカル・ジェイダー・バンドのコンガの椅子に空きができたことに始まる。一説によれば、ステージ上でコンガ奏者が突然いなくなり、途方にくれていたカル・ジェイダーのもとに志願して現れたポンチョが「救世主」になったのだという。この話はちょっとできすぎのような気もするが、アメリカらしいサクセスストーリーといえる。
ただ、ポンチョはカル・ジェイダーのバックで演奏する傍ら、ラテンジャズから徐々に離れていく師とは裏腹に、正当派のアフロ・キューバン・ジャズを追求する構想を練っていたように思われる。1982年のカル・ジェイダーの突然の死(公演先のフィリピンで客死)でその構想の実現が早まったような気がしてならない。まずはNYで活躍する重鎮たちに認められることがポンチョの目標だったに違いない。2作目の『ビエン・サブローソ』ではサックスが1本になり、8人編成の盤石のポンチョバンドが完成した。

ポンチョ・サンチェスの3枚目は1985年にリリースされた『エル・コンジェーロ』(コンガ奏者)。トランペットがスティーブ・ハフステッター(穐吉敏子=ルー・タバキン・ビッグバンドのメンバーで知られる)から名手サル・クラッチオロ、トロンボーンがマーク・レヴァイン(ラテンジャズのピアニストでもある)からアート・ヴェラスコに代わり、バンドが一気に強化された。もし、このメンバーで『ビエン・サブローソ』が録音されていたら間違いなくグラミー賞(ラテンジャズ部門)に輝いていただろう。私感ながらサウンドの魅力は前作に譲るが、ホーンセクションの実力は明らかにこちらが上。ちょっと残念な気もするが仕方ない。
ポンチョ・サンチェスは、その後音楽監督に秀逸なピアニストでもあるダビッド・トーレスを迎え入れてさらにバンドの強化を図る。念願のティト・プエンテやモンゴ・サンタマリアとの共演も果たし、ティト・プエンテ亡き後はラテンジャズの王位を継承。さらに近年はR&Bやソウルのスーパースター達と共演して「グレイト・アメリカン・ミュージック・ヒーロー」の地位を確実なものにしている。
しかし、正直に告白すると、私自身がもっとも愛するポンチョ・サンチェスはチャーリー・オトウェルがピアノを弾いていた初期のシンプルな演奏スタイルの時代。アルバムで言えば、ここで紹介した『ソナンド』から『エル・コンジェーロ』までのあたりになる。NYの本格派も一目置く超正当派のスタイルでありながら、ウェストコーストの空気感に充ちた切々と流れる哀愁感漂うサウンドに惹かれることがその理由だと思う。だからこそローラ・リー女史にも愛されただろうし、新しい音楽を求めていた音楽ファンをレコード店に走らせたのだと思う。