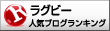「セント・ギガ」といっても、ピンと来る人は殆どいないだろう。世界初の衛星放送によるデジタルラジオ放送局で、1991年3月の本放送開始から2003年に事実上消滅してしまうまで、空から地上に音を送り続けていた。当時WOWOW(BS5ch)と契約していた人は、副音声で音が流されていることに気付いていたかも知れないが、放送当時から陰のような存在の放送局だったと言っていいと思う。
では、そうして痕跡すらも残っていないような放送局のことを話題にしようと思い立ったのか。実はこのセントギガこそ、様々な未知の音楽との出逢いを与えてくれた、忘れ得ぬ想い出がいっぱい詰まった放送局だったから。自分自身の音楽人生を語る上で外すことのできないキーワードのひとつが「セント・ギガ」なのだ。
♪WOWOWのおまけだった「セント・ギガ」
今を遡ること30年前、結婚を機に実家からアパートに移り住みBS放送が受信できるTVを購入した。当時のNHKのBSは3ch(3系統)あり、ニュース、スポーツ中心、映画や音楽などのエンターテイメントにコンテンツが満載で、世界の最新情報を居ながらにして楽しめる番組編成。WOWOWも既に放送を行っていたが、有料放送ということでスクランブルがかかっており、画像は見えてもないも同然だった。
画面をわざわざギザギザにして見せることにしたのは、何を放送しているかをおぼろげながらわかるようにして契約者を増やすための策略だったときく。当時はイタリアサッカーのセリエAが重要コンテンツのひとつになっていて、人影が動く画面を見る都度に「スクランブル何とかならんかなぁ」と思ったものだ。結局は、放送局の策略にまんまと填まり、契約に至ってしまう。ただ、サッカーや映画を観ている分にはセントギガの存在に気付くこともないはず。毎月送られてくる番組表の片隅にあった「セントギガ」のことは少し気になっていたのだが。
「セント・ギガ」も有料放送なのでスクランブルがかかっている。しかし、時々ノンスクランブルの時間帯があり、試しに聴いてみるとジャズやボサノヴァがよくかかっていた。しかも、音質はCD並と言う謳い文句のとおりでFMラジオよりもいい。それでこちらも契約してみるかということになってしまった。
♪さまざまな出逢いを提供してくれたセントギガ
いざスクランブルが外れてみると、セントギガは「音の潮流」と称して一日中「波の音」を流しているような不思議な放送局だった。ニュースどころかトーク番組もなく、ある時間帯にまとまって音楽を流すというシステム。既往のプログラムから曲名まで秒刻みでタイムテーブル化されているラジオ局とはまるで違うコンセプトに面食らった。これでは契約者数が伸びないのは仕方ないなぁと思いつつも、音を流しっぱなしにしておくのがけっこう心地よかったりしたりする。当時はFMラジオでもDJが喋っている時間の方が長いような状態で、肝心の音は何処に?という感じだったから新鮮に聴くことができたのかも知れない。
でも、放送する側もあまりにも捉え所のない番組構成は不味いと悟ったのか、音楽に関しては少しずつ普通のラジオ番組のようなスタイルに変えていったように思う。たとえば、毎週日曜日の10時からは『オール・ザット・ジャズ』と題された90分間のジャズ番組がレギュラー化された。モダンジャズを中心としながらフュージョンも含むメインストリームジャズを独自の構成で紹介する番組で、先に4~5曲流してからまとめて演奏者と曲名のアナウンスがある。ブラインドフォールドテストみたいな形なので、リスナーは予備知識(偏見)なしに曲を聴くことができる。「喰わず嫌いはいけませんよ。」と諭されているような感じで新たな発見がいろいろとあった。とにかく、セレクションが面白く、ミンガスの「直立猿人」を平気でかけるのもこの番組くらいのも。
ちなみに、「オール・ザット・ジャズ」は1996年~1998年頃に放送された番組を殆どカセットテープにエアチェックしてある。一度は壊れて廃棄に至ったカセットデッキだったが、120本以上溜まったテープを処分するのがもったいなく思われ、結局新しいデッキを買い直した。オンキヨーのトレーが前に出てくるタイプのもので、CDプレーヤーの発想が活かされている。テープに収録されている1000曲以上の宝物を棄てなくて本当によかったと思った。それ以外の番組でも、「真のオルガンの女王」ローダ・スコットを知ったことが大きな収穫のひとつ。

♪Mr.フィンガーズとの幸運な出逢い
セントギガの音楽番組で本当に困ったのは、「オール・ザット・ジャズ」のような例外を除き、曲目のアナウンスがまったくないことだった。トークを入れることで音の潮流に棹をさしてしまうことを畏れたわけでもないが、どんなアーティストが演奏しているのかくらいは知りたかった。もちろん曲名を知ることは不可能ではなかった。放送された時間をメモって電話で直接問い合わせると教えてもらえる。でも、時間をチェックするのも電話をするのも面倒な時がある。今ほどネットが手軽に使える時代ではなかったとは言え、J-WAVEのように、曲目リストをホームページにアップしてくれていたら問題ないのにと何度思ったことか。
そのことを一番感じたのは、セントギガがもっとも力を入れていたと思われるハウス/ヒップホップ系の音楽だった。リズムは打込みでシンセを多用したコンピューターミュージック(当時はハウス音楽という言葉すら知らなかった)なのだが、FMラジオでは耳にすることのなかった未知の音楽。70年代のプログレやフュージョンで頻繁に耳にした電化サウンドとは一線を画した洗練されたサウンドに心惹かれることも多く、どんなアーティスト達が演奏しているのか手がかりがまったく掴めないことがもどかしかったのだ。
そんな紆余曲折を経て知ることができたひとりのアーティストがMr.フィンガーズことラリー・ハードだった。電話での問い合わせで教えてもらった「ミスター・フィンガーズ」というアーティスト名を頼りにCDショップへ。ちょうどタイミング良く、セントギガで聴いた曲も収録された『イントロダクション』が見つかった。デジタル技術で産み出されたサウンドにラリー・ハード自身のボーカルがミックスされたソフトな感覚のソウルフルなサウンドが心地よい。とくにリズムが打ち込みとは思えないグルーブ感を感じさせることが驚きだったが、ラリー・ハード自身が元々ドラマーだったことを知り納得だった。

♪『イントロダクション』から『バック・トゥ・ラブ』へ
Mr.フィンガーズ名義の『イントロダクション』は1992年の作品。ラリー・ハードが付け加えた女声コーラスを除き楽器演奏(コンピュータープログラミングとキーボード)と自身で詩を付けたボーカルを手がける。ラリー・ハードの音楽の特徴はデジタル音楽からは想像できないようなシンプルな構成にある。キーボードで弾くブロックコードだけでベーシックなライン(これがとっても魅力的!)を創り、そこに自身の歌と軽めのシンセを乗せているだけなのだが、肌触りがクールであるにも関わらず、豊かなサウンドになっている。
『イントロダクション』にすっかり魅了されたので、続いて1994年にリリースされた『バック・トゥ・ラブ』も手にする。しかし、この作品はちょっと期待外れな内容だった。前作に比べて、より聴きやすいサウンドになっているものの、例えば “on my way” や “closer” や “what about this love?” と言った曲で聴かれた(ソフトな中にも)骨っぽく感じられるような部分が薄くなっているように感じられたから。どちらの作品もハウスミュージックとしては例外的にメジャーレーベルからのリリースなのだが、2作目は多少とも売ることを意識したことで尖った部分が希薄になったのかも知れない。

♪『キャン・ユー・フィール・イット』で「原点」を知る
『バック・トゥ・ラブ』のあとも、ラリー・ハード/Mr.フィンガーズのチェックは続いた。2枚組の『ダンス2000』、そしてディープ・ハウス(と言うのだそうだ)「の世界で古典的な名曲とされる『キャン・ユー・フィール・イット』を手にする。どちらも、『イントロダクション』のようなトータルコンセプトアルバムではなく、1980年代に作られた実験的な作品を含むベスト盤。ただ、1990年代以降の作品の原点のような曲が含まれていて、魅力的なトラックもある。「原点」を知ることで、ラリー・ハードのミュージシャンとしての成長を知ることができるわけだ。
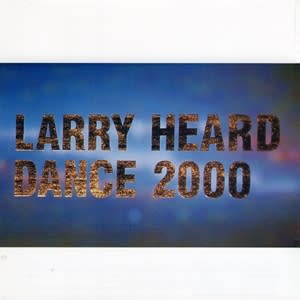
♪至福の作品『ラブズ・アライバル』
現在保有しているラリー・ハード(Mr.フィンガーズ)のCDでもっとも最近の作品は2001年リリースの “Love’s Arrival”。かなり前に手に入れたアルバムだが、どうもあまり真剣に聴いていなかったようだ。購入していたことすら忘れていた。ということで初めて聴く気分でCDトレイに載せたわけだが、1曲目を聴いて(もちろん私が持っている作品の中でということになるが)ラリー・ハードの持ち味が最高に発揮され、かつ円熟味も加わった作品であると実感した。
『イントロダクション』で聴かれたようなある種の「気負い」のようなものは消え、かと言って『バック・トゥ・ラブ』にあったかもしれない「妥協」もない。ソフト路線は一貫して変わらないものの、オープニングからフィナーレまでナチュラルにゆったりとサウンドが流れている。おそらく、メジャーレーベルを離れて自分自身が完全に納得できるサウンドを創り上げることに成功したのではないだろうか。妥協のないことが心地よさの源泉になっているように感じる。
1970年代にジャズに電化楽器が導入されたとき、「エレキには血が通っていないからダメだ。」という声が多くのジャズファンから聞かれた。でもその人達は、ラリー・ハードの作品を聴いても同じことが言えるだろうか。たとえアコースティックの楽器の演奏でも、目の前でどんなに驚異的なテクニックを披露されても聴き手の心を揺り動かさないことはままある。
コンピューターで音楽を創っているミュージシャンは、器楽のミュージシャンとは違った意味で厳しい世界に身を置いているとは言える。演奏技術の巧拙が問われない代わりに、ミュージシャン本人の感性を丸裸にしてしまうような恐ろしさがデジタルミュージックにはある。ラリー・ハードの音楽を聴いていてふとそんなことを思った。
前にも少し書いたように、セントギガのおかげでいろんな音楽に出逢えうことができた。そんな中でまず最初にラリー・ハードを取り上げたのは、セントギガのことを知らなければ、永久に出逢うこともなかった音楽がそこにあったから。一度は行方知らずとなった「ハヤブサ」のように、宇宙の彼方に散ってしまったセントギガの電波が再び地球に戻って来て欲しい。もう一度聴いてみたい音楽がたくさんあるから、そんな永久に充たされることのない馬鹿な願望を抱いてしまったりする。