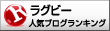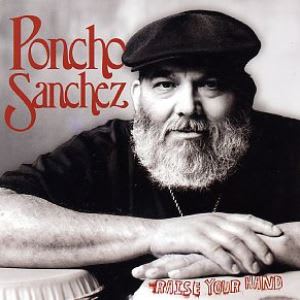幼少期からクラシック音楽に親しんできた私。ではあるが、主に聴いていたのは交響曲であり、協奏曲であり、ピアノ曲だった。室内楽はどちらかというと苦手で、中でも弦楽四重奏にはあまり関心を抱くことがなかった。ジャズはビッグバンドより断然少人数のコンボだから不思議ではあるのだが、たぶん音楽の性格も影響していたのだろう。
しかし、あることがきっかけで今やクラシックも小編成の室内楽中心に楽しむようになっている。とくにマイブームとなっているのは、今までハイドンやバルトークやラヴェルといった例外を除き、殆ど親しむことのなかった弦楽四重奏というから人生はわからない。

♪クラシック倶楽部で知った室内楽の楽しみ
さて、その「あること」だが、音楽とは全然関係なさそうな、いや関係のないNHKの朝ドラだった。現在再放送されている「梅ちゃん先生」になぜか填まり、朝のBS放送分を録画して毎晩観ていた。それは現在の「マッサン」までしっかりと続いている。
普通なら話はそこで終わってしまうのだが、録画予約をしているときにひとつの番組が目に留まったことからひとつの私的ドラマが始まった。その番組は朝ドラ2連発の20分前に終了となる「クラシック倶楽部」。月曜日から金曜日までの毎朝6時から55分間、日本国内で行われたリサイタル(室内楽や声楽の演奏会)の模様を届けてくれる番組。
ついでだからこちらも録音してみるかということで、朝ドラを観たあとに音楽も愉しむことになったのだが、これが驚きの連続だった。ひとつは、東京が中心とはいえ日本ではこんなにも多くの室内楽の演奏会が開かれているということを知らなかったこと。海外の有名な演奏家も頻繁に登場するなど、とてもレベルが高い演奏が毎晩のようにどこかで行われていることに気づいていなかった。
そして、もうひとつはクラシック音楽であっても、小さな編成による音楽の愉しみは、ジャズのライブ演奏と何ら変わらないということ。こうして日常的に室内楽に接していくうちに、とくに魅力を感じることになったのが弦楽四重奏だったというわけなのだ。その面白さについては後々に書いていくこととして、ひとつ確信を持ったことがあった。
それは、「弦楽四重奏団は最小規模のオーケストラであると同時に最大規模のソロ楽器である」ということ。それと楽器の奏法や演奏スタイルの変遷はあるにせよ、ハイドンの時代から現代に至るまで、弦楽四重奏はまったく編成を変えることなく続いていることも興味深い。弦楽四重奏は古今東西の作曲家達を同じ土俵に載せることができる最高の編成と言い換えることもできる。なぜいままでこのことに気づかなかったのだろう。

♪ジオカローレとの幸運な出逢い
前置きがすっかり長くなってしまった。年に2回、大学の同級生で集う飲み会がある。クラシック音楽よりも、そしてジャズよりも、ど演歌の方が似合いそうな業界で働いている仲間の集いなのだが、久しぶりに出席したひとりと音楽の話になった。もともと娘さんが大学のオケでコンマスをしていることは人づてに聞いてはいた。だから話題を音楽に振ってみたのだが、「娘が弦楽四重奏をやっていまして、近々演奏会がありますよ。」という予想をはるかに超える展開になってしまったのだった。
そんなわけで、2月21日の午後、東神奈川駅のカナックホールに足を運んだ。プログラムがまた驚き。第2楽章が「アンダンテ・カンタービレ」としてつとに有名なチャイコフスキーの弦楽四重奏曲は定番なのだが、ベルワルドとシベリウスの弦楽四重奏曲は滅多に聴けない曲。もちろんシベリウスはフィンランドを代表する作曲家で交響曲は有名だが、ベルワルドに至ってはクラシック音楽ファンでも知らない人が多い。スウェーデン人で大変魅力的な交響曲を書いている人ではあるのだが、その素晴らしさを知る人はまだまだ少ない。
プロの弦楽四重奏団は取り上げないような作品が2つ。しかしここがジオカローレの魅力ではないかとプログラムを見て思った。アマチュアだからこそ、珍しい作品に取り組むことができるとも言える訳だ。弦楽四重奏にはまだまだ隠れた名品があるはずだし、それを掘り起こすことが出来るのはプロの団体とは限らない。
そんなことを考えながら開演を待っていると、4人のメンバーがステージに登場。ベルワルドの曲が始まった。ロマン派の時代に生きながらも、ドイツやオーストリアとは違った北欧風の味わいがあり、随所に仕掛けがある作品。比較的有名な交響曲第3番などで味わえる剛気な感覚とはまた違う面白さがあることを知ったのはひとつの発見だった。
次の曲はシベリウス。第2番や第5番などの交響曲を何度も聴いたお馴染みの人のはずなのだが、弦楽四重奏は別の人の作品のように感じるから不思議。しかし、ここも弦楽四重奏の楽しみなのだ。とくに印象に残ったのはチェロ奏者の活躍。両翼に位置するバイオリンとチェロが対話するかのような展開も面白いし楽しかった。
そして最後はチャイコフスキーとなる。やはり、この人は天性のメロディストだったことがよくわかる。ジオカローレは過去にこの曲を取り上げたことがあるそうで、そんなことからもこなれた演奏だったように感じた。だからという訳でもないが、いつの日かベルワルドとシベリウスにも再チャレンジして欲しいと思ったりもする。「マッサン」ではないが、一度じっくりと取り組んだ(仕込んだ)音楽にも熟成はあるはず。

さて、渋いプログラムにも拘わらず、500人収容のホールをほぼ満席にしたジオカローレ。次はどんな曲にチャレンジしてくれるだろうかと、早くも興味は次の演奏会へと向かっていく。私的にはいつの日か我が最愛のアーノルド・バックスの3曲の中からの1曲をリクエストしたい。
バックスは英国生まれながらアイルランドの気候風土をこよなく愛した情熱とロマンの作曲家であり、ロシア音楽のテイストを感じさせる骨太な面も合わせ持っていた人。交響曲やトーンポエム(管弦楽作品)で知られる人だが、実は室内楽作品に逸品が多い。とくに弦楽四重奏はオーケストラを聴いているような分厚いサウンドで迫ってくる魅力を備えている。そんなバックスの魅了を生で伝えてくれるのがジオカローレだったら嬉しいと思ってしまった。