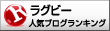ゴールデンウィーク恒例のお楽しみとなったラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン。今年は5月5日の3公演プラス・アルファを丸の内界隈で楽しんだ。今年のテーマは舞曲の祭典のサブタイトルが付いた『ラ・ダンス』。クラシック音楽主体なのは変わらないが、「踊り」をテーマにしたいろいろな音楽を聴くことができた。中でも一際感動的だったのがG409ヌレエフ(座席数153)で聴いたサロン風のリサイタルだった。
プログラムには「ベネズエラ生まれのガスパール&えりか兄妹が歌い上げるスペイン語圏の歌のカタログ」と記載されている。出演者はコロン・えりか(ソプラノ)、ガスパール・コロン(バリトン)、碓井俊樹(ピアノ)の3名。実はクラシック音楽でも声楽は苦手。ラフォル・ジュルネのプログラム紹介を眺めていて“モイセス・モレイロ作曲『ホローポ』”の文字が目に止まらなかったら、おそらく同じ時間帯には別の会場に居ただろう。この作品はベネズエラ生まれのクララ・ロドリゲスがピアノを弾いて録音した「平原の映像」(モイセス・モレイロ作品集:英国ASVレーベルから1994年にリリースされたCD)のフィナーレを飾る曲。
ちなみに「ホローポ」はコロンビアとベネズエラに跨がるジャーノス地方(大平原)で演奏されている情熱とロマン(Recio y Romantico)に溢れた民衆音楽。オリジナルのスタイルや編成(後述)ではなく、クラシック音楽の書法で作曲されたピアノ独奏用の作品とは言え、まさか生で聴くことができるとは思ってもいなかった。その他にも中南米(スペイン語圏)の名曲カタログの名に違わない作品がプログラムに並んでいた。
♪ プログラム ♪
1)マリア・ルイサ・エスコバル/バレンシア・オレンジ[ホローポ]
2)マリア・ルイサ・エスコバル/失望[ボレーロ]
3)チェリーケ・サラヴィア/焦燥[バルス]
4)カルロス・ガルデル/ボルベール(望郷)[タンゴ]
5)シャビエ・モンサルバーチェ/黒人の歌[カンシオン]
6)エルネスト・レクオーナ/マリア・ラ・オー[ロマンサ]
7)エルネスト・レクオーナ/ラ・コンパルサ(仮装行列)[カンシオン]~ピアノ・ソロ~
8)アントニオ・ラウロ/エル・クカラチェーロ[ホローポ]
9)キリノ・メンドーサ・イ・コルテス/シェリート・リンド[カンシオン]
10)チュエカ&バルベルデ/「恩寵の騎士」のワルツ[バルス]
11)モイセス・モレイロ/ホローポ[ホローポ]~ピアノ・ソロ~
12)アウグスト・ブランド/夢の中のくちづけ[カンシオン]
13)ペドロ・エリアス・グティエレス/平原の魂[ホローポ]
14)ベネズエラ民謡/エル・クルチャ ~アンコール~
オレンジ入りの籠を小脇に抱えたえりか・コロンさんが「完熟のオレンジ(ナランハ)はいらんかね~」と歌いながらステージ(というよりはサロン)に登場。明るくて愛嬌のあるソプラノに会場は一気に華やいだムードに。と同時に(声楽だが)この会場をセレクトしてよかったと胸をなで下ろす。この曲からして私の大好きな(究極のラテンアメリカ音楽として愛して止まない)ホローポだから堪らない。

ホローポとの衝撃的な出逢いは凡そ20年前に遡る。出張でコロンビアに出かけた弟に「何かコロンビアの面白そうなCDを買ってきてくれない?」と軽い気持ちで頼んだことが私の音楽人生(ちょっと大げさで「音楽観」)を変えることになってしまったのだから面白い。弟がコロンビアから持ち帰った2枚のCDのうちの1枚がアリエス・ヴィホート(Aries Vigoth)の『プレデスティナシオン』で、これがなんと!生粋のホローポだったのだ。最初に聴いた時、一体何が起こったのか判らなくなってしまうくらいに驚いたことを今でもよく覚えている。
主役は「2トップ」として壮絶なバトルを繰り広げる歌とアルパ(南米の小振りのハープ)で、伴奏は4弦のクアトロ(ウクレレサイズの小ぶりのギターのような楽器)とベースにマラカス。あまりにも情熱的で、そして今まで耳にしたことのないリズムの洪水のようなサウンドに「陽気でロマンティックなラテンアメリカ音楽」のイメージが完全に吹っ飛んでしまった。知り合いのラテン音楽通の人に尋ねたら「それはホローポですよ」と教えてくれた。日本でのラテンアメリカ音楽の紹介のされ方に問題があったのかもしれないが、こんな魅力的な音楽があることを紹介してくれなかったことに対して「裏切られた」という蟠りを持ったことも告白しておく。

ホローポのことをもっと知りたい。そんな想いに駆られて石橋純氏を(掟破りに近い方法を使って)訪ねた。現在は東大でベネズエラ音楽の学生オーケストラを率いておられる石橋教授がベネズエラで制作したCD『衝撃のストリングスバトル』はホローポの最高の教科書。ホセ・アルチーラのマッチョなアルパを聴いて「舞台の袖で淑やかに爪弾かれるハープ」のイメージは完全に吹き飛び、1人で弾いているとは信じられないチェオ・ウルタードのクアトロの神業にまずは圧倒された。軽快に乾いたリズムを刻むのは「マラカスの魔術師」として名高いエルネスト・ラジャで、ベースのダビッド・ペーニャもジャンルを超えた活躍で知られる人。
そんなことを思い出していたら兄のガスパール・コロンが登場。魅惑の(としか言いようのない)バリトンボイスで甘く切なくボレーロの「失望」を歌う。同国人のチェリーケ・サラビアの「焦燥」はバルス。ホローポや5/8拍子のメレンゲとともにベネズエラを代表する音楽でブラジルのショーロに通じる哀愁感が魅力。ここにクアトロ奏者やマラカスを振る人がいたらもっと盛り上がるだろうなと思った。そこに現れたのはモーリス・レイナ氏。ベネズエラ大使館の文化担当官として活躍される方だが、実はクアトロの名手としてもつとに有名。サプライズ・ゲストがあるとすればこの方かなと、ふと思ったがまさか本当になるとは。この展開は実にラテンアメリカ的で楽しい。

カルロス・ガルデルはタンゴの王様として名高い南米を代表する歌手の1人だが、映画俳優としても活躍しアメリカ大陸全域でいまなお高い人気を誇る。そのガルデルの歌を「キング・オブ・タンゴ」の2枚のCDに収めたプリマ・ヴォーチェ(Prima Voce)はSP時代に活躍した名歌手の音源の復刻を手がけるレーベル。カルーソーなどクラシック音楽界で一世を風靡した歌手達の中にポピュラー音楽界からはひとりガルデルだけをセレクト。素晴らしい声はSPの盤起こしの音からでも十二分に伝わってくる。タンゴの楽器と言えばバンドネオンだが、ガルデルの録音で聴くことができるギターの伴奏もなかなか魅力的。

キューバのエルネスト・レクオーナは「シボネイ」や「そよ風と私」などのヒットチューンで知られる人。ポピュラー畑の人と思われがちだが、ピアノ曲などクラシック音楽スタイルの作品も残している。モダンジャズ、キューバ音楽、クラシック音楽とジャンルを超えて活躍したフランク・エミリオ・フリンのピアノ作品集は、そんなレクオーナの魅力を存分に伝えてくれる。余談ながらフランク・エミリオが得意とするダンソンもサロンの雰囲気が濃厚な音楽。キューバの強くて明るい日射しを音で表現した碓井俊樹のピアノタッチも見事。

舞台はキューバから再びベネズエラへ。数多くのギター作品を残したアントニオ・ラウロはベネズエラを代表する作曲家のひとり。名手アダム・ホルツマンがナクソスからリリースしている『ギターのためのベネズエラ・ワルツ集』のオープニングは、ワルツではなくホローポの「セイス・ポル・デレーチョ」。ホローポの特徴のひとつはヨコに拡がる3/4拍子とタテに切れ込む6/8拍子(2拍子)が同時進行のクロスビートの面白さにある。まさに大平原のゆったり感と駿馬の疾走感を同時進行で表現することができる魔法のリズム。えりかさんが手拍子を促すと聴き手も自然にそれに応える。それもホローポの2パターンのリズムのうち、アタマが欠ける難しい方の3拍子(んタタ、んタタ)だっただけに感動もひとしお。おそらくベネズエラの音楽に通じた人達が客席を埋めていたのだと思う。
(寄り道ばかりで申し訳ないと思いつつ。3/4拍子と6/8拍子(2拍子)がクロスするパターンはラテンアメリカ音楽の特徴であり、大きな魅力だと思う。コロンビアとベネズエラのホローポ、ペルーのワルツ、アルゼンチンのチャカレラやチャマメは典型的だし、その他にもいろいろ。2つのリズムの絡み方もルーズだったりタイトだったり、またアクセントが違ったりと多様な展開がある。このラテンアメリカ流のスウィングにはまり込んで脱出不能になってしまったのが私。)
いよいよプログラムも終盤。永遠のポピュラーヒット曲で私も大好きな『シェリート・リンド』、スペインの作曲家コンビのワルツの後は待ちに待ったモイセス・モレイロの『ホローポ』。クララ・ロドリゲスのピアノ作品集ではフィナーレを飾る小品。この作曲家の作品の特徴は大平原の素朴な味わいと「ベネズエラ風バッハ」と表現したくなるフーガなどの技法を駆使したスタイル。この魅力的なアルバムはもっと聴かれていいと改めて思った。同じカリブ海にあってもキューバのきらびやかさとは違った柔らかめのタッチがベネズエラのピアノ演奏の魅力。独特とも言える節回しには、アルパの本場であることの影響もあるのかも知れない。
楽しい時間も終わりが近づいてきた。フィナーレにセレクトされたのはベネズエラの第二の国家とも言われている『平原の魂』(アルマ・ジャネーラ)。鳴り止まないアンコールの拍手に応えて再びモーリス・レイナ氏が登場して『エル・クルチャ』が歌われた。演奏会場は153席でフラットなサロン風のスペース。手拍子も入ったりとクラシック音楽のステージとは思えない状況がごく自然に実現できていることには驚きを禁じ得ない。さながらコロン兄妹により実現したミニ・オペラとも言うべき(規模は小さくても)ゴージャスな味わいに深い感銘を受けた。
コンサートホールという時に巨大な「バリア」の中で、さらにステージと客席というように隔てられた形で静かに聴くのがクラシック音楽の嗜み方。そして、それを不思議と思わないずっとできていたような気がする。しかし、例えばの話、ハイドンが弦楽四重奏曲の作曲を始めた頃の時代は、お喋りもお食事もありの、さながらジャズクラブのような場所で演奏が行われていたと聞く。たとえそれが垣根のないラテンアメリカの音楽だったとしても、クラシック音楽を手軽に楽しむには、案外こういったサロン風の雰囲気も大切なのではないかと思ったのだった。
 | Piano Works |
| クララ・ロドリゲス『モイセス・モレイロ作品集』 | |
| Nimbus Records |