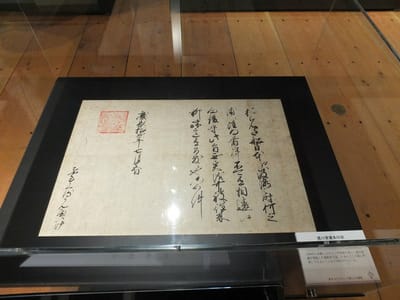地下鉄烏丸線終点の国際会館からバスで大原に向い、終点より4つ手前の戸寺バス停で下車して東側の丘を歩き、三千院へ向かいました。
戸寺バス停→惟喬親王の墓→浄楽堂の一本杉→大原駐在所手前を右へ→三千院 (大原の里・秋の花マップ参照)

大原の風景
戸寺バス停からは丘に上る道になり、一旦森に入り、小川を亘って少し下ると、西方向の視界が開けます。この風景は、NHK-BSプレミアムの「猫のしっぽ カエル手」(ベニシアさん出演)の冒頭で出てきた大原の風景を思い起こさせます。

ウラギンシジミ♂
小さい集落を抜けた斜面にあるツバキを見ると、ウラギンシジミの雄が葉裏に逆さに止まっていました。大原は、京都の北の谷間にあり気温が低いため、もう完全に越冬態勢に入っており、翅に触れても微動だにしませんでした。
※京都の旅で見た蝶は、このウラギンシジミだけでした。

集落にて

寂光院方面
西の方に寂光院方面の集落が見えます。

三千院付近
三千院に近付くと、大勢の参拝者の姿が見られました。
(続く)
戸寺バス停→惟喬親王の墓→浄楽堂の一本杉→大原駐在所手前を右へ→三千院 (大原の里・秋の花マップ参照)

大原の風景
戸寺バス停からは丘に上る道になり、一旦森に入り、小川を亘って少し下ると、西方向の視界が開けます。この風景は、NHK-BSプレミアムの「猫のしっぽ カエル手」(ベニシアさん出演)の冒頭で出てきた大原の風景を思い起こさせます。

ウラギンシジミ♂
小さい集落を抜けた斜面にあるツバキを見ると、ウラギンシジミの雄が葉裏に逆さに止まっていました。大原は、京都の北の谷間にあり気温が低いため、もう完全に越冬態勢に入っており、翅に触れても微動だにしませんでした。
※京都の旅で見た蝶は、このウラギンシジミだけでした。

集落にて

寂光院方面
西の方に寂光院方面の集落が見えます。

三千院付近
三千院に近付くと、大勢の参拝者の姿が見られました。
(続く)