今日は市が主催する90分ほどの講演を聴きに行った。
講演のタイトルは「地下足袋の詩」、講師は入佐(いりさ)明美さん。
私は講師がどんな人か全然予備知識もなし、講演の内容も同じく予備知識なし。
講師として紹介されたのは、パイプ椅子にこじんまりと座っていた「おばちゃん」だった。
彼女の肩書きは「看護士・ボランティアケースワーカー」
24歳のときから大阪の釜ケ崎で28年間ボランテイアでケースワーカーをしてきた人だと分った。
今は釜ケ崎に事務所を設けて
「大阪建設労働者生活相談室、ボランティア相談員」
となっている。
よく質問されるのが
「28年間もボランティアだなんて生活費はどうなってるの」
だという。
最初の3年間は、彼女が看護士として病院に勤務していたときの貯金で暮らし、次の7年間は「入佐明美を支援する会」というのが全国組織で出来てその支援金で何とか暮らせた。
その後本を書いた印税とか、最近は講演料もいくらか入るようになって生活出来ているということだった。
「地下足袋の詩」は彼女が書いた何冊かの本のうちの1冊のタイトルだ。
彼女が何故「釜ケ崎の母」といわれるまでにのめり込んだボランティア活動の軌跡とそこで彼女が学んだ「人生とは何ぞや」の話を淡々と話していた。
釜ケ崎の日雇い労働者は好況時は安い賃金で使われ不況時にはすぐに路頭に迷う。
仕事先でも名前さえ呼んでもらえないという。
「そこの釜ケ崎のひとっ」としか呼んでもらえないという。
今は高齢化した釜ケ先の労働者にアパートを世話して生活保護を受けることが出来るようにする活動続けているという。
アパートといっても三畳一間の最低のアパートだ。
最初アパートの入居費用として6万円を貸してあげるそうだ。
そしてその6万円の貸し金は一度として返済されなかったことはないそうだ。
生活保護費を貯金して半年くらいで返済してくるそうだ。
返済し終わると彼らは「初めて人の信頼を裏切らないことが出来た」と涙を流すという。
そして彼らは
「まるで天国で暮らしているようだ」
「先の不安がない」
「心置きなく安心して眠れる」
「初めて自分を、我を主張できる人生に出会った」
といっているという。
彼らの人生は今日を生き延びるために選択肢のない人生を送ってきた、そして自分がしたいことを選べる人生に生涯で初めてたどり着いた。
と彼女は言っていた。
最初彼女は「彼らを何とかしてあげたい」という思い上がった動機で始めたということだがそれはいかにむなしい動機かを理解した、という。
実際には彼らから教わることのほうが多かった、という。
彼女の話を聞き終わったときは、ひっそり生きてる賢者に見えた。
いい講演だった。
講演のタイトルは「地下足袋の詩」、講師は入佐(いりさ)明美さん。
私は講師がどんな人か全然予備知識もなし、講演の内容も同じく予備知識なし。
講師として紹介されたのは、パイプ椅子にこじんまりと座っていた「おばちゃん」だった。
彼女の肩書きは「看護士・ボランティアケースワーカー」
24歳のときから大阪の釜ケ崎で28年間ボランテイアでケースワーカーをしてきた人だと分った。
今は釜ケ崎に事務所を設けて
「大阪建設労働者生活相談室、ボランティア相談員」
となっている。
よく質問されるのが
「28年間もボランティアだなんて生活費はどうなってるの」
だという。
最初の3年間は、彼女が看護士として病院に勤務していたときの貯金で暮らし、次の7年間は「入佐明美を支援する会」というのが全国組織で出来てその支援金で何とか暮らせた。
その後本を書いた印税とか、最近は講演料もいくらか入るようになって生活出来ているということだった。
「地下足袋の詩」は彼女が書いた何冊かの本のうちの1冊のタイトルだ。
彼女が何故「釜ケ崎の母」といわれるまでにのめり込んだボランティア活動の軌跡とそこで彼女が学んだ「人生とは何ぞや」の話を淡々と話していた。
釜ケ崎の日雇い労働者は好況時は安い賃金で使われ不況時にはすぐに路頭に迷う。
仕事先でも名前さえ呼んでもらえないという。
「そこの釜ケ崎のひとっ」としか呼んでもらえないという。
今は高齢化した釜ケ先の労働者にアパートを世話して生活保護を受けることが出来るようにする活動続けているという。
アパートといっても三畳一間の最低のアパートだ。
最初アパートの入居費用として6万円を貸してあげるそうだ。
そしてその6万円の貸し金は一度として返済されなかったことはないそうだ。
生活保護費を貯金して半年くらいで返済してくるそうだ。
返済し終わると彼らは「初めて人の信頼を裏切らないことが出来た」と涙を流すという。
そして彼らは
「まるで天国で暮らしているようだ」
「先の不安がない」
「心置きなく安心して眠れる」
「初めて自分を、我を主張できる人生に出会った」
といっているという。
彼らの人生は今日を生き延びるために選択肢のない人生を送ってきた、そして自分がしたいことを選べる人生に生涯で初めてたどり着いた。
と彼女は言っていた。
最初彼女は「彼らを何とかしてあげたい」という思い上がった動機で始めたということだがそれはいかにむなしい動機かを理解した、という。
実際には彼らから教わることのほうが多かった、という。
彼女の話を聞き終わったときは、ひっそり生きてる賢者に見えた。
いい講演だった。














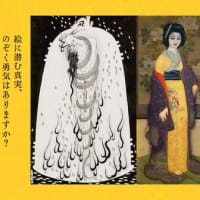

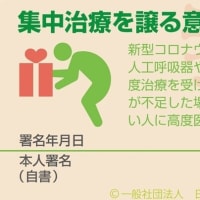
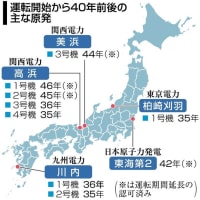

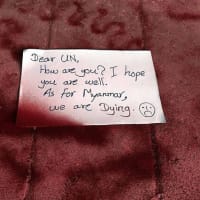
今私は初めて、人生とはこんなに迷うものなのかと、現実を突きつけられている状況の中にいます。
そんなとき、そういう、人と全く違う生き方をしている人の話を聞くと、それはとても強い意思の下でこそ成しえることなのだと痛感します。
私は今までどれだけレールの上を走ってきたのか、思い知らされました。
同時に、人生ってどうにでもなるのだなとも思っています。
私も、いいお話を読ませて頂きました。
ありがとうございました。
ケースワーカーのお仕事を支える団体が出来たというのは、希望がみえる話ですね。
彼女は中学生の頃に既に人生なんて何の意味があるんだろうと考えていたそうです。
それがある医師の活動に感動しその医師のように生きてみたいと心に決めたそうです。
ケースワーカーとして28年間に2度大きな壁にぶち当たったといってました。
「私のやっていることは何か意味があるのだろうか、何の役にも立っていないのではないか」と虚無感に囚われたそうです。
そして多くの人に助けられ乗り切ってきたといってました。
パトラさんへ
夢は叶うといいますが、何事も強い意欲と意志があって努力すば道が開けるのですね。
漫然と生きる人には道は開けませんね。
努力を続ける人には自然と他人も協力してくれて物事が成就してゆくように思えます。
漢字の意味を理解して使い慣れるしかないと思います。
一昔前は看護婦と言ってました。
ただ、講演での彼女の肩書きは「看護士」でした。
私は看護婦も男性の看護人もすべて看護士と思い込んでいました。
Pinkのほうが正しく理解していましたね。
「何とかしてあげたい」って言うのは思い上がり・・・自分が上にいるから、「何とかしてあげたい」んですものね。
私は明日友達に会います。相談したい事があるそうです。
「何とかしてあげたい」と思ってしまったけれども、そのオーラはできるだけ出さないように心がけます。
それを思い上がりだと言い切れる人は聖人ですね。
私も「何とかしてあげたい」と思うことは多々あります。