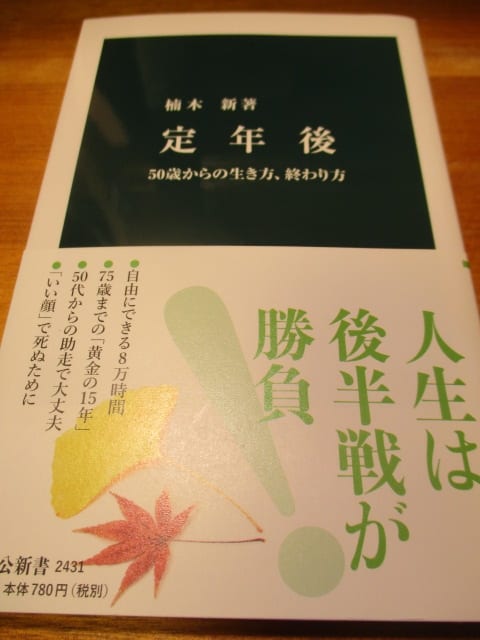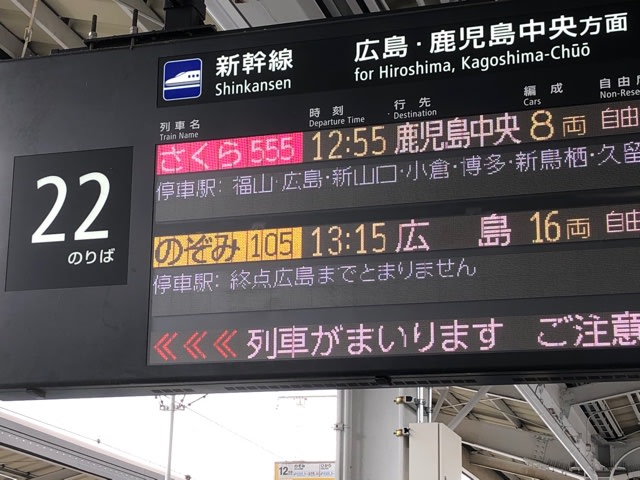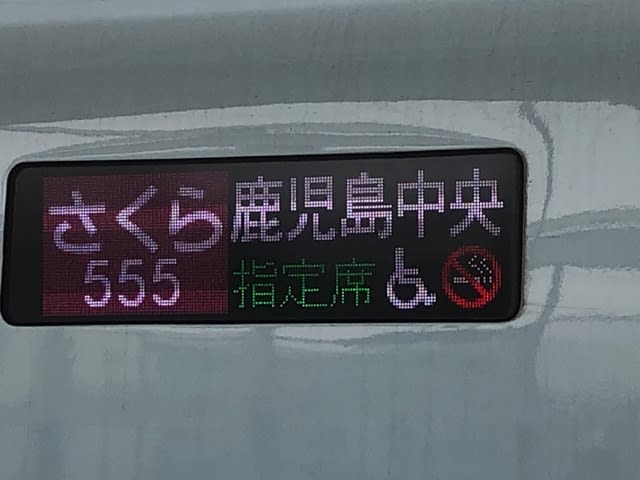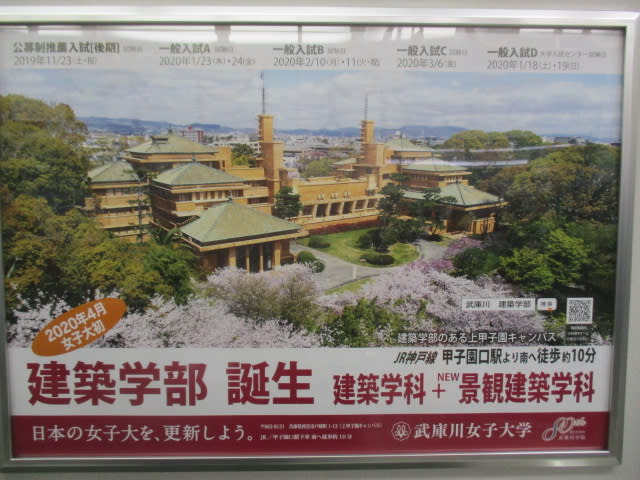カープ球団創立70周年・・・中國新聞で「あの日あの時」の連載がスタートしました。
第1回の特集は、1975年10月15日。
東京・後楽園球場で球界の盟主読売を破り、「球界のお荷物」とまで呼ばれたカープが初優勝を遂げた時の記録がまとめられています。
友岡真彦記者が担当。
なかなかの名文です。
友岡記者の大先輩、故津田一男記者のスピリットがしっかりと引き継がれていて嬉しく楽しく読みました。

中國新聞は4月から26年ぶりに購読料を値上げするとのこと。
その分、しっかりカープの報道をしてくださいね(笑)。
友岡記者のがんばりに期待大です。

津田一男さん・・・
シーズン中、カープが連敗したり、不甲斐ない負け方をした時、必ず読むのが津田一男さんの1975年10月16日の中國新聞の「球心」を読みます。
去年は何度も何度も読むことになりました・・・涙。
今でも中國新聞のスポーツ欄に、「球炎」としてカープの試合の翌日に掲載されています。

津田さんは、カープ創成期からカープを取材し続けた中國新聞のカープ番記者。
その生涯をカープのために捧げたジャーナリストです。
唯一、親会社を持たない市民球団カープ。
本当にビンボーでした・・・
カープ結成時、リーグへの加盟金も払えない、選手への給料は遅延、選手寮の家賃や光熱費が払えない、選手は遠征時には満員の汽車の通路に新聞紙を敷いて寝る・・・
「セリーグのお荷物球団」と蔑視されていた貧乏球団カープ。

そのカープが、1975年、読売巨人軍を破り、セリーグ初優勝。
津田さんは、涙をぬぐいながら、後楽園球場のネット裏で、この名分を書いたという伝説が伝わっています。
「広島の街は喜びの人々であふれていることだろう。よかった。本当によかった。」
ここで、必ず涙が出てきます・・・。
改めて、カープスピリットの原点・・・津田さんの名文を紹介させていただきます。

強じんな雑草 いま大輪の花
球心 津田一男
真っ赤な、真っ赤な、炎と燃える真っ赤な花が、いま、まぎれもなく開いた。
祝福の万歳が津波のように寄せては、返している。
苦節26年、開くことのなかったつぼみが、ついに大輪の真っ赤な花となって開いたのだ。
カープは春の初め、はち切れそうなつぼみをつけても、開くことのない花であった。
花の咲かない雑草であった。
来る年も、来る年も・・・
原爆に打ちひしがれた広島の人びとの心のよりどころに、と結成されたカープ。
カープは原爆の野に息吹いたペンペン草、踏みにじられ、見捨てられても、屈することのない雑草であった。
それ故にカープファンは、いつの日か花開くことを夢見て、愛し続けてきたに違いない。
海の向こうからやってきたルーツおじさんは、この雑草を一年間じっくり観察した。
そして、二年目、「咲かせてみせましょう」と乗り出し、入念な手入れをすませると、さっさと帰っていった。
つぼみは日ごとに赤みを増し、生き生きと膨らんでいった。
水枯れの夏にも屈せず、台風の秋にも折れず・・・十月十五日、つぼみはついに真っ赤な花を咲かせた。
なんと長い、待ちに待ったその瞬間であったことか。
宙に浮く古葉の姿が涙にかすむ。
古葉もまた泣いていることだろう。
浩二はお立ち台で、コブシで涙をぬぐっている。
そして外木場が、大下が、三村が・・・
みんな抱き合って・・・
広島の街は喜びの人々であふれていることだろう。
よかった。
本当によかった。
そして、この喜びを、今は亡きカープを愛した人々に告げ、喜びをともにしたい。
カープを、いまわの際まで愛し続けたみなさん、見ましたか、カープのきょうのこの快挙を。
この一年、不撓不屈、明るく勇ましく、一丸となって戦ってきたカープの集約された姿がそこにありました。
強運の大下がたたいた、あの先制点。
この1点、守り切るぞーとまなじりを決して投げた外木場。
あとは任せておけーと不死身の金城。
そして最後にはホプキンスの3ランがついに、ついに、「V1」へのさん然と輝く栄光の橋を手ごたえも確かにかけた。
あの虹の橋を何度夢見たことか。
その虹の橋が、いまはゆるぎない鉄の橋となり、その上で赤い帽子のナインが、涙の笑顔で手を振っている。
幾万ものファンがその下で万歳を繰り返している。
真っ赤な花、炎と燃える真っ赤な花がそれである。
昭和50年10月16日 中國新聞朝刊