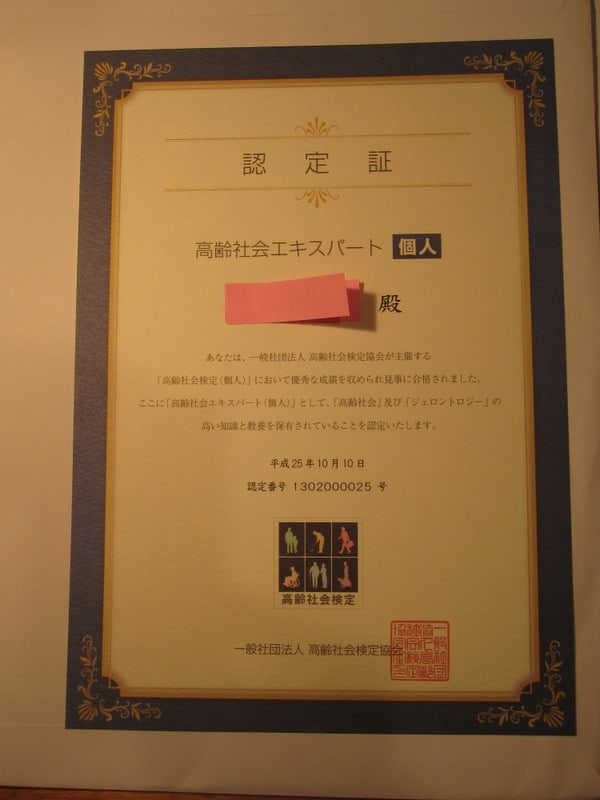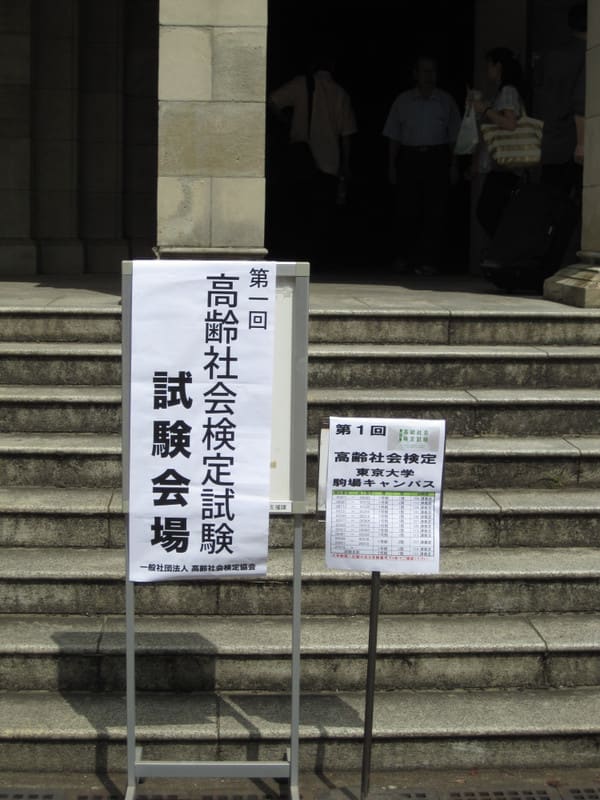11月10日(日曜日)に浜松町であった「公認モチベーションマネジャー(ベーシック)」資格試験の合格証が届きました。
試験から発表まで一か月半・・・。
ちょっと長すぎる感じです(試験の時、試験監督官から大阪、名古屋、九州の試験が終わってから一か月で発表というアナウンスはされていましたが・・・)。
何とか合格、よいクリスマスプレゼントになりました。
封筒に入っていたのは・・・
1.合格証書
2.認定証(プラスティックのカード)
3.シール(名刺に貼るためのもの)
大切にしたいと思います。
この試験は、一般社団法人モチベーションマネジメント協会が実施する試験。
企業向け研修で有名なリンクアンドモチベーション社、東京未来大学、専門学校の三幸学園がバックにあるモチベーションマネジメント協会が主催する試験です。
公認モチベーションマネジャーは、ベーシック、アドバンス、プロフェッショナルの3段階があり、
現在、ベーシックのみの資格試験が実施されています。
組織の力をパワーアップする人々の「モチベーション」。
やる気、仕事に対する姿勢、仕事の意味づけなどなど、モチベーションにスポットを当てた初の資格試験です。
試験時間は、90分。
試験問題は70問。
全問マークシート方式です。
三題も事例問題もあり、自分自身、ギリギリまで問題に取り組んでいた次第です。
一問あたり一分ちょっとで解答していかなければなりません。
また、公式テキストに出ていないであろう部分もあったため、自信のない解答も多々あった次第です。
今回の試験は第2回。
第1回の結果は合格率72%。
890名あまりの合格者が出ているということです。
合格のためには、テキストである「公認モチベーション・マネジャー資格ベーシックテキスト(新曜社刊・1900円+税)」を最低3回は読み込むことで大丈夫だと思います。
ベーシックであれば、直前一か月の集中学習で合格可能です。
基本教材は全八章なので、一日一章を読んで四回転させる・・・これにより合格圏内に入ることが出来るのではないでしょうか。
テキストの内容
第1章 モチベーションとは何か
第2章 内発的モチベーション
第3章 期待とモチベーション
第4章 目標とモチベーション
第5章 リーダーシップへのアプローチ
第6章 リーダーに求められるもの
第7章 対人コミュニケーションの基本
第8章 円滑なコミュニケーション
テキスト、レイアウト、ケースなどに工夫が凝らされた、なかなか充実した教材です。
学習のポイント
1.公式テキストを中心に学習する。
2.一回目は、ざっと全体をつかむ感じで、疑問点を飛びして読み進む。
3.二回目は、熟読。場合によっては、web検索で補完する。
4.同協会のホームページに出ている例題にトライしてみる。
過去問が公表されていないため、これで出題傾向を探ります。
5.出題箇所は、おのずと限られるので、これらをしっかりと暗記する。
特に、理論名、学者名は、正確に。
これでベーシックは大丈夫だと思います。
マズローやデシ、マグレガー、ハーツバーグ、ハックマンとオルダム、レヴインなどの学者の名前を問う問題も多数出てきます。
マネジメントや経営、組織にかかわっている人には、ぜひともお目通しいただきたい一冊です。
体系的な学習により、今までの知識を整理することが出来ます。
今年の最後の目標もクリア。
おいしいウイスキーで乾杯したいと思います。