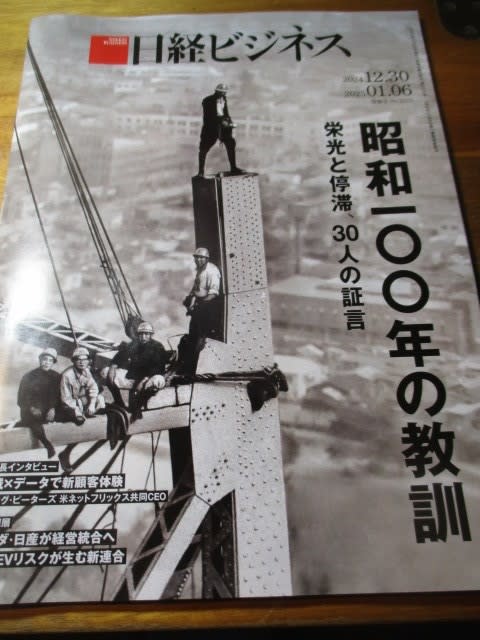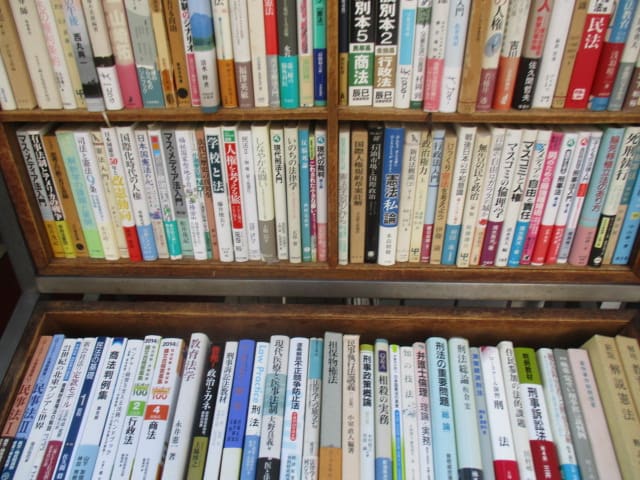パソコンのアプリやバージョンをアップして逆に使いにくくなることが多々あります。
ボタンの位置が変わったり、重くなったり、操作が複雑になったり・・・。
このため、もとのバージョンに戻すこともあります。

ランスの法則
ランスさんは、先日100歳で亡くなられた米国ジミー・カーター大統領の行政管理予算局の要職を務めた方。
政府が問題のない分野に投資していることを揶揄したところから、「ランスの法則」と呼ばれているようです。
「壊れていないなら直すな」
「物事がうまくいっているなら、へたに触るな」
我が国のものづくり精神では、常に改善、常に進化というスピリットがあるため、前へ前へという刷り込みがあります。
工業製品は、年々機能が増え、年配の人にとって使いづらいものになったり、価格が上がったりして不評なことも多々あります。

米国でコカコーラ社が味変したところコークファンから大ブーイングが起きたため、元の味に戻したという事件がありました。
アパレルのGAPが2010年にロゴを変えたところ、GAPファンからバッシングを受けたため、たった1週間で元に戻したという事件もありました。
GAP社は100億円以上の損失を出し、担当役員のクビが飛びました。
不易流行・・・。
変えていいこと悪いこと・・・見極めていかなければなりませんね。