
2026年のNHK大河ドラマは『豊臣兄弟!』で、主人公は秀吉の弟の「豊臣秀長」だ。秀長を演じるのは、仲野太賀さん。お名前のとおり、大河の主役に抜擢された。そして秀長といえば、大和郡山市の名菓「御城之口餅」、粒あんを餅で包み、きな粉をまぶした上品な和菓子である。パッケージには、
天正の頃、郡山城主豊臣秀長が兄の関白・豊臣秀吉を招き茶会を催した折り、初代菊屋治兵衛によって献上された餅菓子。その格調高い風味は代々引き継がれ、今も尚、名菓「御城之口餅」は皆様にご愛顧いただいております。
秀吉はこの菓子をたいそう気に入り、「鶯餅(うぐいすもち)」と命名した。一説には、これが全国にある鶯餅(早春の餅菓子)のルーツとも言われる。のち本家菊屋は郡山城の門を出て1軒目に位置することになり、城の入り口で売っている餅菓子なので、人々から「城之口餅」という通称が付けられ、それで「御城之口餅」という名物になったということである。

では豊臣秀長とは、どんな人物か。司馬遼太郎著『豊臣家の人々』(短編小説集)の第五話が「大和大納言」だ。Wikipedia「豊臣家の人々」に、そのあらすじが出ている。全文を抜粋すると、
他の多くの身内と同様、貧農の境遇から引き上げられた秀吉の異父弟の秀長は、粗漏な者ばかりの秀吉の一族の中で例外的に高い才覚を備えていた。独創性はないものの命ぜられたことは何でもそつなくこなし、その仕事には落ち度というものが無い。
さらにその人柄は温厚で篤実であり、弟として損な役回りを押しつけられることも多かったものの、不満を口にすることもなく黙々と兄を補佐し続けた。野心というものをまるで持たずに静かに自分を支えてくれるこの弟ほど秀吉にとってありがたい存在はなく、秀吉は秀長に対して誰よりも強い信頼を寄せた。
やがて生まれついての徳人といったその人柄は広く信望を集めるようになり、秀吉の累進に伴って舞い込むようになった無数の陳情をうまく裁き、秀長は卓抜した吏才を見せるようになる。難治で有名な紀伊国の統治もよくこなし、同じく難物で知られた大和国に移封された後は、こちらも見事に統治した。
秀吉の見る所、秀長は天性の調整家であった。大納言の官位を朝廷から賜り「大和大納言」と尊称された後も数々の政治問題をうまく処理し、「豊臣家は大納言でもっている」とまで巷間称えられるようになる。
しかし小田原征伐の直前に病に倒れ、ほどなく秀長は息を引き取る。さながら秀吉の影のように生きた弟は、兄に先立って世を去った。後年、関ヶ原の戦い前夜に豊臣家が分裂した際には、古株の家臣たちは「かの卿が生きておわせば」と早すぎるその死を惜しんだ。
奈良新聞(2024.3.22付)によると、大和郡山市は4月1日付で「大河ドラマ2026(ニーマルニーロク)係」という情報発信窓口を設置するそうだ。大河まではあと2年足らず、地元がどんな盛り上がりを見せるか、今から楽しみだ。
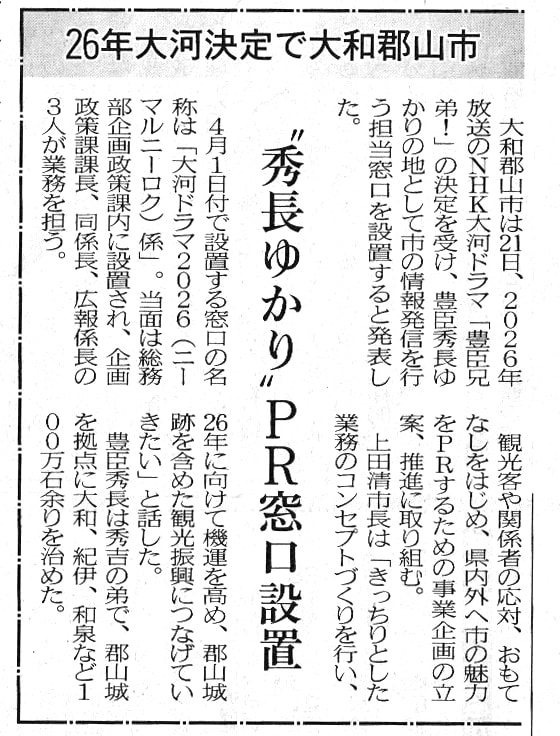
天正の頃、郡山城主豊臣秀長が兄の関白・豊臣秀吉を招き茶会を催した折り、初代菊屋治兵衛によって献上された餅菓子。その格調高い風味は代々引き継がれ、今も尚、名菓「御城之口餅」は皆様にご愛顧いただいております。
秀吉はこの菓子をたいそう気に入り、「鶯餅(うぐいすもち)」と命名した。一説には、これが全国にある鶯餅(早春の餅菓子)のルーツとも言われる。のち本家菊屋は郡山城の門を出て1軒目に位置することになり、城の入り口で売っている餅菓子なので、人々から「城之口餅」という通称が付けられ、それで「御城之口餅」という名物になったということである。

では豊臣秀長とは、どんな人物か。司馬遼太郎著『豊臣家の人々』(短編小説集)の第五話が「大和大納言」だ。Wikipedia「豊臣家の人々」に、そのあらすじが出ている。全文を抜粋すると、
他の多くの身内と同様、貧農の境遇から引き上げられた秀吉の異父弟の秀長は、粗漏な者ばかりの秀吉の一族の中で例外的に高い才覚を備えていた。独創性はないものの命ぜられたことは何でもそつなくこなし、その仕事には落ち度というものが無い。
さらにその人柄は温厚で篤実であり、弟として損な役回りを押しつけられることも多かったものの、不満を口にすることもなく黙々と兄を補佐し続けた。野心というものをまるで持たずに静かに自分を支えてくれるこの弟ほど秀吉にとってありがたい存在はなく、秀吉は秀長に対して誰よりも強い信頼を寄せた。
やがて生まれついての徳人といったその人柄は広く信望を集めるようになり、秀吉の累進に伴って舞い込むようになった無数の陳情をうまく裁き、秀長は卓抜した吏才を見せるようになる。難治で有名な紀伊国の統治もよくこなし、同じく難物で知られた大和国に移封された後は、こちらも見事に統治した。
秀吉の見る所、秀長は天性の調整家であった。大納言の官位を朝廷から賜り「大和大納言」と尊称された後も数々の政治問題をうまく処理し、「豊臣家は大納言でもっている」とまで巷間称えられるようになる。
しかし小田原征伐の直前に病に倒れ、ほどなく秀長は息を引き取る。さながら秀吉の影のように生きた弟は、兄に先立って世を去った。後年、関ヶ原の戦い前夜に豊臣家が分裂した際には、古株の家臣たちは「かの卿が生きておわせば」と早すぎるその死を惜しんだ。
奈良新聞(2024.3.22付)によると、大和郡山市は4月1日付で「大河ドラマ2026(ニーマルニーロク)係」という情報発信窓口を設置するそうだ。大河まではあと2年足らず、地元がどんな盛り上がりを見せるか、今から楽しみだ。
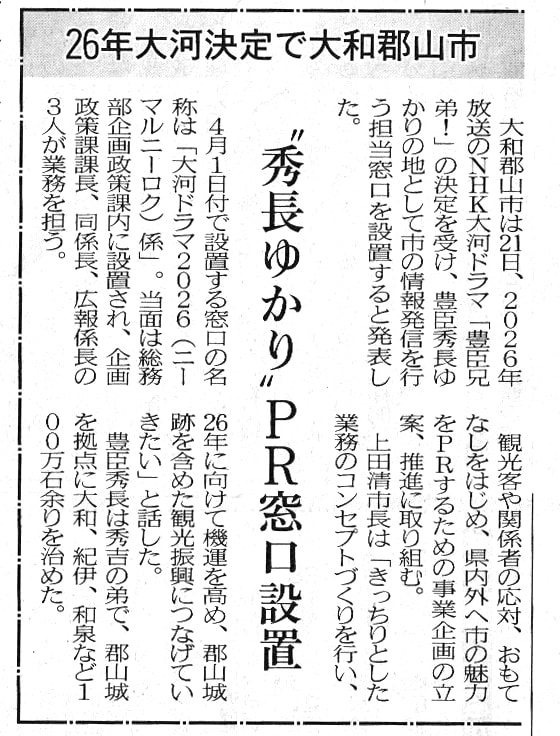



























個人的な印象ながら、地方にはその地を代表する銘菓が必ずあると思っておりまして、その地を代表する地方銀行の頭取が上京する際に手土産に使う和菓子がそれにあたるというのが自説です(少数説です・・・笑)。
かつて小生が単身赴任していた香川県には、木守(きまもり)という銘菓があり、それが百十四銀行御用達と聞いたことがあります。南都銀行さんは何をお使いなんでしょう(笑)?
> 個人的な印象ながら、地方にはその地を代表
> する銘菓が必ずあると思っておりまして…
岡本彰夫先生は、「門前に菓子なきは恥ずかし」とおっしゃいます。大きな寺社の門前では、必ず銘菓があったということで、だから奈良県内には銘菓が多いのでしょう。
> 南都銀行さんは何をお使いなんでしょう(笑)?
各部署それぞれで、あまり決めていなかったように思います。私は菊屋さんの「菊之寿」を、偏愛していました。「御城之口餅」は日持ちがしないのとボリュームがないので、相手を見て買っていました。