
(深大寺(東京都調布市)本堂横に置かれた「蓮」8月21日撮影)
現役時代から行っている「仏教の思想(全12巻、インド編・中国編・日本編各4巻)」による仏教思想の学習ですが、引退後に本格化させて、まず2回通読し、その後ポイントと思われるところの抜き書きなど要点整理のノート作りを行い、さらにそのノートを電子化(Word化)する作業をしてきましたが、先日それも終わり、当面考えていた整理が終わりました。10年ほどかかったことになります。
日本編4巻については、各ノート作成が終わった時点で、それぞれの内容の概要をこのブログでご紹介し、更にword化が終わった時点で、空海(第9巻)と親鸞(第10巻)につてはその補足説明をさせていただきました。その後、道元(第11巻)のword化が5月に、最後の日蓮(第12巻)のword化を先日終えたわけです。そこで、道元と日蓮の補足もと思ったのですが、それぞれの概要整理結果は、内容のレベルは別として、私なりに説明は尽きていると感じていて、この2巻分の補足は無しとしました。(ご興味ある方は、カテゴリー仏教思想より、それぞれ、道元、日蓮の作成ノートの要点整理をご確認ください。)
仏教思想の学習、本来の目的は「日本の仏教史」的な勉強をしてみたいというのがスタートでした。そこで、日本仏教史といった本も読んだのですが、やはり仏教史の勉強には「仏教思想」そのものの勉強が必要と、適当な本を探していたのです。そこで見つけたのが「仏教の思想(全12巻)」でした。その時はまだ単行本での発行でした。その単行本のインド編4巻分を購入して学習がスタートしたのはまだ現役時代でした。
現役時代は確か2巻分読んだ気がします。ともかく難しくてよく分からず、途中でこれはインド哲学の勉強が必要と、インド哲学史の入門書を読んだり、哲学そのものの勉強も必要と、哲学入門の本を読んだりもしましたが、結局よく分からず、現役時代が終わり、引退後、仏教の思想の学習に戻ったのです。その時には文庫本が発行されていて、12巻まとめて購入、学習再開となりました。その後は冒頭の記事のように2回通読しましたが全く理解できず、ノート作り、word化と続けて来たわけです。
で、word化が終わってどうかというと、結果、やはりよく分からいというのが答えです。ですが、日本編4巻での「空海」「親鸞」「道元」「日蓮」の4人の人物像、思想についての私なりの雑感みたいなものをお話し今日の記事とし、word化終了のまとめとしたいと思います。もっとも、学問的裏付けは全くない、個人の感想のようなものですので、その点はご承知おきください。
仏教の思想日本編4巻で取りあげられた4人の高僧ですが、空海は「中国密教」を土台とした真言密教(真言宗)、親鸞は法然の「浄土宗」を土台とした浄土真宗、道元は「中国禅」を土台とした曹洞禅(曹洞宗)、日蓮は『法華経』を土台とした日蓮宗と、それぞれ日本の各宗派の開祖として、独自思想を確立しています。したがって、個々の思想について語り出すと、これまで整理してきた内容をもう一度説明するということでもとに戻ってしまいます。
しかし、個々の思想の核心というより、視点を変えてそれぞれの人物像などをみていくと、4人の中に共通点のようなものを感じます。それは「空海」と「日蓮」、それと「親鸞」と「道元」それぞれは何やら似ている、ということです。
まず、空海と日蓮ですが、空海の曼荼羅世界と日蓮の『法華経』世界は思想的にも近いものです。空海は、仏教真理は法華ー華厳と発展し、真言密教で頂点を迎えた言っています。法然に敢然と挑んだ日蓮も最初は真言宗に対しては寛容でした。真言密教がすべての宗教を取り入れて曼荼羅世界を創造しているのに対して、法華経は他宗派を排斥するという違いがありますが、真言密教の全てを取り込んだ大日如来の曼荼羅世界は、思想的には法華の一念三千(一心に三千世界を含む)の世界と同じ世界です。
思想的にも近い両者ですが、人物像も近い気がします。それは俗な言い方をすれば「立身出世主義」ということです。両者は国家を語ります。千葉の漁師の息子という、4人の開祖者では唯一下賤な出身の日蓮は、立身出世という家族の期待を一身に受けて出家します。期待に応えるべく幕府のお膝元鎌倉で過激な活動を実行、政府に対しても働きかけます。過激なパフォーマンス、鎌倉仏教界で最後に登場したしかも下級階級の日蓮はともかく目立つ必要があったのでしょう。結果は失敗でしたが、彼にとって唯一の手段だった気がします。
一方、空海は下級階級ではありませんが、四国讃岐という地方豪族の三男の息子ということで、決して高い身分ではありません。 18歳で上京、24歳で出家宣言、31歳の時に唐への留学生としてのチャンスを得ます。当初の留学期間は20年でしたが、恵果から密教真理の習得を果たすと多くの経典、仏具などを携えてわずか2年で帰って来ます。朝廷には『請来目録』を献上、3年の準備期間ののち、京都で鎮護国家の修法を始め、朝廷特に当時の天皇嵯峨帝との結びつきを強めていきます。やがて、嵯峨帝からは京都の東寺を賜り、鎮護国家の拠点とすると同時に、許可を得て修行道場としての高野山の開発に取り組みます。こうしてみると、日蓮と反対にこの点では成功者だったわけです。
両者はまた、俗な言い方になりますが、「人たらし」の名人だったように思います。日蓮は幕府に取り入るのに失敗していますが、結果的には「日蓮宗」の開祖として大成功しています。過激な行動で、3度の襲撃、2度の流罪の苦難にあっています。当然弟子などもその苦難の影響を受けています。このため、逃げ出す弟子もありましたが、反面強固な信者も増やしていきます。特に佐渡流罪後の身延での9年間は信者獲得の期間でした。日蓮は信者にせっせと手紙をだしています。その手紙は慈愛に満ちた手紙だったようです。その結果次々と信者は増えていったのです。
空海は前述のように朝廷との結びつきを強めると同時に、当時の仏教界の支配者旧仏教(南都仏教)とも協調して布教活動を続けたといいます。平安仏教の二大巨頭といえば、空海と最澄(日本天台宗開祖)ですが、二人とも旧仏教から見れば当時の新興宗教であったわけで、排斥の対象でもあったわけです。最澄がこの旧仏教と正面衝突したのに対して、空海はいわば上手くやっていたというわけです。最澄の死後、空海のやり方を見ていた天台宗三祖円仁(慈覚大師)はこれに倣って、日本天台は密教化したといわれています。
嵯峨帝の空海に対する寵愛は特別のものがあったようです。空海は嵯峨帝に折々の贈り物をしたようです。当然それは高価なのではありません。超天才空海の本領発揮、書や詩歌でした。嵯峨帝は空海のこうした高い教養を愛したのです。

(深大寺山門の茅葺屋根)
国家主義で人たらしの空海と日蓮に対して、親鸞と道元はどうでしょうか?この両者にはそういった俗っぽさが見られません。逆に「世渡り下手」という気がします。
それは、生まれから来ているのだと思います。親鸞は幼くして親が失脚していますが、貴族の出身です。道元の父は時の最高権力者源通親でした。母が没落貴族の娘ということで、非公認の子という立場でしたが、それでも何不自由なく暮らしていました。立場の違いはありますが、二人ともいわゆるいいとこのお坊ちゃんという立場でした。
個人の性格が生まれのみで決まるものではありませんが、この二人はともかく生真面目でした。それは信仰心の深さに表れています。
親鸞は、叡山での修行で飽き足らないのを感じる中で法然の浄土教を知り、この教えに深く帰依、生涯法然の教えを信じ、それを弟子に説き続けます。その法然の教えそのものが、彼にとっての「真宗」であったわけです。親鸞の死後、親鸞の教えは「浄土真宗」という一派を成立させますが、親鸞自身の意志としては法然の教えの継承者で、一派を起こす意味での「真宗」ではなかったわけです。
親鸞について考える時、どうしても理解できないことがあります。それは「妻帯」したことです。このことは当時の仏教界では大革命だった気がします。僧は妻帯しない、これは僧としての大前提だった時代です。法然も女犯については戒めています。現実に法然の弟子の女犯の罪が原因で、流罪となった法然に連座して、当時法然の高弟でもなかった親鸞も越後への流罪となっています。それは、当時親鸞が妻帯していたことが大きな要因だったと思われます。その親鸞、流罪先の越後でも妻帯しています。残念ながら、「仏教の思想」の中では、妻帯し子供がいたという事実は書かれていますが、その理由・背景などは全く触れられていません。当然、私にも全く分かりませんが、単純に彼の生真面目さから来ているのかと、かってに想像しています。つまり、「誰でも、信ずる者は救われる。浄土に行ける。」「悪人正機」ということだったのかと。
いずれにしろ、親鸞の妻帯についてはもう少し調べてみる価値はありそうです。
一方、道元はどうだったでしょうか。道元も叡山での修行に疑問を感じます。当時の叡山は仏教大学といった場所でしたが、その根本思想は「天台本覚思想」というもので、それは「人は生まれながらにさとっている」というものでした。若い道元はこの思想に疑問を感じます。それは「さとっているのにどうして修行が必要か?」というものでした。その答えは叡山では得られなかったのです。そしてこの答えを得ることが道元の一番の課題となったのです。
大権力者の息子という超おぼちゃまの道元、没落貴族の子で苦労して我慢強さが備わった親鸞が叡山で20年修行したのに対して、そこは我慢が効かず、2年で叡山を下り栄西の下に。そして栄西の弟子明全のもとで修行後、明全とともに宋にその答えを求めて渡ります。
道元は、正師、正法を求めて諸方遍歴、修行の旅をします。そして、遍歴ののち最初の修行の地天竜山に戻ってついに正師如浄に出会います。そして、如浄より正法を得た道元は2年後帰国します。その時、道元は「空手還郷(くうしゅげんきょう、手ぶらで帰るの意味)」と語っています。『正法を得て帰ってきたから、経典などはいらない!』ということだったのでしょうか?経典や仏具をいっぱい持ち帰って、こんなに頑張ってきました、とアピールした空海とは真逆です。生真面目そのものです。
結局、この生真面目さというか、融通の利かないことが結果として、彼の布教の妨げとなります。京都での彼の布教は当初順調でしたが、出る杭は打たれるということでしょう、朝廷と結んだ臨済禅などの圧力を受けて、越前の地へと逃れることとなりました。
越前永平寺での道元はそれまでの一般大衆への布教から、弟子の育成へ、そして彼の思想をまとめた日本史上に燦然と輝く哲学書『正法眼蔵』の執筆に力を入れます。この著作は、「さとっているのにどうして修行が必要か?」という彼の疑問に対する、「只管打坐」(ただただひたすら坐禅をする)そして「証上の修(しょうじょうのしゅ)」(さとったものがさらに修行すること)という道元自身が修行の結果得た答えを、論理的に解説したものです。仏教の思想では『正法眼蔵』の全ての説明があるわけではありませんが、それでも難解で、今もよく分かっていません。ただ、道元はともかく自分が知ったことを文章でとことん説明したかったのだと思います。ここにも彼の生真面目さが十分出ていると思います。永平寺の修行は、現在にも通じるものですが、食事の仕方など全てにルールがあり、ともかく厳しいものだったようです。そこにも道元の性格が表れています。
浄土真宗の開祖親鸞、曹洞宗の開祖道元、ともに今日の日本を代表する仏教宗派の開祖として尊敬されています。しかし、親鸞は越後への流罪の赦免後数年して現在の千葉県で、約20年布教を行い、やがて結果30年に及びますが、60歳で京都に隠棲しています。地方での布教、中央では無名といっていい親鸞、しかも自ら一派を起こそうという気が全くなかった親鸞が、今日大宗派の開祖にという疑問が起こります。
道元も同様です。厳しい修行で弟子がいつかず、道元の愛弟子といえるのは『正法眼蔵随聞記』を書いた懐奘一人だけ、弟子のほとんどは他宗派から帰依した弟子でその数も少なかったといいます。
つまりは、宗派の成立、さらに隆盛という点では、早い話「弟子が偉かった」と言えそうです。この点では空海と日蓮がそれぞれ弟子の育成、宗派の基礎の確立に力を注いだのと、この二人の開祖とは対照的です。親鸞と道元は「祭り上げられた開祖」とも言えそうです。
と、簡潔に説明できないためやたら長くなりましたが、日本編の四人の人物を思想を勉強する中で感じてきたとことを、勝手な解釈でお話ししてみました。
さらに、ざっと区分してみると、平安仏教の空海、鎌倉仏教の親鸞、道元、日蓮という分け方も出来そうですが、それは同時に前者(空海)は理論仏教、後者は実践仏教(親鸞、道元、日蓮)という区分にもなる気がします。
インドから中国に渡って日本にもたらされた仏教ですが、山のような経典や思想が同時に入ってきた中国で、一度整理され主な宗派として「天台(法華)宗」「華厳宗」「禅宗」「浄土宗」が成立します。前2者は理論仏教、後2者は実践仏教に分類されます。仏教の思想日本編には登場しませんが、日本天台宗の開祖最澄により、中国天台と中国華厳は統合され「天台本覚思想」として日本において完成します。同じく空海も当時中国では主流ではなかった「密教」を日本に持ち帰り「真言密教」として日本で完成させます。
つまり、仏教はインドから中国での整理を経て日本渡り、日本において理論的、哲学的な意味において最澄、空海によって完成します。さらに、それらの理論仏教を特に最澄の日本天台に学んだ鎌倉仏教の開祖たちが、実践仏教として日本全国に広めたと言えそうです。もっとも、道元の著作『正法眼蔵』は哲学書といえるもので、禅という範疇を超え、仏教思想の集大成ともいえる理論書という評価がこの仏教の思想(第11巻)ではされています。
と、最後に蛇足のまとめをしてみました。長々となり、最後まで読んでいただいた方には感謝というよりお詫びをしたい気持ちです。ありがとうございました。
で、一応最初の目標の「仏教の思想(全12巻)」の整理は終わりましたが、これが主目的ではありません。「日本仏教史」の勉強の方に主体を移したいと思います。
ただ、その前に、中国編の整理をもう一度と思っています。それは、中国編は日本編のように高僧個人ではなく、宗派別(天台、華厳、禅、浄土)になっていて、多くの高僧が登場します。それらの高僧の関係を年表形式で一度整理しておきたいと思っています。
それと、日本編には「法然」と「最澄」は登場しません。やはり日本仏教史の上では外せない二人です。この二人の勉強も並行にできればと思っています。その後については、またその時考えます。ということで、どうやら終わりは見えないですね。











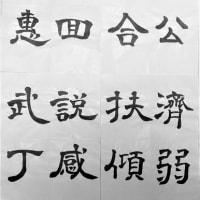
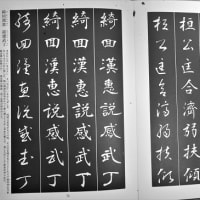








いただきありがとうございます。
仏教の学習というレベルで、研究、まして論文などというものを
これからまとめようとは全く思っていません。
ただ、仰るように、インドで成立した仏教、そのインドでは
13世紀で衰退、中国で事実上整理されますが、これも
儒教や特に道教に吸収合併され、大きく発展せず、
日本に渡って、定着したと言えます。
その仏教も明治政府の神道重視で破壊されたのは
文化的には暴挙だったと思います。
それでも、やはり神道とともに日本は仏教国、
身近な仏教を日本人として少しは語れないとまずいかな、
そんなつもりで勉強しています。
ということで、これからも楽しんで学びます。
次の整理が終わったらまたご紹介したいと思っています。
その時はまたお付き合いください。よろしくお願いいたします。
仏教の思想・・インドで生まれた仏教が
大陸を渡ってこの日本に・・そして純粋な
仏教らしい仏教は東の果てのこの日本で
一番仏教らしく今に残っていると思います
今の時代ですから・・信教の自由は何処も
一緒です、ですが宗教はある意味非常に
重要な社会活動とされます。人間の争い
ごとは、同じ民族であっても宗教の違いで
社会や文化や伝統が違って、争ったり戦争
を起こしたり今でも延々と続いています
その根源についてを この仏教の思想を
通じて探求される・・これは大変な作業
ですが・・意義のあるものと信じます
日本人として・・いつも困った時お願いする時「神様仏様」・・と手を合わせる
その文化の根源を・・期待するものです一言二言で語られることではないでしょうが
これが纏まれば、必ず歴史の中で後世の
者たちに理解されることでしょう。
今は一度だけ拝見しましたが・・
今夜もう一度ゆっくり読ませて頂きます
ありがとうございました、そしてお疲れさまでした