22日にミシュランガイド東京版が出版されて、日本で大きな話題になっていたようですが、フランスでの報道や、いかに―――。

東京のレストランが獲得した星の総数は191、パリの97、ニューヨークの54を大きく上回っています。食においても世界の中心と自負しているのではないかと思われるフランスがどう反応するのか・・・楽しみにしていたのですが、23日のフィガロ紙が早速半ページを割いて紹介してくれました。
見出しは、「東京、世界における食の新たな中心」。どうもミシュランガイドの評価をそのまま認めているようですね。ミシュランの評価を評価する記事や評論家が日本では多いようですが、フランスの新聞はどう見ているのでしょう。
各レストランの評価は、5人の調査員が行ない、しかも公正を期すため、シェフや評論家などを交えての議論を経た上で、今回の発表となっている。ミシュランガイドのような評価を批判していた小野氏の店、つまり「すきや橋 次郎」も三ツ星を獲得していることからも、その公平さは理解できるだろう・・・ということで、ミシュランのアジア戦略の一環から星のインフレがなされたとかいったことはこの記事からはうかがい知ることはできません。素直に喜んで良いようですね!!
ところで、ご紹介している記事はフランスの読者へ向けてのものですから、東京版への評価でおしまいではなく、フランスの食文化に対する意見がしっかり述べられています。具体的には・・・
パリは今でも食の中心なのだろうか。ガーディアン紙のようなアングロ=サクソンの新聞は、フランスのレストランはその伝統に押しつぶされており、パリはもはや食の都たりえない、といったことをすでに10年も前から言っている。どんなに輝かしい料理であろうと、その伝統をただ守るだけでは、より豊かな食文化たりえない。しかし、多くの人がフランス料理には、いわゆる伝統の味を求めるため、礼賛されればされるほど旧態依然としてしまうというパラドックスに陥っている。
ロンドンやニューヨークは、娯楽、つまりエンターテインメントとしての新しい食文化で盛り上がっており、その流れは世界中に広がっている。そうした流れの中で、今なぜ東京でミシュランガイドを出すことにしたのか。それは、食にかける日本人の情熱とそこにある食のバラエティによるためである。
日本人の食に対する情熱はほとんど宗教への情熱と同じで(そう考えるためでしょうか、東京版の出版記念行事、まるで神事のようですね・・・記事中の写真)、例えば、ジャン=ポール・エヴァンのショコラ・ショー(ホットココア)のためになら3時間の行列だって厭わないほどだ。また、築地市場を歩けば数多くの魚が取引されているのを目にするが、ここで扱われる魚の量は1日で250万トン。パリのランジス(Rungis)市場ではわずか一万分の一の255トン。また、レストランの数自体にも大きな差がある。東京には138,000軒ものレストランがあるのに対し、パリには十分の一以下の12,500軒。しかも東京には世界中の料理がそろっている。イタリア料理にしても、シシリー、ナポリ、トスカーナなど各地方の料理さへ堪能できる程。和食にしても、懐石、寿司、ラーメン、蕎麦、うどん、焼き鳥などと多くの種類があり、そのいずれもが素晴らしい味である。
こうしたバラエティの豊かさは、日本人の好奇心の強さ、特に外国のものに対する関心、受容性の高さによるところが大きい。しかも、完璧さへの希求、特に食においてはその素材へのこだわり、調理の技の研鑽ぶりには驚嘆すべきものがある。日本にかつて貼られていた「モノマネ」のレッテルは、もはや通用しない。フランスも、日本を見習うべきだ!
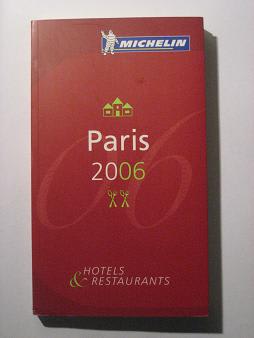
(これは、2006年のパリ版。東京版では、TOKYO 2008になっているのでしょうね)
まさに、人のふり見て我がふり直せ。今回のミシュランガイド東京版からのメッセージは、他所からの栄養を受け入れた食文化は強い―――確固たる文化は異なる文化を受け入れてもそのアイデンティティを失わないはず。より豊かな食文化になるためには、異なる食文化を受け入れることに躊躇すべきではない。そのことを実践している日本の食文化が賞賛されるのは至極当然のことで、フランスも見習うべきだ!
どうやら、この記事が言いたいのは、伝統を守るためにこそ、変革が必要だ、ということのようですね。伝統の上に胡坐を掻いていては、いずれ廃れてしまう。伝統を守るためにこそ、常に新しいものを受け入れ、変革を遂げていかねばならない・・・日本でも、このことを肝に銘じないといけない分野が多くあるような気がします。伝統、しきたり、前例・・・「食」の分野がたまたま例外なのでは、と思えるほどですね。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ

東京のレストランが獲得した星の総数は191、パリの97、ニューヨークの54を大きく上回っています。食においても世界の中心と自負しているのではないかと思われるフランスがどう反応するのか・・・楽しみにしていたのですが、23日のフィガロ紙が早速半ページを割いて紹介してくれました。
見出しは、「東京、世界における食の新たな中心」。どうもミシュランガイドの評価をそのまま認めているようですね。ミシュランの評価を評価する記事や評論家が日本では多いようですが、フランスの新聞はどう見ているのでしょう。
各レストランの評価は、5人の調査員が行ない、しかも公正を期すため、シェフや評論家などを交えての議論を経た上で、今回の発表となっている。ミシュランガイドのような評価を批判していた小野氏の店、つまり「すきや橋 次郎」も三ツ星を獲得していることからも、その公平さは理解できるだろう・・・ということで、ミシュランのアジア戦略の一環から星のインフレがなされたとかいったことはこの記事からはうかがい知ることはできません。素直に喜んで良いようですね!!
ところで、ご紹介している記事はフランスの読者へ向けてのものですから、東京版への評価でおしまいではなく、フランスの食文化に対する意見がしっかり述べられています。具体的には・・・
パリは今でも食の中心なのだろうか。ガーディアン紙のようなアングロ=サクソンの新聞は、フランスのレストランはその伝統に押しつぶされており、パリはもはや食の都たりえない、といったことをすでに10年も前から言っている。どんなに輝かしい料理であろうと、その伝統をただ守るだけでは、より豊かな食文化たりえない。しかし、多くの人がフランス料理には、いわゆる伝統の味を求めるため、礼賛されればされるほど旧態依然としてしまうというパラドックスに陥っている。
ロンドンやニューヨークは、娯楽、つまりエンターテインメントとしての新しい食文化で盛り上がっており、その流れは世界中に広がっている。そうした流れの中で、今なぜ東京でミシュランガイドを出すことにしたのか。それは、食にかける日本人の情熱とそこにある食のバラエティによるためである。
日本人の食に対する情熱はほとんど宗教への情熱と同じで(そう考えるためでしょうか、東京版の出版記念行事、まるで神事のようですね・・・記事中の写真)、例えば、ジャン=ポール・エヴァンのショコラ・ショー(ホットココア)のためになら3時間の行列だって厭わないほどだ。また、築地市場を歩けば数多くの魚が取引されているのを目にするが、ここで扱われる魚の量は1日で250万トン。パリのランジス(Rungis)市場ではわずか一万分の一の255トン。また、レストランの数自体にも大きな差がある。東京には138,000軒ものレストランがあるのに対し、パリには十分の一以下の12,500軒。しかも東京には世界中の料理がそろっている。イタリア料理にしても、シシリー、ナポリ、トスカーナなど各地方の料理さへ堪能できる程。和食にしても、懐石、寿司、ラーメン、蕎麦、うどん、焼き鳥などと多くの種類があり、そのいずれもが素晴らしい味である。
こうしたバラエティの豊かさは、日本人の好奇心の強さ、特に外国のものに対する関心、受容性の高さによるところが大きい。しかも、完璧さへの希求、特に食においてはその素材へのこだわり、調理の技の研鑽ぶりには驚嘆すべきものがある。日本にかつて貼られていた「モノマネ」のレッテルは、もはや通用しない。フランスも、日本を見習うべきだ!
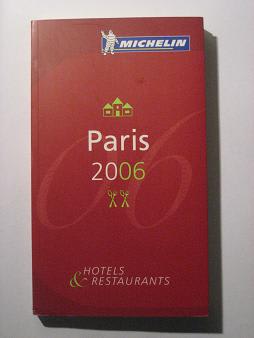
(これは、2006年のパリ版。東京版では、TOKYO 2008になっているのでしょうね)
まさに、人のふり見て我がふり直せ。今回のミシュランガイド東京版からのメッセージは、他所からの栄養を受け入れた食文化は強い―――確固たる文化は異なる文化を受け入れてもそのアイデンティティを失わないはず。より豊かな食文化になるためには、異なる食文化を受け入れることに躊躇すべきではない。そのことを実践している日本の食文化が賞賛されるのは至極当然のことで、フランスも見習うべきだ!
どうやら、この記事が言いたいのは、伝統を守るためにこそ、変革が必要だ、ということのようですね。伝統の上に胡坐を掻いていては、いずれ廃れてしまう。伝統を守るためにこそ、常に新しいものを受け入れ、変革を遂げていかねばならない・・・日本でも、このことを肝に銘じないといけない分野が多くあるような気がします。伝統、しきたり、前例・・・「食」の分野がたまたま例外なのでは、と思えるほどですね。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ




















先日、「日本はダメ出し社会。新しいことをやろうとすること自体が罪とみなされる」という一文を新聞(確か朝日)で読みました。新しいことの善悪の判断は難しい。でも「やってみなはれ」という人が多い社会のほうが、いいものができそうな気がしますね。
ある程度信頼できる客観的なものさしが出来た。あとは自分のものさし(舌、好み)とどう兼ね合いを取っていくかではないかと思っています。ミシュランを金科玉条のごとく鵜呑み、丸呑みするのも寂しい気がしますし、かといって無視もできず・・・
フランシス・レイが先日・・・「寿司・刺身が大好き
で、パリの日本レストランは全部知っています」と
語っておられるのを聞いて、鳥肌が立つほど?嬉しかったですネ♪ 外国に住んでいると、妙に愛国心が強くなり、自分のことをホメラレルより嬉しいですネ。
ところで、私はお刺身が苦手なんですが・・・。
刺身が苦手な日本人・・・周囲のフランス人、ビックリしませんか。でも、辛いモノが嫌いなタイ人とかもいますし、好みですよね。フランスにいても刺身や寿司が恋しくならなくて、ラッキーですね。
ムッシュ ビバンダム セントラルトウキョウだけで、星乱発
ですよ、23区全域と多摩地域を入れたらどう
なるのですか? それと関西地区はどうします。
水の違いでダシも東と西では変わる食文化の
奥深さを今更うんぬんと言いたくありません。
2009年版の覆面調査員の方々、空気まで味に
してしまう納豆を是非ご賞味あれ・・・・
ヒキワリは秋田に行って食べてください。
ご意見、ミシュランに届くと良いですね。
今後も、ご訪問よろしくお願いします。
様々な新しい物を取り入れ、良い物だけを残していく
そしてそれが受け継がれていく事で歴史や伝統となるのである
墨守しているだけでは何も守れない