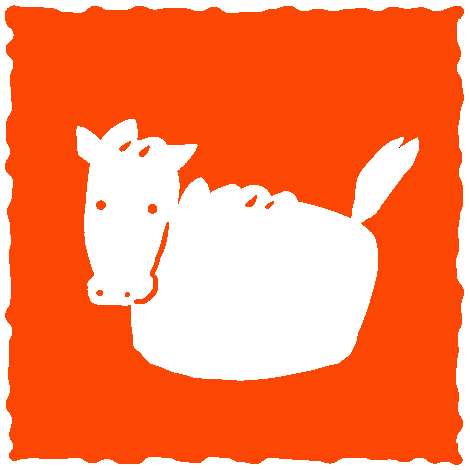お寺から少し上った所に大鶴という地区があります。
そこに「マー棟梁」と言う大工さんが住んでいます。
元々この大鶴地区はトンチ好きな方々が多くて、
棟梁も昔の人の格言などを面白く話してくれます。
大鶴には「延命庵」と言うお地蔵さまをお祀りしている
お堂があります。
大鶴集落の墓地はこの延命庵の裏に共同墓地として
あります。
法事の後には、お墓参りをするのですが、
束になった線香にはなかなか火が着きません。
モタモタしていると「線香と女性は帯を取らないと燃えない」と
すかさず奇妙な格言が飛びます。

線香を束ねている帯封があると火が着きにくく
帯を取って線香をバラバラにすると空気の通りがよくなって
すぐに火が着きます。
「女性も帯を取ると燃える」は言わずともお分かりだと思います。
ただ、ご先祖の眠るお墓の前での「格言」としては、いかがなものか・・
誰が言い出したのか聞いて見ると・・・
どうも私の父(豊嶽和尚)が度々お墓で言っていたと聞かされ
ぐうの音もでなかった事がありました。
マー棟梁は、盆彼岸や年末年始の菩提寺参りは欠かした事はありません。
そんなマー棟梁の格言が「突っ張りと信心は遠い方が効く」と言うものです。
大工さんらしく、傾いた家を支える「突っ張り棒」はなるべく
家から離した方が効きが良い。
信心(ご利益)も近くの神社仏閣よりも遠くに出かけて
お願いする方がご利益がありそうだ言うことらしいのです。
もっともだと思いました。
豊嶽和尚が元気な頃に、大般若で「星祭り(42才の厄除け)」をして欲しいと
言う檀家さんがいました。
豊嶽和尚は「どこか、おがみ屋さんか宣伝しているお参り屋さんでもお願いしてみてください」と
断ったらしいのです。
すると男性は
「普段お参りもしない寺院の仏さまが私を救ってくれるとは思えません。
家族が朝晩お参りしているご先祖さまだったら、必ず災いを除いてくれると思います。
だから、私のご先祖さまをお祀りしている菩提寺で厄除けを受けたいのです。」と望んだと言います。
それがきっかけで「厄除け札」を作るようになりました。
先代が作っていた木札を今でも一枚一枚作ります。

印刷ではなくて手書きのお札です。時間がかかります。
20日の大般若会にお供えしてご祈祷札になります。

遠くの神社仏閣よりも近くの菩提寺ではいかがですか?
大鶴地区の格言は他にもたくさんあります。
私のお爺さん(千巌和尚)は、私と違って顔が長面でした。
そんな千巌和尚を大鶴では
「あごの先から見上げれば、頭のてっぺん明日の朝」と言っていました。
そんなに長くはなかったのですが・・・。