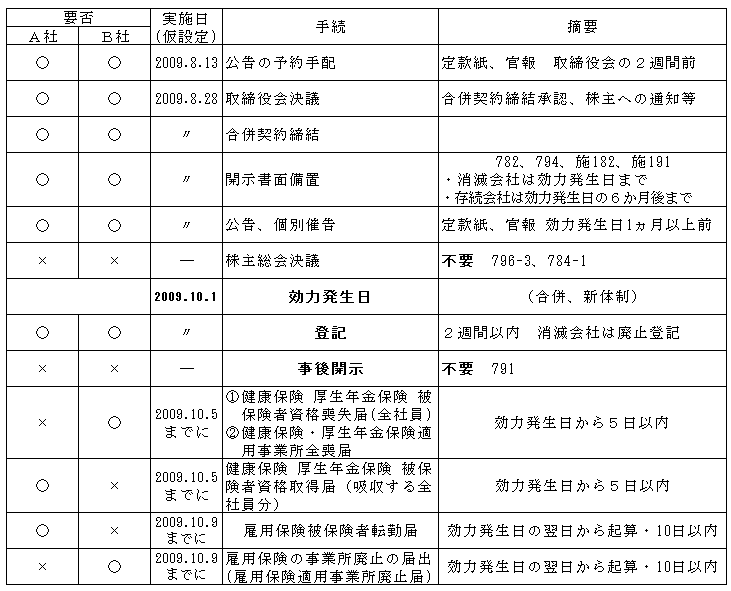就業規則の規程により功労者を表彰し、副賞としてQUOカードを贈呈するのだが、このQUOカードの経理処理と受賞した人の税務処理について教えて貰いたいとの質問がありました。
報奨金(QUOカードなどの金券を含む)の支給であれば、会社としては〔販売費及び一般管理費又は労務費〕(分類)の〔福利厚生費〕(科目)で処理します。
通常の勤務に対する功労賞であれば、受賞者本人には給与と同様の扱いになりますので、源泉徴収の必要があります。
受賞者本人の税務処理については、所得税基本通達「法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係(使用人等の発明等に係る報償金等)23~35共-1」で以下のように規定されています。
事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約などに寄与する工夫、考案などの提案をした人に支払う報奨金(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る)については、
(1)その工夫、考案などがその人の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得
(2)その他の場合には一時所得
(3)継続的に支払われるものは雑所得
となります。
“通常の職務の範囲内の行為”とは、事務や作業の合理化などに寄与する工夫、考案などを、通常の職務をしている人が行うことをいいます。
一般的に、提案制度に基づく工夫、考案などが通常の職務の範囲内の行為として行われることは少ないと思われますので、多くの場合、報奨金は一時所得となります。
即ち、日常業務に関連した報奨金であれば給与として源泉税の対象となり、日常業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。
報奨金贈呈後の直近支給給与に、報奨金額を含めて処理します。
報奨金が現物給与である限り、支払時の源泉徴収が原則となります。
報奨金が『現金』であるか『金券』であるかによって、処理の仕方に少し違いがあります。
1.報奨金を渡すときに仮で源泉税を引いて支給。その後、年末調整時に本来の報奨金額の収入と仮で引いた源泉の支払があったとして、年末調整時に清算する。
2.報奨金はそのままの金額を支給して直後の給与支給時に現物支給があったとして課税対象額に報奨金の金額を加えて計算する。
一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年20万円以下であれば申告の必要が有りません。
ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て含めて申告する必要が有ります。
<参考>
国税庁サイト:通達目次/所得税基本通達