
★ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番・ピアノ・ソナタ『悲愴』
(演奏:アンナ・ゴウラリ(p)、コリン・デイヴィス指揮 ドレスデン・シュターツカペレ)
1.ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
2.自作主題による32の変奏曲
3.ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 『悲愴』
(2001年録音)
類稀なピアノの演奏技術のみならず、類稀な美貌を持ち合わせてスクリーンでも活躍したアイリーン・ジョイス。
彼女のリサイタルでは曲ごとにドレスを着替えたり、いろんな演出が試みられていたようです。
まぁ私なんかは脳天気に「おー・おー(^^)/」なんて喜んじゃうんでしょうけど、一途な音楽愛好家からすれば「ぶー・ぶー」と言いたくなるような振る舞いだったことも十分理解できるところではあります。
私はこのゴウラリというピアニストをディスクの演奏上でしか知らないのですが、ジャケットを見た瞬間にアイリーン・ジョイスのイメージが浮かびました。
このディスク自体が“インヴィンシブル”という映画のサウンドトラックのようでもあり、どうやらピアニスト自身がピアニスト役で出演しているためにこのようなジャケットになったらしいこともアイリーン・ジョイス連想の裏打ちとなりました。
さてさて、それでは演奏はどうなのか?
・・・・・・・・・・これが実に何とも味わいのある演奏なのです。
このベートーヴェンに関して言えば、決して大きく飛翔したり突き抜けたり、かといって深く内面に沈潜するような演奏ではありません。
では平凡な演奏家というと、決してそうではない。。。
サー・コリン・デイヴィスの棒は、いつもながらオーソドックスでありながら非常に端整で美しい伴奏をつけていますが、先に述べたようにピアニストがその演奏に乗って声高に叫ぶわけではありません。
むしろどちらかといったら慎ましい演奏と言ってよいでしょう。
でも、不思議とちゃんと映えてるんです。これ以上論評のしようがありません。(^^;)
“悲愴ソナタ”の演奏もコンチェルト同様に端整で慎ましくありながらも、決して退屈させないもの・・・。
では、何に魅かれるか・・・それがうまく説明できないというか、よく判ってない?
敢えて何とか理由付けするとすれば、どんなに目だなくても音楽に常に推進力があるということでしょうか・・・。
積極的に前に進んでいこうとしていることだけは、よ~くわかります・・・けどそれだけなのかなぁ~。(^^;)
まだなんかあるような気がするんだけど。。。
ゴウラリは1972年生まれのロシアのピアニストとライナーにありました。
ということはもはや駆け出しではないでしょうが、若手であることに間違いない奏者による演奏ではあり、確かに爽快感というか、演奏に新味を感じないわけでもありません。
でもどちらかというと、落ち着きと抑制の中でのトータルな完成度を感じさせるところが只者ではない・・・。
他の作曲家の場合ではどんな演奏を聴かせてくれるのかが、とても気になるピアニストであります。
★アンナ・ゴウラリ・スピールト・ショパン
(演奏:アンナ・ゴウラリ)

1.スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20
2.スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
3.スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39
4.スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54
5.幻想曲 ヘ短調 作品49
6.ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1
7.華麗なる大ワルツ ヘ長調 作品34-3
(2001年)
ゴウラリの魅力はむしろこのショパンでのほうが顕著かもしれません。
総論的な特長はベートーヴェン同様、突き抜けるようなスケール感はないけれどこじんまりまとまるというものではなく、音価・リズムを自在に伸縮させながら曲の中でのパートごとにコントラストを明確につけることで楽しませてくれる・・・とでも言いましょうか。
であるとすれば、当然ベートーヴェンのようなかっちりした音楽よりショパンの方が効果を発揮しやすいのでしょうが、果たしてそのとおり大変魅惑的なショパンになっています。
ゴウラリ節とでも言ったらいいのでしょうか?
まず、かなりの運動性能を秘めた指の廻りを武器にしていることがスケルツォ第1番冒頭から明らかにされています。
そして、巧みなペダル操作により背景となる音に深く淡く靄をかけるテクニックとか、またそのタイミングの自在性とか、ベートーヴェン演奏でも指摘した推進性、あるいは拍節の内でのフレーズの伸縮性などこの人ならではの一貫した味付けがちゃんとある・・・。
殊にフレージングの尻尾を、ジャケットの風貌よろしく神経質なネコがささっと身を翻すように短い間に押し込めることでコケティッシュな魅力を放つなど、これも確信犯であろうとはいえ効果を挙げていることは間違いないでしょう。
おじさん、とりわけ鼻の下の筋肉が弛緩しがちなオジサマ相手には特に有効かもしれません。(^^;)
そんなこんなで私には特に晴朗なスケルツォ第4番などでは、これまでに聴いたことがないような演奏効果を挙がっているように聴こえます。
幻想曲、ワルツと尻上がりに華やかさが増し(かといってやはり天空に飛翔するようなイメージはないんですけど)、賑々しく終わるのも健康的な趣向であると思います。
とにかく聴けば聴くほど味わいがスルメのように増してくるのも、この人の演奏の得がたい特長。
ただし裏を返せば、カキーンと抜けた演奏を聴きたい時にはチョイスしにくいピアニストであるのは・・・これは仕方ないのかもしれませんな。(^^;)
蛇足にして細かい話ですが、1番印象に残っているのは実はスケルツォ第1番の最後の2和音が楽譜より1オクターブ高いのか?
それとも楽譜どおりであったとしても際立たせている音が、高音側なのか・・・要するに最後の音が通常より高く感じたということです。
これによりやや攻撃的な終わり方ではあっても、落ち着きのない終わり方に思えました。
こんなこと、気にしなきゃいいのにねぇ~・・・と思いつつ、そういった瑣末なことを往々にして気にする私には自己コントロール力が欠けているのかもしれません。(>_<)
(演奏:アンナ・ゴウラリ(p)、コリン・デイヴィス指揮 ドレスデン・シュターツカペレ)
1.ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
2.自作主題による32の変奏曲
3.ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 『悲愴』
(2001年録音)
類稀なピアノの演奏技術のみならず、類稀な美貌を持ち合わせてスクリーンでも活躍したアイリーン・ジョイス。
彼女のリサイタルでは曲ごとにドレスを着替えたり、いろんな演出が試みられていたようです。
まぁ私なんかは脳天気に「おー・おー(^^)/」なんて喜んじゃうんでしょうけど、一途な音楽愛好家からすれば「ぶー・ぶー」と言いたくなるような振る舞いだったことも十分理解できるところではあります。
私はこのゴウラリというピアニストをディスクの演奏上でしか知らないのですが、ジャケットを見た瞬間にアイリーン・ジョイスのイメージが浮かびました。
このディスク自体が“インヴィンシブル”という映画のサウンドトラックのようでもあり、どうやらピアニスト自身がピアニスト役で出演しているためにこのようなジャケットになったらしいこともアイリーン・ジョイス連想の裏打ちとなりました。
さてさて、それでは演奏はどうなのか?
・・・・・・・・・・これが実に何とも味わいのある演奏なのです。
このベートーヴェンに関して言えば、決して大きく飛翔したり突き抜けたり、かといって深く内面に沈潜するような演奏ではありません。
では平凡な演奏家というと、決してそうではない。。。
サー・コリン・デイヴィスの棒は、いつもながらオーソドックスでありながら非常に端整で美しい伴奏をつけていますが、先に述べたようにピアニストがその演奏に乗って声高に叫ぶわけではありません。
むしろどちらかといったら慎ましい演奏と言ってよいでしょう。
でも、不思議とちゃんと映えてるんです。これ以上論評のしようがありません。(^^;)
“悲愴ソナタ”の演奏もコンチェルト同様に端整で慎ましくありながらも、決して退屈させないもの・・・。
では、何に魅かれるか・・・それがうまく説明できないというか、よく判ってない?
敢えて何とか理由付けするとすれば、どんなに目だなくても音楽に常に推進力があるということでしょうか・・・。
積極的に前に進んでいこうとしていることだけは、よ~くわかります・・・けどそれだけなのかなぁ~。(^^;)
まだなんかあるような気がするんだけど。。。
ゴウラリは1972年生まれのロシアのピアニストとライナーにありました。
ということはもはや駆け出しではないでしょうが、若手であることに間違いない奏者による演奏ではあり、確かに爽快感というか、演奏に新味を感じないわけでもありません。
でもどちらかというと、落ち着きと抑制の中でのトータルな完成度を感じさせるところが只者ではない・・・。
他の作曲家の場合ではどんな演奏を聴かせてくれるのかが、とても気になるピアニストであります。
★アンナ・ゴウラリ・スピールト・ショパン
(演奏:アンナ・ゴウラリ)

1.スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20
2.スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
3.スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39
4.スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54
5.幻想曲 ヘ短調 作品49
6.ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1
7.華麗なる大ワルツ ヘ長調 作品34-3
(2001年)
ゴウラリの魅力はむしろこのショパンでのほうが顕著かもしれません。
総論的な特長はベートーヴェン同様、突き抜けるようなスケール感はないけれどこじんまりまとまるというものではなく、音価・リズムを自在に伸縮させながら曲の中でのパートごとにコントラストを明確につけることで楽しませてくれる・・・とでも言いましょうか。
であるとすれば、当然ベートーヴェンのようなかっちりした音楽よりショパンの方が効果を発揮しやすいのでしょうが、果たしてそのとおり大変魅惑的なショパンになっています。
ゴウラリ節とでも言ったらいいのでしょうか?
まず、かなりの運動性能を秘めた指の廻りを武器にしていることがスケルツォ第1番冒頭から明らかにされています。
そして、巧みなペダル操作により背景となる音に深く淡く靄をかけるテクニックとか、またそのタイミングの自在性とか、ベートーヴェン演奏でも指摘した推進性、あるいは拍節の内でのフレーズの伸縮性などこの人ならではの一貫した味付けがちゃんとある・・・。
殊にフレージングの尻尾を、ジャケットの風貌よろしく神経質なネコがささっと身を翻すように短い間に押し込めることでコケティッシュな魅力を放つなど、これも確信犯であろうとはいえ効果を挙げていることは間違いないでしょう。
おじさん、とりわけ鼻の下の筋肉が弛緩しがちなオジサマ相手には特に有効かもしれません。(^^;)
そんなこんなで私には特に晴朗なスケルツォ第4番などでは、これまでに聴いたことがないような演奏効果を挙がっているように聴こえます。
幻想曲、ワルツと尻上がりに華やかさが増し(かといってやはり天空に飛翔するようなイメージはないんですけど)、賑々しく終わるのも健康的な趣向であると思います。
とにかく聴けば聴くほど味わいがスルメのように増してくるのも、この人の演奏の得がたい特長。
ただし裏を返せば、カキーンと抜けた演奏を聴きたい時にはチョイスしにくいピアニストであるのは・・・これは仕方ないのかもしれませんな。(^^;)
蛇足にして細かい話ですが、1番印象に残っているのは実はスケルツォ第1番の最後の2和音が楽譜より1オクターブ高いのか?
それとも楽譜どおりであったとしても際立たせている音が、高音側なのか・・・要するに最後の音が通常より高く感じたということです。
これによりやや攻撃的な終わり方ではあっても、落ち着きのない終わり方に思えました。
こんなこと、気にしなきゃいいのにねぇ~・・・と思いつつ、そういった瑣末なことを往々にして気にする私には自己コントロール力が欠けているのかもしれません。(>_<)











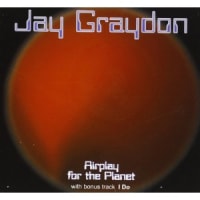
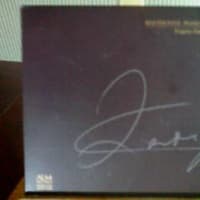
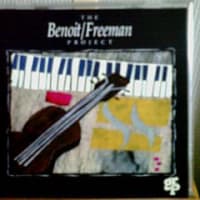
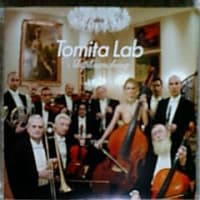
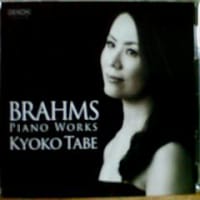

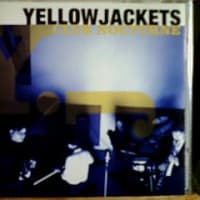


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます