
★シューベルト:ピアノ・ソナタ D.960&D.664
(演奏:高橋 アキ)
1.ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D.960(遺作)
2.ピアノ・ソナタ 第13番 イ長調 D.664 作品120
(2007年録音)
高橋アキさんの演奏に初めて触れたのは、一柳慧さん作曲の“ピアノ・メデイア”でした。
当時はまだクラシックを聴き始めてまもなくの頃で、その曲にもすごく驚かされましたが、こんな曲を生身の人間で演奏できる人がいるとは思いません・・・という程驚かされました。
この高橋アキという人はサイボーグじゃないかって・・・マジで思いましたモン。(^^;)
まさかそんな人が普通のクラシック音楽、それもシューベルトをお弾きになろうという心境になられるとはいかがしたものか・・・また当方とてそんな方の演奏を聴こうと思う気になるとは・・・怖いもの見たさがそうとうあったことはいうまでもありません。
果たして、他には決してないその音楽の淵に、深く感じ入ることになるとはさらにさらに思うはずもなく・・・こんなしっかり大地に根を下ろしたシューベルトが聴けるとは大誤算でしたね、いいほうに。(^^)/
「大地に根ざした」などというと、シューベルトにはハンガリー風のメロディやアレグレット、楽興の時の第3番などでも顕著なように民族色が濃厚なものを想像されるかもしれませんが、ここでは違います。
健康的(かどうかはホントはわからない)で、野にすっくと立つ下半身の強靭さというかそういったイメージの演奏なんです。
それは、楽曲の構造をしっかり理解したうえで、堅固に再現しているところからくる印象なのでしょう。
そして、特徴的なのが使用されているベーゼンドルファー・モデル290・インペリアルとクレジットがある楽器についてですが、本当に不思議な響きがします。
旋律と中声部が立体的になる場面など、クラッと立ちくらみするような感じになる・・・。
全般的に音が乾いているうえ中音域が張り出した音色になっている(録音の関係かもしれません)んですが、これを高橋さんが絶妙なペダリングでしっとりとした響きを混ぜこんでいかれるんです。
もっとも魂を持っていかれるのは高音の透明な響き・・・。
現代音楽の巨匠だけあって、音色のグラデーションの幅が精密でムチャクチャ広いからこそなせる業なんでしょうけど・・・いやはや、音だけでこれだけ痺れさせる技術をもっている人はなかなかいないんじゃないでしょうか?(^^;)
さらにフレーズの『間』の取り方に旨味があるんですね。
それも、時間的な間のみならず音色や強さにも絶妙のズレというか差を織り込みながらじっくりと弾き進めていった・・・という感覚。。。
強調する音には、聴感上もきちんと強調されましたという印が付いているんですが、先のピアノの特性もあってエキセントリックなものにならない・・・こんなところにもこの聴き心地のヒミツがあるような気がします。
いずれにせよ現代音楽の最先端をサイバーに廻ることをライフワークにしてきた彼女が、古典(初期ロマン)派に回帰すると、非常に構造をはっきり意識した地に足の付いたものになり、ピアノの音色はもとより構造まで熟知してその求める音のシルエットを探求していることがつぶさに感じられる仕上がりになる・・・ということがよく判りました。
頭でカヴァーできることは、流石に、ほとんどすべて理詰めで押さえ切っているんだなというのが、率直な想いですね。彼女の経歴をよく考えれば、またお兄さんのことまで考えれば、この帰結はある意味当たり前と言えるかもしれませんけど。(^^;)
さて、あらゆるレコーディングにおいて音響上のこと、ピアノ選択のこと、そして楽曲の解釈のことに至るまであらゆるロジカルに処理できることは(スタッフの力を借りての部分も含み)、事前に最善のことを準備された上で臨まれたであろうレコーディング・・・。
後は、彼女の解釈に関して「いかにそれを音に換え、聴き手が感動できる内容になっているか?」だけが試されるのみとなっていたんでしょうね。
で、プロデューサーノートを見たら高橋さんは大学時代にヴァシャヘーリというお師匠さんにシューベルトの論文まで提出しているぐらい、また、今年の頭のリサイタルには自らこの変ロ長調ソナタをプログラムに組むほどシューベルトに親しんでいらしたとのこと。
決して俄かにシューベルトに入れ込んだり、先祖がえりしたわけではないということだったんでしょう。
心配して損した・・・。(^^;)
シューベルトを演奏するときにはそんなにキーを押し込むモンじゃない・・・という声もありそうなぐらい、しっかり深いタッチで終始弾ききっておられますが、そこまでの深い理解と愛情、何よりも深い思い入れを表現しきることができる証といわんばかりに聴こえてきました。(^^;)
私はタイトルに『抒情』と書きましたが、プロデューサーが高橋さんの持ち味を「優しさ」と表現しているものとほぼ同様のものと思っています。
この独特の楽器の特性を余すところなく・・・あるいはその最良のところが記録されるように工夫され、その堅固な構造表現に根ざした奏楽から件の「優しさ」を十全に引き出すことに成功している、録音スタッフの仕事にも大いに敬意を表したいと思います。
私の所有する46種類目の変ロ長調ソナタのディスクは、かくも印象的なものでありました。(^^)/
(演奏:高橋 アキ)
1.ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D.960(遺作)
2.ピアノ・ソナタ 第13番 イ長調 D.664 作品120
(2007年録音)
高橋アキさんの演奏に初めて触れたのは、一柳慧さん作曲の“ピアノ・メデイア”でした。
当時はまだクラシックを聴き始めてまもなくの頃で、その曲にもすごく驚かされましたが、こんな曲を生身の人間で演奏できる人がいるとは思いません・・・という程驚かされました。
この高橋アキという人はサイボーグじゃないかって・・・マジで思いましたモン。(^^;)
まさかそんな人が普通のクラシック音楽、それもシューベルトをお弾きになろうという心境になられるとはいかがしたものか・・・また当方とてそんな方の演奏を聴こうと思う気になるとは・・・怖いもの見たさがそうとうあったことはいうまでもありません。
果たして、他には決してないその音楽の淵に、深く感じ入ることになるとはさらにさらに思うはずもなく・・・こんなしっかり大地に根を下ろしたシューベルトが聴けるとは大誤算でしたね、いいほうに。(^^)/
「大地に根ざした」などというと、シューベルトにはハンガリー風のメロディやアレグレット、楽興の時の第3番などでも顕著なように民族色が濃厚なものを想像されるかもしれませんが、ここでは違います。
健康的(かどうかはホントはわからない)で、野にすっくと立つ下半身の強靭さというかそういったイメージの演奏なんです。
それは、楽曲の構造をしっかり理解したうえで、堅固に再現しているところからくる印象なのでしょう。
そして、特徴的なのが使用されているベーゼンドルファー・モデル290・インペリアルとクレジットがある楽器についてですが、本当に不思議な響きがします。
旋律と中声部が立体的になる場面など、クラッと立ちくらみするような感じになる・・・。
全般的に音が乾いているうえ中音域が張り出した音色になっている(録音の関係かもしれません)んですが、これを高橋さんが絶妙なペダリングでしっとりとした響きを混ぜこんでいかれるんです。
もっとも魂を持っていかれるのは高音の透明な響き・・・。
現代音楽の巨匠だけあって、音色のグラデーションの幅が精密でムチャクチャ広いからこそなせる業なんでしょうけど・・・いやはや、音だけでこれだけ痺れさせる技術をもっている人はなかなかいないんじゃないでしょうか?(^^;)
さらにフレーズの『間』の取り方に旨味があるんですね。
それも、時間的な間のみならず音色や強さにも絶妙のズレというか差を織り込みながらじっくりと弾き進めていった・・・という感覚。。。
強調する音には、聴感上もきちんと強調されましたという印が付いているんですが、先のピアノの特性もあってエキセントリックなものにならない・・・こんなところにもこの聴き心地のヒミツがあるような気がします。
いずれにせよ現代音楽の最先端をサイバーに廻ることをライフワークにしてきた彼女が、古典(初期ロマン)派に回帰すると、非常に構造をはっきり意識した地に足の付いたものになり、ピアノの音色はもとより構造まで熟知してその求める音のシルエットを探求していることがつぶさに感じられる仕上がりになる・・・ということがよく判りました。
頭でカヴァーできることは、流石に、ほとんどすべて理詰めで押さえ切っているんだなというのが、率直な想いですね。彼女の経歴をよく考えれば、またお兄さんのことまで考えれば、この帰結はある意味当たり前と言えるかもしれませんけど。(^^;)
さて、あらゆるレコーディングにおいて音響上のこと、ピアノ選択のこと、そして楽曲の解釈のことに至るまであらゆるロジカルに処理できることは(スタッフの力を借りての部分も含み)、事前に最善のことを準備された上で臨まれたであろうレコーディング・・・。
後は、彼女の解釈に関して「いかにそれを音に換え、聴き手が感動できる内容になっているか?」だけが試されるのみとなっていたんでしょうね。
で、プロデューサーノートを見たら高橋さんは大学時代にヴァシャヘーリというお師匠さんにシューベルトの論文まで提出しているぐらい、また、今年の頭のリサイタルには自らこの変ロ長調ソナタをプログラムに組むほどシューベルトに親しんでいらしたとのこと。
決して俄かにシューベルトに入れ込んだり、先祖がえりしたわけではないということだったんでしょう。
心配して損した・・・。(^^;)
シューベルトを演奏するときにはそんなにキーを押し込むモンじゃない・・・という声もありそうなぐらい、しっかり深いタッチで終始弾ききっておられますが、そこまでの深い理解と愛情、何よりも深い思い入れを表現しきることができる証といわんばかりに聴こえてきました。(^^;)
私はタイトルに『抒情』と書きましたが、プロデューサーが高橋さんの持ち味を「優しさ」と表現しているものとほぼ同様のものと思っています。
この独特の楽器の特性を余すところなく・・・あるいはその最良のところが記録されるように工夫され、その堅固な構造表現に根ざした奏楽から件の「優しさ」を十全に引き出すことに成功している、録音スタッフの仕事にも大いに敬意を表したいと思います。
私の所有する46種類目の変ロ長調ソナタのディスクは、かくも印象的なものでありました。(^^)/











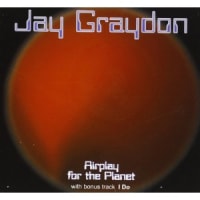
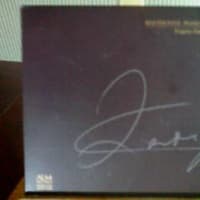
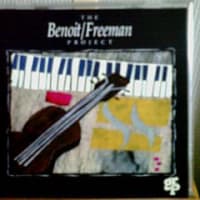
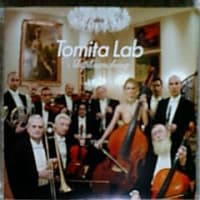
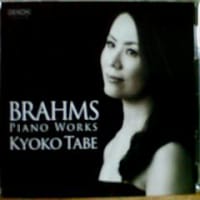

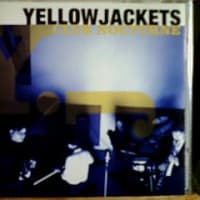


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます