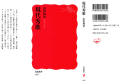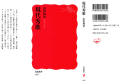

いつものように覚書として何か所か引用。
「普段考えることもなく見ていた普通の風景が、改めて指摘されてはじめて、なるほどそんな見かたもあったのかと驚く。歌を読む楽しみのひとつは、確かにそのような他の人の〈感性の方程式〉とでもいったものに触れる喜びでもあるのである。」(第3章)
「渡辺松男の歌は、一首だけ取り出して解説しても、そのおもしろさが十分には伝わらないもどかしさが残る。しかし歌集として読んでいくと、自然との不思議な親和性、かつ意表を衝く作者の精神の段差とでもいったものに、こちらの精神がくらくらしてくる。ある種の酩酊状態に読者を落とし込む作品がならぶ。‥理屈と文体の乖離と破綻によって、破綻の全体像が作者の内部に抱え込まれたまま、それがそのまま読者の胸になだれ込んでくる‥。」(第3章)
「(三枝昂之の歌は)敵とか味方とか、はっきりしていればまだいいのである。しかし、「終の敵」も「終なる味方」もとうとう自分には居なかったという苦い思い。まことに中途半端な仲間でしかないという忸怩たる思い。そんな内部と鬱屈とは関りがないように「あかるさの雪」が流れよる。明るさがいっそう内部の昏さを浮き立たせたのであろう。」(第4章)
「(前登志夫について)村は変えるべきところであるとともに、ついに己れの違和として存在する場所でもあった。吉野はいつも温かく自らを包んでくれる母郷なのではなく、常に拭いがたい違和感とともにある存在でもあったのであろう。」(第8章)
「大和には、長い、そして深い歴史の襞が刻まれ、深い闇を抱えている。普段見ている大和の景は、そんな襞や闇から濾されてきた上澄みにしか過ぎないのではないか。とっとどろどろと深い闇にこそ大和の本質はあるはずなのだ、作者(前川佐美雄)は気づくのである。」(第8章)
「そんな卑怯は、実は自らの裡にこそ根を張っているのではないかと、深く思っている作者(伊藤一彦)がいる‥。そんな見苦しい卑怯が、確かに自らのなかにあると気づくとき、人は、他人のを非を一方的に攻撃する傲慢さから少し距離を置くことができるのである。それが〈自己相対化〉ということに他ならず、自己相対化を通して、人間は謙虚になり‥。」(第9章)
歌の世界だけでなく、人は他者との関係の中で、このように変わっていくものである。
私の注目している渡辺松男、三枝昂之についての言及は新鮮であった。