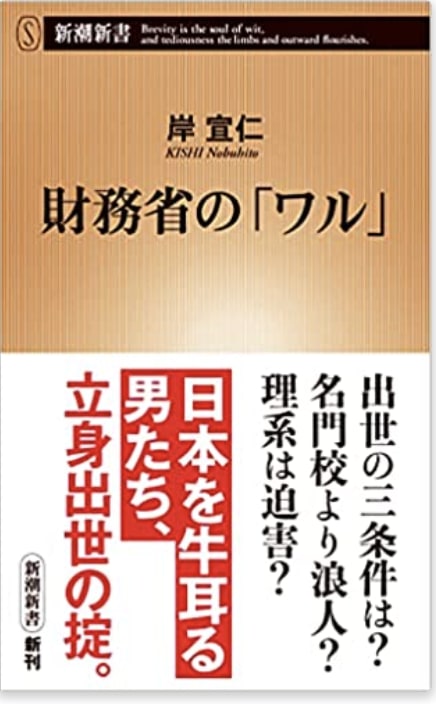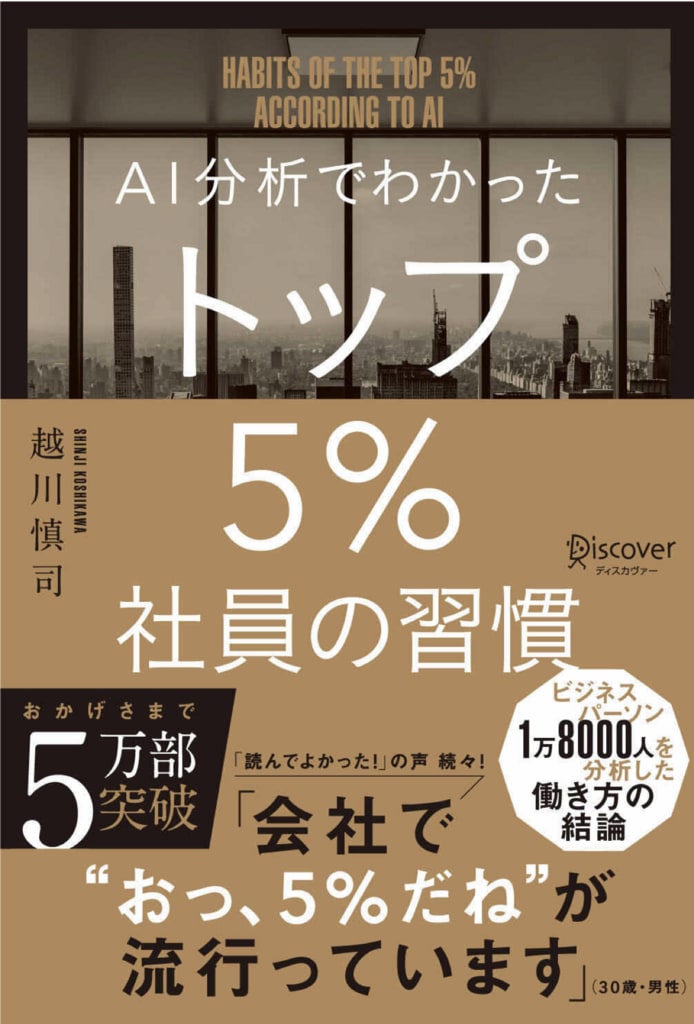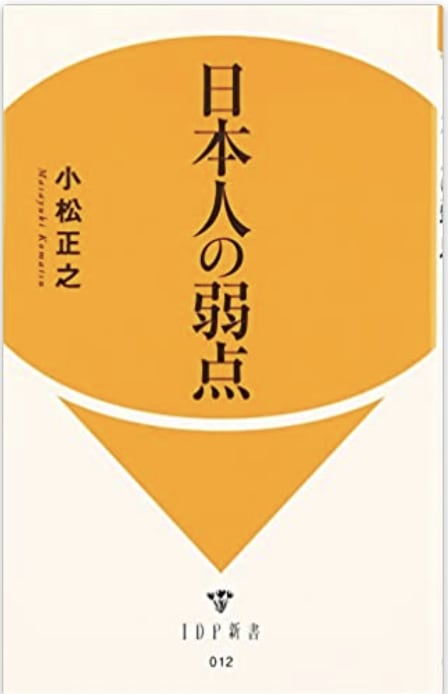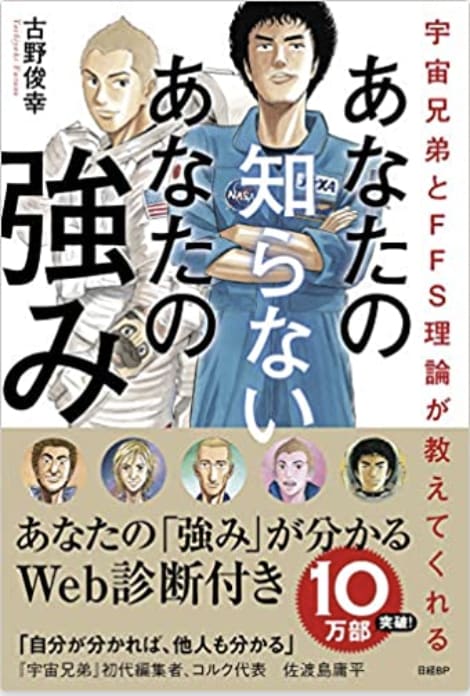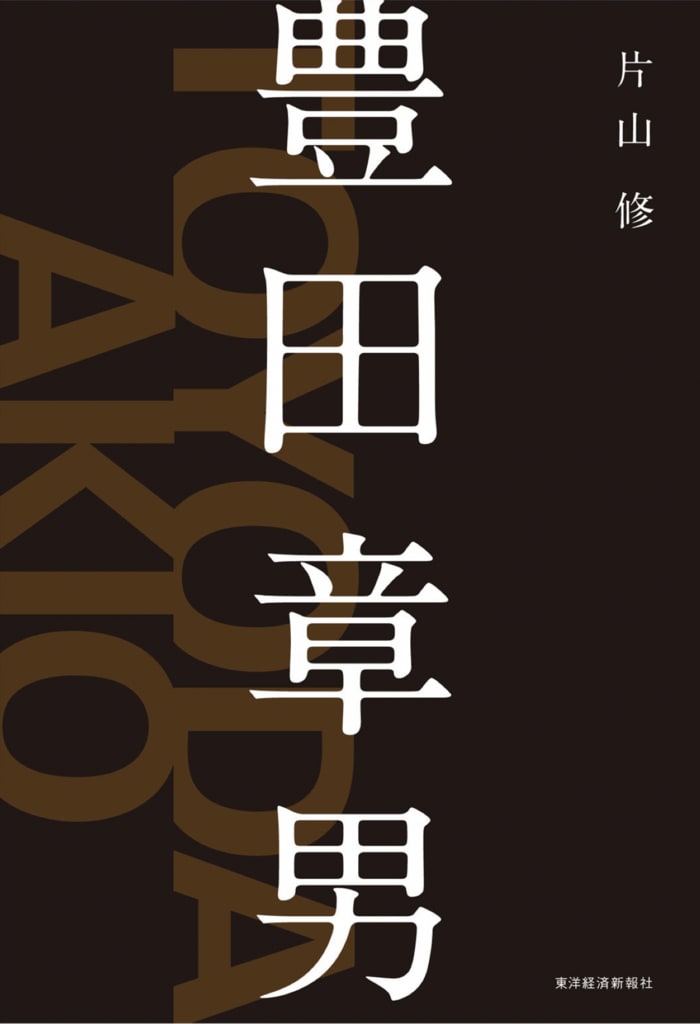@戦時中の「参謀」とは「権限を発令するが一切責任がなかった」とある。現代の政治家、一部官僚の世界がまさにそのまま引き継がれている。「無責任」、日本人に多くあるのは「理論武装した秀才」がいざという時に「行動・実践」が出来ないことだと察する。言葉巧みに「言い回し」できる秀才は多い、だが実際には実務実行欠如なのだ。結果「〜はず」という言葉がよくあるのは戦時中の大本営の姿勢と同じだ。
真のリーダーシップが日本に欠けているのは「何もしないことで失敗もしない」、ハイゼル司令官の言う「日本人は繰り返しが得意」(一度の成功を重視する)、新規提案などは「愚の骨頂」で「出る杭は打たれる」、そのままなのだ。
『日本型リーダーはなぜ失敗するのか』半藤一利
リーダー不在が叫ばれて久しい日本。しかし、リーダーシップという言葉のもとは軍事用語。
ー戦国時代の兵法書は「孫子の兵法」と「六韜・三略」(ろくとう・さんりゃく)
孫子の兵法:大将の大将たる人間は「智・信・仁・勇・巌」
六韜・三略:大将には5材十過あり(韜とは弓とか剣を入れる袋)
古代中国の周の国を建てた武王が軍師太公望呂尚に質問した兵法書
「勇・智・仁・信・忠」
ー明治大正昭和の軍事教育は西欧の「戦争論」(プロセインの軍事学者:クラウゼビッツ)
「勇気・理性・沈着・意志・忍耐力・感情・強い性格」(攻撃は最大の防御なり)
零戦も戦艦大和も攻勢防御のみで対空防衛は考えていなかった
ー「参謀」が生まれた理由
西南戦争と明治の帝国海軍(総大将は戦に疎くても参謀さえしっかりしていれば大丈夫)
「威厳と人徳を持つ人」である事(秀才だけを集めた集団教育・士官学校)
「権限発揮せず責任も取らない」東條英機の腰巾着富永恭次中将
「権限発揮せず責任だけ取らされる」海軍の南雲忠一中将
「権限発揮して責任取らず」陸軍牟田口兼也
日本の参謀はトップの司令官が細かく口を出すことを敬遠した、その結果派遣参謀が誕生
「大本営派遣参謀」とは参謀総長の代理で派遣される参謀=現地の司令官の上司となる
参謀の教育は戦略、戦術等以外の国際情勢、経理、法学、国際法は無知だった
太平洋戦争の結果:戦死者160万人の内70%が飢餓での死亡者
参謀には何ら責任が課されなかった(理由:狼狽えたり、いじけたり発想が阻害)
ー日本の参謀のタイプ
書記官型:事務方・まとめるのが上手い(陸軍瀬島龍三・満洲赴任・情報の握りつぶし)
分身型:上司の代理指導型(海軍秋山慎之中将・東郷平八郎連合艦隊)
独立型:己の信念を通す(陸軍石原莞爾・関東軍満州事変)
準備指導型:指揮権を行使する(陸軍辻政信・関東軍ノモンハン)
長期構想型:戦略化タイプ(陸軍永田鉄山・関東軍慮溝橋事件)
政略担当型:折衝に能力(海軍石川慎吾・三国同盟)
ー優れた参謀とは
指揮官の頭脳を補う能力、計画立案、決断、情報収集、分析、助言
伝達能力、隅々まだ指揮官の指示指導をまとめ伝える能力
推察能力:将来の推移を察知する能力
ー戦時からのリーダーの条件(至誠・礼儀・気力・質素)
決断力(判断力)
明確な目標を示す(目標・目的の明示)
焦点に位置する(立場をはっきりさせる)
情報は確実に捉えよ(情報収集・分析能力)
規格化された理論に縋るな(臨機応変な対応・予知能力)
部下には再断言の任務の遂行を求めよ(権限委譲)
ー司令官・トップの言葉
山本五十六にかけていた事:人見知り癖で口が重い
ロンメル将軍「人を共通うの目的に団結させる能力と意志であり、人に信頼の念を起こさせる人格の力である」
ハイゼル太平洋司令官「日本人という奴は一回うまくいくと必ず同じ事を繰り返す」
陸軍阿南大臣「統率は人格なり」
海軍井上成美「米国と戦争になったら、どんな戦いをすることになるのか、何で勝つのか、それには何が必要なのか、といったような説明もなければ、計画にも表れていない」(新軍備計画案・戦艦戦争から航空機戦争が反故にされる)
大和護衛船「雪風」寺内艦長「速やかに行動を起こされたし」
「飛龍」艦長山口多聞我、今より航空戦の指揮を執る」
硫黄島陸軍栗林忠道中将「たとえ草を食み、土を頬張り、野に伏するとも断じて戦うところ死中自ずから活あるを信じています。事ここに至っては一人百人殺、これ以外にありません。本職は諸君らの忠誠を信じている。」
硫黄島:戦死者数日本軍20,129名、米軍25,851名
東條英機「自分は2つの間違いをした。1つは南方占領地区の資源を急速に戦力化し得ると思ったこと。その2は、日本は負けるかもしれないと想いも及ばなかったことだ」
帝国か陸海軍の「あるはずだ」「あろうはずがない」=「はず」が多かった事
ー現代のリーダー能力
アイデア
先見の明
ファイトとスタミナ
人間的な魅力
信用
本田宗一郎の言葉「日本人はこうやると良いという理屈だけ知っていて実行しない。その点米国人は違う、すぐ実行に移す」「古い伝統と歴史を持つ会社は必ず伝統を大事にする。しかし大事にしすぎると古い観念と技術が温存され、退歩するばかりとなる。昔の枠を外さぬとパイオニア的仕事は出来ぬ」