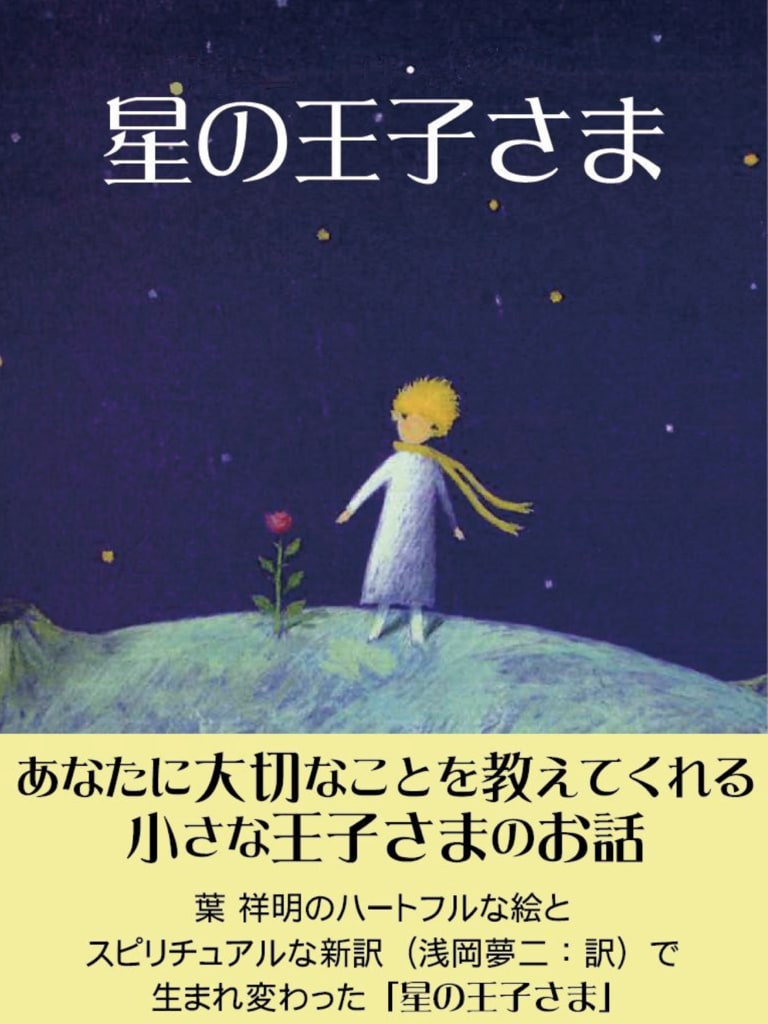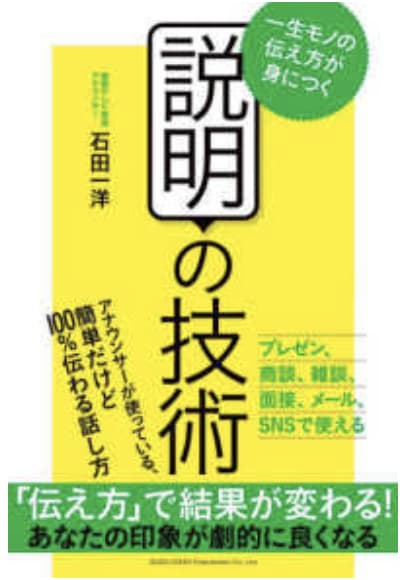@起業家、あるいは起業しようとする人にとって良い参考資料となることは間違いない。但し小説のように金銭感覚が少々麻痺し上手くいくことは滅多にないことを覚悟しておくべきかもしれない。私的にも海外含め過去4社立ち上げ3社は生き残っていない。起業家としてのチャレンジは常に必要だが特に資金・キャッシュフローには要注意が必要だ。更に、銀行との付き合い方も経営者は要注意しておくべきだ。成功するには、経営者自らが率先しアイデアと行動を起こす、あとはチームワーク、適材適所の人材を選択し、力強く後押しできる体制も必須だ。メンター(経験者として)の起業家のポイントは下記だ。
・経営課題とポイント
財政改善:キャシュフロー・支払い条件
商品改善:製品群・ブランド・価格
競合対策:価格・ブランド・製品ライン・店舗展開
価格競争対策:競合との差別化
新製品投資:投資と収支・価格・ブランド・製品ライン(自社ブランド・OEM)
広告宣伝対策:予算と目的・ネット広告・展開(メッセージ)、期間
顧客対策:製品対象像・ラインナップ・自社店舗・フランチャイズ店
自然災害対策:地震・火災・台風(停電・生産ライン停止・人材補填)
海外戦略:海外事情把握(競争相手・市場性・商習慣・貿易業務(法的情報)・専門家)
・更なる飛躍へのポイント
競争力:資本金・投資金額・販促力・ブランド力・店舗数・商品化価値
社員教育:決断力・販売力・行動力・率先力、最後に統率力(結束力)
社長おより幹部の提案力・仮想力(予測・目標)・説得力、最後に実行力
『破天荒フェニックス』田中修治
人生を大きく変えるため、倒産寸前のメガネチェーン店を買収した田中。しかし、社長就任 3 か月で銀行から「死刑宣告」が下される。度重なる倒産の危機、裏切りに次ぐ裏切り、決死の資金繰り……。何度も襲いかかる絶体絶命のピンチに破天荒な施策で立ち向かっていく。実在する企業「 OWNDAYS 」の死闘の 日々を描いた、ノンストップ実話ストーリー
・「波乱万丈」、一か八か「大博打」とでも言うような商売を展開していく。社長の決断と行動は「金はないけどスピードには自信がある」の如く他者との競合は、何を持って優先するか、しなければならないかを十分理解し、即決することだ。金がなければアイデアを出し、スピード感を持って行動することで安売り眼鏡店からの脱却を図る。
・文中の言葉
「20億の売り上げしかないのに14億の負債を抱えているということは、2tトラックの荷台に1.4tの砂利が載っかっているようなもんだ」
「金の苦労が無くなれば自分なんかいらない。金の苦労があるから自分が必要とされているんだ」
「やっぱり百聞は一見に如かずだ。これは観に来ないと絶対にわからない。決算書なんかじゃ伝わり切らないものを持っている勢いと、とんでもない可能性が改めてわかりましたよ」