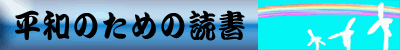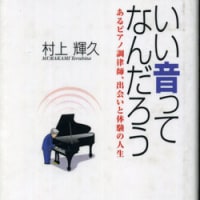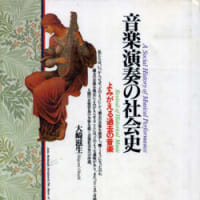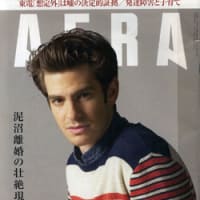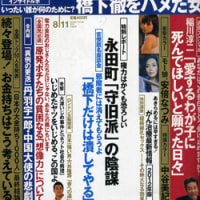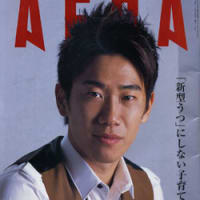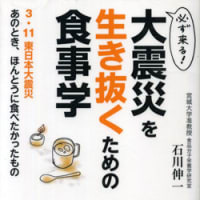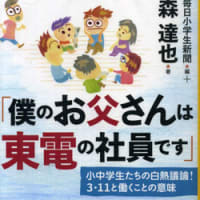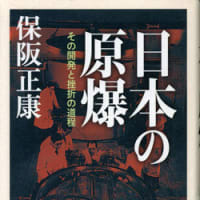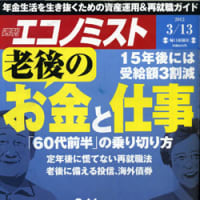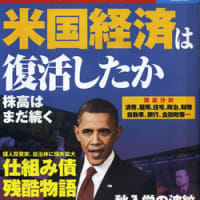『フェミニズムと戦争-婦人運動家の戦争協力-新版』
鈴木裕子・著/マルジュ社1997年
--このようなことに目をつむれることはないと思うが……。

戦争協力をした日本基督教婦人矯風会など……。下「」引用。
「愛婦や国婦と違って、政府や軍部の後援を受けない。いわゆる自主的婦人運動の側は、この事態にどう対処したろうか。日本の婦人参政権運動や廃娼運動にパイオニア的な役割を果たした婦選獲得同盟そして日本基督教婦人矯風会は、他の婦人諸団体を語らって連合組織をつくり、「時局に協力」する道を選んだ。八団体による日本婦人団体連盟の創立(一九三七年九月二八日)がそれであった(会長・日本基督教婦人矯風会会頭ガントレット恒子、書記・婦選獲得同盟総務理事市川房枝)。
日本婦人団体連盟の性格はその「宣言」よりうかがえよう。
日本婦人団体連盟宣言
国家総動員の秋、我等婦人団体も亦協力以て銃後の護りを真に固からしめんと希ひ、〓(*玄玄)に日本婦人団体連盟を結成して起たんとす。我等はよく持久その目的を達成せんと誓ふと共に、冀(こひねがわ)くば我等の精神よく全女性に潤ひて非常時局克服に、女性の真価の発揮せられんことを。
昭和十二年九月二十八日」
女性ファシストたちがいたという。下「」引用。
「そのことよりもさきの発言録を読む限り、高良とみはもう立派な「女性ファシスト」である。「女性ファシスト」で思い出されるのは、戦時下、中国に渡り、抗日運動に加わった反戦エスペランティスト、長谷川テルの次の言葉である。-略-
-略-開戦直後は自ら進んで慰問袋や千人針のために奔走してた婦人労働者さえも、いまでは上からの強制がなければ、決してそのために動こうとはしない。いまなお不平や嘲笑なしに、こんな仕事を続けているのは排外的愛国心によって身を太らせている女性ファシストだけである。(「戦時下日本の婦人労働」一九三九年、宮本正男編『長谷川テル作品集』一八九~一九二ページ、一九七年・亜紀書房)」
今も、そのような女性たちがいる。
--反民主主義(ファシスト)は、とてもひどい人権侵害などの言論もしているが、文化人だという……。
市川房枝……。下「」引用。
「とはいえ、総動員運動への市川房枝の参加の仕方は、単線的ではない。いうならば協力しつつ、注文しつつのコースをたどっていった、といえよう。
市川房枝の、「支那事変」を機として“転回”の第一のあらわれが、日本婦人団体連盟の結成だとするなら、第二のあらわれは、市川自身による「公職」への就任であった。こころみに精動連盟発足(一九三七年一○月)後の主な公職を年代順にあげていくと、次の通りである。
精動連盟中央連盟委員会委員(一九三七年一二月)、同非常時国民生活様式改善委員会委員(一九三八年六月)、厚生省国民服制定委員会委員(同年一一月)、大蔵省貯蓄奨励婦人講師(一九四○年四月)、大政翼賛会調査委員会委員(一九四一年五月)、大日本婦人会審議会(一九四二年二月)、大日本言論報国会理事(同年一二月)。」
南京大虐殺を知っていた市川房枝。下「」引用。
「日本軍による占領統治がはかばかしくいってないのを、市川はその眼でとくとみてきたのである。また『市川房枝自伝』によれば、南京占領のさい、日本軍が中国女性をはじめとして、あらん限りの蛮行をはたらいた(いわゆる一九三七年一二月の「南京事件」)ことも聞いている(四九六ページ)。だが、市川は、中国における日本統治を中国侵略とは考えない。ナショナルな志向を拒絶しえない市川は、こうして、いわゆる「日支親善」のイデオロギーへと収れんされていく。」
 もくじ
もくじ
「女子の「根こそぎ動員」化に向けて」 下「」引用。
「労務の不足を婦人によって補う為には、女子の徴用は不可避であり、婦人に対する動員についての特殊な施策が必要だと思うのである。(同書四二ページ、「労務動員計画と婦人」の項。なお執筆は市川房枝)」
吉岡弥生(一八七一~一九五九年)。下「」引用。
「吉岡は、戦時中に設けられた教育審議会の唯一の女性委員に就任、「婦人国策委員」第一号になった人である。これ以外にも吉岡は愛国婦人評議員、大日本連合女子青年団長、大日本青年少年団顧問、大日本婦人会顧問など、たくさんの要職につき、多数の女性や青少年たちを戦争協力に引っ張っていった張本人であった。
「われわれ婦人は一発必中の精神と技術を現はす日本男子の母であります」(「戦争と婦人」『婦女新聞』二一六九号・一九四二年一月四日)とあおっていながら、空襲を一度受けるや、さっさと疎開し、そして戦争が終わると、また東京に戻ってきて自分の学校(東京女子医専--現在の東京女子医大の再建に取りかかるといった、“不死身”の人であった。
この吉岡は、戦後、相次いで教職追放(一九四七年四月)、公職追放(同年一一月)の処分を受けるが、この処分は不当ととらえるばかりで、自分が戦争に協力し、多くの人を犠牲にしたという責任への痛覚はまったくない(くわしくは吉岡著『この十年間--続吉岡弥生伝--』〔一九五二年・学風書院〕をみられたい)。」
大妻コタカ(一八八四~一九七○年)。下「」引用。
「大妻の自伝に一風かわった名をもつ『ごもくめし』(一九六一年、私家版。のち一九七八年に大妻学院より再刊)というのがある。だが、この『ごもくめし』には、驚いたことに、戦時中の事故の活動に触れた記述がない。関連してわずかにあるのは「追放から解除まで」の一節(同書八六~九一ページ)のみである。
「『多くの学校の校長でありながら、あらゆる婦人団体に相当な役割をもった故をもって追放する』。この瞬間から私の長いさびしい生活が始まりました。昭和二十二年四月一日……。文部省適格審査からの通知をうけとった時のおどろき、悲しみ……あらゆる不安に唯、茫然とするばかりでした」(同書八六ページ)
これが、この筋の書き出しである。このあと、自分が創立者でありながらも学校を逐われ、家をも失って、いかに不自由な生活をしいられ、苦労したかということがめんめんと語られるのである。
まるで、自分こそ戦争の被害者である、といわんばかりである。
わたしは何か「倒錯」しているのではないかと思う。吉岡も大妻も、二重の意味で戦争の「加害者」であった。一つは、いうまでもなく日本が侵略していったアジア諸国の人びとに対し、いま一つは、純真椋な女学生たちを戦争動員・協力にかりたてた指導者として。
だが、彼女らの意識のなかには、「加害者意識」はすっぽりと抜け落ちている。むしろ、顕著なのは、自分も戦争犠牲者の一人、といった「被害者意識」である。
このような大妻、吉岡に体現される。倒錯した戦争観・戦争認識の生じる思想的土壌というものを、わたくしたちは大いに問題にせねばなるまい。」
今のファシスト(反民主主義)の文化人も、自己中毒の文章を恥かしげもなく書いているが、同様だったようだ……。
--平気でうそをつく人たちでもあるように思える……。
 もくじ
もくじ
 もくじ
もくじ
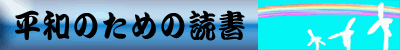


鈴木裕子・著/マルジュ社1997年
--このようなことに目をつむれることはないと思うが……。

戦争協力をした日本基督教婦人矯風会など……。下「」引用。
「愛婦や国婦と違って、政府や軍部の後援を受けない。いわゆる自主的婦人運動の側は、この事態にどう対処したろうか。日本の婦人参政権運動や廃娼運動にパイオニア的な役割を果たした婦選獲得同盟そして日本基督教婦人矯風会は、他の婦人諸団体を語らって連合組織をつくり、「時局に協力」する道を選んだ。八団体による日本婦人団体連盟の創立(一九三七年九月二八日)がそれであった(会長・日本基督教婦人矯風会会頭ガントレット恒子、書記・婦選獲得同盟総務理事市川房枝)。
日本婦人団体連盟の性格はその「宣言」よりうかがえよう。
日本婦人団体連盟宣言
国家総動員の秋、我等婦人団体も亦協力以て銃後の護りを真に固からしめんと希ひ、〓(*玄玄)に日本婦人団体連盟を結成して起たんとす。我等はよく持久その目的を達成せんと誓ふと共に、冀(こひねがわ)くば我等の精神よく全女性に潤ひて非常時局克服に、女性の真価の発揮せられんことを。
昭和十二年九月二十八日」
女性ファシストたちがいたという。下「」引用。
「そのことよりもさきの発言録を読む限り、高良とみはもう立派な「女性ファシスト」である。「女性ファシスト」で思い出されるのは、戦時下、中国に渡り、抗日運動に加わった反戦エスペランティスト、長谷川テルの次の言葉である。-略-
-略-開戦直後は自ら進んで慰問袋や千人針のために奔走してた婦人労働者さえも、いまでは上からの強制がなければ、決してそのために動こうとはしない。いまなお不平や嘲笑なしに、こんな仕事を続けているのは排外的愛国心によって身を太らせている女性ファシストだけである。(「戦時下日本の婦人労働」一九三九年、宮本正男編『長谷川テル作品集』一八九~一九二ページ、一九七年・亜紀書房)」
今も、そのような女性たちがいる。
--反民主主義(ファシスト)は、とてもひどい人権侵害などの言論もしているが、文化人だという……。
市川房枝……。下「」引用。
「とはいえ、総動員運動への市川房枝の参加の仕方は、単線的ではない。いうならば協力しつつ、注文しつつのコースをたどっていった、といえよう。
市川房枝の、「支那事変」を機として“転回”の第一のあらわれが、日本婦人団体連盟の結成だとするなら、第二のあらわれは、市川自身による「公職」への就任であった。こころみに精動連盟発足(一九三七年一○月)後の主な公職を年代順にあげていくと、次の通りである。
精動連盟中央連盟委員会委員(一九三七年一二月)、同非常時国民生活様式改善委員会委員(一九三八年六月)、厚生省国民服制定委員会委員(同年一一月)、大蔵省貯蓄奨励婦人講師(一九四○年四月)、大政翼賛会調査委員会委員(一九四一年五月)、大日本婦人会審議会(一九四二年二月)、大日本言論報国会理事(同年一二月)。」
南京大虐殺を知っていた市川房枝。下「」引用。
「日本軍による占領統治がはかばかしくいってないのを、市川はその眼でとくとみてきたのである。また『市川房枝自伝』によれば、南京占領のさい、日本軍が中国女性をはじめとして、あらん限りの蛮行をはたらいた(いわゆる一九三七年一二月の「南京事件」)ことも聞いている(四九六ページ)。だが、市川は、中国における日本統治を中国侵略とは考えない。ナショナルな志向を拒絶しえない市川は、こうして、いわゆる「日支親善」のイデオロギーへと収れんされていく。」
 もくじ
もくじ「女子の「根こそぎ動員」化に向けて」 下「」引用。
「労務の不足を婦人によって補う為には、女子の徴用は不可避であり、婦人に対する動員についての特殊な施策が必要だと思うのである。(同書四二ページ、「労務動員計画と婦人」の項。なお執筆は市川房枝)」
吉岡弥生(一八七一~一九五九年)。下「」引用。
「吉岡は、戦時中に設けられた教育審議会の唯一の女性委員に就任、「婦人国策委員」第一号になった人である。これ以外にも吉岡は愛国婦人評議員、大日本連合女子青年団長、大日本青年少年団顧問、大日本婦人会顧問など、たくさんの要職につき、多数の女性や青少年たちを戦争協力に引っ張っていった張本人であった。
「われわれ婦人は一発必中の精神と技術を現はす日本男子の母であります」(「戦争と婦人」『婦女新聞』二一六九号・一九四二年一月四日)とあおっていながら、空襲を一度受けるや、さっさと疎開し、そして戦争が終わると、また東京に戻ってきて自分の学校(東京女子医専--現在の東京女子医大の再建に取りかかるといった、“不死身”の人であった。
この吉岡は、戦後、相次いで教職追放(一九四七年四月)、公職追放(同年一一月)の処分を受けるが、この処分は不当ととらえるばかりで、自分が戦争に協力し、多くの人を犠牲にしたという責任への痛覚はまったくない(くわしくは吉岡著『この十年間--続吉岡弥生伝--』〔一九五二年・学風書院〕をみられたい)。」
大妻コタカ(一八八四~一九七○年)。下「」引用。
「大妻の自伝に一風かわった名をもつ『ごもくめし』(一九六一年、私家版。のち一九七八年に大妻学院より再刊)というのがある。だが、この『ごもくめし』には、驚いたことに、戦時中の事故の活動に触れた記述がない。関連してわずかにあるのは「追放から解除まで」の一節(同書八六~九一ページ)のみである。
「『多くの学校の校長でありながら、あらゆる婦人団体に相当な役割をもった故をもって追放する』。この瞬間から私の長いさびしい生活が始まりました。昭和二十二年四月一日……。文部省適格審査からの通知をうけとった時のおどろき、悲しみ……あらゆる不安に唯、茫然とするばかりでした」(同書八六ページ)
これが、この筋の書き出しである。このあと、自分が創立者でありながらも学校を逐われ、家をも失って、いかに不自由な生活をしいられ、苦労したかということがめんめんと語られるのである。
まるで、自分こそ戦争の被害者である、といわんばかりである。
わたしは何か「倒錯」しているのではないかと思う。吉岡も大妻も、二重の意味で戦争の「加害者」であった。一つは、いうまでもなく日本が侵略していったアジア諸国の人びとに対し、いま一つは、純真椋な女学生たちを戦争動員・協力にかりたてた指導者として。
だが、彼女らの意識のなかには、「加害者意識」はすっぽりと抜け落ちている。むしろ、顕著なのは、自分も戦争犠牲者の一人、といった「被害者意識」である。
このような大妻、吉岡に体現される。倒錯した戦争観・戦争認識の生じる思想的土壌というものを、わたくしたちは大いに問題にせねばなるまい。」
今のファシスト(反民主主義)の文化人も、自己中毒の文章を恥かしげもなく書いているが、同様だったようだ……。
--平気でうそをつく人たちでもあるように思える……。
 もくじ
もくじ もくじ
もくじ