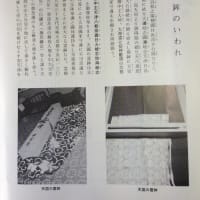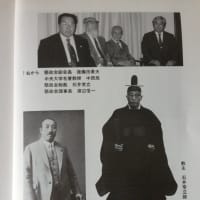ほそかわかずひこさんが「天皇と武士の確執~建武の中興」について掲載している。
非常に参考になるため、以下、要約し記す。
⇒
源頼朝の幕府開設以後、約7百年に及ぶ武家政治の時代に、日本古来の天皇親政が試みられた時代がありました。それが建武の中興です。
●天皇親政の志
承久の乱において、北条泰時は天皇に譲位をさせ、後嵯峨天皇を立てました。その後、後嵯峨天皇が私情によって皇位継承の仕方を乱すという出来事が起こりました。ここで時の執権・時宗が口を出したことをきっかけに、幕府が皇位継承に関与するようになります。そして、後嵯峨天皇の子孫は大覚寺統と持明院統とに分かれ、交互に天皇を出すという申し合わせができました。
そんな中、文保2年(1318)、大覚寺統から後醍醐天皇が即位しました。天皇は時に、30歳。即位したとはいえ、政治の実権は幕府が握り、皇統は二系統に分かれ、父親の御宇多法皇が院政を布いているという変則的な状態でした。シナから入ってきた朱子学の大義名分論を学んでいた天皇は、この現状はおかしいと思いました。
この時代には、元寇で神風が吹き蒙古の侵攻から日本が守られたことにより、我が国は神国なりという信念が高まっていました。神国思想により、皇室中心の国柄への自覚も深まりました。天皇親政は、わが国の古い伝統です。当時は平安期の醍醐天皇・村上天皇による延暦・天暦の治が理想と信じられていました。
後醍醐天皇は、変則的な現状を正し、直接政治を行いたいと考えました。理想の実現のためには、皇統を一統に戻し、院政を廃止し、幕府を倒さなければなりません。後醍醐天皇は、まず朝廷内での天皇親政を確立し、政治の革新に努め、武芸や学問の振興を図りました。
当時は、元寇を乗り切ったものの戦後、幕府の財政は極度に悪化していました。また恩賞を与えられない武士たちは、不満を募らせていました。幕府の支配体制にゆるみが出てきたのです。天皇は、この機を見て、倒幕のための計画を立てました。しかし、これは事前に露見します。元亨4年(1324)9月、日野資朝・俊基が逮捕され、土岐頼兼らが討ち取られます。天皇は自分は知らないと、しらを切り通し、責任追及を逃れました。「正中の変」です。
天皇はこれに屈せず、翌年赦免された日野俊基を中心に、再度倒幕の計画を進めますが、元徳3年(1331)5月、密告によって幕府は俊基らを逮捕します。今度は追及を逃れきれないと考えた天皇は、8月24日突然、皇位の象徴である「三種の神器」を携帯して脱出し、27日に笠置山に入ります。9月14日、楠木正成が河内の赤坂城にてこれに呼応して挙兵しました。
しかし、頼みの延暦寺が幕府側に付いてしまい、後醍醐天皇の皇子・大塔宮護良(だいとうのみや・もりなが)親王らは比叡山を脱出する羽目に、楠木の赤坂城も幕府軍の攻勢の前に落城し、笠置の帝も捕らえられてしまいます。これを「元弘の変」と呼びます。
これに対して、持明院統の後伏見上皇は、皇太子の量仁(かずひと)親王に皇位継承を指示し、親王は9月20日践祚(せんそ)して光厳(こうごん)天皇となります。しかし、「三種の神器」を持たないため、正式な天皇とは認められませんでした。後醍醐天皇は結局、笠置山を持ちこたえることができず、やむなく「三種の神器」を光厳天皇に差し出し、捕らわれの身となりました。
幕府は、承久の乱の例にならって、翌年3月後醍醐天皇を隠岐へ配流しました。天皇はこの時44歳でした。忠臣の日野資朝・俊基らは処刑されました。光厳天皇は3月正式に即位、4月には改元が行われ正慶元年となります。
承久の乱の際は、隠岐に流された後鳥羽上皇は、その地で最期を迎えました。後醍醐天皇の命も、もはや風前の灯火かと思われました。しかし、天皇は、これで引き下がりはしませんでした。不屈の闘志をもって再起を図ったのです。
●不徳と失政による蹉跌
後醍醐天皇の隠岐配流という状況において、幕府に屈せずに大活躍をしたのが、大塔宮護良(もりなが)親王と楠木正成です。
後醍醐天皇の皇子のうち最年長だったのが、大塔宮です。大塔宮は、天皇が隠岐にいる間、全国に号令を下し続けました。その令旨(りょうじ)なくしては、各地の官軍は動かなかったことでしょう。元弘3年(1333)の春、幕府は大軍で吉野山の大塔宮を攻略したものの、ついに拘束することはできませんでした。
ここで人々を奮起させたのは、楠木正成の活躍でした。大塔宮を逃した幕府軍は、全力を上げて千早城の楠木正成を攻めました。しかし、千早城の天険と正成の知謀とに阻まれて、身動きができません。正成は小勢でありながら、幕府軍をここに釘付けにすることができました。当時80万といわれた大軍が何ヶ月もの間、小城一つ落とせないでいるのを見て、各地の反幕府勢力が奮起しました。楠木正成は「菊水の紋」で知られますが、「菊水」こそ敬神尊皇の旗印となったものです。
正成が奮戦している間に、正慶2年(1333)閏2月、後醍醐天皇が隠岐から脱出しました。陸地にたどりついた天皇は、この地の豪族・名和長年に決起を要請します。しかし長年は幕府の家臣でした。天皇を助けることは、恩義のある幕府に背くことになります。大いに悩んだ長年でしたが、「屍(しかばね)を戦場にさらすとも、名を後世に残すことこそ名誉」と挙兵を決意。天皇を奉じて、船上山(せんじょうざん)に立て籠もります。隠岐の判官たちは大軍を率いて取り囲みますが、長年は見事にこれを撃破。さらに幕府軍と戦って周辺一帯を平定し、天皇を守りました。
後醍醐天皇側の動きに対し、幕府は足利尊氏を討伐に向かわせました。しかし、鎌倉幕府の命数は尽きていると見ていた尊氏は、後醍醐天皇側に寝返り、北条氏の立てた光厳天皇を京都から追い出してしまいます。形勢逆転です。この時、新田義貞も呼応して関東で挙兵しました。義貞は鎌倉に攻め入り、激しい戦闘を繰り広げます。戦況不利と見た北条氏は、執権高時以下、多数が自害し、5月22日ついに鎌倉幕府は滅亡しました。高時は元寇の際の英雄・時宗の孫に当たります。
6月4日後醍醐天皇は京都に戻り、元号を建武とし、新しい政治を目指しました。これが「建武の中興」です。天皇は、幕府も院政も摂政・関白も否定して、天皇親政を実現しようとしました。新政府は、中央に最高機関としての記録所や幕府の引付を受け継いだ雑訴決断所などを設置し、諸国に守護と地頭を併置するなど、天皇中心の政治機構を整えようとしました。
しかし、建武の中興は失敗に終わりました。その大きな原因は、後醍醐天皇の不徳・失政にあります。天皇は高い理想を掲げた反面で、贅沢な宮廷生活を復興しようとしました。また阿野廉子(かどこ)を寵愛しすぎたため、廉子が政治に口を出しました。そのため、賞罰が乱れて、武士たちに不満を抱かせることになりました。所領が命である武士たちは、論功行賞への不満が募り、王政をやめて幕府に戻すべしという主張に変わります。
さらにまずいことに、廉子は自分の子供を皇太子にするために、最年長の皇子である大塔宮を除こうとしました。宮は武勇に優れ、武将たちの間で人気がありました。足利尊氏が、最も煙たがっていた皇子です。廉子は尊氏の言うことを聞いて、大塔宮が天皇を倒そうと謀(はかりごと)をしていると讒言しました。これを真に受けた天皇は、大塔宮を拘禁し、宮は弁明も許されず、鎌倉に流され、最期は暗殺されてしまいます。このことは、朝廷の武の要が取り除かれたようなものでした。武士たちの心は、後醍醐天皇から離れていきました。
後醍醐天皇は、重ねて失策をしました。足利尊氏が裏切って兵を挙げた時、天皇は楠木正成の軍略を受け入れようとしなかったのです。そのため、正成は不利を承知で湊川(みなとがわ)に向かい、そこで玉砕する結果となりました。知将正成を失った後醍醐天皇は、ますます敗色を濃くし、ついに吉野に逃れざるを得なくなったのです。
かくして、天皇親政を目指す後醍醐天皇によって起こされた建武の中興は、天皇自身の不徳・失政によって費(つい)えたのでした。