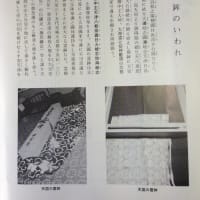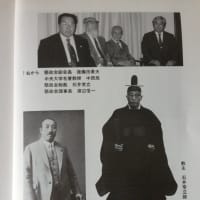Q ダイジェストにKojima Tadashiさんが、分かりやすく適切な回答をしている。
以下、参考に!
「コロナは、感染率は高いが致死率の低いインフルエンザ並みの風邪。むしろピーク時に週200万人以上が感染し、年間1万人以上が死亡したインフルのほうが危険な感染症」は正しい見解でしょうか?
最近、インフルエンザと新型コロナでつまり何が違うのか、実際のところ、医療システム全体や日本社会として何が起こっているのか、について考えが少しまとまってきました。
結論から言えば、
私個人としての視点から見れば、インフルエンザのほうが危険。なぜならインフルエンザにかかった場合、必要な治療をされずに放置される(その結果死亡する)可能性があるのに対して、新型コロナでは必要な治療を受けられる可能性が高い。
社会全体という視点から見れば、新型コロナのほうが危険。なぜなら、インフルエンザは医療システムへの負荷が軽いのに対して、新型コロナ患者はとくに高度な医療システムに与える負荷が大きいため医療崩壊を招く可能性がある。
ということなのですが、この結論に至るまでには長い長いストーリーがあります。
・まず、インフルエンザの例年の死者1万人にたいして、2020年の日本の新型コロナの死者は3500人ですから、結果的に見れば、日本においては、2020年の新型コロナよりも、例年のインフルエンザのほうが危険であった、と言えます。しかも、新型コロナの死者が極端に高齢者に偏っているのに対して、インフルエンザは若い人もたくさん死にますし、とくに乳幼児の死亡者数が高齢者を上回る場合もあったりして、もし死亡者の絶対数が同じだとすると、一般的な「怖さ」はインフルエンザのほうが新型コロナよりも大きそうです。
・もちろん、2020年の日本の新型コロナの死者が3500人ですんだのは、緊急事態宣言を含む大規模な社会的な抑制策がとられたからです。ただ、日本において、例年インフルエンザによる1万人の死者が社会的に許容されていたことを考えれば、結果論で言えば、2020年の日本の新型コロナの抑制策の厳しさは過剰であった(死者数1万人になる程度の厳しさで十分であった)とも言えます。
・2020年の日本全体の死亡者数は、前年に比べて1万人近く減りました。とくに、例年10万人程度いる肺炎(ただし新型コロナによる肺炎を除く)の死亡者が1万6千人も減少しました。
年間死亡数11年ぶり減 コロナ対策で感染症激減
・肺炎には主に誤嚥性肺炎と感染性肺炎がありますが、誤飲性肺炎の死亡者が急に減る理由はないでしょうから、1万6千人もの肺炎死亡者数減少は、主に、インフルエンザなどを含む感染性肺炎の死亡者の減少と考えられます。つまり、2020年には例年1万人いるインフルエンザの死亡者がほぼゼロになったわけです。
・とにかく、2020年はインフルエンザなどによる肺炎の死亡者が1万6千人減りました。。あれ?となると、、少しおかしなコトに気づきます。死亡者の多くは死亡する直前は重症者であったはずで、2020年の肺炎の死亡者数(≒肺炎の重症者数)が例年よりも1万6千人減ったんなら、重症の肺炎患者の治療にあたる高度な医療リソース(病床や人工呼吸器やECMOなどの高度な医療機器や、呼吸専門医などの人的リソース)が例年よりも1万6千人分浮いていたはずです。それを、そのまま新型コロナの治療に割り当てていれば、医療リソースの逼迫とか、ましてや医療崩壊なんか起こるはずがないのでは???あれれ??何が起こってるんだろう??
・まず、今回のコロナ禍で、高度な医療リソース(病床、人工呼吸器、ECMO、専門医など)の逼迫、ひいては、医療崩壊に近い状態が起こっているコト自体は事実でしょう。さすがに、本当は医者も病床も余ってるのに、政府も医師会もそれを隠して騒ぎ立てている、というのはないです。
・じゃあ、例年の1万人のインフルエンザの死者数(≒高度な治療を必要とする重症者数)で医療リソース逼迫が起きないのに、なぜ、新型コロナは3500人の死者数で医療逼迫がおきるのか?その違いは何でしょうか??
・この理由として、「インフルエンザは人工呼吸器やECMOといった高度な治療を必要とする重症状態になることは、ほとんどない」と言われることがあります(実際、他の方の回答の中にこういう趣旨のものがあります)。しかしながら、普通に考えて、例年のインフルエンザの死亡者1万人は、その「ほとんど起きないこと」が起きた人でしょう。結果的に死亡した人は、死亡する直前には重症者だったはずです。
・だんだん核心に近づいてきました。となると、残る可能性は、、。結論から言うと、インフルエンザの死者1万人でも医療リソースが逼迫しない理由は、「インフルエンザでは、たとえ重症になっても、人工呼吸器やECMOといった高度な医療を提供されないから」です。日本では、インフルエンザの場合、たとえ本来は高度な治療を必要とする重症になったとしても、高度医療は提供されない(そのまま放置されて死亡する)ために、インフルエンザでは(とくに高度な)医療リソースの逼迫が起きないんです。
・そんなハズはない、医療従事者は最善を尽くしている、と反論(反発)されるかもしれませんが、日本の医療システム全体というマクロな視点で見れば、そういうことです。
・なぜ、新型コロナでは重症者には高度な治療が提供される(その結果、医療リソースの逼迫が起きる)のに対して、インフルエンザでは重症者に必要な高度な医療が提供されないで放置される(その結果、医療リソースの逼迫は起きない)のでしょうか?
・その理由は、インフルエンザは町医者が診られるの対して、新型コロナは専門病院でしか診られないから、に尽きるでしょう。
・インフルエンザでは、まずかかりつけ医、そこで面倒が見られないほど重症化すると地域の病院に入院する、更に重症化すると専門病院に転院することになります。その過程で、結果的に手遅れになって(本来必要であった高度な医療を提供されることなく)死んでしまう人がかなりいるのでしょう。言い換えれば、インフルエンザでは、もし最初から専門病院に入院していれば死ななかったであろう人が、多数死亡しているということです。
・それに対して、新型コロナは、(少なくとも今現在は)町医者や地域の病院を飛び越して、いきなり専門病院に入院するという仕組みになっています。結果として、必要な人(重傷者)には確実に高度な医療が提供される一方で、高度な医療リソースがすぐに逼迫してしまう、というわけです。
・となると、今回のコロナ禍の収束の道筋(の一つ)が見えてきました。やるべきことは、新型コロナについても、従来のインフルエンザと同様に、(本来必要とする人に対しても)高度な医療を提供しない、とすることです。もちろん、あからさまに医療拒否するなんてことはできませんが、インフルエンザと同様に「医療システム全体」としてそういう(本来必要とする人にも高度な医療を提供しない)体制にするということです。具体的には、よく言われるように、「新型コロナを5類に指定替えして町医者で診るようにする」ということになるでしょう。その結果、ほぼ確実に、「お医者さんは全力を尽くしてくれたんだけど力及ばず亡くなってしまった」という新型コロナの死亡者が今より増えますが、それを社会全体として許容する、ということです。
◎あまりに過激に書き過ぎた、と思えてきたので補足。
まず、大前提として、私は、インフルエンザについて個々のお医者さんが最善を尽くしていないと貶めているつもりは全くなくて、「日本の医療システム全体として」そういう仕組みになっている、と主張しています。
「日本の医療システム全体として」インフルエンザではごく少数の患者にしか本当の最善(最先端)の治療を行わない仕組みになっている、かつ、それが一般社会にも当然のこととして受けいれられている、ということです。
それに対して、新型コロナは、無症状や軽症の段階から専門病院でしか診られない、という縛りをつけてしまったせいで、従来のインフルエンザなどではごく自然に働いていた、日本の医療システム全体として、高度な専門医療になればなるほど、受けられる患者の絶対数を絞っていく(患者を選択する)仕組みが働かなくなってしまっている、ということでしょう。
例えるなら、入試という仕組みを無くして、全ての人に最善の教育を与えようとしたら、東大がパンクした、みたいな話だと思っています。
もちろん、全ての学校の全ての先生が、自分の生徒に最高の教育を受けさせようと最善を尽くすわけですが、日本の教育システム全体として、「本当に最高の教育を受ける生徒の数」を絞る仕組みは厳然として存在するわけで。
医療システムというのは、あらためて考えてみれば不思議なシステムでして、当然ながら高度な医療になればなるほど医療リソースの絶対数(供給量)は減ります。しかしながら、人はいつか必ず死にますから、誰もが必ず(高度な医療を必要とする)重症者になる。つまり、医療リソース(医療の供給側)は高度になればなるほど数が減るのに、医療の需要そのものは高度な医療だからといって全く減らない。何もしなければ絶対に需給バランスがとれないわけで、どこかに必ず、高度な医療の需要を(本来必要とされる量よりも)抑えて供給とマッチさせる仕組みが備わっているはずです。
経済の教科書であれば、需要超過の場合は価格を上げて需要を減らしますが、日本の医療システムの場合は「価格」は変えられませんから、とにかく、価格(市場原理)ではない何らかの「謎の仕組み」が存在して需要を抑制していた(その結果、需給がマッチして医療逼迫が発生しなかった)、と考える以外にないです。
ところが、今回の新型コロナは、はからずも、その「(高度な医療に対する需要を本来の量よりも抑制して需給をマッチさせる)謎の仕組み」をバイパスしてしまった結果、需要の大幅な超過、すなわち、医療崩壊が起きたということでしょう。
「高度な医療に対する需要量を抑制する(市場原理ではない)謎の仕組み」が何なのかはよくわかりませんが、例えば、
・病状の悪化につれて、かかりつけ
医 → 地域の病院 → 専門病院 と転院するところで必然的に発生する遅延(結果的に手遅れになる)とか、手続き的あるいは心理的に障壁がある?
・あるいは、純粋に医学的に「転院」によって患者にかかる負担が、高度医療のメリットよりも大きいという判断?(この負担は、もし軽症のときから専門病院に入院していればなかったものです)
・もしかしたら、医者の側にも、転院なんかしないでもうちで十分診られるというプライドみたいなものがある?
・本当によくわかりませんが、それこそ、医療従事者の間に学閥みたいなものがあって、〇〇専門病院に転院できるのは、〇〇大卒のお医者さんの紹介状があるときだけ、みたいな暗黙の縛りがある?(つまり、最初のかかりつけ医の選択の時点で、重症化したときに高度治療を受けられるかどうかが決まっていた?)
・あるいは患者の側にも高度医療に対する忌避感(「チューブ人間」というか、そんなことまでして生かされたくない、みたいな)がかなり強い?
とかなんでしょうか。