祝!言葉の格闘、子供科学相談室は通年になりました
2019年春、NHKの夏休み子供科学相談室は、通年番組に格上げされました。めでたいことです。少数ですが、NHKにはとてもよい子供向け番組があり、いままでも、『ユウガタ・クインテット』、『考えるカラス』、『<旧>プレキソ英語』など、このブログで紹介してきましたが、それらを高く評価する声はあまり聞こえませんでした。そのうち、それらの番組は終了しそれを発展させることもなかったようです。
 夏休み子供科学相談室は、以下のページでも繰り返し紹介してきたように、科学的な思考を養うだけでなく、(大人にとっても)言葉の使い方の訓練として秀逸であるにも拘らず、夏の限られた時期だけなので惜しいことだと思ってきました。ところが、ここ数年、夏休みだけでなく冬休み子供科学相談室が始まるなど、人気が高まる兆しが見えてきました。とうとう、今春から通年番組に昇格されることになりました。この10連休には9日間連続で放送されるというめでたさ。聞き逃しサービス(らじるらじる)でも例外的に一か月間聴けるサービスも始まりました。
夏休み子供科学相談室は、以下のページでも繰り返し紹介してきたように、科学的な思考を養うだけでなく、(大人にとっても)言葉の使い方の訓練として秀逸であるにも拘らず、夏の限られた時期だけなので惜しいことだと思ってきました。ところが、ここ数年、夏休みだけでなく冬休み子供科学相談室が始まるなど、人気が高まる兆しが見えてきました。とうとう、今春から通年番組に昇格されることになりました。この10連休には9日間連続で放送されるというめでたさ。聞き逃しサービス(らじるらじる)でも例外的に一か月間聴けるサービスも始まりました。
言葉の格闘、夏休み子供科学相談室は9月まで聴けます!1/2
「Why?」の疑問に対する二種類の答え方
2018-9冬、言葉の格闘、子供科学相談室がまた始まりました
 何がこの番組の注目点かというと、すべて生放送、しかも、音声だけで、だれだか分からない子供に、内容を理解させるという試練が学者とアナウンサーに課せられるということです。なんでも映像で、しかも結論の分かった大衆受けすること、慣れ合いばかりが主流となるマスコミの流れに逆行しているという点です。これは大衆社会の競争の法則に反している、きわめて特異なことだと思います。ひょっとしたら、局はこの番組をアナウンサーの修行の場としてとらえているのかもしれません。そうだとしたらNHKもまだ捨てたものではないでしょう。
何がこの番組の注目点かというと、すべて生放送、しかも、音声だけで、だれだか分からない子供に、内容を理解させるという試練が学者とアナウンサーに課せられるということです。なんでも映像で、しかも結論の分かった大衆受けすること、慣れ合いばかりが主流となるマスコミの流れに逆行しているという点です。これは大衆社会の競争の法則に反している、きわめて特異なことだと思います。ひょっとしたら、局はこの番組をアナウンサーの修行の場としてとらえているのかもしれません。そうだとしたらNHKもまだ捨てたものではないでしょう。
私はなるべくこの番組を注意して聴くようにしているのですが、いくつか改善も近年行われたようです。
⓵ 一つの質問に対して複数の先生に答えてもらおうとしていること。たとえば、植物につく害虫についても質問には、まず植物の先生、そのあと、昆虫の先生に答えてもらうということがありました。
② 昨年出た質問に対して出された課題がその後どうなったか、数か月後に質問者に訊いてみるという企画。上の害虫の質問は昨年の夏にでたのですが、その後、先生によって提案された方法が効果的だったかどうか、先日の番組では再質問が行われました。ちなみに、有効でなかったというのが結果でした。うまく行ったという結果より失敗したということの方が次の対策を練ることにつながるのでよりよい展開でしょう。
③ 専門用語が出てきた場合、アナウンサーが割り込んで解説をする。
 ⓵は課題を「膨らませる」のでとても有効です。同じ問題でも違う立場、(この場合、虫か植物か、ですね)、で考えることに導きます。科学といえども、植物の先生は植物より、虫の先生は虫よりの立場でものを言いがちだということも子供の段階でうすうす気づくというのも大きな経験です。
⓵は課題を「膨らませる」のでとても有効です。同じ問題でも違う立場、(この場合、虫か植物か、ですね)、で考えることに導きます。科学といえども、植物の先生は植物より、虫の先生は虫よりの立場でものを言いがちだということも子供の段階でうすうす気づくというのも大きな経験です。
②は、私がとくに好ましいと思う点です。前からこの番組で気になっていたのは、「~ちゃん、分かったあ?」と訊いて「うん、分かった」という答えを半ば強制する点です。冬休みの番組では、タレントさんが「すっきりした?」などと言うこともありました。疑問の解決は次の課題を呼ぶというのが、科学に限らず世の中の原則。解決のなかに次の問題の萌芽が含まれているということを知るのがこういう番組の意義だと思うのですが、「分かった」と子供に言わせることで思考の流れを断ち切る方向に誘導してしまいます。再質問の新企画は、質問の答えで問題を終わらせません。答が余韻を引き、行動を促し、半年にわたる理論と実践の循環へと誘導します。放送始まって以来、この効果を生み出す番組が今まであったでしょうか。たいてい、「ああ、面白かった」で終わり、忘れられ、後は視聴率というリヴァイアサン、つまり怪物がのさばるという結末を迎えます。
③には、多少気になる点があります。以前から、先生たちが、聴いている子供が知らないと思える専門用語を、うまく割り込んで解説、または補助の質問をしてくれるFというアナウンサーがいました。どうも、この春から局の申し合わせで他のアナウンサーもそれをしてくれということになったようです。ところが、タイミングが悪い、割り込みが多すぎるということがあって、質問と答えの流れが断ち切られることがときどきあるようです。このとき、アナウンサーは、解説をするか、質問と答えの流れを重んじるか、を考え、直感的にバランスをとる必要があるのですが、まだまだかなというのが私の印象です。この番組にかぎらず、最近、元気よく、早口に話すアナウンサーが目立ちますが、そういう人気アナウンサーが登場すると、不要な割り込み、ご機嫌取りが多く耳障りに聞こえます。考えていないのです。漫才のように相手にどう反応するか、どうやって反応を引き出すかしか念頭にないのかと思います。
 言語活動は、何を言うか、ということと、何を言わないかによって成り立ちます。表面的に音声にでる言葉の背景で、氷山の下に隠れている氷塊も大いに活動しているのです。一見見えない部分ですが、ずっと通して聴いていると、この人は考えて言っているな、この人は相手に気に入られることしか考えていないな、ということが分かるというものです。ときどき、政治家の失言などで、その氷山の下の部分が露呈することがあります。数年前、「自衛隊も応援しています」と国会議員の選挙の演説で口走って辞職した大臣がいましたが、三権分立の原則という氷塊の部分に思念が及んでないことが分かり、有権者に不安を抱かせました。(誰のことか分かる読者がいるかもしれませんが、筆者はこの政治家の考えに反対しているわけではありません。)
言語活動は、何を言うか、ということと、何を言わないかによって成り立ちます。表面的に音声にでる言葉の背景で、氷山の下に隠れている氷塊も大いに活動しているのです。一見見えない部分ですが、ずっと通して聴いていると、この人は考えて言っているな、この人は相手に気に入られることしか考えていないな、ということが分かるというものです。ときどき、政治家の失言などで、その氷山の下の部分が露呈することがあります。数年前、「自衛隊も応援しています」と国会議員の選挙の演説で口走って辞職した大臣がいましたが、三権分立の原則という氷塊の部分に思念が及んでないことが分かり、有権者に不安を抱かせました。(誰のことか分かる読者がいるかもしれませんが、筆者はこの政治家の考えに反対しているわけではありません。)
子供科学相談室では、何を言うか、何を言わないか、という言語活動の全身的な構えが試されます。この番組を通し浮彫になってくることは、いかに大人同士の会話では相手に依存しているか、ということです。何を言うか、何を言わないかなど考えもしないことが多いのです。この番組を聴くことで、「依存」ということが、二つの形をとっていることが目立ってきたので、最期にそれについて触れておきましょう。
一つは専門用語への依存です。複雑化した現代社会で生産活動をしている場合、一歩先へ進むことだけに集中します。そのため今まで人間が積み重ねてきた知識の最先端の抽象的な概念しか頭に浮かばなくなります。知識を共有する同僚や競争相手と渡り合うにはそれで十分だからです。その概念が何に基づくのかは忘れてしまうものです。自衛隊員が政治的立場から距離を置くという原則もかくして忘れ去られてしまったのです。この番組で、専門用語を「難しい言葉」と言ったり、子供が専門用語を知っていると大人が「すご~い」と言って感心したり、しますが、どんなもんでしょう。専門用語とはたんに抽象化したというだけのことで、なにも難しい言葉ではありません。その分、原初の経験から遠ざかっているということです。それを知っていたからと言ってえらいわけでもなんでもありません。こんなところにも、「専門用語」が単に自分の同僚や競争相手の人への依存によっているだけだ、ということへの自覚の乏しさが見られると思いますが。
 二つめは流行語や流行する言い回しへの依存です。なぜ人は、標準的な表現があることを知っていながら、流行表現を使うか。無意識に行われることでしょうが、それは自分があなたと同様のグループに属している人間だということをアッピールするためです。村八分にしないでくださいねというへつらいとい言ったら言い過ぎでしょうか。ともかく人間関係のための言語であって、科学の言語には相応しくありません。さすがに科学者である各先生はそういう表現に毒されていません。科学的事実という共通事項を子供と共有するだけに言葉を使っているからです。もっとも、「~ちゃん、わかるかなあ?」の類の幼児相手の言葉は耳障りです。大人と話すのと同じ話し方をする先生の方が私には好感がもてます。問題はアナウンサーの方、とりわけ人気アナウンサーです。ここでは一つだけ例を挙げてこの記事を締めくくりましょう。それは「大丈夫」の多用です。私たちの日常生活でも、スーパーなどで、「駐車券、大丈夫ですか。」の類をよく耳にしませんか。転んだ人に「大丈夫ですか」なら分かりますが、駐車券であろうと、レジブクロであろうと、なんでも同意を求める際に「大丈夫」。答える方も「大丈夫です」。番組では、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?。」というのがアナウンサーにも及んでいるようですが、局の方には方針がなさそうです。先日も、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?」と訊かれて、質問者は、流行表現によって相手に合わせることを知らないので、「大丈夫です。」とは答えませんした。なんて答えたと思いますか。
二つめは流行語や流行する言い回しへの依存です。なぜ人は、標準的な表現があることを知っていながら、流行表現を使うか。無意識に行われることでしょうが、それは自分があなたと同様のグループに属している人間だということをアッピールするためです。村八分にしないでくださいねというへつらいとい言ったら言い過ぎでしょうか。ともかく人間関係のための言語であって、科学の言語には相応しくありません。さすがに科学者である各先生はそういう表現に毒されていません。科学的事実という共通事項を子供と共有するだけに言葉を使っているからです。もっとも、「~ちゃん、わかるかなあ?」の類の幼児相手の言葉は耳障りです。大人と話すのと同じ話し方をする先生の方が私には好感がもてます。問題はアナウンサーの方、とりわけ人気アナウンサーです。ここでは一つだけ例を挙げてこの記事を締めくくりましょう。それは「大丈夫」の多用です。私たちの日常生活でも、スーパーなどで、「駐車券、大丈夫ですか。」の類をよく耳にしませんか。転んだ人に「大丈夫ですか」なら分かりますが、駐車券であろうと、レジブクロであろうと、なんでも同意を求める際に「大丈夫」。答える方も「大丈夫です」。番組では、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?。」というのがアナウンサーにも及んでいるようですが、局の方には方針がなさそうです。先日も、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?」と訊かれて、質問者は、流行表現によって相手に合わせることを知らないので、「大丈夫です。」とは答えませんした。なんて答えたと思いますか。
「平気です。」
とても小さなことでしたが、私には印象的でした。
■










 最初に文系 - humanities-と理系 -science-の対立が言論界で論争の的になったのは、1959年、英国で、C.P. スノーが『二つの文化と科学革命』(The Two Cultures) という論文を発表したときのことでしょう。スノーは著名は物理学者で、かつ推理小説なども書いていました。この論文では、以下のようなエピソードが挙げられているそうです。伝統的な教養人とされる人々の集まりにでたら、科学者はものを知らないという話をしていたので、彼が「熱力学の第二法則」を知っていますかと訊いたら、はっきりした答えが返ってこなかった。スノーに言わせれば、シェイクスピアの何かを読んだことがありますかと同じレベルの質問をしたつもりだったそうです。文系、理系ということが話題になるのは、このころから理系の立場の人の不満表明として表れていました。一言で文系といいますが、欧州では中世以来の伝統的なラテン語教育に基づく文系教養主義が制度化し、不動の権威を持っていたのです。それに対し、一矢を報いるという性格の発言だったのでしょう。発表された年月にも注意していただきたいです。原子力の力で世界の命運を握るのは一握りの核物理学者だということが分かってきて、「文系」の学者の土台が揺らぎだしたころのことです。この文脈で初めてスノーの論文の歴史的価値が分かります。
最初に文系 - humanities-と理系 -science-の対立が言論界で論争の的になったのは、1959年、英国で、C.P. スノーが『二つの文化と科学革命』(The Two Cultures) という論文を発表したときのことでしょう。スノーは著名は物理学者で、かつ推理小説なども書いていました。この論文では、以下のようなエピソードが挙げられているそうです。伝統的な教養人とされる人々の集まりにでたら、科学者はものを知らないという話をしていたので、彼が「熱力学の第二法則」を知っていますかと訊いたら、はっきりした答えが返ってこなかった。スノーに言わせれば、シェイクスピアの何かを読んだことがありますかと同じレベルの質問をしたつもりだったそうです。文系、理系ということが話題になるのは、このころから理系の立場の人の不満表明として表れていました。一言で文系といいますが、欧州では中世以来の伝統的なラテン語教育に基づく文系教養主義が制度化し、不動の権威を持っていたのです。それに対し、一矢を報いるという性格の発言だったのでしょう。発表された年月にも注意していただきたいです。原子力の力で世界の命運を握るのは一握りの核物理学者だということが分かってきて、「文系」の学者の土台が揺らぎだしたころのことです。この文脈で初めてスノーの論文の歴史的価値が分かります。 夏休み子供科学相談室は、以下のページでも繰り返し紹介してきたように、科学的な思考を養うだけでなく、(大人にとっても)言葉の使い方の訓練として秀逸であるにも拘らず、夏の限られた時期だけなので惜しいことだと思ってきました。ところが、ここ数年、夏休みだけでなく冬休み子供科学相談室が始まるなど、人気が高まる兆しが見えてきました。とうとう、今春から通年番組に昇格されることになりました。この10連休には9日間連続で放送されるというめでたさ。聞き逃しサービス(らじるらじる)でも例外的に一か月間聴けるサービスも始まりました。
夏休み子供科学相談室は、以下のページでも繰り返し紹介してきたように、科学的な思考を養うだけでなく、(大人にとっても)言葉の使い方の訓練として秀逸であるにも拘らず、夏の限られた時期だけなので惜しいことだと思ってきました。ところが、ここ数年、夏休みだけでなく冬休み子供科学相談室が始まるなど、人気が高まる兆しが見えてきました。とうとう、今春から通年番組に昇格されることになりました。この10連休には9日間連続で放送されるというめでたさ。聞き逃しサービス(らじるらじる)でも例外的に一か月間聴けるサービスも始まりました。 何がこの番組の注目点かというと、すべて生放送、しかも、音声だけで、だれだか分からない子供に、内容を理解させるという試練が学者とアナウンサーに課せられるということです。なんでも映像で、しかも結論の分かった大衆受けすること、慣れ合いばかりが主流となるマスコミの流れに逆行しているという点です。これは大衆社会の競争の法則に反している、きわめて特異なことだと思います。ひょっとしたら、局はこの番組をアナウンサーの修行の場としてとらえているのかもしれません。そうだとしたらNHKもまだ捨てたものではないでしょう。
何がこの番組の注目点かというと、すべて生放送、しかも、音声だけで、だれだか分からない子供に、内容を理解させるという試練が学者とアナウンサーに課せられるということです。なんでも映像で、しかも結論の分かった大衆受けすること、慣れ合いばかりが主流となるマスコミの流れに逆行しているという点です。これは大衆社会の競争の法則に反している、きわめて特異なことだと思います。ひょっとしたら、局はこの番組をアナウンサーの修行の場としてとらえているのかもしれません。そうだとしたらNHKもまだ捨てたものではないでしょう。 ⓵は課題を「膨らませる」のでとても有効です。同じ問題でも違う立場、(この場合、虫か植物か、ですね)、で考えることに導きます。科学といえども、植物の先生は植物より、虫の先生は虫よりの立場でものを言いがちだということも子供の段階でうすうす気づくというのも大きな経験です。
⓵は課題を「膨らませる」のでとても有効です。同じ問題でも違う立場、(この場合、虫か植物か、ですね)、で考えることに導きます。科学といえども、植物の先生は植物より、虫の先生は虫よりの立場でものを言いがちだということも子供の段階でうすうす気づくというのも大きな経験です。 言語活動は、何を言うか、ということと、何を言わないかによって成り立ちます。表面的に音声にでる言葉の背景で、氷山の下に隠れている氷塊も大いに活動しているのです。一見見えない部分ですが、ずっと通して聴いていると、この人は考えて言っているな、この人は相手に気に入られることしか考えていないな、ということが分かるというものです。ときどき、政治家の失言などで、その氷山の下の部分が露呈することがあります。数年前、「自衛隊も応援しています」と国会議員の選挙の演説で口走って辞職した大臣がいましたが、三権分立の原則という氷塊の部分に思念が及んでないことが分かり、有権者に不安を抱かせました。(誰のことか分かる読者がいるかもしれませんが、筆者はこの政治家の考えに反対しているわけではありません。)
言語活動は、何を言うか、ということと、何を言わないかによって成り立ちます。表面的に音声にでる言葉の背景で、氷山の下に隠れている氷塊も大いに活動しているのです。一見見えない部分ですが、ずっと通して聴いていると、この人は考えて言っているな、この人は相手に気に入られることしか考えていないな、ということが分かるというものです。ときどき、政治家の失言などで、その氷山の下の部分が露呈することがあります。数年前、「自衛隊も応援しています」と国会議員の選挙の演説で口走って辞職した大臣がいましたが、三権分立の原則という氷塊の部分に思念が及んでないことが分かり、有権者に不安を抱かせました。(誰のことか分かる読者がいるかもしれませんが、筆者はこの政治家の考えに反対しているわけではありません。) 二つめは流行語や流行する言い回しへの依存です。なぜ人は、標準的な表現があることを知っていながら、流行表現を使うか。無意識に行われることでしょうが、それは自分があなたと同様のグループに属している人間だということをアッピールするためです。村八分にしないでくださいねというへつらいとい言ったら言い過ぎでしょうか。ともかく人間関係のための言語であって、科学の言語には相応しくありません。さすがに科学者である各先生はそういう表現に毒されていません。科学的事実という共通事項を子供と共有するだけに言葉を使っているからです。もっとも、「~ちゃん、わかるかなあ?」の類の幼児相手の言葉は耳障りです。大人と話すのと同じ話し方をする先生の方が私には好感がもてます。問題はアナウンサーの方、とりわけ人気アナウンサーです。ここでは一つだけ例を挙げてこの記事を締めくくりましょう。それは「大丈夫」の多用です。私たちの日常生活でも、スーパーなどで、「駐車券、大丈夫ですか。」の類をよく耳にしませんか。転んだ人に「大丈夫ですか」なら分かりますが、駐車券であろうと、レジブクロであろうと、なんでも同意を求める際に「大丈夫」。答える方も「大丈夫です」。番組では、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?。」というのがアナウンサーにも及んでいるようですが、局の方には方針がなさそうです。先日も、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?」と訊かれて、質問者は、流行表現によって相手に合わせることを知らないので、「大丈夫です。」とは答えませんした。なんて答えたと思いますか。
二つめは流行語や流行する言い回しへの依存です。なぜ人は、標準的な表現があることを知っていながら、流行表現を使うか。無意識に行われることでしょうが、それは自分があなたと同様のグループに属している人間だということをアッピールするためです。村八分にしないでくださいねというへつらいとい言ったら言い過ぎでしょうか。ともかく人間関係のための言語であって、科学の言語には相応しくありません。さすがに科学者である各先生はそういう表現に毒されていません。科学的事実という共通事項を子供と共有するだけに言葉を使っているからです。もっとも、「~ちゃん、わかるかなあ?」の類の幼児相手の言葉は耳障りです。大人と話すのと同じ話し方をする先生の方が私には好感がもてます。問題はアナウンサーの方、とりわけ人気アナウンサーです。ここでは一つだけ例を挙げてこの記事を締めくくりましょう。それは「大丈夫」の多用です。私たちの日常生活でも、スーパーなどで、「駐車券、大丈夫ですか。」の類をよく耳にしませんか。転んだ人に「大丈夫ですか」なら分かりますが、駐車券であろうと、レジブクロであろうと、なんでも同意を求める際に「大丈夫」。答える方も「大丈夫です」。番組では、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?。」というのがアナウンサーにも及んでいるようですが、局の方には方針がなさそうです。先日も、「~ちゃん、難しいかな。大丈夫?」と訊かれて、質問者は、流行表現によって相手に合わせることを知らないので、「大丈夫です。」とは答えませんした。なんて答えたと思いますか。 たしか、2年前からNHK AM第1『子供科学相談』は冬休みにも行われています。だいぶ人気番組になったようで、聞き逃しサービスのラジルラジルも昨年の夏は、ほかの番組より長く聴けるようになっていました。
たしか、2年前からNHK AM第1『子供科学相談』は冬休みにも行われています。だいぶ人気番組になったようで、聞き逃しサービスのラジルラジルも昨年の夏は、ほかの番組より長く聴けるようになっていました。 昨年の夏には、「すっきりしましたか?」というタレントさんの発言に苦言を述べました。科学の説明は宗教とちがって、常に覆される可能性があるので、あまり簡単に「すっきり」してもらっては困るのです。今回の冬も、まだ、答えを急ぐというムードが見られます。ある答えがそれでおしまいにならず、次の問へと導くような工夫があったらと思うことがよくあります。
昨年の夏には、「すっきりしましたか?」というタレントさんの発言に苦言を述べました。科学の説明は宗教とちがって、常に覆される可能性があるので、あまり簡単に「すっきり」してもらっては困るのです。今回の冬も、まだ、答えを急ぐというムードが見られます。ある答えがそれでおしまいにならず、次の問へと導くような工夫があったらと思うことがよくあります。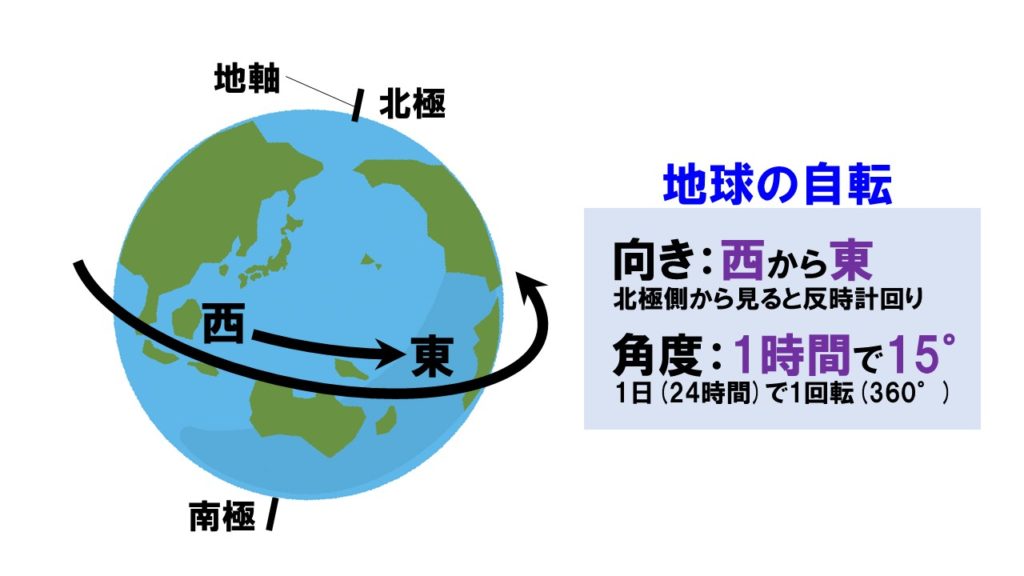 的側面のことを述べたいのでしょう。しかし、
的側面のことを述べたいのでしょう。しかし、
 外は、多少の違いはあれ、表にも裏にも気孔があるというのが実際だそうです。その答えを聴いてスタジオの先生たちは膝を打って(かどうか知りませんが)、大喜びで、先入観なしに事実を観察したその6年生を称えていました。小学生も高学年になると、質問が「哲学的」なものから、鋭い観察眼に基づくものが多くなります。先入観でしかものを見ない大人とは違う新鮮な疑問です。そういう目を受験に追われる中等教育の波にさらわれずにも持ち続けてほしいものです。最期に、この質問者に対しては、「ミズハコベの場合はどうだか調べてみたらどうでしょう」、という次なる課題が与えられていました。好ましい展開でした。
外は、多少の違いはあれ、表にも裏にも気孔があるというのが実際だそうです。その答えを聴いてスタジオの先生たちは膝を打って(かどうか知りませんが)、大喜びで、先入観なしに事実を観察したその6年生を称えていました。小学生も高学年になると、質問が「哲学的」なものから、鋭い観察眼に基づくものが多くなります。先入観でしかものを見ない大人とは違う新鮮な疑問です。そういう目を受験に追われる中等教育の波にさらわれずにも持ち続けてほしいものです。最期に、この質問者に対しては、「ミズハコベの場合はどうだか調べてみたらどうでしょう」、という次なる課題が与えられていました。好ましい展開でした。 さて、「鳥人間がいれば学校に遅刻しませんか」という質問への答えはよく考えられていたので、ここで答えの構成をご紹介しましょう。
さて、「鳥人間がいれば学校に遅刻しませんか」という質問への答えはよく考えられていたので、ここで答えの構成をご紹介しましょう。