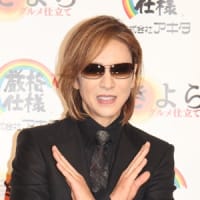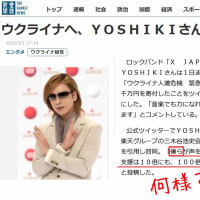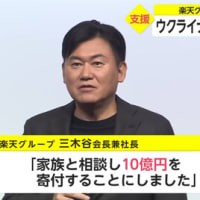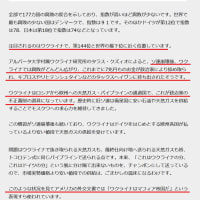僕の「よく漂流するリンク集」中ほどにある沖縄出身の古代史研究家のサイトですが・・
古代の貝の装身具(イモガイ製貝輪は北海道伊達市の遺跡からも発掘されているし・・
それ以前の縄文時代には黒曜石矢尻と共にシベリアとの貴重な交易品)が太陽信仰に関係しているのではないかという書き込みを読んでふと思ったのだが・・
天皇制の三種の神器の鏡・勾玉・剣等はそれ以前の縄文時代の信仰の換骨奪胎や変形なのかもしれないナーと思う。
蛇信仰を受け継ぐ神奈備という蛇がとぐろを巻いた形の山への信仰もまた。銅鐸もたぶんシャーマンの儀式の際に使われたものだろうと思う。
そしてそれはズバリと言ってー
シベリアのシャーマンが光り輝き、音の鳴るものを体中につけて踊るのを見るにつけても、シャーマンの儀式に起源があるのではないかと思う。
全くの独断と偏見で言うと、勾玉は再生のイメージが強い蛇や胎児を連想させられるし・・鏡は、沖縄での太陽信仰や東北・北海道での日高見国や伊勢等の冬至の太陽を弓で射て太陽の再生を祝う祭を連想させられる。
鏡もまた吉野裕子氏の本にあったように、蛇や蛇の光り輝く目を「カガミ」と呼んだ例から推測するに、蛇信仰の名残なのかもしれないナと思う。
剣についてはー台湾先住民や東南アジアの蛇をかたどったという蛇行剣や、沖縄のシャーマンのユタ等が持って歩き霊がそこに降臨するというススキや、同様に神が天から降臨するという御柱等の神聖な柱や、東北や古代日本のシャーマンのイタコの梓弓や・・古代の金属加工者たちの信仰もまた連想させられる。
それらについての、系統だった研究によって縄文時代の信仰のいったいどの部分・・、どのような地方に、どのような形で残ったのかを調べることが急務ではないかと思う。
そしてそれらが特に濃厚に残ったのが、沖縄やアイヌ民族であり、古代日本でもあったとおもうのだが・・
古代の貝の装身具(イモガイ製貝輪は北海道伊達市の遺跡からも発掘されているし・・
それ以前の縄文時代には黒曜石矢尻と共にシベリアとの貴重な交易品)が太陽信仰に関係しているのではないかという書き込みを読んでふと思ったのだが・・
天皇制の三種の神器の鏡・勾玉・剣等はそれ以前の縄文時代の信仰の換骨奪胎や変形なのかもしれないナーと思う。
蛇信仰を受け継ぐ神奈備という蛇がとぐろを巻いた形の山への信仰もまた。銅鐸もたぶんシャーマンの儀式の際に使われたものだろうと思う。
そしてそれはズバリと言ってー
シベリアのシャーマンが光り輝き、音の鳴るものを体中につけて踊るのを見るにつけても、シャーマンの儀式に起源があるのではないかと思う。
全くの独断と偏見で言うと、勾玉は再生のイメージが強い蛇や胎児を連想させられるし・・鏡は、沖縄での太陽信仰や東北・北海道での日高見国や伊勢等の冬至の太陽を弓で射て太陽の再生を祝う祭を連想させられる。
鏡もまた吉野裕子氏の本にあったように、蛇や蛇の光り輝く目を「カガミ」と呼んだ例から推測するに、蛇信仰の名残なのかもしれないナと思う。
剣についてはー台湾先住民や東南アジアの蛇をかたどったという蛇行剣や、沖縄のシャーマンのユタ等が持って歩き霊がそこに降臨するというススキや、同様に神が天から降臨するという御柱等の神聖な柱や、東北や古代日本のシャーマンのイタコの梓弓や・・古代の金属加工者たちの信仰もまた連想させられる。
それらについての、系統だった研究によって縄文時代の信仰のいったいどの部分・・、どのような地方に、どのような形で残ったのかを調べることが急務ではないかと思う。
そしてそれらが特に濃厚に残ったのが、沖縄やアイヌ民族であり、古代日本でもあったとおもうのだが・・