ブログ友のバロンさんが、先日、遠野で仕入れてきた情報によると、日本の馬には、『和芝』という、牧草?がいいそうです。日本の馬と言っても在来種を指すわけではなく、日本に暮らす馬ということです。
遠野は、今は、乗用馬の立派な産地です。外国の品種も取り入れられています。
『和芝』というのがどういうものなのかわかりません。ネットでは高麗芝に対して日本の芝を指している様な感じです。
まきばには、いろいろな草が生えています。Hさんがかって牧草の種を撒いたので、中には、牧草らしき草もありますが、ほとんど、イネ科の雑草と呼んでいいと思います。
草を食べるポニー達を見ていて、ここに、『和芝』が生えているのだろうか?と思いました。

牛も一緒に草をはんでいますが、可愛そうに、この長さの草を牛が食べるのは大変なんです。
牛は、前歯が下顎にしか生えていないのです。
草を食べる時は、長めの草を舌で巻き取り、口の中に運びます。だから、短い草は食べ難いのです。
馬は、前歯で千切って口の中に入れます。ですから、このように短めの草の方が食べやすいのです。
この草は『和芝』なのでしょうか?

アポ 「そうかもね。ムシャ。」
『和』ということで、もうひとつ。

今、私が使っている机兼作業台です。
これは、和裁の裁ち板だったものです。
栃木のある有名な建物を作った大工の棟梁が、娘さんが嫁ぐ時に持たせたものです。この娘さんの娘さんが私の友人で、使い道があるのなら、と譲ってくれました。恐れおおい気もしたのですが、捨てたくない気持ちをわかってくれるだけでよいという友人の言葉に甘えて、使わせてもらうことにしました。
長さは150cm位あり、先のほうは、棚の中に入れてます。

この足は取り外し可能です。
しかも、入れやすく、外し難いんです。高さを調節するために、材木を2本、足の下に敷いてます。
足の右の方に、黒っぽい点が見えるでしょう?これは、木の釘を埋めてあるんです。一枚板なので、反るのを防いでいるのかも?両側面に4本ずつ打ち込まれています。

棚の中に入っている側には、こんな裂け目があります。
大きな木の表面に近い所から取られた材木のようで、これは、元々木にあったものです。作業をする面が完璧ならば、裏まで平らな必要はないわけです。
木の性質を知っている大工さんだからこそ、こんなギリギリの取り方が出来るのでしょう。

棟梁の娘さんが裁縫をした跡です。隙間なくヘラの跡があります。
裏の裂け目は、何十年使われても、全く問題ありません。
南側の日が強く当たる所に置いても、反りもしなければ、ヒビ割れる事もありません。
私にとって、大切な宝物です。
プチ自慢話でした。
遠野は、今は、乗用馬の立派な産地です。外国の品種も取り入れられています。
『和芝』というのがどういうものなのかわかりません。ネットでは高麗芝に対して日本の芝を指している様な感じです。
まきばには、いろいろな草が生えています。Hさんがかって牧草の種を撒いたので、中には、牧草らしき草もありますが、ほとんど、イネ科の雑草と呼んでいいと思います。
草を食べるポニー達を見ていて、ここに、『和芝』が生えているのだろうか?と思いました。

牛も一緒に草をはんでいますが、可愛そうに、この長さの草を牛が食べるのは大変なんです。
牛は、前歯が下顎にしか生えていないのです。
草を食べる時は、長めの草を舌で巻き取り、口の中に運びます。だから、短い草は食べ難いのです。
馬は、前歯で千切って口の中に入れます。ですから、このように短めの草の方が食べやすいのです。
この草は『和芝』なのでしょうか?

アポ 「そうかもね。ムシャ。」
『和』ということで、もうひとつ。

今、私が使っている机兼作業台です。
これは、和裁の裁ち板だったものです。
栃木のある有名な建物を作った大工の棟梁が、娘さんが嫁ぐ時に持たせたものです。この娘さんの娘さんが私の友人で、使い道があるのなら、と譲ってくれました。恐れおおい気もしたのですが、捨てたくない気持ちをわかってくれるだけでよいという友人の言葉に甘えて、使わせてもらうことにしました。
長さは150cm位あり、先のほうは、棚の中に入れてます。

この足は取り外し可能です。
しかも、入れやすく、外し難いんです。高さを調節するために、材木を2本、足の下に敷いてます。
足の右の方に、黒っぽい点が見えるでしょう?これは、木の釘を埋めてあるんです。一枚板なので、反るのを防いでいるのかも?両側面に4本ずつ打ち込まれています。

棚の中に入っている側には、こんな裂け目があります。
大きな木の表面に近い所から取られた材木のようで、これは、元々木にあったものです。作業をする面が完璧ならば、裏まで平らな必要はないわけです。
木の性質を知っている大工さんだからこそ、こんなギリギリの取り方が出来るのでしょう。

棟梁の娘さんが裁縫をした跡です。隙間なくヘラの跡があります。
裏の裂け目は、何十年使われても、全く問題ありません。
南側の日が強く当たる所に置いても、反りもしなければ、ヒビ割れる事もありません。
私にとって、大切な宝物です。
プチ自慢話でした。













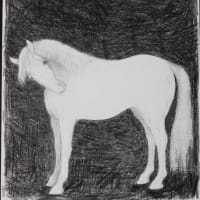
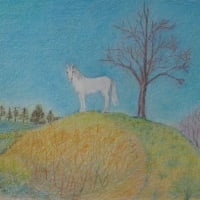
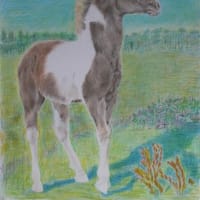





立派な作業台ですネ、いまどきこんな木の台はないでしょうね。なんにでも使えそうですね、貴重品!!
写真のような草の総称かも?
日本の庭に芝生が現れたのは、いつ頃なんでしょうね。
でしょう!
裏は裂けていますが、節がひとつもありません。
カンナをかければ、ヘラの跡も消せますが、このまま使うつもりです。
いいものを長く使うのも素敵ですね
私の友人は、子供の時、これを滑り台にして遊んだそうです。私が和裁をするので声をかけてくれました。
お気に入り…ここだと色々なことがはかどりそうですね(*^_^*)
周りの物を片付けなくては、全体が見えなくなっていました。
こうして、改めてみると、私の見方が間違っていたことに気付きました。
今夜、訂正します。
聞きかじりの情報をもう少し。「野芝は、どこにでもある」と、東種山のブチさんは言ってました。「それが、広範囲に生えていて、馬の群れの食欲を満たすだけの量が十分に残っている地域は少ない」とも言ってみえました。
だから、P太郎さんのところにもあるはず。参考になれば、幸いです。
そこで、ブチさんからの聞きかじり情報をもう少し。「野芝は、どこにでも残っているよ」「ただ、馬の群れを一年間育てるのに十分な量が、ひとつの山・地域に保存されていることはまれだ」と。
だから、P太郎さんの地域にも残っているはずです。
参考になれば幸いです。