◆ 「2025年の共通テスト」報道におかしな点あり。
大学入試センターから注意を促す文書も (ハーバー・ビジネス・オンライン)
<文/清 史弘>
10月21日のNHKの報道をきっかけとして、2025年の共通テストの情報が流れました。
2025年の共通テストとは、現在の中学2年生が新学習指導要領の元で受ける最初の共通テストです。報道では、新たな教科である「情報」を新設したうえで、現在の6教科30科目を7教科21科目に再編するとしていました。
ところが、この共通テストの報道が、誤情報とまではいえないものの、誤解を与えかねない内容、不十分な内容であったため、10月23日に大学入試センターから注意を促す文書が出されました。
なぜなら、報道は、検討中の内容が、あたかも報道通りに決まっていくような印象を与えるものになっていたからです。
これについては、高校関係者からも「おかしいのではないか」という声があがっています。ここでは、その中で説明の足りなかった部分を補います。
◆ 報道された内容の情報源は何か?
まず、事実説明の出発点を整理しましょう。
報道の中には、記事になった情報を「関係者の話」から得たとしているものがありますが、内容を考えると、その前日の10月20日に大学入試センターから、「全国都道府県教育委員会連合会会長」「指定都市教育委員会協議会会長」「全国市町村教育委員会連合会会長」「全国高等学校長協会会長」宛てに送られた「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入学共通テストの出題教科・科目等の検討状況について」(入試セ企第74号、以下「文書74」と記す。)が元になっていると考えられます。
これには、最後に「本件に関して、御意見等がある場合には、貴団体においてお取りまとめいただいた上で、令和2年11月30日(月)までに御連絡いただくようお願いいたします」とあり、これらの団体の意見によっては今後変わりうるという内容です。
したがって、現在の共通テストが6教科30科目から7教科21科目になる場合もあれば、ならない場合もあり、また報道で発表される内容が一部変更されることもあります。(一部報道には「検討中」と書いてあるものの)あたかも、報道通りになるような表現もありましたが、そうならないこともあるので、10月23日に大学入試センターからホームページで、次のような通達があったのです。
「新学習指導要領に対応した令和7年度からの大学入学共通テストの出題教科・科目等について報道がありました。大学入試センターでは、これまで、幅広い分野の専門家のご参画を得て、令和7年度からの大学入学共通テストの出題教科・科目等についての検討を行っているところです。この度、途中段階ではありますが、一定の方向性について整理を行いましたので、大学入学共通テストを共同で実施する大学関係者はもちろん、高校関係者に対しても情報提供を行い、ご意見を伺っているところです。今後、いただいたご意見をもとに、必要な修正を行ってまいります。(原文ママ)」
さて、以下においては、報道の情報源が何かではなく、10月20日に大学入試センターから提示された「文書74」を元に説明します。
◆ 共通テストで「情報」が入るというが
新学習指導要領では「情報I」「情報II」が設定されることになっていますが、「文書74」では、そのうちの必履修科目である「情報I」を「情報」として共通テストの試験科目にしては「どうか」と書かれています。
もちろんこの「情報」が、今後、共通テストの科目になる可能性もありますが、第15回大学入試のあり方に関する検討会議において、国立大学協会の岡正朗委員から「入試科目にするのであれば、教員が本当に全国にいるのか、どのレベルまで同じにできるのか」という懸念も出されています。したがって、今後どうなるのかはまだわからない状況です。
なお、一部報道で、新学習指導要領で「情報が必修に入る」というものがありましたが、現行課程でも「情報」という科目(「社会と情報」「情報の科学」)はあります。
この科目としての「情報」は2003年から実施されましたが、その時点でそれを教える専門の教員がほとんどいなかったことから、当時の教員が決められた講習を受ければ、比較的簡単に追加の形で「情報」の教員免許を取れる形になりました。
この結果、数学の教員が「情報」を担当することが多いものの、「理科」や「家庭科」の教員が担当している例が私のまわりにもいます。この延長での現在なので、「情報」の教員には、知識が浅い人も多く、そのような現状を岡委員は心配されているのでしょう。したがって、「情報」を共通テストの科目に入れる前に、教える側の質も向上すべきなのです。
◆ 共通テストの「数学ⅡBC」は
数学は現在の共通テストでは、「数学I」「数学I、数学A」「数学II」「数学II、数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」の6科目ありますが、これを「数学I」「数学I、数学A」「数学II、数学B、数学C」の3科目にするという報道でした。
(※) 多くの人は、「数学I、数学A」と「数学II、数学B、数学C」を選択することになります。
ここまでは正しいのですが、実際はもう少し踏み込んだ内容が「文書74」には書かれています。
そこには、「数学II、数学B、数学C」(以下、「数学IIBC」と記す)について書かれており、「『数学B』及び『数学C』については、『数学B』の2項目の内容(数列、統計的な推測)及び『数学C』の2項目の内容(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)に対応した出題とし、このうち3項目の内容の問題を選択解答させる」とあります。
この検討中案どおりであるとすれば、非常におかしなことを含んでいますので、少なくともこのままの形で令和7年の共通テストは実施されないと考えられます。以下にそのおかしな点を記しましょう。
おかしな点1:数学Bは、「数列」「統計的な推測」「数学と社会生活」の3項目で構成されているが、「数学と社会生活」を履修した場合、共通テストでは選ぶものがない。また、数学Cについても「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」「数学的な表現の工夫」の3項目で構成されているが、「数学的な表現の工夫」を履修した場合も共通テストでは選ぶものがない。
数学B、数学Cではどの2つを選んでもよいことになっているので、共通テストにおいて学習した項目で受験できないなどの差別があってはならない。
おかしな点2:もしも、本当に「数学B」「数学C」の中のここで指定された範囲から3項目を選ぶことになれば、この試験を受ける人は「数学B」「数学C」の両方を履修しなければならない。(例えば「数学B」だけでは3項目は選べない。)
「数学B」、「数学C」の片方だけの履修ではすまないとなれば、もはや「数学B」「数学C」と分ける意味はない。(実際、新課程において「数学B」「数学C」といった教科の分け方はいろいろな意味ですでに崩壊している。)
◆ 日本学術会議の提言が元に
実は、検討案は今年の夏に日本学術会議の数理科学委員会の中の数学教育分科会で提言された「新学習指導要領下での算数・数学教育の円滑な実施に向けた緊急提言:統計教育の実効性の向上に焦点を当てて」が元になっていると考えられていますので、そちらを見る方がこのような検討案に至った経緯はわかります。(こちらの提言についても別の問題点はあるのですが、ここでは割愛します。)
それによると、次のような説明になります。
”「数学B」では「数列」「統計的な推測」の他に「数学と社会生活」、「数学C」では「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」の他に「数学的な表現の工夫」という項目が用意されていますが、今回除かれた2つの項目は知ることを目的とする内容なので、共通テストのような試験には向かないため除外し、残りの4項目を試験に課すべきである。
しかしながら、「数学IIBC」の試験時間は70分にするのが限界であるので、3問を選択という形がよい”
このような内容の提言ですので、これに沿うように大学入試センターでも今後検討していくものと考えられます。
しかしながら、実際は、「数学II」で問わなければならない項目も多いため、試験時間を70分にしたところで3問の選択問題を解くのは時間的に厳しいので、今後は2問選択になる可能性も大いにあります。
そして、そのようにすることで「数学B」「数学C」の片方だけを履修することも可能になります。
※ 清史弘 せいふみひろ●Twitter ID:@f_sei。
数学教育研究所代表取締役・認定NPO法人数理の翼顧問・予備校講師・作曲家。小学校、中学校、高校、大学、塾、予備校で教壇に立った経験をもつ数学教育の研究者。著書は30冊以上に及ぶ受験参考書と数学小説「数学の幸せ物語(前編・後編)」(現代数学社) 、数学雑誌「数学の翼」(数学教育研究所) 等。
『ハーバー・ビジネス・オンライン』(2020.10.26)
https://hbol.jp/231018?cx_clicks_art_mdl=1_title
大学入試センターから注意を促す文書も (ハーバー・ビジネス・オンライン)
<文/清 史弘>
10月21日のNHKの報道をきっかけとして、2025年の共通テストの情報が流れました。
2025年の共通テストとは、現在の中学2年生が新学習指導要領の元で受ける最初の共通テストです。報道では、新たな教科である「情報」を新設したうえで、現在の6教科30科目を7教科21科目に再編するとしていました。
ところが、この共通テストの報道が、誤情報とまではいえないものの、誤解を与えかねない内容、不十分な内容であったため、10月23日に大学入試センターから注意を促す文書が出されました。
なぜなら、報道は、検討中の内容が、あたかも報道通りに決まっていくような印象を与えるものになっていたからです。
これについては、高校関係者からも「おかしいのではないか」という声があがっています。ここでは、その中で説明の足りなかった部分を補います。
◆ 報道された内容の情報源は何か?
まず、事実説明の出発点を整理しましょう。
報道の中には、記事になった情報を「関係者の話」から得たとしているものがありますが、内容を考えると、その前日の10月20日に大学入試センターから、「全国都道府県教育委員会連合会会長」「指定都市教育委員会協議会会長」「全国市町村教育委員会連合会会長」「全国高等学校長協会会長」宛てに送られた「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入学共通テストの出題教科・科目等の検討状況について」(入試セ企第74号、以下「文書74」と記す。)が元になっていると考えられます。
これには、最後に「本件に関して、御意見等がある場合には、貴団体においてお取りまとめいただいた上で、令和2年11月30日(月)までに御連絡いただくようお願いいたします」とあり、これらの団体の意見によっては今後変わりうるという内容です。
したがって、現在の共通テストが6教科30科目から7教科21科目になる場合もあれば、ならない場合もあり、また報道で発表される内容が一部変更されることもあります。(一部報道には「検討中」と書いてあるものの)あたかも、報道通りになるような表現もありましたが、そうならないこともあるので、10月23日に大学入試センターからホームページで、次のような通達があったのです。
「新学習指導要領に対応した令和7年度からの大学入学共通テストの出題教科・科目等について報道がありました。大学入試センターでは、これまで、幅広い分野の専門家のご参画を得て、令和7年度からの大学入学共通テストの出題教科・科目等についての検討を行っているところです。この度、途中段階ではありますが、一定の方向性について整理を行いましたので、大学入学共通テストを共同で実施する大学関係者はもちろん、高校関係者に対しても情報提供を行い、ご意見を伺っているところです。今後、いただいたご意見をもとに、必要な修正を行ってまいります。(原文ママ)」
さて、以下においては、報道の情報源が何かではなく、10月20日に大学入試センターから提示された「文書74」を元に説明します。
◆ 共通テストで「情報」が入るというが
新学習指導要領では「情報I」「情報II」が設定されることになっていますが、「文書74」では、そのうちの必履修科目である「情報I」を「情報」として共通テストの試験科目にしては「どうか」と書かれています。
もちろんこの「情報」が、今後、共通テストの科目になる可能性もありますが、第15回大学入試のあり方に関する検討会議において、国立大学協会の岡正朗委員から「入試科目にするのであれば、教員が本当に全国にいるのか、どのレベルまで同じにできるのか」という懸念も出されています。したがって、今後どうなるのかはまだわからない状況です。
なお、一部報道で、新学習指導要領で「情報が必修に入る」というものがありましたが、現行課程でも「情報」という科目(「社会と情報」「情報の科学」)はあります。
この科目としての「情報」は2003年から実施されましたが、その時点でそれを教える専門の教員がほとんどいなかったことから、当時の教員が決められた講習を受ければ、比較的簡単に追加の形で「情報」の教員免許を取れる形になりました。
この結果、数学の教員が「情報」を担当することが多いものの、「理科」や「家庭科」の教員が担当している例が私のまわりにもいます。この延長での現在なので、「情報」の教員には、知識が浅い人も多く、そのような現状を岡委員は心配されているのでしょう。したがって、「情報」を共通テストの科目に入れる前に、教える側の質も向上すべきなのです。
◆ 共通テストの「数学ⅡBC」は
数学は現在の共通テストでは、「数学I」「数学I、数学A」「数学II」「数学II、数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」の6科目ありますが、これを「数学I」「数学I、数学A」「数学II、数学B、数学C」の3科目にするという報道でした。
(※) 多くの人は、「数学I、数学A」と「数学II、数学B、数学C」を選択することになります。
ここまでは正しいのですが、実際はもう少し踏み込んだ内容が「文書74」には書かれています。
そこには、「数学II、数学B、数学C」(以下、「数学IIBC」と記す)について書かれており、「『数学B』及び『数学C』については、『数学B』の2項目の内容(数列、統計的な推測)及び『数学C』の2項目の内容(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)に対応した出題とし、このうち3項目の内容の問題を選択解答させる」とあります。
この検討中案どおりであるとすれば、非常におかしなことを含んでいますので、少なくともこのままの形で令和7年の共通テストは実施されないと考えられます。以下にそのおかしな点を記しましょう。
おかしな点1:数学Bは、「数列」「統計的な推測」「数学と社会生活」の3項目で構成されているが、「数学と社会生活」を履修した場合、共通テストでは選ぶものがない。また、数学Cについても「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」「数学的な表現の工夫」の3項目で構成されているが、「数学的な表現の工夫」を履修した場合も共通テストでは選ぶものがない。
数学B、数学Cではどの2つを選んでもよいことになっているので、共通テストにおいて学習した項目で受験できないなどの差別があってはならない。
おかしな点2:もしも、本当に「数学B」「数学C」の中のここで指定された範囲から3項目を選ぶことになれば、この試験を受ける人は「数学B」「数学C」の両方を履修しなければならない。(例えば「数学B」だけでは3項目は選べない。)
「数学B」、「数学C」の片方だけの履修ではすまないとなれば、もはや「数学B」「数学C」と分ける意味はない。(実際、新課程において「数学B」「数学C」といった教科の分け方はいろいろな意味ですでに崩壊している。)
◆ 日本学術会議の提言が元に
実は、検討案は今年の夏に日本学術会議の数理科学委員会の中の数学教育分科会で提言された「新学習指導要領下での算数・数学教育の円滑な実施に向けた緊急提言:統計教育の実効性の向上に焦点を当てて」が元になっていると考えられていますので、そちらを見る方がこのような検討案に至った経緯はわかります。(こちらの提言についても別の問題点はあるのですが、ここでは割愛します。)
それによると、次のような説明になります。
”「数学B」では「数列」「統計的な推測」の他に「数学と社会生活」、「数学C」では「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」の他に「数学的な表現の工夫」という項目が用意されていますが、今回除かれた2つの項目は知ることを目的とする内容なので、共通テストのような試験には向かないため除外し、残りの4項目を試験に課すべきである。
しかしながら、「数学IIBC」の試験時間は70分にするのが限界であるので、3問を選択という形がよい”
このような内容の提言ですので、これに沿うように大学入試センターでも今後検討していくものと考えられます。
しかしながら、実際は、「数学II」で問わなければならない項目も多いため、試験時間を70分にしたところで3問の選択問題を解くのは時間的に厳しいので、今後は2問選択になる可能性も大いにあります。
そして、そのようにすることで「数学B」「数学C」の片方だけを履修することも可能になります。
※ 清史弘 せいふみひろ●Twitter ID:@f_sei。
数学教育研究所代表取締役・認定NPO法人数理の翼顧問・予備校講師・作曲家。小学校、中学校、高校、大学、塾、予備校で教壇に立った経験をもつ数学教育の研究者。著書は30冊以上に及ぶ受験参考書と数学小説「数学の幸せ物語(前編・後編)」(現代数学社) 、数学雑誌「数学の翼」(数学教育研究所) 等。
『ハーバー・ビジネス・オンライン』(2020.10.26)
https://hbol.jp/231018?cx_clicks_art_mdl=1_title















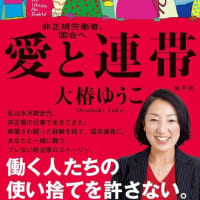

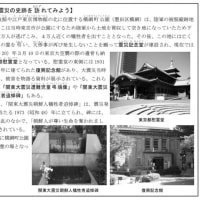







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます