《第3回子どもの権利条約市民・NGO報告書をつくる会統一報告書》9-12
◎ 女性差別撒廃条約批准後にみられる教育の逆行
1 男女平等教育への消極的施策と男女特性論の再燃
女性差別撤廃条約の批准後、政府によれば、男女共同参画を促進し【政府277】、女児に対する差別の根絶及び第4回女性会議のフォローアップとして男女共同参画社会基本法を制定した【政府155・156】。教育はその施策の実現に一定の役割を果たしてきた【政府157】。だが実際には、第二次男女共同参画基本計画から、「ジェンダーに敏感な視点」の文言が削除されている【基礎382】。
日本社会では、実際の労働や子育てにおける性別役割分業はなかなか克服されない。M字型雇用に加え、男性の育児休業取得率は極めて低い。女性労働者の約30%しか正規職でない【基礎216】ため、女性の方が収入が低い。
保育園・学童保育・幼稚園では教員の給与は低く、女性が多数を占める【基礎266】。小学校では、教員の6割が女性だが、管理職の女性割合は20%前後、中・高等学校の教員の女性割合は半分に満たず、管理職は1割に満たない。女性教員が文科・芸術系、男性が理科・体育系と偏りがみられる。
職業教育の軽視、進路選択等が示すように、男女の能力の発達は十分に保障されていない【基礎213・214】。政府の教育目的は、男女平等や男女の相互理解は「人権尊重についての考え方」、すなわち意識を深めるに留まっている【政府418】。
政府の男女平等教育への消極的姿勢は、1998年ごろより始まった「ジェンダー否定・批判」(バックラッシュ)により強化された【基礎213】。侵略戦争・天皇制の美化など近代日本の国家的伝統を尊重するグループは、男女の社会参加を促進する上で重要な「ジェンダー」という考え方、すなわち生まれつきの性別とされているものの多くが社会や文化の産物であるという考え方、の教育への導入を阻止しようとしている。
社会科や家庭科の教科書検定では、ジェンダーという言葉が自由に使用できず【基礎008】、家庭科では女性差別撤廃条約の記述がなくなった事例もある【基礎382】。日本軍「慰安婦」についても多くの教科書が記述しなくなくなった【基礎019】。
むしろ政府は、男女の特性の尊重を主張している。一例として男女共学条項の削除と家庭教育の重視(後述の「1947教育基本法「改正」が学校・家庭にもたらしたもの」参照【基礎215】)をあげることができる。
また新自由主義的教育改革による教育内容の効率化・スリム化で、共修家庭科の時間数減【基礎OO7・217】が実施され、成果主義的教員評価の導入は女性教員業績評価を低くしがちである。家庭科と深く関わる子育てや家事の能力は、競争重視の教育で軽視されている【基礎OI3】。
子どもの発達保障には、遅れている男女平等教育を改め、「ジェンダー」の考え方を積極的にとりいれ、「教育の自由」を回復する必要がある【基礎019・021】、
◎ 女性差別撒廃条約批准後にみられる教育の逆行
1 男女平等教育への消極的施策と男女特性論の再燃
女性差別撤廃条約の批准後、政府によれば、男女共同参画を促進し【政府277】、女児に対する差別の根絶及び第4回女性会議のフォローアップとして男女共同参画社会基本法を制定した【政府155・156】。教育はその施策の実現に一定の役割を果たしてきた【政府157】。だが実際には、第二次男女共同参画基本計画から、「ジェンダーに敏感な視点」の文言が削除されている【基礎382】。
日本社会では、実際の労働や子育てにおける性別役割分業はなかなか克服されない。M字型雇用に加え、男性の育児休業取得率は極めて低い。女性労働者の約30%しか正規職でない【基礎216】ため、女性の方が収入が低い。
保育園・学童保育・幼稚園では教員の給与は低く、女性が多数を占める【基礎266】。小学校では、教員の6割が女性だが、管理職の女性割合は20%前後、中・高等学校の教員の女性割合は半分に満たず、管理職は1割に満たない。女性教員が文科・芸術系、男性が理科・体育系と偏りがみられる。
職業教育の軽視、進路選択等が示すように、男女の能力の発達は十分に保障されていない【基礎213・214】。政府の教育目的は、男女平等や男女の相互理解は「人権尊重についての考え方」、すなわち意識を深めるに留まっている【政府418】。
政府の男女平等教育への消極的姿勢は、1998年ごろより始まった「ジェンダー否定・批判」(バックラッシュ)により強化された【基礎213】。侵略戦争・天皇制の美化など近代日本の国家的伝統を尊重するグループは、男女の社会参加を促進する上で重要な「ジェンダー」という考え方、すなわち生まれつきの性別とされているものの多くが社会や文化の産物であるという考え方、の教育への導入を阻止しようとしている。
社会科や家庭科の教科書検定では、ジェンダーという言葉が自由に使用できず【基礎008】、家庭科では女性差別撤廃条約の記述がなくなった事例もある【基礎382】。日本軍「慰安婦」についても多くの教科書が記述しなくなくなった【基礎019】。
むしろ政府は、男女の特性の尊重を主張している。一例として男女共学条項の削除と家庭教育の重視(後述の「1947教育基本法「改正」が学校・家庭にもたらしたもの」参照【基礎215】)をあげることができる。
また新自由主義的教育改革による教育内容の効率化・スリム化で、共修家庭科の時間数減【基礎OO7・217】が実施され、成果主義的教員評価の導入は女性教員業績評価を低くしがちである。家庭科と深く関わる子育てや家事の能力は、競争重視の教育で軽視されている【基礎OI3】。
子どもの発達保障には、遅れている男女平等教育を改め、「ジェンダー」の考え方を積極的にとりいれ、「教育の自由」を回復する必要がある【基礎019・021】、


















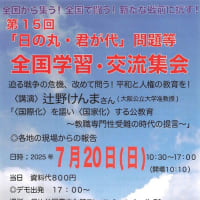





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます