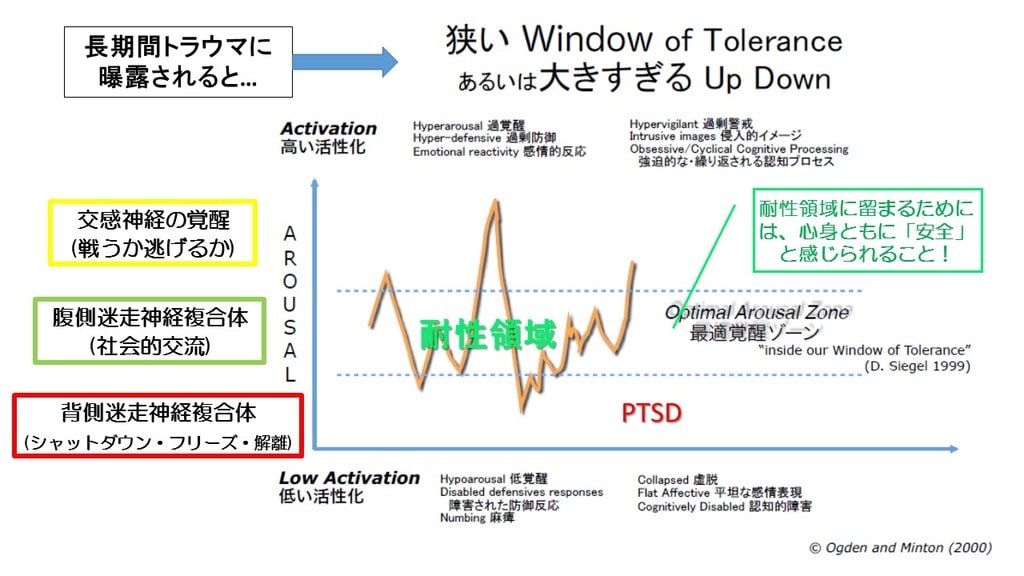
普段は製薬会社に厳しく、批判的なトランプ大統領ですが、先日FDAに承認されたSPRAVATO(エスケタミン点鼻薬)については、「悩めるどの退役軍人にも与えるべきであり、同剤で自殺が激減しうる」と述べています。
トランプ大統領は「SPRAVATOを開発したJohnson & Johnson(J&J)は気前よく分けてくれるだろうし、必要ならJ&Jとの仲を取り持つ」と退役軍人省長官(VA)のRobert Wilkie氏に話しています。
Wilkie氏も同剤はとても有効だと言っており、年内にどの退役軍人病院にも備わることを目指して手続きが進められているとのことです。
アメリカ大統領の発言力は大きですので、今後の日本での開発にもはずみがつくことを期待したいですね!
以前、本ブログでも紹介したことがありますが、うつ病に対する有望な新薬として期待されていた「rapastinel」が、アメリカの3つの第3相試験いずれにおいても主要項目を達成できず、失敗に終わった旨が本年3月に報告されました。
rapastinelは第2相試験では、1回の静脈注射後1日で速やかに抗うつ効果が得られることが示され、FDAより画期的治療薬(既存治療を超える大幅な改善を示す可能性が示される薬剤)にも指定されておりましたが、今回は残念な結果に終わりました。
同じく画期的治療薬として開発が進められ、つい先日FDAに承認されたエスケタミン点鼻薬「spravato」とは明暗が分かれました。
rapastinelもspravatoも、ともにNMDA受容体という部位に作用する点では類似していますが、やはりその先の細かな作用機序に違いがあるのでしょう。
近年、新たなアルツハイマー病治療候補薬が第3相試験でことごとく失敗しているように、治験は最後の最後まで分からないものだと改めて感じさせられました。やはり新薬の開発は難しく、一筋縄ではいかないものです。
なお、今回の治験の失敗で、rapastinelを開発していたAllergan社の今年の四半期決算では、なんと24億ドル超(約2600億円)の赤字(純損失)となったとのことです... 。同社は他にもNMDA受容体に作用する新薬(NRX-1074やAGN-241751など)を開発中であり、今後の動向が注目されます。
。同社は他にもNMDA受容体に作用する新薬(NRX-1074やAGN-241751など)を開発中であり、今後の動向が注目されます。
本年1月に、Roche社のバソプレッシンV1a受容体遮断薬Balovaptan (RG7314) が米国のFDAより画期的治療薬に指定されました。Balovaptanは自閉スペクトラム症の社会相互作用やコミュニケーションの障害を改善することが期待されています。今回の同薬の画期的治療薬への指定は、昨年の5月にInternational Congress for Autism Researchにて発表された、成人の自閉スペクトラム症に対する第2相試験の結果を受けたものです。その結果では、安全性や忍容性にも問題はなかったとのことでした。
米国では、現在、児童・思春期の自閉スペクトラム症に対しても第2相試験が行われています。自閉スペクトラム症の中核症状に対して認可されている薬剤はまだ全くないのが現状ですので、Balovaptanや過去に本ブログでも取り上げましたオキシトシン点鼻薬の今後の治験結果には期待をもって注目しております。
今年の8月に、パーキンソン病を治療しうるαシヌクレイン抗体MEDI1341の治験を開始することをアストラゼネカ株式会社が発表しました。今年中に始まる予定の第1相試験はアストラゼネカが行い、その後の臨床開発は武田薬品に委ねられるとのことです。
パーキンソン病患者の脳内では、レビー小体という異常なタンパク質の凝集体が見られ、その主成分であるαシヌクレインが発症の重要な鍵を握ると考えられています。そして今回の治験薬であるαシヌクレイン抗体は、αシヌクレイン自体の生成を抑制し、パーキンソン病を治癒させることが期待されています。
実は、αシヌクレインはパーキンソン病だけでなく、レビー小体病や多系統委縮症の発症にも大きく関与しており、αシヌクレインを標的とした治療薬がこれらの神経変性疾患の治療薬になる可能性も秘めています。
すでにダブリンのProthena社とスイスのRoche社のαシヌクレイン抗体PRX-002 (RO-7046015) は第2相試験段階に進んでおり、実用化が期待されています。抗体以外のαシヌクレイン標的治療薬の開発もいくつか進んでおり、そう遠くない未来にパーキンソン病は不治の病ではなくなるかもしれません 。今後の臨床試験の動向に注目です。
。今後の臨床試験の動向に注目です。
Alkermes社が開発中の抗うつ薬「ALKS 5461」が米国において、今年後半の承認申請に向けて準備が順調に進んでいる旨が、昨日、同社の決算報告の際に発表されました。「ALKS 5461」は既存の標準的な抗うつ薬であるSSRIやSNRI、NaSSAなどとは作用機序が全く異なる新しい抗うつ薬に分類されます。この抗うつ薬は「治療抵抗性うつ病」と呼ばれる難治性のうつ病に対して適応取得を目指しており、その効果が期待されます。
ALKS 5461はμ-およびκ-オピオイド部分作動薬であるbuprenorphineとμ-オピオイド拮抗薬であるsamidorphanの合剤であり、オピオイドの調節により抗うつ効果が発揮されると推定されています。オピオイドは従来、鎮痛薬として知られていますが、この部分作動薬と拮抗薬の合剤が抗うつ薬として作用するということは興味深いです 。確かに、うつ病の患者さんはしばしば体の痛みも訴えますので、うつ病と痛みには密接な関連があるのかもしれません。
。確かに、うつ病の患者さんはしばしば体の痛みも訴えますので、うつ病と痛みには密接な関連があるのかもしれません。
近年、アルツハイマー病の発症メカニズムの一端が明らかになりつつあります。そういった中で、さまざまな種類のアルツハイマー病治療候補薬が現在、世界中で開発途上にあります。
Eli Lilly社は、アルツハイマー病治療候補薬の一つである抗Aβ抗体「ソラネズマブ」の開発を進めてきましたが、昨年11月に臨床第3相試験での主要評価項目を満たすことができず、この度、同社CEOのDavid Ricks氏が同薬の開発中止を発表しました。この薬の開発の動向には、実は私も大きな期待を持って注目していました。なぜなら、現在、上市されているアルツハイマー病治療薬(アリセプトやレミニール、メマリーなど)はいずれも対症療法薬であり、単に「認知症の進行を遅らせる」効果しかないのに対し、この抗Aβ抗体はアルツハイマー病の根治を目指せる可能性を秘めていたからです。
昨年11月、当時のCEOのJohn C. Lechleiter氏は「ソラネズマブの第3相試験の結果は期待とは異なるものだった。何百万人もの方々が有望なアルツハイマー病の疾患修飾薬の登場を待っていることを考えると、大変残念に思っている」とコメントし、失望を隠せませんでした。
薬の開発には治験が必須であり、治験は第1相試験、第2相試験、第3相試験の3段階から成ります。各段階の詳細は割愛しますが、第3相試験では多数の患者さんで有効性や安全性、使用方法などを確認します。そして、どうやら近年のアルツハイマー病の開発薬にとってはこの「第3相試験」が高い壁となり、立ちはだかっているようです。ソラネズマブに関しては2012年8月に続き、今回が2回目の第3相試験での失敗でした。他にも、2012年夏にPfizer社の抗Aβ抗体「バピネオズマブ」が同様の理由で、開発の断念を余儀なくされました。
他には現在、Biogen社が抗Aβ抗体「アデュカヌマブ」を治験中で、昨年12月に第1相試験にてその有効性が示されました。しかしまだ第1相試験の結果しか出ておらず、予断を許さない状況です。Eli Lilly社も今回のソラネズマブの開発中止にもめげずに、AstraZeneca社との共同開発にて経口βセクレターゼ(BASE)阻害剤「AZD3293」の治験を進めており、現在、第3相試験に入っております。
日本においては、中外製薬が抗Aβ抗体「ガンテネルマブ」の第3相試験を、MSD社がBACE阻害薬「MK-8931」の第3相試験を、エーザイ社が抗Aβプロトフィブリル抗体「BAN2401」の第2相試験をそれぞれ実施中です。「BASE阻害薬」や「抗Aβプロトフィブリル抗体」も「抗Aβ抗体」と同様にアルツハイマー病根治の可能性を持つアルツハイマー病治療候補薬であり、これらの今後の開発の動向にも目が離せません。
アルツハイマー病は加齢自体が発症の危険因子であることが分かっており、今後、ますますアルツハイマー病の患者さんが増えることが予想されます。今後の急速な高齢化社会化に向けて、根治可能なアルツハイマー病治療薬の開発に世界中が注視しています。また、アルツハイマー病の発症メカニズム自体の全容解明にも期待がかかります。
本年8月16日付で、以前、本ブログでもご紹介したことがある「エスケタミン点鼻薬」が、米国FDAより2回目の画期的治療薬に指定されました。これは治験の第Ⅱ相試験で、差し迫った自殺の危険のあるうつ病患者に同薬剤が効果を示す予備的な結果が報告されたことによるものです。プレスリリース配信会社のPRニュースワイヤーは、「もしFDAに認可されれば、エスケタミンは過去50年間で、うつ病治療における最初の新しいアプローチの一つになりうる」と報じています。つまりは、これまでの抗うつ薬とは全く作用機序が異なり、かつ画期的な抗うつ作用を持つ薬剤になり得るということです。
エスケタミンはNMDA受容体遮断薬の一種で、これまでにない作用機序により抗うつ効果を発揮することが期待されており、これまでの治験の結果から治療抵抗性うつ病への効果も示されております。現在、エスケタミンの治験は日本でも行われており、一日も早い認可が望まれます。
発達障害のひとつに、自閉スペクトラム症という診断名があります。かつてはアスペルガー症候群、高機能自閉症、自閉症(カナータイプ)などいくつかのタイプに分類されていましたが、近年はこれらを総称して自閉スペクトラム症(Autistic Spectrum Disorders;ASD)と呼称されるようになっております。
ASDの中核症状には以下の3つがあります
・社会性の障害:他者との共感性や相互性が乏しくトラブルが多い、常識の欠如
・コミュニケーションの問題:言葉や動作、目線などを使って、情報の受信・発信がうまくできない
・想像力の問題:こだわりが強く、先読みができない。変化によってパニックをおこす
発達障害には他に注意欠如・多動症(かつての注意欠陥・多動性障害)、いわゆるADHDがありますが、ADHDに関してはその中核症状(不注意や多動、衝動性)に対する治療薬が既にあります。しかしASDについては上記の中核症状に対する治療薬はないのが現状です。
ところが、2003年にASDの中核症状(反復的行動)に対するオキシトシン点鼻薬の有効性を示す最初の研究成果が報告され、その後これまでにASDの中核症状に対するオキシトシン点鼻薬の有効性を検討した研究が約20報ほど報告されています。結論から言うと、どうやらオキシトシンにはASDの中核症状のうち、対人交流症状や感情認識能力、反復的活動などに効果があることが分かってきております。なお、オキシトシン点鼻薬には明確な有害事象は今のところ認められておりません。
日本では東大や金沢大の研究グループが現在、ASDに対するオキシトシン点鼻薬の治験を行っており、昨年の9月には東大の研究グループがASDの中核症状(社交的相互性)に対するオキシトシン点鼻薬の有効性を報告しております(“Brain”という一流医学雑誌に掲載されました)。近い将来、日本でオキシトシン点鼻薬がASDの治療薬として正式に認可されることが期待されます 。
。










