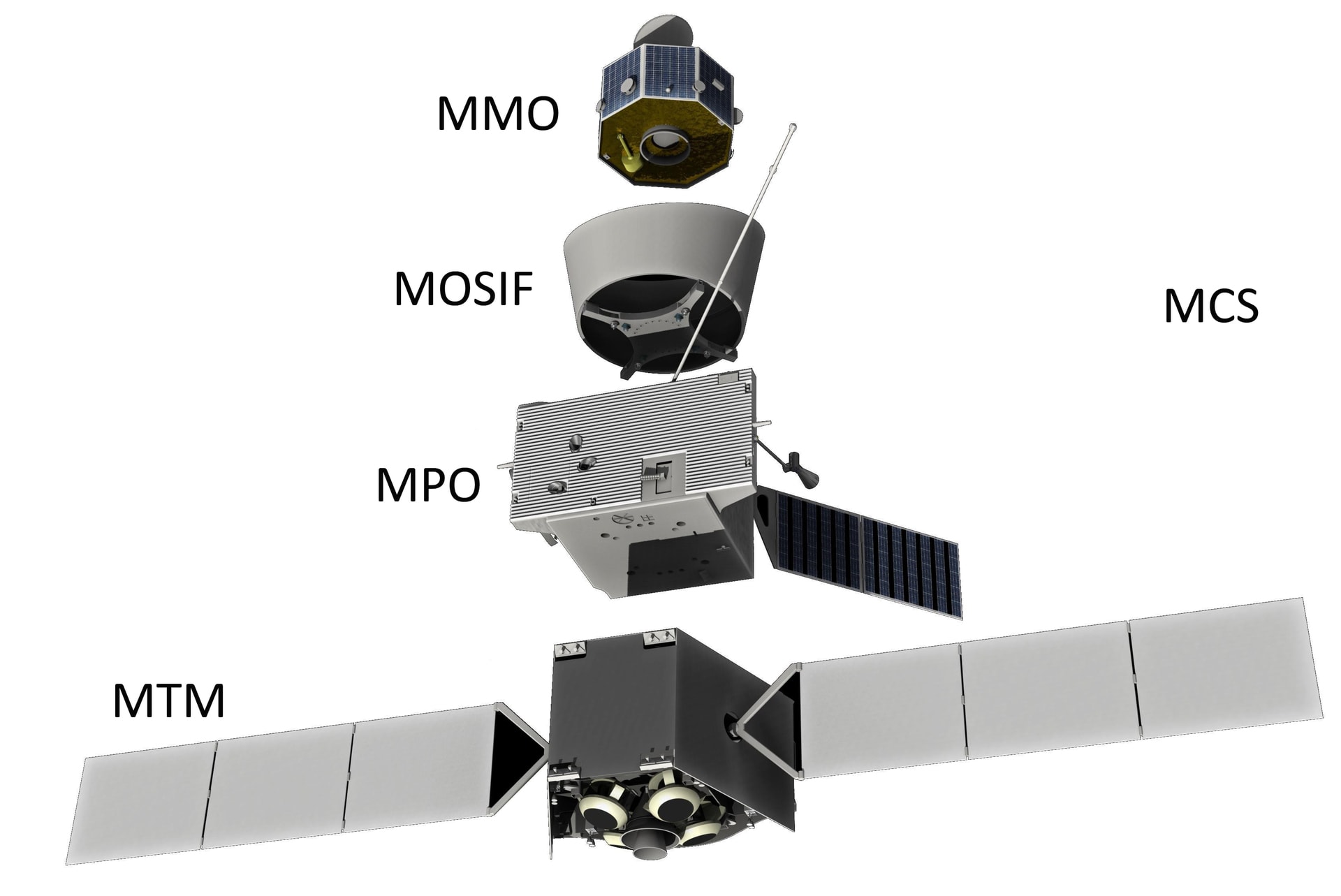NASAの水星探査機“メッセンジャー”のデータから、
初めて水星全球の立体モデルが作られたんですねー
これにより、水星全体の地形が驚くほど詳細に分かり、
水星の地質学的な歴史を解明していく道が開かれそうですよ。
画期的な地図
2011年から昨年まで水星を周回探査していた“メッセンジャー”は、
10テラバイト以上に及ぶ水星のデータを地球へ送り届けてくれました。
そのデータにより約30万枚もの画像や多くのスペクトル、
地図データなどが得られました。
15回目になる今回のデータ公開で発表されたのは、
プロジェクトにとって最も画期的な成果の1つになる、
水星全球の立体モデル(高度図)でした。
これまでにも地形図はあったのですが、北半球と赤道付近の領域のみのもので、
南半球のほとんどは、これまで知られていませんでした。
今回のモデル作成には、
“メッセンジャー”が周回軌道上のいろいろな地点から撮影した、
光の当たり方が異なる画像10万枚以上を使用。
そのおかげで、水星全球の表面にある地形が決定できたんですねー
水星の最高地点は、
水星で最も古い地形のうちの1つである赤道の南にあり、
標高は4.48キロです。
一方でラフマニノフ盆地の底が、
水星の平均高度より5.38キロ低い最低地点になります。
二重の天体衝突の跡であるラフマニノフ盆地には、
水星上で一番最近起こった火山活動による堆積物が、
存在しているのではないかと考えられています。
また、水星の北極近くに見られる、
火山活動で作られた平原の詳しい様子も明らかになっています。
極の付近は太陽の光が横からしか当たらないので、
長い影ができ岩石の色の特徴がはっきりしないのですが、
影が最も短い時に5つの異なるフィルターで撮影して作らています。
今後もミッションで得られたデータを活用することにより、
水星の現在の様子だけでなく、
形成や進化に関わる幅広い謎の解明に役立てられるといいですね。
こちらの記事もどうぞ
“メッセンジャー” 水星に落下しミッションは終了
地表の組成分布で明らかになる水星の過去
初めて水星全球の立体モデルが作られたんですねー
これにより、水星全体の地形が驚くほど詳細に分かり、
水星の地質学的な歴史を解明していく道が開かれそうですよ。
画期的な地図
2011年から昨年まで水星を周回探査していた“メッセンジャー”は、
10テラバイト以上に及ぶ水星のデータを地球へ送り届けてくれました。
そのデータにより約30万枚もの画像や多くのスペクトル、
地図データなどが得られました。
15回目になる今回のデータ公開で発表されたのは、
プロジェクトにとって最も画期的な成果の1つになる、
水星全球の立体モデル(高度図)でした。
 |
| 水星全球の立体モデル。 茶、黄、赤が高度の高い領域、青、紫が高度の低い領域を表している。 |
これまでにも地形図はあったのですが、北半球と赤道付近の領域のみのもので、
南半球のほとんどは、これまで知られていませんでした。
今回のモデル作成には、
“メッセンジャー”が周回軌道上のいろいろな地点から撮影した、
光の当たり方が異なる画像10万枚以上を使用。
そのおかげで、水星全球の表面にある地形が決定できたんですねー
水星の最高地点は、
水星で最も古い地形のうちの1つである赤道の南にあり、
標高は4.48キロです。
一方でラフマニノフ盆地の底が、
水星の平均高度より5.38キロ低い最低地点になります。
二重の天体衝突の跡であるラフマニノフ盆地には、
水星上で一番最近起こった火山活動による堆積物が、
存在しているのではないかと考えられています。
また、水星の北極近くに見られる、
火山活動で作られた平原の詳しい様子も明らかになっています。
極の付近は太陽の光が横からしか当たらないので、
長い影ができ岩石の色の特徴がはっきりしないのですが、
影が最も短い時に5つの異なるフィルターで撮影して作らています。
 |
| 水星の北極に近い領域。 異なる種類の岩石を強調するために、色を強調している。 |
今後もミッションで得られたデータを活用することにより、
水星の現在の様子だけでなく、
形成や進化に関わる幅広い謎の解明に役立てられるといいですね。
こちらの記事もどうぞ
“メッセンジャー” 水星に落下しミッションは終了
地表の組成分布で明らかになる水星の過去