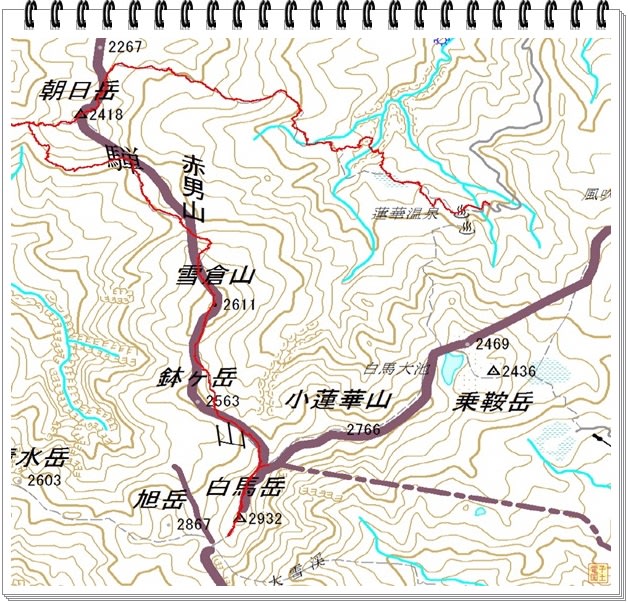梅雨はまだ明けませんが、日に日に夏の訪れを感じます。
日中の街中では強い日差しの照り返しと熱せられたアスファルトが不快になって来ました。
それでも森の入り口では快適な気温と湿度が保たれていて、環境を快適に保つ森の力を改めて実感します。
しかし、やはりここで色々な作業をすれば汗だくになりますから水辺が恋しくなります。
という訳で、森の入り口脇を流れる川上川へ降りる仮の階段を作ることにしました。
材料は森の入り口の豊富な間伐材です。
先ず最初に階段を立てかけるための櫓を作る事にします。
櫓の4本の柱をつなぐ横木のホゾを小屋の中で加工します。

一方、川縁では柱のホゾ穴を加工します。

そして加工し終わった横木と柱を繋ぎます。
この時ホゾ、ホゾ穴のサイズと角度の精度が問題になります。
微調整をしながら組み立てます。

午後から帰らなくてはいけない参加者が多かったので、ここまでで本日の作業は終了しました。
後日、全ての横木と柱を組み立てました。

完成です。
次は、階段本体を取り付けます。

日中の街中では強い日差しの照り返しと熱せられたアスファルトが不快になって来ました。
それでも森の入り口では快適な気温と湿度が保たれていて、環境を快適に保つ森の力を改めて実感します。
しかし、やはりここで色々な作業をすれば汗だくになりますから水辺が恋しくなります。
という訳で、森の入り口脇を流れる川上川へ降りる仮の階段を作ることにしました。
材料は森の入り口の豊富な間伐材です。
先ず最初に階段を立てかけるための櫓を作る事にします。
櫓の4本の柱をつなぐ横木のホゾを小屋の中で加工します。

一方、川縁では柱のホゾ穴を加工します。

そして加工し終わった横木と柱を繋ぎます。
この時ホゾ、ホゾ穴のサイズと角度の精度が問題になります。
微調整をしながら組み立てます。

午後から帰らなくてはいけない参加者が多かったので、ここまでで本日の作業は終了しました。
後日、全ての横木と柱を組み立てました。

完成です。
次は、階段本体を取り付けます。