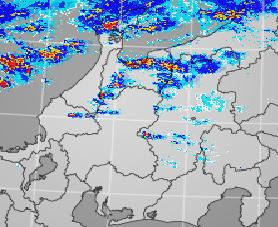寒さが益々厳しくなって来ました。
幸い岐阜県恵那市の市街地ではまだ積もるような雪には見舞われていませんが、北国では大雪の模様です。
雪下ろしや雪かきが欠かせない毎日は、想像するだけで大変です。
北国の雪の中での暮らしはどんなものなんでしょう。
さて、23日は3回目の竹細工講習でした。
前回で篭の胴部分を巻き終わりましたので、今回は口の部分の仕上げです。
しかし今回初めての参加者が二人と、自分で2個め3個目の篭を作りかけている参加者がいて夫々バラバラの工程を作業することになったので、先生は大忙しでした。

胴部分のヒゴが足らなくなって先生が大急ぎで竹を割ってくれています。
竹の割れる音が小気味良く響きます。
我々が割るとこんな音が出ません。
タライには、口の部分を仕上げるために篭を逆さまに水に付けほぐした縦骨を柔らかくしています。

これも初めて来た参加者のために先生が底の部分を編んでいる所です。

今度は胴部分がまだの中二人の参加者に編み上げ方を教えています。
両側の二人は竹ヒゴ作りです。
先生は息つく暇もありません。
口部分を仕上げるために2つと半分に割った縦骨を5cmの長さに切り揃えます。

口の部分の仕上げに幅のある竹ひごを巻きつけています。
巻きつける竹ひごは、一昼夜水に漬け柔らかくしてあります。

そして4時過ぎに竹籠が出来上がりました。

左が先生の作品、右が私の作品です。
私の作品は、形が歪で胴部分のヒゴに隙間が目立ちます。
でも一応篭らしく出来上がりました。
クリの木の天板とコナラの足の台の上に篭を載せてみました。

下の台を含めて素材全てを山から切り出し加工し作品となりました。
自然の素材を身近な道具に仕上げる最も必要な要素は、アイデアと時間でした。
大した道具は必要ありませんので、是非皆さんも山から素材を手に入れ色々な作品を作ってみて下さい。
楽しいですよ。
先生の都合もありこれで竹細工講習は一応終了です。
講習再開は今後検討します。
それまで各自自習です。
外に出ると丁度夕陽が山の端に沈むところでした。
空のほとんど覆った暗い雪雲と山の端の隙間から細いオレンジ色の光が真直ぐ届き、北風が一層冷たく感じられました。
後少しで今年も終わりますね。
色々あった1年でした。
皆さん良いお年をお迎え下さい。
幸い岐阜県恵那市の市街地ではまだ積もるような雪には見舞われていませんが、北国では大雪の模様です。
雪下ろしや雪かきが欠かせない毎日は、想像するだけで大変です。
北国の雪の中での暮らしはどんなものなんでしょう。
さて、23日は3回目の竹細工講習でした。
前回で篭の胴部分を巻き終わりましたので、今回は口の部分の仕上げです。
しかし今回初めての参加者が二人と、自分で2個め3個目の篭を作りかけている参加者がいて夫々バラバラの工程を作業することになったので、先生は大忙しでした。

胴部分のヒゴが足らなくなって先生が大急ぎで竹を割ってくれています。
竹の割れる音が小気味良く響きます。
我々が割るとこんな音が出ません。
タライには、口の部分を仕上げるために篭を逆さまに水に付けほぐした縦骨を柔らかくしています。

これも初めて来た参加者のために先生が底の部分を編んでいる所です。

今度は胴部分がまだの中二人の参加者に編み上げ方を教えています。
両側の二人は竹ヒゴ作りです。
先生は息つく暇もありません。
口部分を仕上げるために2つと半分に割った縦骨を5cmの長さに切り揃えます。

口の部分の仕上げに幅のある竹ひごを巻きつけています。
巻きつける竹ひごは、一昼夜水に漬け柔らかくしてあります。

そして4時過ぎに竹籠が出来上がりました。

左が先生の作品、右が私の作品です。
私の作品は、形が歪で胴部分のヒゴに隙間が目立ちます。
でも一応篭らしく出来上がりました。
クリの木の天板とコナラの足の台の上に篭を載せてみました。

下の台を含めて素材全てを山から切り出し加工し作品となりました。
自然の素材を身近な道具に仕上げる最も必要な要素は、アイデアと時間でした。
大した道具は必要ありませんので、是非皆さんも山から素材を手に入れ色々な作品を作ってみて下さい。
楽しいですよ。
先生の都合もありこれで竹細工講習は一応終了です。
講習再開は今後検討します。
それまで各自自習です。
外に出ると丁度夕陽が山の端に沈むところでした。
空のほとんど覆った暗い雪雲と山の端の隙間から細いオレンジ色の光が真直ぐ届き、北風が一層冷たく感じられました。
後少しで今年も終わりますね。
色々あった1年でした。
皆さん良いお年をお迎え下さい。