
見てきました
太田記念美術館
会期は2014年7月1日から2014年9月25日。
3部構成となっていて、
第一部は【化け物】7月1日から7月27日。
第二部は【幽霊】8月1日から8月26日。
第三部は【妖術使い】8月30日から9月25日。
今回は第二部の【幽霊】を見てきました。
第一部の記事はこちら→「江戸妖怪大図鑑 第一部【化け物】」
さて。
夏です。
暑い暑い夏です。
幽霊や妖怪たちも元気になる(!?)夏です。
鬼や天狗、土蜘蛛などの【化け物】
お菊やお岩などの【幽霊】
蝦蟇や蛇を操る【妖術使い】
本当に怖いものから、笑ってしまうものまでさまざまなものが描かれています。
今回はそれぞれをカテゴリーで分け、葛飾北斎や歌川国芳、菱川師宣から月岡芳年まで、総展示数は約270点。
まさに妖怪大集合な展示となっています。
さらっと見てきた中で印象に残ったものを数点書いておきます。
まずは靴を脱いで畳の上へ。
99.葛飾北斎「百物語 お岩さん」
とっても有名な作品。
左目のところが崩れてしまったお岩さん。
この作品では提灯に顔が映し出されています。
提灯の破れたところがちょうど口になっています。
怖いはずなのに、なんとなくユーモラス。
116.葛飾北斎「百物語 こはだ小平二」
描かれているのは後頭部を残してすべての皮をはがされた骸骨。
男女の眠る蚊帳を上から覗き込んでいます。
ちょっと、、かなり怖い。
この幽霊は幽霊役を得意としていた歌舞伎役者小平次。
旅先で、妻とその密通相手に殺されてしまい、この2人のもとへ幽霊となって戻ってきた場面です。
148.葛飾北斎「百物語 しうねん」
位牌の前に水の入った器、まとわりつくように蛇。
幽霊は描かれていませんが、逆にこの世への執着を感じさせ怖いです。
位牌に書かれている北斎オリジナル梵字が人間の横顔のように見えるのがちょっとおもしろい。
147.葛飾北斎「百物語 笑ひはんにや」
角と牙を生やした鬼のような女が、子供の生首をつかんで笑顔を浮かべた恐ろしい作品。
手にした子どもの首の切り口はぶつぶつしていて気味が悪い。。
「百物語」シリーズですから、ベースの話があるかと思いますが、調べたところそのような話は見つかっていないよう。
笑般若はこの北斎の作品と長野県の伝承に見られるようで、他の情報が少ないのです。
なお、この北斎の「百物語」
百物語ですから100あるはずなのに、現在5点しか確認されていません。
最初にその4点が見れちゃいます。
この先は幽霊別(!?)に展示されていました。
《累》
累(かさね)は四谷怪談のお岩さん、皿屋敷のお菊さんと並ぶ江戸時代の三代幽霊スター。(→!!??)
下総国岡田郡羽生村(現在の茨城県常総市)の累ヶ淵に伝わる伝承を題材にしたもの。
百姓・与右衛門と、その後妻・お杉の夫婦には、お杉の連れ子である娘・助(すけ)がいました。
助は生まれつき顔が醜く、足が不自由であったため、与右衛門は助を嫌っていました。
助が邪魔になった与右衛門は、助を川に投げ捨てて殺してしまうのです。
あくる年に与右衛門とお杉は女児をもうけ、累(るい)と名づけますが、累は助に生き写しでした。
村人は助の祟りと噂し、「助がかさねて生まれてきたのだ」と「るい」ではなく「かさね」と呼ばれました。
両親が相次いで亡くなり一人になった累。
病気で苦しんでいた流れ者の谷五郎を看病し、二代目与右衛門として婿に迎えます。
しかし谷五郎は容姿の醜い累を疎ましく思うようになり、累を殺して別の女と一緒になる計画を立てるのです。
正保4(1647)年8月11日、谷五郎は累を川に突き落とし殺害しました。
その後、谷五郎は幾人もの後妻を娶りましたが、死んでしまいます。
6人目の後妻・きよとの間にようやく菊という名の娘が生まれますが、菊に累の怨霊がとり憑き、菊の口を借りて谷五郎の非道を語ります。
そして、供養を求めて菊の体を苦しめました。
近隣の飯沼にある弘経寺遊獄庵に所化として滞在していた祐天上人はこのことを聞きつけ、累の解脱に成功。
しかし再び菊に何者かがとり憑きました。
祐天上人が問いただしたところ、助という子供の霊。
古老の話から累と助の経緯が明らかになり、祐天上人は助にも十念を授け戒名を与えて解脱させました。
とい伝承。
なんだか怖いというより悲しいお話なのです。
これを基にした歌舞伎や落語により話は広まります。
設定は作品によって若干違いますが、「累」という名の女性が「与右衛門」という名の夫に殺害され、怨霊となる、という筋立てです。
94.歌川国芳「三代目尾上菊五郎のかさねぼうこん」
描かれているのは幽霊となった累。
暗い背景に白く描かれています。
鬼火が浮かぶ不気味な景色。
この鬼火の色彩がとてもきれいなグラデーションです。
《お岩》
お岩さんは解説いらないでしょう。
とても有名で現代でもなんども映像化されています。
基本的には「貞女・岩が、夫・伊右衛門に惨殺され、幽霊となって復讐を果たす」というもの。
怪談の定番で歌舞伎・落語、舞台、映画など様々なVer.があります。
102.歌川国芳「四代目市川小団次の於岩ぼうこん」
これはとにかく美しい。
幽霊で美しいはおかしいかもしれませんが、美しい。
蛇山庵室での夢の場面。
美しい娘に折り重なって抜け出たかのようにお岩の幽霊が登場しています。
この演出がすごい。
106.歌川国貞(三代歌川豊国)「三代目関三十郎の直助権兵衛 八代目片岡仁左衛門の民谷伊右衛門 五代目坂東彦三郎のお岩の亡霊/小仏小平亡霊 五代目坂東費お三郎の佐藤与茂七」
3枚つづりの大きなもの。
この作品の見せ場でもある、戸板返しの場面です。
お岩と小平を両面に釘付けした戸板が、自分の前に漂着して驚く伊右衛門。
左には与茂七、右には直助が描かれています。
この作品の面白いところは戸板の部分に紙が貼ってあること。
折り返すとお岩と小平が交互に現れるのです。
107.楊洲周延「三代目片岡我童の田宮伊右衛門 五代目尾上菊五郎のお岩ノ霊」
こちらも3枚もの。
真ん中には大きな提灯。
これも紙がついていて、めくるとお岩の顔が出るようになっています。
周りに描かれた唐茄子も怖い顔をしています。
《お菊》
お菊さんも有名過ぎて解説不要かな。
主人が大事にしていたお皿、10枚のうち1枚を割ってしまい、古井戸に身を投げてしまいます。
そして夜な夜な1枚ずつ数えている、、、というお話。
113.豊原国周「歌舞伎座中満久 皿屋敷化粧姿鏡」
縦に3枚という長細い構図。
珍しい。
上には五代目尾上菊五郎演じるお菊。
下には九代目市川団十郎演じる浅山鉄山。
お菊の背後がぼかされていて、怪しい雰囲気を出しています。
《小幡小平次》
114.豊原国周「初代尾上松助の小はだ小平次/同女房」
先ほども出てきましたが、小平次は幽霊役を得意としていた歌舞伎役者。
こちらも妻お塚と密通相手の左九郎の夢枕に立つ場面です。
なんだか切ない。
さぞかし無念だっただろうなぁ。
《朝倉当吾》
朝倉当吾は藩主の過酷な年貢取り立てを将軍家綱に直訴し、死罪となった佐倉の名主、佐倉惣五郎のこと。
手に書簡を持った状態をよく描かれています。
119.歌川国芳「四代目市川小団次の浅倉当吾亡霊」
将軍に直訴し磔刑となった当吾。
髪はざんばらで首は真っ赤。
青白い顔をしています。
人々の生活を思い直訴したのに無念でしょう……
121.歌川国芳「四代目市川小団次の茶道印馬実ハ当吾ノ霊/浅倉当吾の霊/こし元小桜実ハ当吾霊 三代目岩井条三郎の如桂木 四代目坂東彦三郎の織越大領」
嘉永4(1851)年、中村座で上演されたものに取材しています。
右手に願書をもつ浅倉の幽霊は画面上部から登場。
左側には骸骨も描かれています。
3枚の大きな作品です。
125.歌川国芳「木曽海道六十九次 細久手 堀越大領」
当吾の幽霊は領主織越大領を悩ませます。
ここでは当吾の姿は細い煙で描かれています。
背景の木々の妖しさ、雲の模様も骸骨のように見えてきます。
《崇徳院》
崇徳天皇は第75代天皇。
鎌倉初期の『保元物語』によると、怨念の為に、経文に血で呪文を記し、生きながら天狗となった、とされています。
日本史上最大の怨霊としても有名です。
この天皇の人生も詳しくしればなかなか悲しいもの。
難しいのです。
127.歌川国芳「百人一首之内 崇徳院」
稲妻が走り、波が渦巻く中、伸びた髪を振り乱し、青い顔をした崇徳院。
なかなか迫力あります。
そして、右上には"瀬を早み…"との歌。
百人一首を取り上げたシリーズものなので、その歌が書かれているのですが、歌とのイメージが違いすぎる。。
そして私はこの歌が好き。
学生時代は百人一首、ほぼすべて覚えていたのですが、今ではすっかり忘れてしまいました。
でも、今でも覚えている数少ない歌。
128.歌川芳艶「為朝誉十傑 白縫姫 崇徳院」
沸き立つ雲と荒れる波が画面を覆います。
平家滅亡を願い天狗となった崇徳院。
怨霊と恐れられただけあり、かなり怖い顔つきです。
《平清盛と亡霊》
129.歌川芳房「清盛布引滝遊覧義平霊難波討図」
源義朝の長男、義平は悪源太とも呼ばれていました。
この場合の悪は悪人の意味ではなく、"強い"、"猛々しい"という意味だそう。
平治の乱に敗れ処刑されるのですが、その後、雷となって自身を処刑した経房を焼き殺した、という伝承があります。
描かれているのは雷となった義平が経房を殺す場面。
稲妻が鋭く走り、迫力あります。
130.葛飾北斎「福原殿舎怪異之図」
1180年、平清盛は京都から福原へ都を遷します。
そんななか、ある朝、庭を眺めると無数の骸骨が。
睨みつけたら消えてしまったそうですが、その光景は異様。
庭の植木、灯籠など骸骨の山。
清盛の周りには一族郎党が集まっていますがさぞびっくりしたことでしょう。
《平家の亡霊たち》
138.歌川芳員「大物浦難風之図」
平知盛が1人船の先頭に立っています。
波の形が人の顔や手のようになっていて怪しげな雰囲気。
波の下から顔を出すのは幽霊たちですが、その表情がちょっと間抜けです。
140.月岡芳年「つきの百姿 大物海上月 弁慶」
月明かりの下、波に一人向かう弁慶。
幽霊など直接的なものは描かれていませんが、怪しい波の動きがその状況を示しています。
ドラマチックでかっこいい作品。
《清姫》
143.歌川国芳「真子庄司愛女 喜代姫」
能などでおなじみの清姫。
美形の僧、安珍に一目ぼれした清姫。
逃げた安珍を追いかけ、蛇となった清姫は安珍の隠れた道成寺の梵鐘に絡みつき焼き殺してしまうという恐ろしい話。
描かれているのはちょうど鐘に絡みついている場面。
髪が乱れ、清姫の帯が蛇に変身しています。
144.月岡芳年「和漢百物語 清姫」
安珍を追いかけ、日高川を渡り終えた清姫。
濡れた髪が顔にまとわりついています。
視線も前かがみとなり、これから蛇になるという様子が見て取れます。
桜の花びらがひらひらと舞っています。
《姑獲鳥》
146.月岡芳年「和漢百物語 主馬介卜部季武」
あれ、うぶめって産女って書くんじゃ……と思い調べました。
姑獲鳥は"うぶめ"と"こかくちょう"と読む場合があるそうです。
"こかくちょう"は中国の伝承上の鳥。
鬼神の一種であって、よく人間の生命を奪うそう。
夜間に飛行して幼児を害する怪鳥で、鳴く声は幼児。
子どもや夜干しされた着物を見つけると血で印をつけます。
付けられた子どもはたちまち魂を奪われてしまう……
中国の古典で様々な伝承がありますが、姑獲鳥は出産で死んだ妊婦が化けたもの、という説があるそうです。
日本でも茨城県で似た伝承があり、夜に子供の着物を干すと"ウバメトリ"という妖怪が自分の子供の着物だと思って、その着物に目印として自分の乳を搾り、その乳には毒があるのだとか。
これは中国の姑獲鳥が由来とされています。
江戸時代初期の日本では、日本の伝承上の妖怪"産女"が中国の妖怪である姑獲鳥と同一視され、"姑獲鳥"と書いて"うぶめ"と読むようになったそう。
これは産婦にまつわる伝承において、産女が姑獲鳥と混同され、同一視されたためだとか。
なるほどなるほど~。
で描かれているのは"産女"のほう。
腰から下が血まみれの青白い女が抱いているのは赤ちゃん。
この赤ちゃんは肌の色から生きているかのようです。
《その他》
152.歌川国貞(三代歌川豊国)「見立三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」
世の中に絶へて桜のなかりせば春の心はのどけからまし
この歌は三十六歌仙のひとり、在原業平が詠んだもの。
この世の中に、桜というものがなかったら、春をのどかな気持ちを過ごせるだろうなぁ
という意味。
さて、描かれいているのは桜姫に恋い焦がれた清玄。
目は金色に輝き、既にこの世のものではないようです。
桜(桜姫)がなかったら、穏やかに過ごせたのでしょうか。。。
155.歌川芳員「新田義興の霊怒て警を報ふ図」
新田義興は南北朝時代の武将。
28歳のときに謀殺されました。
その後、怨霊になった、というよくある話。
連銭葦毛の馬に乗った義興の周りには黒雲がもくもくと。
雷様となったんですね。
迫力あります。
157.月岡芳年「英名二十八衆句 姐妃の於百」
お百は殺人、強盗、御家騒動など様々な悪事をはたらいた女性。
行燈に青白い幽霊がいますが、お百は驚きません。
さすが、肝が据わっています。
159.月岡芳年「芳年戯画 応挙の幽霊 雪舟活画」
上下で違う作品ですが、今回取り上げるのは上の作品。
"応挙の幽霊"
応挙とは四条丸山派の祖、丸山応挙。
応挙は幽霊画でも有名でした。
一説によると足のない幽霊を描いたのは丸山応挙が最初とされています。
その応挙が自身の描いた幽霊画から幽霊が飛び出してきて驚く場面。
なるほど、描いた本人もびっくりの出来なのかぁ。。
面白い作品です。
160.月岡芳年「月百姿 源氏夕顔巻」
源氏物語の夕顔を描いたもの。
夕顔は六条御息所の怨念で亡くなります。
夕顔の花と月が描かれ、繊細で美しい作品。
166.三代歌川国輝「本所七不思議之内 置行堀」
釣りの大好きな男。
"錦糸町のとある堀で釣りをすると化け物が出る"とのうわさを耳にします。
化け物が出る、だけならきっと興味を持たなかったでしょうが、釣りが関係するのなら……
と早速出かけます。
すると釣れる釣れる。
男は笑いが止まりません。
"化け物も出ないし、こんなに釣れたし、帰るか"
と釣果の入った籠を持ち岐路につこうとしたところ。
"おいてけ~、おいてけ~"と恐ろしい声が。
男はびっくり。一目散に帰りました。
そして籠を見てみると空っぽ……
そんなお話。
現代でも一人取り残されたりすることを「おいてきぼり」とか言いますが、これが語源です。
作品のなかでは白抜きの幽霊に驚く男性が描かれています。
168.三代歌川国輝「本所七不思議之内 片葉の芦」
これは恐ろしく悲しい話。
江戸時代、本所にお駒という美しい娘がいました。
近所に住む留蔵という男が恋心を抱き幾度も迫ったものの、お駒は一向になびきません。
遂に留蔵は、隅田川からの入り堀にかかる駒止橋付近でお駒を襲い、片手片足を切り落とし殺した挙げ句に堀に投げ込んでしまうのです。
それ以降、駒止橋付近の堀の周囲に生い茂る葦は、何故か片方だけの葉しか付けなくなった……
想像しただけでも恐ろしい話。
作品は今まさに切りかかろうとしている場面。
今も昔も恐ろしいのは人間かな。
169.小林清親「清親放痴 東京谷中天王地」
明治時代には、西洋諸国に対して恥ずかしくないように、明治5(1872)年に人前で裸になることを禁止する法令が出されました。
腰布を巻いた骸骨を注意するという風刺画です。
《地獄》
170.歌川国芳「地獄変相図」
剣の山に灼熱地獄、釜ゆでや火の車へ投げ込むなど地獄の様子が描かれています。
泣く亡霊たち。
この世で恐れられている亡霊たちも地獄の恐怖があるのですね。
171.歌川芳艶「どうけじごくごくらくのず」
閻魔大王や獄卒たちを歌舞伎のヒーローが倒すという場面。
亡霊も恐れる閻魔大王たちをやっつける歌舞伎のヒーロー。
迫力ある場面です。
173「ゑんまの子」
安政の大地震のあと、地獄へ来る人が急増ってことで悩む閻魔大王が描かれています。
これって、、どうなの??
今なら確実に不謹慎!!ってたたかれますね。。。
174.歌川芳豊「柳川豊後大掾 浅草奥山にて興行仕候」
柳川豊後大掾は江戸で活躍した手品師。
その興行の様子が描かれています。
大きな骸骨と炎が描かれ、不思議な雰囲気。
《驚く人々》
178.歌川広重「東海道五十三対 二川」
弥次さんと喜多さんが縁側に干してある手ぬぐいをお化けだと勘違いしてびっくり仰天している場面。
話の中では浜松でのエピソードだそうですが、ここでは二川になっています。
ひらひらとなびく様子はたしかに幽霊にも見えてきます。
以上になります。
今回は前回よりもすいていました。
残りは9月の第3部。
【妖術使い】がテーマとなると、歌川国芳や月岡芳年らが大活躍しそうですね。
楽しみです。
ブログランキングよかったらお願いします


太田記念美術館

会期は2014年7月1日から2014年9月25日。
3部構成となっていて、
第一部は【化け物】7月1日から7月27日。
第二部は【幽霊】8月1日から8月26日。
第三部は【妖術使い】8月30日から9月25日。
今回は第二部の【幽霊】を見てきました。
第一部の記事はこちら→「江戸妖怪大図鑑 第一部【化け物】」
さて。
夏です。
暑い暑い夏です。
幽霊や妖怪たちも元気になる(!?)夏です。
鬼や天狗、土蜘蛛などの【化け物】
お菊やお岩などの【幽霊】
蝦蟇や蛇を操る【妖術使い】
本当に怖いものから、笑ってしまうものまでさまざまなものが描かれています。
今回はそれぞれをカテゴリーで分け、葛飾北斎や歌川国芳、菱川師宣から月岡芳年まで、総展示数は約270点。
まさに妖怪大集合な展示となっています。
さらっと見てきた中で印象に残ったものを数点書いておきます。
まずは靴を脱いで畳の上へ。
99.葛飾北斎「百物語 お岩さん」
とっても有名な作品。
左目のところが崩れてしまったお岩さん。
この作品では提灯に顔が映し出されています。
提灯の破れたところがちょうど口になっています。
怖いはずなのに、なんとなくユーモラス。
116.葛飾北斎「百物語 こはだ小平二」
描かれているのは後頭部を残してすべての皮をはがされた骸骨。
男女の眠る蚊帳を上から覗き込んでいます。
ちょっと、、かなり怖い。
この幽霊は幽霊役を得意としていた歌舞伎役者小平次。
旅先で、妻とその密通相手に殺されてしまい、この2人のもとへ幽霊となって戻ってきた場面です。
148.葛飾北斎「百物語 しうねん」
位牌の前に水の入った器、まとわりつくように蛇。
幽霊は描かれていませんが、逆にこの世への執着を感じさせ怖いです。
位牌に書かれている北斎オリジナル梵字が人間の横顔のように見えるのがちょっとおもしろい。
147.葛飾北斎「百物語 笑ひはんにや」
角と牙を生やした鬼のような女が、子供の生首をつかんで笑顔を浮かべた恐ろしい作品。
手にした子どもの首の切り口はぶつぶつしていて気味が悪い。。
「百物語」シリーズですから、ベースの話があるかと思いますが、調べたところそのような話は見つかっていないよう。
笑般若はこの北斎の作品と長野県の伝承に見られるようで、他の情報が少ないのです。
なお、この北斎の「百物語」
百物語ですから100あるはずなのに、現在5点しか確認されていません。
最初にその4点が見れちゃいます。
この先は幽霊別(!?)に展示されていました。
《累》
累(かさね)は四谷怪談のお岩さん、皿屋敷のお菊さんと並ぶ江戸時代の三代幽霊スター。(→!!??)
下総国岡田郡羽生村(現在の茨城県常総市)の累ヶ淵に伝わる伝承を題材にしたもの。
百姓・与右衛門と、その後妻・お杉の夫婦には、お杉の連れ子である娘・助(すけ)がいました。
助は生まれつき顔が醜く、足が不自由であったため、与右衛門は助を嫌っていました。
助が邪魔になった与右衛門は、助を川に投げ捨てて殺してしまうのです。
あくる年に与右衛門とお杉は女児をもうけ、累(るい)と名づけますが、累は助に生き写しでした。
村人は助の祟りと噂し、「助がかさねて生まれてきたのだ」と「るい」ではなく「かさね」と呼ばれました。
両親が相次いで亡くなり一人になった累。
病気で苦しんでいた流れ者の谷五郎を看病し、二代目与右衛門として婿に迎えます。
しかし谷五郎は容姿の醜い累を疎ましく思うようになり、累を殺して別の女と一緒になる計画を立てるのです。
正保4(1647)年8月11日、谷五郎は累を川に突き落とし殺害しました。
その後、谷五郎は幾人もの後妻を娶りましたが、死んでしまいます。
6人目の後妻・きよとの間にようやく菊という名の娘が生まれますが、菊に累の怨霊がとり憑き、菊の口を借りて谷五郎の非道を語ります。
そして、供養を求めて菊の体を苦しめました。
近隣の飯沼にある弘経寺遊獄庵に所化として滞在していた祐天上人はこのことを聞きつけ、累の解脱に成功。
しかし再び菊に何者かがとり憑きました。
祐天上人が問いただしたところ、助という子供の霊。
古老の話から累と助の経緯が明らかになり、祐天上人は助にも十念を授け戒名を与えて解脱させました。
とい伝承。
なんだか怖いというより悲しいお話なのです。
これを基にした歌舞伎や落語により話は広まります。
設定は作品によって若干違いますが、「累」という名の女性が「与右衛門」という名の夫に殺害され、怨霊となる、という筋立てです。
94.歌川国芳「三代目尾上菊五郎のかさねぼうこん」
描かれているのは幽霊となった累。
暗い背景に白く描かれています。
鬼火が浮かぶ不気味な景色。
この鬼火の色彩がとてもきれいなグラデーションです。
《お岩》
お岩さんは解説いらないでしょう。
とても有名で現代でもなんども映像化されています。
基本的には「貞女・岩が、夫・伊右衛門に惨殺され、幽霊となって復讐を果たす」というもの。
怪談の定番で歌舞伎・落語、舞台、映画など様々なVer.があります。
102.歌川国芳「四代目市川小団次の於岩ぼうこん」
これはとにかく美しい。
幽霊で美しいはおかしいかもしれませんが、美しい。
蛇山庵室での夢の場面。
美しい娘に折り重なって抜け出たかのようにお岩の幽霊が登場しています。
この演出がすごい。
106.歌川国貞(三代歌川豊国)「三代目関三十郎の直助権兵衛 八代目片岡仁左衛門の民谷伊右衛門 五代目坂東彦三郎のお岩の亡霊/小仏小平亡霊 五代目坂東費お三郎の佐藤与茂七」
3枚つづりの大きなもの。
この作品の見せ場でもある、戸板返しの場面です。
お岩と小平を両面に釘付けした戸板が、自分の前に漂着して驚く伊右衛門。
左には与茂七、右には直助が描かれています。
この作品の面白いところは戸板の部分に紙が貼ってあること。
折り返すとお岩と小平が交互に現れるのです。
107.楊洲周延「三代目片岡我童の田宮伊右衛門 五代目尾上菊五郎のお岩ノ霊」
こちらも3枚もの。
真ん中には大きな提灯。
これも紙がついていて、めくるとお岩の顔が出るようになっています。
周りに描かれた唐茄子も怖い顔をしています。
《お菊》
お菊さんも有名過ぎて解説不要かな。
主人が大事にしていたお皿、10枚のうち1枚を割ってしまい、古井戸に身を投げてしまいます。
そして夜な夜な1枚ずつ数えている、、、というお話。
113.豊原国周「歌舞伎座中満久 皿屋敷化粧姿鏡」
縦に3枚という長細い構図。
珍しい。
上には五代目尾上菊五郎演じるお菊。
下には九代目市川団十郎演じる浅山鉄山。
お菊の背後がぼかされていて、怪しい雰囲気を出しています。
《小幡小平次》
114.豊原国周「初代尾上松助の小はだ小平次/同女房」
先ほども出てきましたが、小平次は幽霊役を得意としていた歌舞伎役者。
こちらも妻お塚と密通相手の左九郎の夢枕に立つ場面です。
なんだか切ない。
さぞかし無念だっただろうなぁ。
《朝倉当吾》
朝倉当吾は藩主の過酷な年貢取り立てを将軍家綱に直訴し、死罪となった佐倉の名主、佐倉惣五郎のこと。
手に書簡を持った状態をよく描かれています。
119.歌川国芳「四代目市川小団次の浅倉当吾亡霊」
将軍に直訴し磔刑となった当吾。
髪はざんばらで首は真っ赤。
青白い顔をしています。
人々の生活を思い直訴したのに無念でしょう……
121.歌川国芳「四代目市川小団次の茶道印馬実ハ当吾ノ霊/浅倉当吾の霊/こし元小桜実ハ当吾霊 三代目岩井条三郎の如桂木 四代目坂東彦三郎の織越大領」
嘉永4(1851)年、中村座で上演されたものに取材しています。
右手に願書をもつ浅倉の幽霊は画面上部から登場。
左側には骸骨も描かれています。
3枚の大きな作品です。
125.歌川国芳「木曽海道六十九次 細久手 堀越大領」
当吾の幽霊は領主織越大領を悩ませます。
ここでは当吾の姿は細い煙で描かれています。
背景の木々の妖しさ、雲の模様も骸骨のように見えてきます。
《崇徳院》
崇徳天皇は第75代天皇。
鎌倉初期の『保元物語』によると、怨念の為に、経文に血で呪文を記し、生きながら天狗となった、とされています。
日本史上最大の怨霊としても有名です。
この天皇の人生も詳しくしればなかなか悲しいもの。
難しいのです。
127.歌川国芳「百人一首之内 崇徳院」
稲妻が走り、波が渦巻く中、伸びた髪を振り乱し、青い顔をした崇徳院。
なかなか迫力あります。
そして、右上には"瀬を早み…"との歌。
百人一首を取り上げたシリーズものなので、その歌が書かれているのですが、歌とのイメージが違いすぎる。。
そして私はこの歌が好き。
学生時代は百人一首、ほぼすべて覚えていたのですが、今ではすっかり忘れてしまいました。
でも、今でも覚えている数少ない歌。
128.歌川芳艶「為朝誉十傑 白縫姫 崇徳院」
沸き立つ雲と荒れる波が画面を覆います。
平家滅亡を願い天狗となった崇徳院。
怨霊と恐れられただけあり、かなり怖い顔つきです。
《平清盛と亡霊》
129.歌川芳房「清盛布引滝遊覧義平霊難波討図」
源義朝の長男、義平は悪源太とも呼ばれていました。
この場合の悪は悪人の意味ではなく、"強い"、"猛々しい"という意味だそう。
平治の乱に敗れ処刑されるのですが、その後、雷となって自身を処刑した経房を焼き殺した、という伝承があります。
描かれているのは雷となった義平が経房を殺す場面。
稲妻が鋭く走り、迫力あります。
130.葛飾北斎「福原殿舎怪異之図」
1180年、平清盛は京都から福原へ都を遷します。
そんななか、ある朝、庭を眺めると無数の骸骨が。
睨みつけたら消えてしまったそうですが、その光景は異様。
庭の植木、灯籠など骸骨の山。
清盛の周りには一族郎党が集まっていますがさぞびっくりしたことでしょう。
《平家の亡霊たち》
138.歌川芳員「大物浦難風之図」
平知盛が1人船の先頭に立っています。
波の形が人の顔や手のようになっていて怪しげな雰囲気。
波の下から顔を出すのは幽霊たちですが、その表情がちょっと間抜けです。
140.月岡芳年「つきの百姿 大物海上月 弁慶」
月明かりの下、波に一人向かう弁慶。
幽霊など直接的なものは描かれていませんが、怪しい波の動きがその状況を示しています。
ドラマチックでかっこいい作品。
《清姫》
143.歌川国芳「真子庄司愛女 喜代姫」
能などでおなじみの清姫。
美形の僧、安珍に一目ぼれした清姫。
逃げた安珍を追いかけ、蛇となった清姫は安珍の隠れた道成寺の梵鐘に絡みつき焼き殺してしまうという恐ろしい話。
描かれているのはちょうど鐘に絡みついている場面。
髪が乱れ、清姫の帯が蛇に変身しています。
144.月岡芳年「和漢百物語 清姫」
安珍を追いかけ、日高川を渡り終えた清姫。
濡れた髪が顔にまとわりついています。
視線も前かがみとなり、これから蛇になるという様子が見て取れます。
桜の花びらがひらひらと舞っています。
《姑獲鳥》
146.月岡芳年「和漢百物語 主馬介卜部季武」
あれ、うぶめって産女って書くんじゃ……と思い調べました。
姑獲鳥は"うぶめ"と"こかくちょう"と読む場合があるそうです。
"こかくちょう"は中国の伝承上の鳥。
鬼神の一種であって、よく人間の生命を奪うそう。
夜間に飛行して幼児を害する怪鳥で、鳴く声は幼児。
子どもや夜干しされた着物を見つけると血で印をつけます。
付けられた子どもはたちまち魂を奪われてしまう……
中国の古典で様々な伝承がありますが、姑獲鳥は出産で死んだ妊婦が化けたもの、という説があるそうです。
日本でも茨城県で似た伝承があり、夜に子供の着物を干すと"ウバメトリ"という妖怪が自分の子供の着物だと思って、その着物に目印として自分の乳を搾り、その乳には毒があるのだとか。
これは中国の姑獲鳥が由来とされています。
江戸時代初期の日本では、日本の伝承上の妖怪"産女"が中国の妖怪である姑獲鳥と同一視され、"姑獲鳥"と書いて"うぶめ"と読むようになったそう。
これは産婦にまつわる伝承において、産女が姑獲鳥と混同され、同一視されたためだとか。
なるほどなるほど~。
で描かれているのは"産女"のほう。
腰から下が血まみれの青白い女が抱いているのは赤ちゃん。
この赤ちゃんは肌の色から生きているかのようです。
《その他》
152.歌川国貞(三代歌川豊国)「見立三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」
世の中に絶へて桜のなかりせば春の心はのどけからまし
この歌は三十六歌仙のひとり、在原業平が詠んだもの。
この世の中に、桜というものがなかったら、春をのどかな気持ちを過ごせるだろうなぁ
という意味。
さて、描かれいているのは桜姫に恋い焦がれた清玄。
目は金色に輝き、既にこの世のものではないようです。
桜(桜姫)がなかったら、穏やかに過ごせたのでしょうか。。。
155.歌川芳員「新田義興の霊怒て警を報ふ図」
新田義興は南北朝時代の武将。
28歳のときに謀殺されました。
その後、怨霊になった、というよくある話。
連銭葦毛の馬に乗った義興の周りには黒雲がもくもくと。
雷様となったんですね。
迫力あります。
157.月岡芳年「英名二十八衆句 姐妃の於百」
お百は殺人、強盗、御家騒動など様々な悪事をはたらいた女性。
行燈に青白い幽霊がいますが、お百は驚きません。
さすが、肝が据わっています。
159.月岡芳年「芳年戯画 応挙の幽霊 雪舟活画」
上下で違う作品ですが、今回取り上げるのは上の作品。
"応挙の幽霊"
応挙とは四条丸山派の祖、丸山応挙。
応挙は幽霊画でも有名でした。
一説によると足のない幽霊を描いたのは丸山応挙が最初とされています。
その応挙が自身の描いた幽霊画から幽霊が飛び出してきて驚く場面。
なるほど、描いた本人もびっくりの出来なのかぁ。。
面白い作品です。
160.月岡芳年「月百姿 源氏夕顔巻」
源氏物語の夕顔を描いたもの。
夕顔は六条御息所の怨念で亡くなります。
夕顔の花と月が描かれ、繊細で美しい作品。
166.三代歌川国輝「本所七不思議之内 置行堀」
釣りの大好きな男。
"錦糸町のとある堀で釣りをすると化け物が出る"とのうわさを耳にします。
化け物が出る、だけならきっと興味を持たなかったでしょうが、釣りが関係するのなら……
と早速出かけます。
すると釣れる釣れる。
男は笑いが止まりません。
"化け物も出ないし、こんなに釣れたし、帰るか"
と釣果の入った籠を持ち岐路につこうとしたところ。
"おいてけ~、おいてけ~"と恐ろしい声が。
男はびっくり。一目散に帰りました。
そして籠を見てみると空っぽ……
そんなお話。
現代でも一人取り残されたりすることを「おいてきぼり」とか言いますが、これが語源です。
作品のなかでは白抜きの幽霊に驚く男性が描かれています。
168.三代歌川国輝「本所七不思議之内 片葉の芦」
これは恐ろしく悲しい話。
江戸時代、本所にお駒という美しい娘がいました。
近所に住む留蔵という男が恋心を抱き幾度も迫ったものの、お駒は一向になびきません。
遂に留蔵は、隅田川からの入り堀にかかる駒止橋付近でお駒を襲い、片手片足を切り落とし殺した挙げ句に堀に投げ込んでしまうのです。
それ以降、駒止橋付近の堀の周囲に生い茂る葦は、何故か片方だけの葉しか付けなくなった……
想像しただけでも恐ろしい話。
作品は今まさに切りかかろうとしている場面。
今も昔も恐ろしいのは人間かな。
169.小林清親「清親放痴 東京谷中天王地」
明治時代には、西洋諸国に対して恥ずかしくないように、明治5(1872)年に人前で裸になることを禁止する法令が出されました。
腰布を巻いた骸骨を注意するという風刺画です。
《地獄》
170.歌川国芳「地獄変相図」
剣の山に灼熱地獄、釜ゆでや火の車へ投げ込むなど地獄の様子が描かれています。
泣く亡霊たち。
この世で恐れられている亡霊たちも地獄の恐怖があるのですね。
171.歌川芳艶「どうけじごくごくらくのず」
閻魔大王や獄卒たちを歌舞伎のヒーローが倒すという場面。
亡霊も恐れる閻魔大王たちをやっつける歌舞伎のヒーロー。
迫力ある場面です。
173「ゑんまの子」
安政の大地震のあと、地獄へ来る人が急増ってことで悩む閻魔大王が描かれています。
これって、、どうなの??
今なら確実に不謹慎!!ってたたかれますね。。。
174.歌川芳豊「柳川豊後大掾 浅草奥山にて興行仕候」
柳川豊後大掾は江戸で活躍した手品師。
その興行の様子が描かれています。
大きな骸骨と炎が描かれ、不思議な雰囲気。
《驚く人々》
178.歌川広重「東海道五十三対 二川」
弥次さんと喜多さんが縁側に干してある手ぬぐいをお化けだと勘違いしてびっくり仰天している場面。
話の中では浜松でのエピソードだそうですが、ここでは二川になっています。
ひらひらとなびく様子はたしかに幽霊にも見えてきます。
以上になります。
今回は前回よりもすいていました。
残りは9月の第3部。
【妖術使い】がテーマとなると、歌川国芳や月岡芳年らが大活躍しそうですね。
楽しみです。
ブログランキングよかったらお願いします


















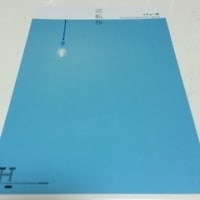
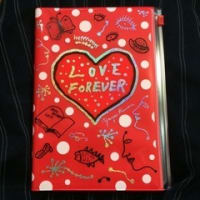



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます