イタリア旅行4日目の午後。ピサへ。
現地日本人ガイドがピサを案内することに。
駅の構内からバス乗り場へ直行。



しばらくバスに乗り、ピサの斜塔のそばまで。ここからはシャトルバスで行く。

着いた。遠くにピサの斜塔が見える。



寺院の中。ガリレオ・ガリレイが振り子の等時性を発見したシャンデリアか?


ピサの斜塔を囲む城壁と中華料理店


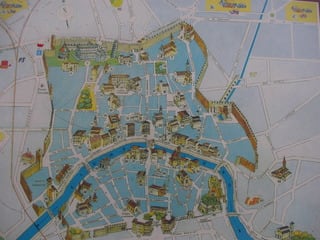

夕食は中華料理。そろそろイタリア料理に飽きた頃か?








こうして4日目が終わりホテルに戻った。
イタリア旅行4日目の午後。ピサへ。
現地日本人ガイドがピサを案内することに。
駅の構内からバス乗り場へ直行。



しばらくバスに乗り、ピサの斜塔のそばまで。ここからはシャトルバスで行く。

着いた。遠くにピサの斜塔が見える。



寺院の中。ガリレオ・ガリレイが振り子の等時性を発見したシャンデリアか?


ピサの斜塔を囲む城壁と中華料理店


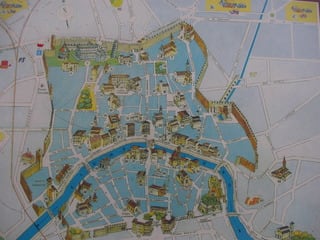

夕食は中華料理。そろそろイタリア料理に飽きた頃か?








こうして4日目が終わりホテルに戻った。


