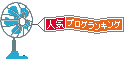立春を過ぎ例年のように庭のフクジュソウは咲きました。(今年はイマイチです)
あちらこちらで梅の頼りを聞きますが、我が家の梅は1ミリ程度のつぼみのままです。
ブルーベリーのつぼみも少し膨らんで来ましたが、こちらは4月にならないと咲きません。
フクジュソウ

梅のつぼみ

ブルーベリーのつぼみ

あちらこちらで梅の頼りを聞きますが、我が家の梅は1ミリ程度のつぼみのままです。
ブルーベリーのつぼみも少し膨らんで来ましたが、こちらは4月にならないと咲きません。
フクジュソウ

梅のつぼみ

ブルーベリーのつぼみ