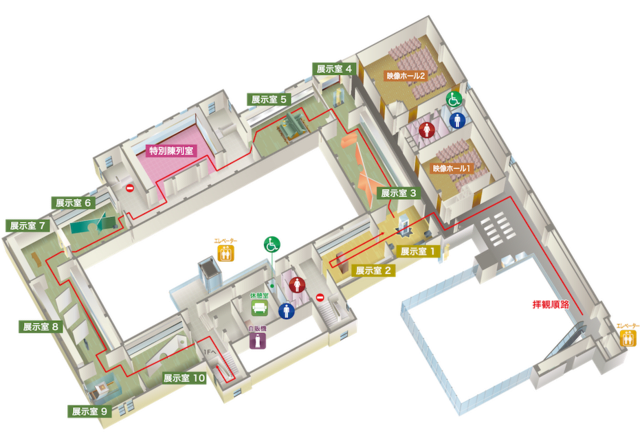今日は、朝から根津へ。

珍しく、カミさんも一緒です。
目的地は、ここ。

根津神社。

日本武尊(やまとたけるのみこと)が
1900年近く前に創祀したと伝えられる古社で、
東京十社の一社に数えられています。

東京十社とは、↓。

根津神社が現在の姿を整えたのは、
江戸幕府第5代将軍の徳川綱吉の治下にあった宝永3年(1706年)。
当時嗣子のなかった綱吉は、
甥で甲府藩主の綱豊(綱吉の兄、後の六代将軍家宣)を世嗣に定めたが、
根津にあった甲府徳川家の江戸屋敷で出生した綱豊は
根津権現を産土神としていたことから、
綱豊が江戸城へ移る際に、
藩邸跡を根津権現へ献納し、
社殿を造営したもの。

主祭神は、
須佐之男命(すさのおのみこと)
大山咋神(おおやまくいのかみ)
誉田別命(ほんだわけのみこと)
正面の鳥居から入って、


神橋

御遷座300年を記念に造営されました。
楼門

江戸内の神社の楼門で唯一残っているもの。
ここから、国宝が続きます。

唐門

社殿

江戸幕府第5代将軍・徳川綱吉による造営で、
お参りする際、目の前にあるのが拝殿。
その奥に本殿・幣殿があります。
一番奥にある一段高い建物が神様のお住まい「本殿」。
拝殿と本殿をつなぐ中間を「幣殿」といい、
権現造(本殿、幣殿、拝殿を構造的に一体に造る)の傑作とされています。
社殿7棟が国の重要文化財に指定されています。
全て本物の漆塗りです。

願掛け榧(カヤ)の木

神使の白蛇が住処とし、
人々が願いごとをするとその願いが不思議と叶ったと言われています。
絵馬の撮影は禁止です。
透塀

社殿の周囲を囲んでいる塀。
細い木で菱形に組まれた窓から中が透けて見えるのでこの名があります。
全長200mの塀が300年経っても歪みなく、
最近の調査で地中8mの深さまで
基礎工事がされていることが分かりました。
西門

棟門という形式の門。
2本脚のシンプルな形で構造上強度に欠けるため、
現存するものが少ない貴重なものです。
北門

このあたりは屋台が並びます。


この日は平日だからか、
閉店の屋台が多かったです。

社務所(客殿)

古木が多く、

保護されています。

神楽殿

文京区の無形文化財に指定されている
社伝神楽「三座ノ舞」などが奉納されます。
千本鳥居

乙女稲荷に通じる参道には奉納された数多くの鳥居が並びます。


徳川家宣公胞衣塚

綱豊(六代将軍家宣)が生まれた屋敷のため、
家宣の胞衣(胎盤)を収めた場所。
乙女稲荷


池を見下ろす舞台造り。
祠は穿たれた穴の中。
古い記録には穴稲荷とあります。
庚申塔

暦の庚申の日の夜に集まり寝ずに夜を明かす、
江戸時代に流行した民間信仰があり、
道の辻などに塔が建てられました。
道路拡幅の際、根津神社へ遷されたものです。

塞大神碑

悪疫が入らぬよう道を守る神で道祖神とも言われます。
駒込追分の一里塚に立てられていたもので、
これも道路拡幅の際、根津神社へ遷されました。
駒込稲荷

根津神社が千駄木村より遷座する前、
この地が甲府宰相徳川綱重の下屋敷だった頃の守り神。


文豪の石

夏目漱石や森鴎外も氏子で、
境内散歩の際に腰を下ろした石。
これは、拝借した写真。
当日見つけられなかったのは、
参拝者が座っていたため、
ゆかりのある石とは思えなかったので。
森鴎外碑銘水

日露戦争戦勝記念に陸軍軍医監だった森林太郎(森鴎外)が
戦利砲弾を奉納した時の台座を転用したもの。
これも見つけられなかったので、拝借した写真。
観光ルートになっているのと、

とにかく外国人が多い。

どうやって名所を知るのでしょうか。
今の時期に訪れたのは、
つつじ苑の一般公開だったからですが、
つつじ苑の写真は、後日。