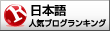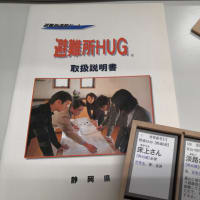今日の日本語教育史では、
ここまでの流れを少し振り返ってから、
ドキュメンタリー番組の視聴に移りました。
初回、「歴史を学ぶ」ことについてお話をして、年代を覚える、ようなことが歴史の勉強じゃないのよーと。
過去の事例を見て、今の問題を考え、未来への対策を考える学問なんだよー、といって、
初回は1919年の新聞に掲載された、第一次大戦後の好景気の中、人手不足を朝鮮人労働者の移入で解決しようという記事を紹介しました。
1990年には日系人の移入で解決しようとし、
2019年は特定技能、技能実習制度で解決しようとしています。
いつも、外から人を入れようとするわけですよ。1990年のは、リーマンショック後に、帰国させないといけないという騒ぎになりましたよね。日本を支えに来てくれた人たちに、私たちはどう対応しているのか。
それを、2回目の授業では「日本国憲法と外国人」というテーマの番組を見て考えてもらいました。
3回目では、「アジア留学生が見た明治日本」というテーマの番組から、日本に寄せられていた期待が結果として裏切られ、日本に対する評価が落ちていくという様子を見てもらい、今、日本にいる外国人にどう対応するべきなのかを考えました。
4回目は、1940年代の映画「授業料」を見て、植民地における日本語使用の実態を観察し、
5回目は、当時の教科書を自由に見てもらうということを、
6回目は、植民地朝鮮における学校教育制度と日本語教育の話をしました。
7回目の今日、ドキュメンタリー番組「巨文島 戦後47年目のにっぽん村」を見てもらい、1992年の番組なんですが、韓国の世代別の日本観、60台の方々の流ちょうな日本語、「故郷に帰ってきたはずの日本人からあいさつ程度の朝鮮語も聞かれないこと」などを見せました。
あ、そうそう。番組を見せるわけですから、それをすべて受け入れるのではなくて批判的に見る、却下されたり編集でカットされたものがどれだけあるのか、取材する内容も記者さんたちの取捨選択があった、ということを念押ししながら見てもらっています。
来週、解説しつつ、後半に向けての地ならしです。「セデックパレ」、見せるかどうか、まだ検討中。
ここまでの流れを少し振り返ってから、
ドキュメンタリー番組の視聴に移りました。
初回、「歴史を学ぶ」ことについてお話をして、年代を覚える、ようなことが歴史の勉強じゃないのよーと。
過去の事例を見て、今の問題を考え、未来への対策を考える学問なんだよー、といって、
初回は1919年の新聞に掲載された、第一次大戦後の好景気の中、人手不足を朝鮮人労働者の移入で解決しようという記事を紹介しました。
1990年には日系人の移入で解決しようとし、
2019年は特定技能、技能実習制度で解決しようとしています。
いつも、外から人を入れようとするわけですよ。1990年のは、リーマンショック後に、帰国させないといけないという騒ぎになりましたよね。日本を支えに来てくれた人たちに、私たちはどう対応しているのか。
それを、2回目の授業では「日本国憲法と外国人」というテーマの番組を見て考えてもらいました。
3回目では、「アジア留学生が見た明治日本」というテーマの番組から、日本に寄せられていた期待が結果として裏切られ、日本に対する評価が落ちていくという様子を見てもらい、今、日本にいる外国人にどう対応するべきなのかを考えました。
4回目は、1940年代の映画「授業料」を見て、植民地における日本語使用の実態を観察し、
5回目は、当時の教科書を自由に見てもらうということを、
6回目は、植民地朝鮮における学校教育制度と日本語教育の話をしました。
7回目の今日、ドキュメンタリー番組「巨文島 戦後47年目のにっぽん村」を見てもらい、1992年の番組なんですが、韓国の世代別の日本観、60台の方々の流ちょうな日本語、「故郷に帰ってきたはずの日本人からあいさつ程度の朝鮮語も聞かれないこと」などを見せました。
あ、そうそう。番組を見せるわけですから、それをすべて受け入れるのではなくて批判的に見る、却下されたり編集でカットされたものがどれだけあるのか、取材する内容も記者さんたちの取捨選択があった、ということを念押ししながら見てもらっています。
来週、解説しつつ、後半に向けての地ならしです。「セデックパレ」、見せるかどうか、まだ検討中。