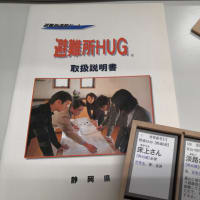今回、個人的に、学会に来たメインは、この一般公開プログラムを聞くことでした。
外国人住民とともに考える安心安全な町づくり
ー日本語教育から見たリスク・コミュニケーション
というタイトルで、
全盲の高校教師の方から「災害時の情報保障と情報発信」
避難所運営ゲームを開発された元静岡県職員の方から「避難所運営ゲーム(HUG)体験」
立命館大学専門研究員の方からは「災害時の地域言語(方言)とコミュニケーション」
もと報道キャスター、311の時は政府の審議官だった方からは、「現場報告 311官邸広報に起こったこと」
日系ブラジル人の方からは、「被災地に求められる真の支援とは」
というテーマでお話を聞くことができました。
急遽、とおっしゃっていましたが、司会の嶋田先生がおっしゃっていたように、日本語教育関係者ではbないぱねりすとばかり、という中で、実に多様な話が伺えたのが、とても大きな財産となりました。
自分が進めていることも、若干関わっていて、
「情報弱者への情報提供」、「情報弱者に伝われば、みんなに伝わる」、「避難所をどう運営するか」といったあたり、また、EPAの介護士看護師候補生の方々への日本語教育を通じては、方言とコミュニケーションが重大な問題としてあることを認識していました。
避難所運営ゲームは、もう7、8年前に購入し、いつか愛教大でやってみようと思いつつ、一度もできていないものです。
日本語教育が、もっといろんなことに関われるということを再認識しつつも、これまで関われてきていない、ということについても改めて考えさせられました。
今後、外国人住民が増えていくわけで、被災時には、一緒に助け合わなければならなくなるわけですから。
情報弱者、の話は、阪神大震災後のやさしい日本語の話から、学生にはよくしています。
戦前のBASIC ENGLISHから始まって、土居光知の基礎語、戦後は国立国語研究所の簡約日本語まで、日本語教育史の中でも取り上げる話題です。
そういった動きと合わせ、今回の問題提起は、日本語教育や日本語教育を学んだ人材がどのように社会に役立っていけるのかを、きちんと示せたのではないか、と思いました。
とてもいいシンポジウムでした。
今日のような話題提供であれば、もっとお一人の長さがなくても、きっと実り多いものだったと思います。
メモをたくさんしましたが、戻って学生さんたちに話せるかな、うまく伝えられるかな。一緒に来られればいいんですけどね。
外国人住民とともに考える安心安全な町づくり
ー日本語教育から見たリスク・コミュニケーション
というタイトルで、
全盲の高校教師の方から「災害時の情報保障と情報発信」
避難所運営ゲームを開発された元静岡県職員の方から「避難所運営ゲーム(HUG)体験」
立命館大学専門研究員の方からは「災害時の地域言語(方言)とコミュニケーション」
もと報道キャスター、311の時は政府の審議官だった方からは、「現場報告 311官邸広報に起こったこと」
日系ブラジル人の方からは、「被災地に求められる真の支援とは」
というテーマでお話を聞くことができました。
急遽、とおっしゃっていましたが、司会の嶋田先生がおっしゃっていたように、日本語教育関係者ではbないぱねりすとばかり、という中で、実に多様な話が伺えたのが、とても大きな財産となりました。
自分が進めていることも、若干関わっていて、
「情報弱者への情報提供」、「情報弱者に伝われば、みんなに伝わる」、「避難所をどう運営するか」といったあたり、また、EPAの介護士看護師候補生の方々への日本語教育を通じては、方言とコミュニケーションが重大な問題としてあることを認識していました。
避難所運営ゲームは、もう7、8年前に購入し、いつか愛教大でやってみようと思いつつ、一度もできていないものです。
日本語教育が、もっといろんなことに関われるということを再認識しつつも、これまで関われてきていない、ということについても改めて考えさせられました。
今後、外国人住民が増えていくわけで、被災時には、一緒に助け合わなければならなくなるわけですから。
情報弱者、の話は、阪神大震災後のやさしい日本語の話から、学生にはよくしています。
戦前のBASIC ENGLISHから始まって、土居光知の基礎語、戦後は国立国語研究所の簡約日本語まで、日本語教育史の中でも取り上げる話題です。
そういった動きと合わせ、今回の問題提起は、日本語教育や日本語教育を学んだ人材がどのように社会に役立っていけるのかを、きちんと示せたのではないか、と思いました。
とてもいいシンポジウムでした。
今日のような話題提供であれば、もっとお一人の長さがなくても、きっと実り多いものだったと思います。
メモをたくさんしましたが、戻って学生さんたちに話せるかな、うまく伝えられるかな。一緒に来られればいいんですけどね。