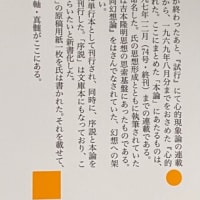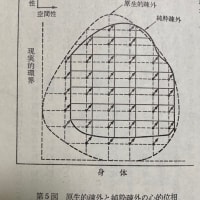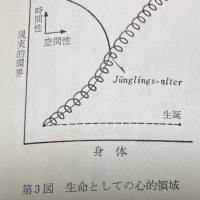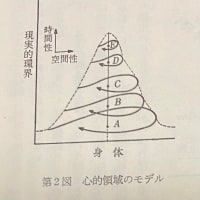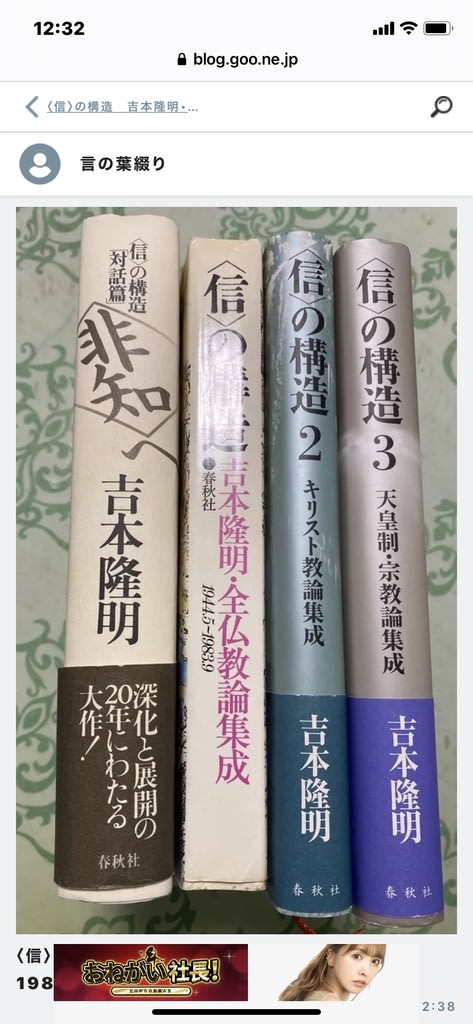
126〈信〉の構造2 キリスト教論集成
吉本隆明
⑦喩としてのマルコ伝 治癒
投稿者 古賀克之助

〈信〉の構造2 ——キリスト教論集成
ニ〇〇四年十一月三十日 新装版第一刷発行 著者ー吉本隆明 発行所ー株式会社春秋社
喩としてのマルコ伝 治癒より抜粋
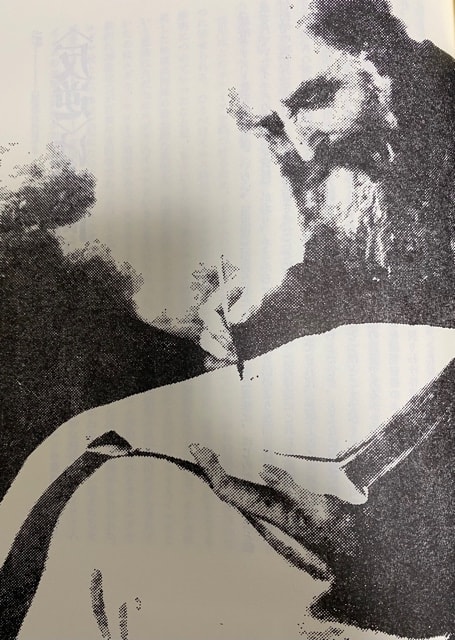
喩としてのマルコ伝
治癒
主人公イエスは繰り返し飽きずに廃疾とされる病気を治癒させる。治癒させる行為の意味は治癒させる行為の記述の意味を包括している。かれの行為のくどさと荒唐さは、わたしたちをうんざりさせる。けれどその記述の意味はちがう。マルコ伝の主人公に配与される行為としては、もっとも本質的で逸しえなかったので、記述が繰り返されたとみるほかない。それは疾病概念と喩の行為とから構成されていた。
マルコ伝の主人公イエスが治癒させる病気の種類と繰り返しの度数はつぎのようなものである。
「穢汚した霊(悪鬼)」に憑かれた者4
「熱」に病んで臥している者 1
癩病 1
中風 1
手なえ 1
血漏病(血友病) 1
(瀕)死 1
盲•聾•啞 4
いままでは精神病•身体障害•不治•老人病とみられるもので、いずれも恢復は不可能とみなされた心身の病と欠陥ばかりであった。主人公は一瞬に治癒させる。マルコ伝によるこの病気の選択には〈不可能〉という意味の象徴がこめられている。だいいちに回復が人智をこえるという〈不可能〉がある。またある意味では人間だけの力ではその病になることの〈不可能〉がこめられている。そのところで治癒の願望がやはり人間的な願望の彼方にまで達しなければならないものの象徴であった。主人公がこれを治癒させうるとすれば時空を超えて一瞬のうちに成就しなければならなかった。なぜならば薬石によって徐々に治癒されてゆく過程があるとするなら、人間的な願望のこちら側で到達できるものにほかならないからである。このうち「穢汚した霊(悪鬼)」が体内に宿って精神を狂わせ、これを外へ追いだすことが治療だという祈祷性精神病は四例である。それ以外の病気でも悪い霊が身体の部位にとどまるとき、その部位が病むという概念が流布されていた。マルコ伝第九章で主人公イエスが「啞であつて耳聾の霊よ。わたしはおまえに命ずる。この子から出てゆけ、そして二度と入るな」というと、霊がさけびだし子供にひきつけをおこさせながら出てゆき、子供が死んだようになったと記述されている。また第一章で癩病人を治癒させるという個処では、主人公は「じぶんの存念だから潔くなれ」というと「癩病がさって」その人は潔くなった。癩病も穢汚の霊の仕業とおもわれていた。もうひとつの概念では〈罪〉が病気を結果する。あるいはすべての病気は〈罪〉であるという概念があった。第二章でカペナウムにきたイエスが四人に担われた中風の者の信仰が深いのをみて、中風のものに「子よおまえの罪は許された」という個処がある。そこでは神自身でなくその子(人の子)にしかすぎない主人公に〈罪〉をゆるす権威があるかどうかが問題にされる。このばあいに「おまえの罪はゆるされた」ということと「起きよ、床をとりさって歩け」ということは同義であった。ここは「おまえの罪はゆるされた」から「起きよ、床をとりさって歩け」というものではない。このふたつは別々の距りであらわれる。「おまえの罪は赦された」というのは人間の存在にたいして根源的な容認がなされたことを告げる言葉になっている。この容認のなかには〈罪〉の概念にあたるすべてのことが包括される。そして〈罪〉がマルコ伝によって普遍人間性にあたるとすれば、この容認は人間の内在的根拠のすべてにわたる容認を意味したのである。 それならば中風患者の病気のごときは当然この容認に含まれるはずである。この〈含まれる〉ということには〈表現的〉な関係の概念も計上される。そこで「おまえの罪はゆるされた」と「起きよ、床をとりさって歩け」とは
同義的な喩の関係がおかれている。マルコ伝が繰り返し記述する病気の治癒行為は、同時代の習俗的な医療行為にたいして教義の有効性を強調しているようにみえる。けれどその繰り返しへの固執は人間の普遍的な根拠である〈罪〉にたいする特赦の同義的な暗喩から構成されている。マルコ伝のイエスの廃疾者にたいする治癒行為は、原始キリスト教時代のイスラエルにおける疾病観を露わにした。執拗に繰り返されているイエスの治癒行為は、病気が〈罪〉の暗喩であり〈罪〉は人間の内在的な根拠だから〈罪〉を一身に背おう本質的な行為とみなされた。治癒行為の記述はちょっとかんがえると、主人公イエスが強大な超能力を行使し、奇跡をなすことができる示威のようにみえる。でもそうではなかった。〈病者〉は〈罪人〉の一種であり〈罪人〉とは人間的な余りに人間的な存在として、いわば原始キリスト教よってもっとも重要な人間の精髄とみなされていた。不治、先天的な疾患、老衰とみなされてどうにもならない病者たちが〈信〉の存在する徴候を代償に即座に癒されるという概念が、すべての人間の〈罪〉を一身に背負ったために身を滅ぼすキリストという概念と交換されるところに治癒行為があった。これはたぶんマルコ的教義にとって逸することができないメシアの喩的な意味をなしていた。
マルコ的世界にただひとつの標語を掲げよということになれば内在する〈罪〉とその〈治癒〉という言葉に帰着する。〈罪〉こそはマルコ伝の世界によって発明された概念であり、それ以前にもそれ以外にもこれを発見した人類はいなかった。
(中略)
あることが言説の重要な対象や関心のまとになったとたんに、そのことは内面化するというのはマルコ的な世界の特徴である。〈貧困〉は救抜さるべき対象としては現実的な飢え、乏しさ、不如意のことをさしているが、なくてはならぬもの、それなしには教義が成立しないものとしては内面的な貧しさ、謙虚、へりくだり、つねに願い渇望する心の意味を分化する。この内面化をうけた〈貧困〉はもはや人間にとって必要な普遍倫理になっている。
「イエスは応えた。『じっさいきみたちに云うが、わたしのため、善い知らせのために、家とか兄弟とかまたは姉妹、あるいは母とか父、あるいは子、また土地を捨てる者は誰でもいま現世でもっているよりは百倍もの家、兄弟、姉妹、母、子、土地を迫害と一緒に受けとり、また未来の世で永遠の生命をあたえられる。最初の者の多くは最後の者になり、最後の者の多くが最初の者になろう』。」(「マルコ伝」第十章二九ー三○)
「イエスはかれらを呼んで云った。『諸国家の支配者とみられているものがそれらを圧制し、偉大な者とみられている者がそれらを統治していることは、きみたちが知っている。けれでもきみたちのなかではおなじではない。きみたちのあいだで最初の者であろうとする者は、すべての人の奴隷になるだろう。だから人の子は仕えられるためではなくて、かえって仕え、そうして沢山の人たちの代償としてその命を与えるために来たのだ』。」(「マルコ伝」第十章四二ー四五)
百倍もの「家、兄弟、姉妹、母、子、土地を迫害と一緒に受けとり」といっているときには、すでにこの「家」「兄弟」「姉妹」「母」「子」「土地」は現実に対応する概念ではないことは明瞭であった。内面化をうけた喩としての「家」「兄弟」「姉妹」「母」「子」「土地」等になってしまった。すでにもっとも強い絆、もっとも断ち難い関係、もっとも依存しうる他者、あるいは本能の選択のようなものの各種をさしていた。つぎにはこの言葉は普遍的な人間性に対立するものに転化された。この馴染みの深い倫理は、宗教のものではなくて現実的な迫害にたいする処方箋を与えている。ただ紙包みになかにはどんな薬もはいっていなかっただけだ。
このマルコ的な世界の強要するところは重大であった。現実的な絆と執着のうちもっとも強力な所有物を、わずかな教義の言葉ととりかえたよと説きふせたときに、それに従うことによって人類は心の法規、その罰則、本能に反することの喜び、抽象と快•不快との結合などをはじめて身につけて知った。
さらにそのさきでは現実的な秩序と内面化された秩序とでは出現され方(表現の仕方)が逆にならなくてはいけないし、そうなることが強調される。この強調は繰り返しあらわれる。ローマ帝国的な秩序でも、ユダヤ的な地域支配の秩序でも、民衆の上に立って支配権と行政権をふるっているものは。偉大な者とみられている者である。けれどイエスの口から吐き出される教義的な秩序では、これは逆倒される。偉大なといわれている者であろうとすれば、人々に使役される者になり、最初の者になろうとすれば、すべてのものの下僕にならなければならないし、またそうなるはずだ。その世界は現実のどんな所有よりも観念の所有のほうが価値があるものだという世界から戻ってきたものが、ふたたび現実の世界で結ぶ関係の仕方の世界である。そこで鏡像のように価値の序列は逆に像を結ぶはずである。どうしても「最初の者」、先導者、支配者はもっともへりくだった現実の姿でなければならない。また偉大であろうとするものは下僕であろうとするものでなければならない。この鏡像にうつった価値の姿にいたって、その生々しさに時間と空間を超えて人々を捉えたといっていい。誰でもが思いあたるふしがあることになってしまった。これはわたしたちが内面性と呼んでいるものの現実からの自己類別の仕方と、また内面性と呼ばれるものの側からの現実へのかかわり方を指示してあるかも知れないのである。けれどここまできてマルコ的な世界の言葉が、自己規制の倫理のようなものとして重く受けとられるようになったことが重大であった。わたしたちはほんとうにマルコ伝の同時代の言葉のあり方をそこまで知っているわけではない。言葉が帯びてしまう概念との多様な関係のなかで〈倫理的〉と呼ばれる関係の成立を、このマルコ的世界にみたいと思うだけだ。マルコ伝の主人公イエスとは何者なのか。かれは人々の召使いである者、人々の奴隷である者、人々に仕える者のうち最大のものである。したがって最低の者でなければならぬ。かれはすべての人間の〈罪〉〈穢れ〉それから〈病い〉〈貧しさ〉を一身に背負い込んでしまったため、すべての人々のいちばんあとから従ってゆく召使いである。かれは不可能なほどの重荷のためにかならず生命をすり減らし、迫害され、殺されて死ぬことが決定されている者である。
こういうイエス像の〈発明〉はニーチェのもっとも反撥をかったところだった。なんとなればかくしてイエスはイスラエルの支配とひとびとの最大の敵として、盗人バラバよりももっと憎まれ卑しまれ、十字架にかけられて死ぬという迂路をとおることにより、イスラエルの敵である〈全世界〉が躊躇なくこのイエスに喰いついてくるように仕向けたというのがニーチェの底意地の悪い解釈だった。「かえりみて思うに、いかに老獪きわる精神の者といえども、およそこれにもまして危険な餌を考えだすことができるであろうか?誘惑し、陶酔させ、麻痺させ、堕落させる力の点で、あの〈聖なる十字架〉という象徴(シンボル)に匹敵すべきものを、あの〈十字架にかけられた神〉という戦慄すべき逆説(パラドックス)、人間の救済のために神自らが十字架にかかるという想像を絶した極端な残忍きわまるあの秘蹟劇に匹敵すべきものを、誰が考えだすことができるだろうか?」(「ニーチェ「道徳の系譜」信大正三訳)言葉はいくらか現在では変えたり緩和したりできるが、云いたいまとはきちっとしている。ニーチェがマルコ的世界に嗅ぎわけた危険な誘惑、まるで人間であることの総てをさらい尽くすもののように戦慄した惧れは、すべての人間の普遍的な〈罪〉を背負い込み、最大の「良心の疚しさ」と〈痛み〉とを感じながら、イスラエルの人々に蔑まれ迫害され、遺棄されて十字架の死につくという構図がけっして〈天上〉へ昇華されるものではなく、ますます近代以後の人間の現実の内面的な構図に生々しく近づいてゆくという点にあった。神の子であることが同時に人の子であるという論理によって〈発明〉されたイエスが、人々の無理解のうちに支配者に殺害されることによって、〈天上〉の神の貌を代償として得るというのではない。むしろますます現実の人間のリアリティに近づいてくるという構想がニーチェを苛立たせるのだ。ここに最も人間らしいというトートロジーに耐えるところの人間像が占拠されているからだ。人々はこのマルコ的世界のイエス像に背反するときには人でなしに変貌しなければならぬ。そうはいわれないまでも人間とはなにかという問いに、別様にこたえなければならない。ニーチェはもちろんそれに応えてみせたのである。
人間という奴は自然にほおっておけば暴力的であり利己的であり、残酷であり、圧倒的であり、つまり動物たちがもっているすべての本能をみなもっていて、それを最大限にに放散して振る舞うものだ。二人がいればかならず債権者と債務者の関係をつくりだすし、これを緩和するために掟を共同でつくって統御し合うようになる。これこそが人間の存在の仕方におけるもっとも自然な形である。挙動における〈意識〉の発生は、いわばそれ以外の無意識の部分を〈疚しさ〉〈罪〉〈べからざるもの〉として軛をかけることになり、〈良心〉〈道徳〉〈倫理〉〈同情〉等々の感情を生みだしてしまった。人間の心が内部にめくれ込むようになり、挙動に清朗さがなくなったのは、ここ二千年くらいのあいだ、マルコ的世界の教義に人間がなぎ倒されたからに過ぎない、いうように。
(中略)
マルコ伝の主人公はしきりにこの類のこと、つまり自分に従うものは現世では生命を失うつもりでなければならない、そうすれば来世では 永遠の生命が得られるといったことを強調しはじめる。この強調は具体性を帯びたときには、じぶんはかならず多くの苦難をうけ、長老、司祭長、律法学者たちのような神権と支配権力をもだたものたちから、疎んじられ、かつ殺される。そして三日のあとに甦るという言説になっている(「マルコ伝」第八章三一ー三ニ)。場所が具体的になって、エルサレムに上がったところで祭司長や学者たちにひきわたされ、死罪を定められて、異邦人にゆだねられ、異邦人に嘲られ、虐げられて遂に殺され、後に三日たって甦ることが〈意図
〉的に繰り返される(「マルコ伝」第十章三ニー三四)。マルコ伝の教義では、イスラエルのすべての犯罪人、取税人、貧困者、廃疾者に象徴される最も人間的な人間たちの不可避の属性である〈罪〉〈疎まれ〉〈貧困〉〈病い〉などの業悪を背負った一人の人物は、最大の悪人、最大の取税人、最大の廃疾者、最大の貧困な者として打ちひしがれ、疎まれた極限として殺されなければならないからである。そして現世で殺されたあとで「神の国(天国)」へいって浄化され、再び現世に「永遠の生命」をもって来臨する。ふたたび来臨するときの形像はエリヤとモーゼが左右にいるとされていたり(「マルコ伝」第九章ニー四)、天使たちにかこまれている(「マルコ伝第八章三八)とかかれたりしている。
マルコ伝の主人公が神権と政治権を現に支配している者たちから盗賊として十字架にかけられ、群衆から罵られ、蔑まれて殺され、「神の国(天国)」に召喚されたのち、再び現実の世界へもどってくるという言説はもっとも〈作為〉と〈意図〉に充ちている。ここからすべての問題が派生する。〈作為〉や〈意図〉がなければ、刑死して「神の国(天国)」へいった主人公が、生きかえってまたこの現世にやってきたと記され個処を記された通りに解すればよいだろう。「神の国(天国)」はそのとおり〈神の国(天国)〉であり〈甦り〉はそのとおり〈甦り〉である。けれどマルコ伝の」作為〉や〈意図〉は宗教的な〈信〉の表白、しかもマルコ伝の主人公の個性的な〈意図〉を超えた共同的な〈作為〉や〈意図〉にかかわっていることが明確にうけとれる。そしてこの復活、再臨は〈信〉の構造の端から端にわたらなければならない。マルコ伝自体は、つぎのように「神の国(天国)」へ行ったものの再臨と復活について語る。
「復活はないと云っているサドカイ人たちが、イエスのそばにやってきて、こう質問した。『師よ、モーゼは、兄弟が子供もなくて妻をのこして死んだときは、その兄弟がかれの妻を娶って、かれの兄弟の子孫をもうけるべきだと、わたしたちに規定している。いまここに七人の兄弟があった。兄が妻を娶って後嗣ががないままに死んだ。次男がその女性を娶り、後嗣がなくて死んだ。三男もまた同じようであって、七人の誰もが後嗣なくおわった。あげくの果てにその女性もまた死んだ。復活のときにみな甦るだろうに、この女性は誰の妻として甦ればよいのか。七人ともこの女性を妻としたからである』。イエスは応えた。『きみたちが誤っているのは、聖書をも、神能力をも認知せぬせいではないのか。死者の甦りには、人間は娶らないし、嫁にもいかないで、天にいる天使のようになるのである。死者の甦りについて、モーゼの書のなかに、燃える荊の話のところで神がモーゼに「わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だ」と告げているのを、きみたちはまだ読んでいないのか。神は死んだ者のための神ではない。生きている者の神である。きみたちは大へん誤っている』。」(「マルコ伝」第十ニ章一八ーニ七)
マルコ伝の本文に則していえば「復活」などはないという宗派(サドカイ派)があったことがわかる。そしてこのことは主人公にたいする荘厳や愛惜の問題ではなく、純教理上の問題にほかならなかった。サドカイ人はこのばあいに理知派の象徴だからマルコ伝の世界にたいする追究の比喩は理詰めになっている。言語の外からいえば死んだ者が「神の国(天国)」へ行くことは認めるが、死者が蘇生してこの現世に再びやってくるなどということはありえないではないか、と主張している。これにたいしてマルコ伝の教理は主人公の言葉をかりて述べられる。
「死者の甦りには、人間は娶らないし、嫁にもいかないで、天にいる天使たちのようになるのである」という応えはマルコ伝の教理が「神の国(天国)」に接触して「復活」した人間を、肉体をもった生身の人間とかんがえていたことを証明している。しかしながらこの「復活」した者は、擬人的な形像(天使たちのような)をもつものとして考えられていた。〈娶る〉とか〈嫁する〉とかいう比喩で「復活」を否定しようとするサドカイ派は無意味である。生身の人間でないものにもともと〈娶る〉とか〈嫁する〉とかいうことは有りえないから。
けれども、〈娶る〉ことも〈嫁する〉こともなく甦った死者の擬人的な形像(天使)は、現実的な人間からは「神の国(天国)」により近いとみなされて、後世に禁欲的な僧侶概念の原型を生みだすことになった。生きながら再臨したというのが僧侶の定義であった。マルコ伝の教理はそこにはないようにみえる。それにつづいて「神は死んだ者のための神ではない。生きている者の神である」と記しているところによれば、死者が甦るかどうか、甦るところの死者はほんとうの死者であるか、甦った死者は生きた人間であるか、という問題は第二義的なもので、現実の「アブラハム」や「イサク」や「ヤコブ」がどう救済されるかが問題なのだ、主張しているようにみえる。
マルコ的な教義は宗教的な空間と時間の全体に分布しうる可能性をもっている。「神の国(天国)」というイメージに叶ったある空間を占めた想像的実在の場所であり、「復活」はそこへ行った死者がまたもどってきて、現実の世界で肉体をもって蘇生することである。このかんがえは宗教的思惟の一端を支えている。非宗教的な思惟も比喩としてそう語る実在感をもっているといってもよい。「神の国(天国)」はいわば自己意識のこしらえた至上空間、あるいは空間的に至上化された自己意識そのものであって「復活」というのはそこに触れて内面を浄化される人間、あるいは人間的に浄化された内面を指している。だから、無形の思惟にほかならないという考えがもう一方の端を支えている。この両端にわたる領域にインテグレートされるものが、マルコ的な世界における「神の国(天国)」と「復活」の暗喩の世界であったといってよい。この分布のどこに特異点をおくかについてマルコ伝の教義は「死者の甦りには、人間は娶らないし、嫁にもいかないで、天にいる天使のようになるのである」という暗喩をもってこたえている。
これは後代の組織的神学ともかかわりなく、また未開の自然宗教ともちがった過度的な特異な宗教がつくりあげた喩的な一形像であった。マルコ伝はあとに加えた復活譚のなかで「この後その中の二人が、田舎に往く路を歩いていると、イエスが異なった姿で現れた」(第十六章一ニ)と記している。マルコ伝のイエスは「普通の人間とは異なった姿」でだがたしかに人間の形像をして復活せねばならなかった。人間が「娶らないし、嫁にもいかないで、天にいる天使たちのように」なるという直喩の「復活」なるものは「天にいる天使たち」の姿がわからぬかぎりわかりようがない。しかし直喩としてはわかることができる。またそのときの人間の「異なった姿」も亡霊のように不分明だが、直喩としての人間のいわばマルコ伝の主人公が甦った姿であることは確かであった。
たぶんわたしたちは死者が「神の国(天国)」に触れてふたたび「復活」によりこの世界に蘇生するというマルコ伝の説話の背後にひとつの原型を読んでいる。この原型は〈自由になった〉という感じの発生の形態である。〈死〉のこだわりから自由になるためには〈死〉へ没入しなければならない。それからひとりでに離脱して蘇生の思いが得られるまでは、そこには事物から自由になる感じの原型が動いている。これがマルコ伝の「神の国(天国)」や「復活」の説話の意味を認めているわたしたちの姿である。
マルコ伝から抽出することができる教義的なものは、ついに教義そのものとして再構成したり再組織したりすることを許さない喩的な流れに終始している。マルコ伝自身がじぶんを教義化しようとしている個処ではつまらない寓喩に代えてしまっている。これを暗喩または直喩になるほかはなかった教義的なものとして放置するとき、もっとも自然な形が得られる。
けれども教義的なものに、たぶんマルコたち初期の教団が当面した情況の生々しさがくわわるときは、事態はちがってくる。それは教義的なものから思想的なものへ、喩から直叙へと変貌してゆく。その屈伸する筋肉の動きのような生々しさは類をみつけることができないほどだ。