今日は「数のやりとり」について書きたいと思います。
小学校の算数の授業で最初につまずくのは、「繰り上がりの計算」ではないでしょうか。
今まで、たくさんのお母さまから相談されました。
ここでつまずかない為には、コツがあります。
「10」のかたまり、「5」のかたまりで考えることができるかどうか。
日本の算数の授業は「3+5=□」という形が多い気がします。
でも本当は、もっと自由なものであってほしいのです。
「□+□=5」「□+□=6」「□+□=7」「□+□=8」・・・という様に。
足して「5」になる組み合わせはどんなものがあるのか。
「1+4」「2+3」「3+2」「4+1」などがありますよね。
あと、「0+5」「5+0」も重要です。
「0」の概念を早いうちからしっかり教えてあげましょう。
このような練習をして、数を「5」と「10」のかたまりで考えられるようにします。
これができれば、繰り上がりの計算は簡単です。
「3+8」という問題があったとします。
大きい数字は「8」なので、それを基準に考えます。
「8」が「10」になるためには、あといくつ必要か。
かたまりで考えることができる子は、すぐに「2」とわかります。
「3」から「2」をもらってきて・・・「1」残るから・・・「11」と簡単に解けるのです。
でも、かたまりで考えることができない子にとっては、すっごく難しい問題に感じてしまいます。
指を使って数えようとしても、指は10本しかないし…。
「先生、指かして~」なんて言ってくる子もいました
さらっと書いてしまいましたが、この考え方も子供にとっては意外と難しいものです。
では、どうすれば簡単に理解できるのか…。
それは、小学校受験の問題によく出る「数のやりとり」が効果的です。
例えば・・・
「二人のお友達のりんごの数を同じにするには、左のお友達が右のお友達にいくつあげたらいいですか。」
こんな問題があります。
この考え方が重要です。
もう少し難易度を上げると、こんな問題もあります。
「表が黒、裏が白のカードがあります。どちらを何枚裏返せば、両方同じ数になりますか。」
このような問題は、小学生にやらせてもできない場合が多いんですよね~。
この考え方がすんなりできるようになれば、繰り上がりの計算なんて余裕です
これができたら、「等分」の問題もやってみるといいと思います。
2等分は意外とできるのですが、3等分や4等分は意外と難しいかもしれません。
普段から、おやつの時間などに練習してみてください。
言い方も「2分の1」「3分の1」などと変えてみるのも効果があります。
小さいうちから「何分の一」という意味を理解させておくと、授業で分数が出てきたときにもすんなり理解できますよ。
我が家では、おやつの時間に「そのどら焼き、3分の1だけママにもちょうだい 」なんて言って練習してます
」なんて言って練習してます
もちろん、分数の意味も忘れずに教えてあげてくださいね。
「3個に分けたうちの1個分 = 3分の1」と。
小学校受験を考えていないお子様にも、この手の問題は今後の役に立つと思いますよ
最後まで読んでくださってありがとうございます
↓ ランキングに参加しています。下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです
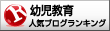
 にほんブログ村
にほんブログ村
小学校の算数の授業で最初につまずくのは、「繰り上がりの計算」ではないでしょうか。
今まで、たくさんのお母さまから相談されました。
ここでつまずかない為には、コツがあります。
「10」のかたまり、「5」のかたまりで考えることができるかどうか。
日本の算数の授業は「3+5=□」という形が多い気がします。
でも本当は、もっと自由なものであってほしいのです。
「□+□=5」「□+□=6」「□+□=7」「□+□=8」・・・という様に。
足して「5」になる組み合わせはどんなものがあるのか。
「1+4」「2+3」「3+2」「4+1」などがありますよね。
あと、「0+5」「5+0」も重要です。
「0」の概念を早いうちからしっかり教えてあげましょう。
このような練習をして、数を「5」と「10」のかたまりで考えられるようにします。
これができれば、繰り上がりの計算は簡単です。
「3+8」という問題があったとします。
大きい数字は「8」なので、それを基準に考えます。
「8」が「10」になるためには、あといくつ必要か。
かたまりで考えることができる子は、すぐに「2」とわかります。
「3」から「2」をもらってきて・・・「1」残るから・・・「11」と簡単に解けるのです。
でも、かたまりで考えることができない子にとっては、すっごく難しい問題に感じてしまいます。
指を使って数えようとしても、指は10本しかないし…。
「先生、指かして~」なんて言ってくる子もいました

さらっと書いてしまいましたが、この考え方も子供にとっては意外と難しいものです。
では、どうすれば簡単に理解できるのか…。
それは、小学校受験の問題によく出る「数のやりとり」が効果的です。
例えば・・・
「二人のお友達のりんごの数を同じにするには、左のお友達が右のお友達にいくつあげたらいいですか。」
こんな問題があります。
この考え方が重要です。
もう少し難易度を上げると、こんな問題もあります。
「表が黒、裏が白のカードがあります。どちらを何枚裏返せば、両方同じ数になりますか。」
このような問題は、小学生にやらせてもできない場合が多いんですよね~。
この考え方がすんなりできるようになれば、繰り上がりの計算なんて余裕です

これができたら、「等分」の問題もやってみるといいと思います。
2等分は意外とできるのですが、3等分や4等分は意外と難しいかもしれません。
普段から、おやつの時間などに練習してみてください。
言い方も「2分の1」「3分の1」などと変えてみるのも効果があります。
小さいうちから「何分の一」という意味を理解させておくと、授業で分数が出てきたときにもすんなり理解できますよ。
我が家では、おやつの時間に「そのどら焼き、3分の1だけママにもちょうだい
 」なんて言って練習してます
」なんて言って練習してます
もちろん、分数の意味も忘れずに教えてあげてくださいね。
「3個に分けたうちの1個分 = 3分の1」と。
小学校受験を考えていないお子様にも、この手の問題は今後の役に立つと思いますよ

最後まで読んでくださってありがとうございます

↓ ランキングに参加しています。下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです











