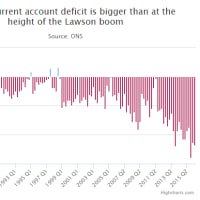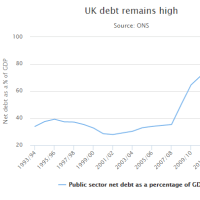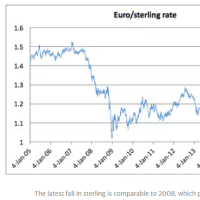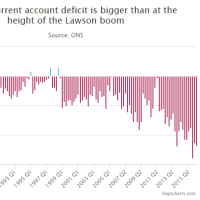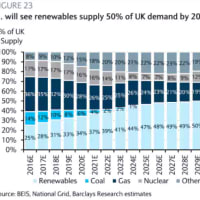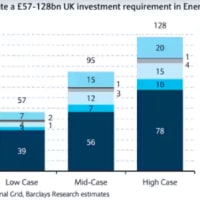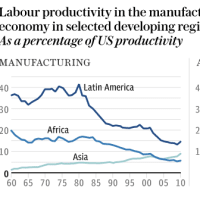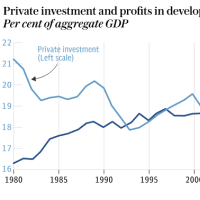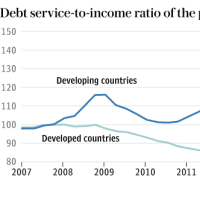フラストレーションがにじみ出るエントリです。
ほんと、このごろすこーしヘンよー、みたいな。
Schizophrenic investors expect slump: bet on boom
(統合失調症な投資家、不況を予測しながら、好況に賭ける)
By Ambrose Evans-Pritchard Economics
Telegraph Blog: Last updated: May 21st, 2013


ほんと、このごろすこーしヘンよー、みたいな。
Schizophrenic investors expect slump: bet on boom
(統合失調症な投資家、不況を予測しながら、好況に賭ける)
By Ambrose Evans-Pritchard Economics
Telegraph Blog: Last updated: May 21st, 2013
The latest poll of Morgan Stanley's top clients from across the world says it all.
モルガン・スタンレーの世界中の上客を対象に行った最新調査が、全てを物語ってますね。
Chief economist Joachim Fels tells us that not a single investor at the bank's Florence forum thought the world economy would rebound with any strength later this year.
キャピタル・エコノミクスのヨアヒム・フェルス氏は、同行のフィレンツェ・フォーラムに出席した投資家で、世界経済は年末まで堅調なリバウンドを見せるだろう、などと考えている人は一人もいなかったとしています。
Just a quarter expect a return to trend growth. Some 57pc think there will be no escape from the "twilight" conditions afflicting the western world, and 20pc expect an full-blown global recession. That is a remarkably bearish set of views. Yet the same investors are overwhelmingly bullish on stocks and property.
成長トレンド復活を予測する投資家も僅か4分の1。
約57%は、西側世界に影響している「黄昏」から逃げることは不可能だと考えていて、20%は全面的な世界不況の到来を予測しています。
これは素晴らしくベアな見解です。
でも、同じ投資家達が株やら不動産については圧倒的にブルなのです。
This schizophrenic exuberance seems entirely based on the assumption that QE and central bank largesse will keep the game going, flooding asset markets with liquidity. Indeed, 80pc think the ECB will cut rates again, and half think it will have to swallow its pride and join the QE club in the end.
この統合失調症的騒ぎは完全に、QEと中央銀行の気前の良さでゲームは続き、資産市場は流動性でジャブジャブだ、という憶測に基づくものです。
そうなのです。
80%はECBが再び利下げするだろうと考えている上に、半数は、ECBは誇りを捨てて遂にQEクラブに加わるだろう、と考えています。
Four fifths think equities will gallop on upwards over the next year. Complacency is rife. "It became very clear – and many investors were quite explicit about this – that markets are lulled by the lure of liquidity resulting from negative real interest rates and global QE," said Mr Fels.
5分の4は、株価は来年も上昇すると考えています。
自己満足満々です。
「非常にハッキリした。多くの投資家はこれについてかなりあからさまだ。マーケットはネガティブ実質金利と世界的QEによる流動性の誘惑にデレデレになっている」とフェルス氏は言いました。
This then is the bull market of May 2013. Remember the infamous words of Citi's Chuck Prince in July 2007. "When the music stops, in terms of liquidity, things will be complicated. But as long as the music is playing, you've got to get up and dance. We're still dancing."
で、これが2013年5月のブル相場です。
2007年7月にシティのチャック・プリンスが出した、悪名高い発言を覚えておきましょう。
「音楽が止まったら、流動性について言えば、事態は複雑になる。だが、音楽が流れ続ける限り、立ち上がって踊らなければいけない。我々は今も踊っている」
I defy anybody to explain what liquidity is. At the end of the day, it is really just risk appetite. It can vanish in a second. (If people mean the quantity of money, that is a different story, and not uber-bullish right now).
僕は流動性が何なのか誰にも説明してもらいたくありません。
結局、それは本当はリスク嗜好なんですから。
一瞬で消え失せることもあるんです。
(マネーの量のことを言ってるなら、それは別の話ですし、今のところ超ブルなんかじゃありません。)
Stephen Lewis from Monument Securities says markets seem to think they are in a "no-lose" play: if the economy gains traction, stocks will rise: if it doesn't, central banks will pump in more money.
モニュメント・セキュリティーズのスティーヴン・ルイス氏は、マーケットは「負けなし」勝負をしていると思ってるようだ、と言います。
経済が勢い付けば株は上がる。
経済が勢い付かなければ中銀がマネーを増やしてくれる。
Mr Lewis said they overlook a nasty possibility that the Fed will start to wind down QE before the US economy has fully recovered. He cites the minutes of Fed's 19-20 March meeting showing growing worries about a new asset bubble, a worry shared by the BIS and the IMF: "A number of participants remained concerned about the potential for financial stability risks to build".
米国経済が完全復活する前にFRBがQEを片付け始める、という凶悪な可能性を彼らは見落としている、とルイス氏は言います。
彼は3月19-20日に開かれたFOMC会合の議事録を採り上げました。
議事録からは、新たな資産バブルへの懸念が深まっていることがわかりますし、これはBISとIMFも同意見です。
「多くの参加者は金融安定リスクが高まる可能性を引き続き懸念している」
The concerns were spelt out in a landmark paper for US Monetary Policy Forum published by the Fed in February: "Crunch Time: Fiscal Crises and the Role of Monetary Policy".
この懸念は、FRBが2月に米国マネタリー・ポリシー・フォーラムのために出した画期的論文『Crunch Time: Fiscal Crises and the Role of Monetary Policy』にはっきりと記されました。
The paper was by co-written by former Fed Governor Frederic Mishkin, Ben Bernanke's alter ego. It warned that the Fed could struggle to extract itself from QE from 2014 onwards. The longer it goes on, the more dangerous it becomes.
同論文はベン・バーナンキFRB議長の分身、フレドリック・ミシュキン元FRB理事が共著したものです。
FRBは2014年からQE脱却に悪戦苦闘するかもしれない、と警鐘を鳴らしました。
QEが長引けば長引くほど、もっともっと危険になるのだぞ、と。
It argued that rising long rates could lead to a bond market rout, inflicting big losses on its $3 trillion portfolio. This could "wipe out" its capital base several times over.
長期金利の上昇は債券相場の大混乱を引き起こして、FRBの3兆ドルものポートフォリオに大赤字を出させるだろう、と論じました。
これはFRBの資本ベースを数回「吹き飛ばせる」そうです。
Mishkin said the Fed is badly exposed because it has stretched the average maturity of its bond holdings to 11 years, and the longer the date, the bigger the losses when yields rise. Trouble could compound at an alarming pace by the middle of the decade, with yields spiking up to double-digit rates by the late 2020s.
ミシュキン教授曰く、FRBは酷くエクスポーズされていると。
何故なら、FRBは保有する債券の平均残存期間を11年まで延ばしちゃったと。
それでもって、延びれば延びるほど、金利が上昇すれば損は大きくなるぞと。
問題は2015年頃までに強烈なペースで膨れ上がるかもしれないぞと。
2020年代後半までに金利が二桁台に急上昇しちゃうかもしれないぞと。
By then Fed will be forced to finance federal spending directly to avert the greater evil of default. By then, the US really will be facing the sort of hyperinflationary denouement long-feared by QE sceptics.
その頃までには、FRBはデフォルトというより大きな悪を回避するために、連邦政府の支出を直接ファイナンスしなくちゃいけなくなってるでしょ。
その頃までには、米国は本当に、QE懐疑派がずーっと前から心配してるハイパーインフレという結末みたいなもんに直面することでしょ。
Just to be clear, this the Mishkin concern, not mine. I think exit risks are greatly exaggerated. The Fed extracted itself from Great Depression policies without any losses, and such losses are in any case irrelevant. They are an electronic accounting fiction. There may be many good reasons for opposing QE, but fretting about the Fed's capital base is not one of them.
念のために書きますが、これはミシュキンの心配であって、僕の心配じゃありませんから。
この出口リスクとやらは、無茶苦茶大袈裟だと思います。
FRBは損をせずに大恐慌対策から出口しましたし、いずれにせよ、そんな損なんてどうでも良いわけですよ。
あれは電子会計的なフィクションなんです。
QEハンターイとやるご尤もな理由は幾らでもあるかもしれませんが、FRBの資本ベースがどうだこうだってのは理由になりませんよ。
But this is the view of several Fed governors and regional presidents, so it matters. And it may have got under Ben Bernanke's skin as well.
でもまあ、FRB理事やら各地の連銀総裁やらの中には、このご意見を抱えている人も複数いるので、確かに問題なんですね。
それに、バーナンキFRB議長にまで感染しちゃったかもしれませんし。
As for the Morgan Stanly investors who think that central bank policy is "expansionary", they are wrong. Market monetarist Scott Sumner reminds us in this self-described rant that global money is in fact tight, especially in Europe.
で、中銀の政策は「拡大的」だと考えているモルガン・スタンレーの投資家はどうかと言えば、間違っています。
マーケット・マネタリストのスコット・サムナー氏は、世界のマネーは実際にはタイトなのだ、特にヨーロッパがキツキツ、という自称「暴言」の中で僕らにリマインドしています。
There seems to be a near universal assumption – shared by most governors at the ECB – that low rates necessarily mean loose money. This is antediluvian. Japan had near zero rates for sixteen years, yet descended ever deeper into deflation and an as asset slump. Zero means nothing.
低金利は絶対マネージャブジャブを引き起こす!という仮説はほぼ全会一致のようです(ECB理事の殆ども同意)。
時代遅れですって。
日本は16年間ゼロ金利でしたが、どんどんデフレと資産不況の深みにはまっていったんですよ。
ゼロ金利がなんだっつーの。
Milton Friedman taught us long ago that zero rates can be extremely tight, which is why central banks then have to step in to expand the broad money supply (M2 in his day, now M3). And what do you know? Eurozone M3 has contracted over the last three months (M-on-M), and US M3 is no longer growing briskly.
ミルトン・フリードマンは随分昔に、僕らにこう教えてくれました。
ゼロ金利は酷くタイトたり得るのであって、だからこそ、中銀はブロード・マネー・サプライを拡大に乗り出さなければならないんだよ、と(彼の時代はM2でしたが、今はM3ね)。
で?
ユーロ圏のM3は過去3ヶ月間も(前月比で)縮小しましたよ。
米国のM3だってもう順調に伸びてませんから。
We will find out tomorrow from Ben Bernanke's testimony to Congress whether he aims to "taper" QE sooner or later. The markets are all on one side betting that it will be later. They are probably right, but they had better be.
明日のベン・バーナンキFRB議長の証言でわかりますね。
議長がさっさとQE「撤収」を狙っているのか、もっと後にしようと思ってるのか。
マーケットはそろって「後」だと思ってます。
正しいかもしれませんが…正しいと良いんですけどねえ…。
As Warren Buffett said, it will be the shot heard around the world the day Bernanke hints at anything else. By the way, Mr Buffett is not dancing right now. Berkshire Hathaway is sitting on a record $49bn in cash. Speaks for itself.
ウォーレン・バフェット氏が言っていたように、バーナンキ議長がそれ以外のことを言ったら、それは世界中に響き渡る銃声となるでしょうよ。
あ、ところで、バフェット氏は今は踊ってませんですよ。
バークシャー・ハサウェイは490億ドルなんて史上最高のキャッシュを握ってじっとしてます。
それ自体が物語ってますね。