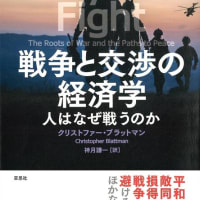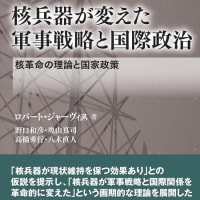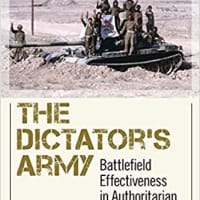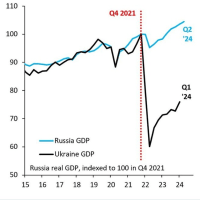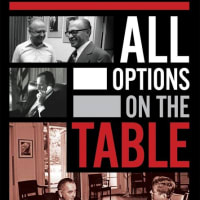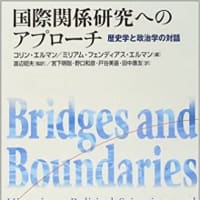国際政治学の名著 Man, the State, and War の邦訳出版を目前にして、著者のケネス・ウォルツがこの世を去りました。享年88歳、学界は構造的リアリズムの国際政治学を構築した偉大な学者を失いました。国際政治学の一つの時代が幕を閉じていくのを感じます。
ウォルツの主著 Theory of International Politics (邦訳『国際政治の理論』)は、私に最も大きな学問的影響を与えた学術書の1つです。私はこの原書を繰り返して何度読んだことでしょう(最近、日本語訳がでましたので、日本の学生はウォルツの理論に接しやすくなりました)。本書は、現代の古典にふさわしく、読めば読むほど、新しい発見がありました。

『国際政治の理論』(原書)は、学術書としてはページ数が少ないにもかかわらず、これほど無駄がなく内容の濃い洗練された国際政治の専門書は、そうありません。要するに、シンプルであるにもかかわらず奥が深いのです。同時に、論争的な本でもありました。ウォルツの「国際政治の理論」をいかに覆すかが、80年代以後の国際政治学の1つのメインテーマだったと言っても、過言ではないでしょう。
ウォルツは卓越した研究者であったと同時に、厳しくも優れた教育者であったようです。詳しくは、彼の弟子のスティーヴン・ウォルト(ハーバード大学)の追悼ブログをご覧ください。なお、リチャード・べッツ(コロンビア大学)やバリー・ポーゼン(MIT)など、そうそうたる国際政治学が、フォーリン・ポリシー誌のウェブサイトに追悼文を寄せています。
残念ながら、ウォルツが日本の国際政治学界に与えた影響は、英米の国際政治学界とは比べるべくもなく、小さなものでした。その1つの理由は、ウォルツの理論があまりにも抽象的で現実離れしているとみなされたことにあるようです。確かに、そうかもしれません。他方、科学の方法論上、より少ない変数でより多くの事象を説明できるほど、理論の価値(説明力)が高いとすれば、構造的リアリズムの諸理論は、疑いなく優れた理論です。
その意味で、ケン・ブース(アベリストウェルズ大学)が、ウォルツは国際関係論のダーウィンだったと評してるのは、的を射た指摘でしょう。なにしろ、ダーウィンは、自然選択の単純なロジックで想像を絶するほどの複雑な生物体系を説明してしまうのですから。ウォルツの構造的リアリズムも、アナーキーやパワー配分から、複雑な国際政治の帰結を説明してしまいます。両者の理論は、方法論上、似ていますね。
ウォルツの理論は、わが国において、もっと注目され、研究され、応用され、挑戦されてよかったと思います。
ウォルツの主著 Theory of International Politics (邦訳『国際政治の理論』)は、私に最も大きな学問的影響を与えた学術書の1つです。私はこの原書を繰り返して何度読んだことでしょう(最近、日本語訳がでましたので、日本の学生はウォルツの理論に接しやすくなりました)。本書は、現代の古典にふさわしく、読めば読むほど、新しい発見がありました。

『国際政治の理論』(原書)は、学術書としてはページ数が少ないにもかかわらず、これほど無駄がなく内容の濃い洗練された国際政治の専門書は、そうありません。要するに、シンプルであるにもかかわらず奥が深いのです。同時に、論争的な本でもありました。ウォルツの「国際政治の理論」をいかに覆すかが、80年代以後の国際政治学の1つのメインテーマだったと言っても、過言ではないでしょう。
ウォルツは卓越した研究者であったと同時に、厳しくも優れた教育者であったようです。詳しくは、彼の弟子のスティーヴン・ウォルト(ハーバード大学)の追悼ブログをご覧ください。なお、リチャード・べッツ(コロンビア大学)やバリー・ポーゼン(MIT)など、そうそうたる国際政治学が、フォーリン・ポリシー誌のウェブサイトに追悼文を寄せています。
残念ながら、ウォルツが日本の国際政治学界に与えた影響は、英米の国際政治学界とは比べるべくもなく、小さなものでした。その1つの理由は、ウォルツの理論があまりにも抽象的で現実離れしているとみなされたことにあるようです。確かに、そうかもしれません。他方、科学の方法論上、より少ない変数でより多くの事象を説明できるほど、理論の価値(説明力)が高いとすれば、構造的リアリズムの諸理論は、疑いなく優れた理論です。
その意味で、ケン・ブース(アベリストウェルズ大学)が、ウォルツは国際関係論のダーウィンだったと評してるのは、的を射た指摘でしょう。なにしろ、ダーウィンは、自然選択の単純なロジックで想像を絶するほどの複雑な生物体系を説明してしまうのですから。ウォルツの構造的リアリズムも、アナーキーやパワー配分から、複雑な国際政治の帰結を説明してしまいます。両者の理論は、方法論上、似ていますね。
ウォルツの理論は、わが国において、もっと注目され、研究され、応用され、挑戦されてよかったと思います。