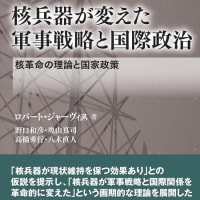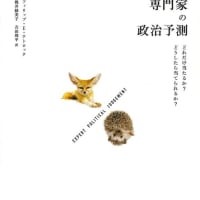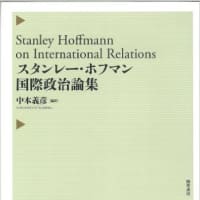攻撃的リアリズムは、主要な国際関係理論の1つです。この理論は、大国間の政治を説明する、いわゆる「大理論(ground theory) 」です。攻撃的リアリズムの中心的命題は、アナーキー(無政府状態)が大国にパワーを最大化することを強いるというものです。大国は他国の意図を完全に知ることはできません。大国は他国から安全を脅かされる「恐怖」にさいなまれます。そこで、大国はあらゆる機会を利用して、ライバルとなりそうな国家を排除しながら、地域的覇権国(regional hegemon)になることを目指します。なぜなら、覇権的地位を確立することこそが、大国に望みうる最大の安全保障を提供するからです。こうした簡潔で論理的な攻撃的リアリズムの理論を体系的に構築したのが、ジョン・ミアシャイマー氏(シカゴ大学)です。かれが著した『大国政治の悲劇』(奥山真司訳、五月書房、2007年〔原著2001年〕)は、攻撃的リアリズムの標準的なテキストとなっています。
攻撃的リアリズムが理論として提出されてから、20年以上の時間が過ぎました。その間、攻撃的リアリズムは、さまざまな角度から研究されてきました。あらゆる主要理論がそうであるように、攻撃的リアリズムは多方面からの批判にさらされてきました。それらをあえて大別すれば、1つは、攻撃的リアリズムの論理構成に欠陥があるとするものです。もう1つは、攻撃的リアリズムの諸仮説を経験的データに照らしながら、その問題点を指摘するものです。
ミアシャイマー氏が『大国政治の悲劇』を上梓した直後に、『国際安全保障(International Security)』誌は、同書に関するレヴュー・エッセイを掲載しました。その著者は、国際関係研究の重鎮であるグレン・スナイダー氏です。かれは「ミアシャイマーの世界」("Mearsheimer's World—Offensive Realism and the Struggle for Security," International Security, Vol. 27, No. 1, Summer 2002)と題する書評論文において、こう述べています。「この本(『大国政治の悲劇』)の主要な弱点は、国家行動の動機としてのパワーと安全保障の最大化を過大に強調していることである…同書における問題は、そのロジックにある。(攻撃的リアリズムの)ロジックは一貫しており明白な矛盾もないが、時として極端に走りすぎている」(同書評論文、151、171ページ)。
はたして、攻撃的リアリズムのパワー最大化の仮説は、ロジックとして「極論」なのでしょうか。これは攻撃的リアリズム理論の「公理」のようなものなので、その妥当性を論理の観点から評価するのが難しい反面、ミアシャイマー氏自身が「非現実的、もしくは間違った仮定によって成り立つ理論というのは、結局私たちの世界がどのように動くのかをうまく説明できないと考える」(『大国政治の悲劇』53ページ)ので、その「現実性」は吟味しなければなりません。
この点について、興味深い研究論文が数年前に発表されました。その著者は、このブログでも紹介したドミニク・ジョンソン氏(オックスフォード大学)とブラッドリー・セイヤー氏です。かれらは共著論文「攻撃的リアリズムの進化」("The Evolution of Offensive Realism: Survival under Anarchy from the Pleistocene to the Present," Politics and Life Science, Vol. 35, No. 1, Spring 2016)において、攻撃的リアリズムの中心的仮定は、人間の行動論的な進化に関する科学的知識によって裏づけることができると主張しています。攻撃的リアリズムを構成する中核的概念は、「自助(self-help)」、「パワーの最大化(power maximization)」(=覇権の追求)、「外集団への恐怖(outgroup fear)」です。これらは生命科学や進化生物学の用語におきかえると、それぞれ「エゴイズム」、「支配」、「内集団/外集団バイアス」ということになります。かれらによれば、これらの特性は、何百万年もの進化の過程を経て、人間が「気質(disposition)」として身に着けたもです。したがって、攻撃的リアリズムの公理は、非現実的なものではなく、自然科学である生命科学や生物学の堅実な研究成果に裏打ちされるのです。
スナイダー氏はミアシャイマー氏の攻撃的リアリズムが極端な悲観論であると批判しましたが、ジョンソン氏とセイヤー氏は、人間を含む生物の世界が、そもそも、そういうものであると以下のように指摘しています。
「パワーの不均衡は時代に関係なく低コストで侵略する体系的な機会を提供するので、われわれは、人間集団が目の前に現れた機会を利用して他集団に侵略的な行動をとる気質を発展させたと考えるべきである。なぜならば、機会主義的な侵略は平均すると割が合う戦略だからだ…これらの発見は、人間が自然状態において、お互いに協調的かつ平和的に過ごしてきたという、通俗的な観念を信奉する人たちにとって、驚くべきことかもしれない。しかし、証拠は逆であることを示している。侵略は文化的な偶然性によるものではなく、資源を確保して守るための進化的適応によるものなのである」(同論文、7ページ)。
さらにジョンソン氏とセイヤー氏は、自助やパワーの極大化、外集団への恐怖の起源をアナーキーに求める必要はないと主張しています。そうではなく、これらは「人間本性」に根差しているのです。われわれが進化した結果、人間は攻撃的リアリストのよう行動するになったのです。もしこの主張が正しいとすれば、国家や人間の「攻撃的」行動はアナーキーという国際構造から導かれるのではなく、人間本性に由来することになります。このことは攻撃的リアリズムの理論の適用範囲を大きく広げます。同理論は、大国間の政治だけではなく、民族紛争や内戦など、人間がかかわる全ての事象に適用できてしまうのです。そうなると理論の簡潔性(parsimony)、すなわち、少ない変数で多くの事象を説明する科学的方法論の評価基準からすれば、攻撃的リアリズムは非常に優れた理論ということになるでしょう。
それでは、攻撃的リアリズムの理論は、どのくらい経験的検証に耐えられるものでしょうか。「大標本(large-N)」の研究手法を使ってミアシャイマー氏の攻撃的リアリズムの理論を批判したのが、ブランドン・ヴァレリアーノ氏(海兵隊大学)です。かれは論文「攻撃的リアリズムの悲劇」("The Tragedy of Offensive Realism: Testing Aggressive Power Politics Models," International Interactions, Vol. 35, No. 2, 2009)において、次のように論じています。1816年から1992年の大国行動のデータによれば、大国が(攻撃的政策をとることにより)紛争を引き起こしやすいという仮説は支持されるものの、大国が戦争での勝利を追求する仮説(大国はパワー極大化の合理的手段として戦争に訴えるという仮説)やバンドワゴン行動よりバランシング行動を選好するという仮説、さらには二極構造が最も安定的であり、不安定な多極構造で最も戦争が起こりやすいとする仮説は支持されないと結論づけています。
攻撃的リアリズムの理論は、ミアシャイマー氏自身によって、定性的な事例研究により検証されています。他方、攻撃的リアリズムに関する定量的な大標本による検証は、別の科学的方法による同理論の妥当性の確認作業として歓迎すべきことです。確かに、ヴァレリアーノ氏の上記の研究結果は注目すべきものでありますが、残念ながら、こうした分析結果は、攻撃的リアリズムの大国間政治への正確な説明能力を疑う強力な根拠になりにくいと思います。
ヴァレリアーノ氏は、攻撃的リアリズムの反証として、大国の勝利で終わる紛争の割合の低さを挙げています。かれは「大国による勝利は、大国の紛争の必然的な性質となっていない。戦勝する確率が低くても、それは国家にとって納得のいくものであるならば、(攻撃的リアリズムの)理論は経験的にそれほど価値がないといえる」(同論文、195ページ)と指摘しています。しかしながら、戦争を始めた国家が勝利を収める割合は、別の研究では高いことが報告されています。紛争研究の大家であるブルース・ブエノ・デ・メスキータ氏(ニューヨーク大学)は、戦争研究で頻繁に引用される高著『戦争の罠(The War Trap)』(イェール大学出版局、1981年)において、ウィーン会議以降の58件の国家間戦争では、戦闘を開始した国が42回の勝利を収めていると述べています(同書、21-22ページ)。このデータは、戦争は大国を含む国家が「合理的な計算』にもとづいて開始することを示唆しています。つまり、開戦国の戦勝確率は、経験的証拠によって異なる値を示しているのです。エヴァン・ルアード氏(オックスフォード大学)は、1400年以後の戦争を社会学の視点から総合的に研究した著作『国際社会における戦争―国際社会学の研究―(War in International Society)』(イエール大学出版局、1986年)において、「開戦国が戦争に負けた、いかなる場合でも、そこには誤算があった。(開戦国は)勝利するだろうと考えたから戦争を始めたのだ」と断言しています(同書、232ページ)。これらの研究は、戦争が大国の「パワー獲得の1つの手段」であることを支持するものです。少なくとも、戦争の勝利確率のデータだけでは、攻撃的リアリズムの「戦争行動」仮説は棄却できないでしょう。
バンドワゴン行動とバランシング行動の比較データは、攻撃的リアリズムを疑う根拠としては的外れです。なぜならば、攻撃的リアリズムは、大国がバランシング行動のみならずバックパッシング(責任転嫁)行動をとることも予測しているからです。ミアシャイマー氏によれば、大国のバックパッシング行動は「多極システム」においてとられる傾向があります。こうした国際構造において、大国はライバルとなりそうな大国のパワーの拡大をその隣国に阻止させようとするインセンティヴをもつのです。したがって、攻撃的リアリズムは、少なくとも大国のバックパッシング行動に関するデータによって検証されなければなりません。
国際システムの構造と安定性や戦争の相関関係については、これまで実にたくさんの研究がさまざまな分析をしていますが、未だに統一された見解には至っていません。グレグ・キャッシュマン氏(ソールズベリー大学)は、戦争原因研究を網羅的かつ総合的にまとめた大著『何が戦争を引き起こすのか(What Causes War? An Introduction of Theories of International Conflict)』(ローマン&リトルフィールド社、2014年)において、この論点に関する既存の研究を総合的に幅広く調べた結論として、こうまとめています。「パワー配分と戦争の関係は、完全に理解されたものとはほど遠い。実際、システムの極性を使って戦争の開始を説明する試みは、理論的に行き詰っているといえる」(同書、405ページ)。既存の研究においては、二極安定論を支持するものもあれば、そうでないものもあり、また、多極不安定論を支持するものもあれば、そうでないものもあります。
二極安定論に対する最も強力な批判は、おそらく反実仮想を用いた反論でしょう。ラーズ=エリック・セダーマン氏(チューリッヒ工科大学)は、二極システムが最も戦争を招きにくいかどうかは、第二次世界大戦後の世界に関する反実的シナリオを提示して検証しないと分からないと主張します。もしイギリスが大国としてのパワーを維持できたとして、戦後の国際システムが米英ソの三極からなる多極システムになったとしても、米英の「特殊な関係」が保たれるだろから、ソ連の現状打破行動はもっと確実に抑止できたことになるため、大戦争は起こらなかったと推論できます。他方、ナチス・ドイツが極として存続していたら、冷戦は熱戦になっていただろうことは想像に難くありません。要するに、システムの安定性は極を構成する大国が権威主義的で国家主義的かどうかで左右されるのです(Lars-Erik Cederman, "Rerunning History: Counterfactual Simulation in World Politics, in Philip E. Tetlock and Aaron Belkin, eds., Counterfactual Though Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives, Princeton University Press, 1996, p. 251)。国際構造と戦争の関係について、他の条件が等しいとの前提にもとづき(ceteris paribus)、極性だけから安定性を演繹するのは無理があるのかもしれません。
攻撃的リアリズムは、大理論として大国間の「政治」を説明するものです。世界における大国の行動を大局的に説明したり、予測したりする知的道具として、われわれは攻撃的リアリズムから推論のヒントを得ることができます。もちろん、攻撃的リアリズムは万能薬のようなものではありません。それでは、攻撃的リアリズムの理論は、大国間政治の診断ツールとして、あるいは政策立案の処方箋として、どの程度、役に立つものなのでしょうか。わたしは、ジョンソン氏とセイヤー氏の主張、すなわち、「攻撃的リアリズムは、国際政治の歴史を横断して、主要な事象を説明する最も説得力をもつ今ある理論の1つである」(「攻撃的リアリズムの進化」19ページ)との結論に同意します。なぜならば、かれらの議論は科学的に強力であるからです。他方、ヴァレリアーノ氏の攻撃的リアリズムへの批判は再反論の余地を広く残しているので、相対的に弱いのではないでしょうか。理論の棄却は科学的に難しいことを考慮しても、攻撃的リアリズムは、やはりパワフルなものであるように思います。
攻撃的リアリズムが理論として提出されてから、20年以上の時間が過ぎました。その間、攻撃的リアリズムは、さまざまな角度から研究されてきました。あらゆる主要理論がそうであるように、攻撃的リアリズムは多方面からの批判にさらされてきました。それらをあえて大別すれば、1つは、攻撃的リアリズムの論理構成に欠陥があるとするものです。もう1つは、攻撃的リアリズムの諸仮説を経験的データに照らしながら、その問題点を指摘するものです。
ミアシャイマー氏が『大国政治の悲劇』を上梓した直後に、『国際安全保障(International Security)』誌は、同書に関するレヴュー・エッセイを掲載しました。その著者は、国際関係研究の重鎮であるグレン・スナイダー氏です。かれは「ミアシャイマーの世界」("Mearsheimer's World—Offensive Realism and the Struggle for Security," International Security, Vol. 27, No. 1, Summer 2002)と題する書評論文において、こう述べています。「この本(『大国政治の悲劇』)の主要な弱点は、国家行動の動機としてのパワーと安全保障の最大化を過大に強調していることである…同書における問題は、そのロジックにある。(攻撃的リアリズムの)ロジックは一貫しており明白な矛盾もないが、時として極端に走りすぎている」(同書評論文、151、171ページ)。
はたして、攻撃的リアリズムのパワー最大化の仮説は、ロジックとして「極論」なのでしょうか。これは攻撃的リアリズム理論の「公理」のようなものなので、その妥当性を論理の観点から評価するのが難しい反面、ミアシャイマー氏自身が「非現実的、もしくは間違った仮定によって成り立つ理論というのは、結局私たちの世界がどのように動くのかをうまく説明できないと考える」(『大国政治の悲劇』53ページ)ので、その「現実性」は吟味しなければなりません。
この点について、興味深い研究論文が数年前に発表されました。その著者は、このブログでも紹介したドミニク・ジョンソン氏(オックスフォード大学)とブラッドリー・セイヤー氏です。かれらは共著論文「攻撃的リアリズムの進化」("The Evolution of Offensive Realism: Survival under Anarchy from the Pleistocene to the Present," Politics and Life Science, Vol. 35, No. 1, Spring 2016)において、攻撃的リアリズムの中心的仮定は、人間の行動論的な進化に関する科学的知識によって裏づけることができると主張しています。攻撃的リアリズムを構成する中核的概念は、「自助(self-help)」、「パワーの最大化(power maximization)」(=覇権の追求)、「外集団への恐怖(outgroup fear)」です。これらは生命科学や進化生物学の用語におきかえると、それぞれ「エゴイズム」、「支配」、「内集団/外集団バイアス」ということになります。かれらによれば、これらの特性は、何百万年もの進化の過程を経て、人間が「気質(disposition)」として身に着けたもです。したがって、攻撃的リアリズムの公理は、非現実的なものではなく、自然科学である生命科学や生物学の堅実な研究成果に裏打ちされるのです。
スナイダー氏はミアシャイマー氏の攻撃的リアリズムが極端な悲観論であると批判しましたが、ジョンソン氏とセイヤー氏は、人間を含む生物の世界が、そもそも、そういうものであると以下のように指摘しています。
「パワーの不均衡は時代に関係なく低コストで侵略する体系的な機会を提供するので、われわれは、人間集団が目の前に現れた機会を利用して他集団に侵略的な行動をとる気質を発展させたと考えるべきである。なぜならば、機会主義的な侵略は平均すると割が合う戦略だからだ…これらの発見は、人間が自然状態において、お互いに協調的かつ平和的に過ごしてきたという、通俗的な観念を信奉する人たちにとって、驚くべきことかもしれない。しかし、証拠は逆であることを示している。侵略は文化的な偶然性によるものではなく、資源を確保して守るための進化的適応によるものなのである」(同論文、7ページ)。
さらにジョンソン氏とセイヤー氏は、自助やパワーの極大化、外集団への恐怖の起源をアナーキーに求める必要はないと主張しています。そうではなく、これらは「人間本性」に根差しているのです。われわれが進化した結果、人間は攻撃的リアリストのよう行動するになったのです。もしこの主張が正しいとすれば、国家や人間の「攻撃的」行動はアナーキーという国際構造から導かれるのではなく、人間本性に由来することになります。このことは攻撃的リアリズムの理論の適用範囲を大きく広げます。同理論は、大国間の政治だけではなく、民族紛争や内戦など、人間がかかわる全ての事象に適用できてしまうのです。そうなると理論の簡潔性(parsimony)、すなわち、少ない変数で多くの事象を説明する科学的方法論の評価基準からすれば、攻撃的リアリズムは非常に優れた理論ということになるでしょう。
それでは、攻撃的リアリズムの理論は、どのくらい経験的検証に耐えられるものでしょうか。「大標本(large-N)」の研究手法を使ってミアシャイマー氏の攻撃的リアリズムの理論を批判したのが、ブランドン・ヴァレリアーノ氏(海兵隊大学)です。かれは論文「攻撃的リアリズムの悲劇」("The Tragedy of Offensive Realism: Testing Aggressive Power Politics Models," International Interactions, Vol. 35, No. 2, 2009)において、次のように論じています。1816年から1992年の大国行動のデータによれば、大国が(攻撃的政策をとることにより)紛争を引き起こしやすいという仮説は支持されるものの、大国が戦争での勝利を追求する仮説(大国はパワー極大化の合理的手段として戦争に訴えるという仮説)やバンドワゴン行動よりバランシング行動を選好するという仮説、さらには二極構造が最も安定的であり、不安定な多極構造で最も戦争が起こりやすいとする仮説は支持されないと結論づけています。
攻撃的リアリズムの理論は、ミアシャイマー氏自身によって、定性的な事例研究により検証されています。他方、攻撃的リアリズムに関する定量的な大標本による検証は、別の科学的方法による同理論の妥当性の確認作業として歓迎すべきことです。確かに、ヴァレリアーノ氏の上記の研究結果は注目すべきものでありますが、残念ながら、こうした分析結果は、攻撃的リアリズムの大国間政治への正確な説明能力を疑う強力な根拠になりにくいと思います。
ヴァレリアーノ氏は、攻撃的リアリズムの反証として、大国の勝利で終わる紛争の割合の低さを挙げています。かれは「大国による勝利は、大国の紛争の必然的な性質となっていない。戦勝する確率が低くても、それは国家にとって納得のいくものであるならば、(攻撃的リアリズムの)理論は経験的にそれほど価値がないといえる」(同論文、195ページ)と指摘しています。しかしながら、戦争を始めた国家が勝利を収める割合は、別の研究では高いことが報告されています。紛争研究の大家であるブルース・ブエノ・デ・メスキータ氏(ニューヨーク大学)は、戦争研究で頻繁に引用される高著『戦争の罠(The War Trap)』(イェール大学出版局、1981年)において、ウィーン会議以降の58件の国家間戦争では、戦闘を開始した国が42回の勝利を収めていると述べています(同書、21-22ページ)。このデータは、戦争は大国を含む国家が「合理的な計算』にもとづいて開始することを示唆しています。つまり、開戦国の戦勝確率は、経験的証拠によって異なる値を示しているのです。エヴァン・ルアード氏(オックスフォード大学)は、1400年以後の戦争を社会学の視点から総合的に研究した著作『国際社会における戦争―国際社会学の研究―(War in International Society)』(イエール大学出版局、1986年)において、「開戦国が戦争に負けた、いかなる場合でも、そこには誤算があった。(開戦国は)勝利するだろうと考えたから戦争を始めたのだ」と断言しています(同書、232ページ)。これらの研究は、戦争が大国の「パワー獲得の1つの手段」であることを支持するものです。少なくとも、戦争の勝利確率のデータだけでは、攻撃的リアリズムの「戦争行動」仮説は棄却できないでしょう。
バンドワゴン行動とバランシング行動の比較データは、攻撃的リアリズムを疑う根拠としては的外れです。なぜならば、攻撃的リアリズムは、大国がバランシング行動のみならずバックパッシング(責任転嫁)行動をとることも予測しているからです。ミアシャイマー氏によれば、大国のバックパッシング行動は「多極システム」においてとられる傾向があります。こうした国際構造において、大国はライバルとなりそうな大国のパワーの拡大をその隣国に阻止させようとするインセンティヴをもつのです。したがって、攻撃的リアリズムは、少なくとも大国のバックパッシング行動に関するデータによって検証されなければなりません。
国際システムの構造と安定性や戦争の相関関係については、これまで実にたくさんの研究がさまざまな分析をしていますが、未だに統一された見解には至っていません。グレグ・キャッシュマン氏(ソールズベリー大学)は、戦争原因研究を網羅的かつ総合的にまとめた大著『何が戦争を引き起こすのか(What Causes War? An Introduction of Theories of International Conflict)』(ローマン&リトルフィールド社、2014年)において、この論点に関する既存の研究を総合的に幅広く調べた結論として、こうまとめています。「パワー配分と戦争の関係は、完全に理解されたものとはほど遠い。実際、システムの極性を使って戦争の開始を説明する試みは、理論的に行き詰っているといえる」(同書、405ページ)。既存の研究においては、二極安定論を支持するものもあれば、そうでないものもあり、また、多極不安定論を支持するものもあれば、そうでないものもあります。
二極安定論に対する最も強力な批判は、おそらく反実仮想を用いた反論でしょう。ラーズ=エリック・セダーマン氏(チューリッヒ工科大学)は、二極システムが最も戦争を招きにくいかどうかは、第二次世界大戦後の世界に関する反実的シナリオを提示して検証しないと分からないと主張します。もしイギリスが大国としてのパワーを維持できたとして、戦後の国際システムが米英ソの三極からなる多極システムになったとしても、米英の「特殊な関係」が保たれるだろから、ソ連の現状打破行動はもっと確実に抑止できたことになるため、大戦争は起こらなかったと推論できます。他方、ナチス・ドイツが極として存続していたら、冷戦は熱戦になっていただろうことは想像に難くありません。要するに、システムの安定性は極を構成する大国が権威主義的で国家主義的かどうかで左右されるのです(Lars-Erik Cederman, "Rerunning History: Counterfactual Simulation in World Politics, in Philip E. Tetlock and Aaron Belkin, eds., Counterfactual Though Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives, Princeton University Press, 1996, p. 251)。国際構造と戦争の関係について、他の条件が等しいとの前提にもとづき(ceteris paribus)、極性だけから安定性を演繹するのは無理があるのかもしれません。
攻撃的リアリズムは、大理論として大国間の「政治」を説明するものです。世界における大国の行動を大局的に説明したり、予測したりする知的道具として、われわれは攻撃的リアリズムから推論のヒントを得ることができます。もちろん、攻撃的リアリズムは万能薬のようなものではありません。それでは、攻撃的リアリズムの理論は、大国間政治の診断ツールとして、あるいは政策立案の処方箋として、どの程度、役に立つものなのでしょうか。わたしは、ジョンソン氏とセイヤー氏の主張、すなわち、「攻撃的リアリズムは、国際政治の歴史を横断して、主要な事象を説明する最も説得力をもつ今ある理論の1つである」(「攻撃的リアリズムの進化」19ページ)との結論に同意します。なぜならば、かれらの議論は科学的に強力であるからです。他方、ヴァレリアーノ氏の攻撃的リアリズムへの批判は再反論の余地を広く残しているので、相対的に弱いのではないでしょうか。理論の棄却は科学的に難しいことを考慮しても、攻撃的リアリズムは、やはりパワフルなものであるように思います。