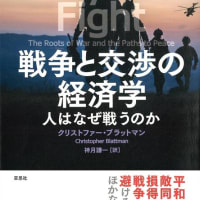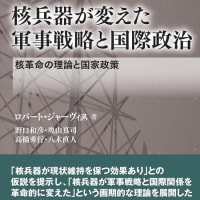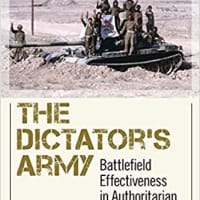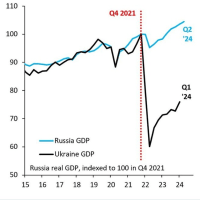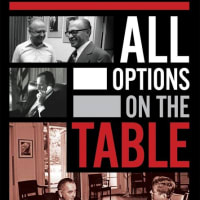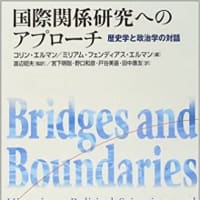ある調査によると、小学生男子がなりたい職業の第1位は、「学者・博士」のようです。確かに、メディアには、学者を肩書にする人物がしばしば登場して、さまざまな社会問題にコメントをよせたり、意見を発したりしています。優れた研究成果を残した学者は、社会から高い尊敬を集めます。こうしたことから、小学生が「学者・博士」に憧れても、不思議ではありません。
私は小学生の「夢」を壊したいと思いませんが、「学者・博士」の実態が、どれだけ世間で理解されているのか、とても気になっています。おそらく、ほとんど理解されてないのでしょう。
第1に、博士号を取得しても、大学で学問を生業にできる研究者は、ごく一部です。ある教育社会学者によれば、大学教員のポストは、今や博士14人に1人です。とても狭き門をくぐらないと、大学教授にはなれません。一生涯「フリーター」の博士は珍しくないといったら、多くの人達は驚くでしょう。しかし、これが実態なのです。
第2に、大学教員の最高位である教授は、世の中の多くの人がイメージするほど、給与が高くありません。大学教授(60歳)の平均年収は、大手企業の課長クラスと指摘されています。しかも、大学教員の就職は、一般企業や公務員より、はるかに遅い。博士号を取得するまでに時間がかかり、さらに、専任教員や研究員のポストを得るための「就活期間」も決して短くありません。30歳代半ばから40歳前後といったところでしょう。20歳代で正職がみつかる学者は、そうとうな幸運に恵まれいます。したがって、生涯賃金は、大手企業のビジネスパーソンに比べると、さらに下がります。さらに、多くの「学者」は、大学院時代に受けていた奨学金を返済しなければなりません。
運良く大学教員のポストを得たとしても、その仕事の実際はどうでしょうか。興味のある人は、櫻田大造『大学教員採用・人事のカラクリ』中公新書、2011年を読んで下さい。
キャリア教育は、今では子どもの時からから行われています。果たして、「職業としての学問」は、どのくらい小学生に教えられているのでしょうか。
私は小学生の「夢」を壊したいと思いませんが、「学者・博士」の実態が、どれだけ世間で理解されているのか、とても気になっています。おそらく、ほとんど理解されてないのでしょう。
第1に、博士号を取得しても、大学で学問を生業にできる研究者は、ごく一部です。ある教育社会学者によれば、大学教員のポストは、今や博士14人に1人です。とても狭き門をくぐらないと、大学教授にはなれません。一生涯「フリーター」の博士は珍しくないといったら、多くの人達は驚くでしょう。しかし、これが実態なのです。
第2に、大学教員の最高位である教授は、世の中の多くの人がイメージするほど、給与が高くありません。大学教授(60歳)の平均年収は、大手企業の課長クラスと指摘されています。しかも、大学教員の就職は、一般企業や公務員より、はるかに遅い。博士号を取得するまでに時間がかかり、さらに、専任教員や研究員のポストを得るための「就活期間」も決して短くありません。30歳代半ばから40歳前後といったところでしょう。20歳代で正職がみつかる学者は、そうとうな幸運に恵まれいます。したがって、生涯賃金は、大手企業のビジネスパーソンに比べると、さらに下がります。さらに、多くの「学者」は、大学院時代に受けていた奨学金を返済しなければなりません。
運良く大学教員のポストを得たとしても、その仕事の実際はどうでしょうか。興味のある人は、櫻田大造『大学教員採用・人事のカラクリ』中公新書、2011年を読んで下さい。
キャリア教育は、今では子どもの時からから行われています。果たして、「職業としての学問」は、どのくらい小学生に教えられているのでしょうか。