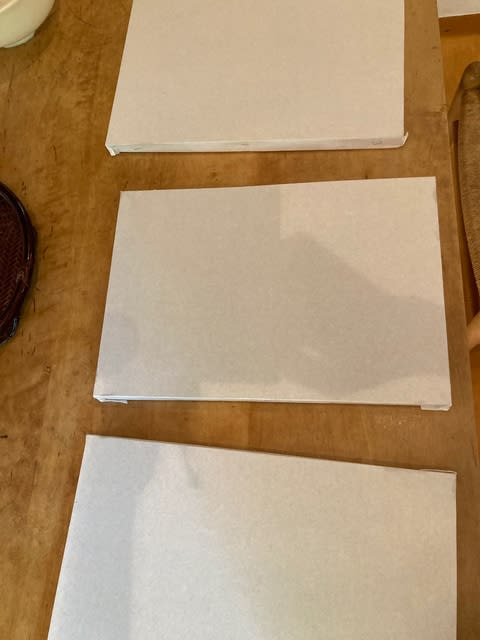実家への食事作りもリズムが出てきた、食材も結構無駄なく繰りまわしができるようになってきた。
母もデイサービスのおかげで他の人とおしゃべりしたり、規則正しい生活が少し戻り、ちゃんと靴も暑くなってきたらサンダルとか履いてTPOで選べるのは凄いなと思う。
晩御飯を作っておいておくと「あんたも忙しいのに。いいよ。」と何度も言うが、「仕事を完全に辞めたら時間は一杯あるから。」と言ってもピンとこないみたい。
それでもかなり食欲も戻ってきて、冷蔵庫の物がコンスタントに無くなっていく。野菜は減り方が少ないけれど。
私もボチボチお絵描き再開。

ガラっと色見が明るい植物を。
午前中少しずつ描いている。
描いてもなかなか上達しないし、決して上手くない。集中力も続かない。
でも時間があると紙に向かうのは岩絵の具の色の美しさに惹かれるからだろうとこの前気がついた。
仕事をしている時に「あー毎日美しい物だけを観ていたい。」と思ったことがある。
何とも言えない岩絵の具の美しさに出会えたことは幸福だった。
昨日の晩御飯は鶏手羽の甘酢炊き、サラダの残り、玉ねぎ中華スープ、長浜で買って来た赤こんにゃく、蓮根、ごぼう、にんじんの煮物。

母もデイサービスのおかげで他の人とおしゃべりしたり、規則正しい生活が少し戻り、ちゃんと靴も暑くなってきたらサンダルとか履いてTPOで選べるのは凄いなと思う。
晩御飯を作っておいておくと「あんたも忙しいのに。いいよ。」と何度も言うが、「仕事を完全に辞めたら時間は一杯あるから。」と言ってもピンとこないみたい。
それでもかなり食欲も戻ってきて、冷蔵庫の物がコンスタントに無くなっていく。野菜は減り方が少ないけれど。
私もボチボチお絵描き再開。

ガラっと色見が明るい植物を。
午前中少しずつ描いている。
描いてもなかなか上達しないし、決して上手くない。集中力も続かない。
でも時間があると紙に向かうのは岩絵の具の色の美しさに惹かれるからだろうとこの前気がついた。
仕事をしている時に「あー毎日美しい物だけを観ていたい。」と思ったことがある。
何とも言えない岩絵の具の美しさに出会えたことは幸福だった。
昨日の晩御飯は鶏手羽の甘酢炊き、サラダの残り、玉ねぎ中華スープ、長浜で買って来た赤こんにゃく、蓮根、ごぼう、にんじんの煮物。