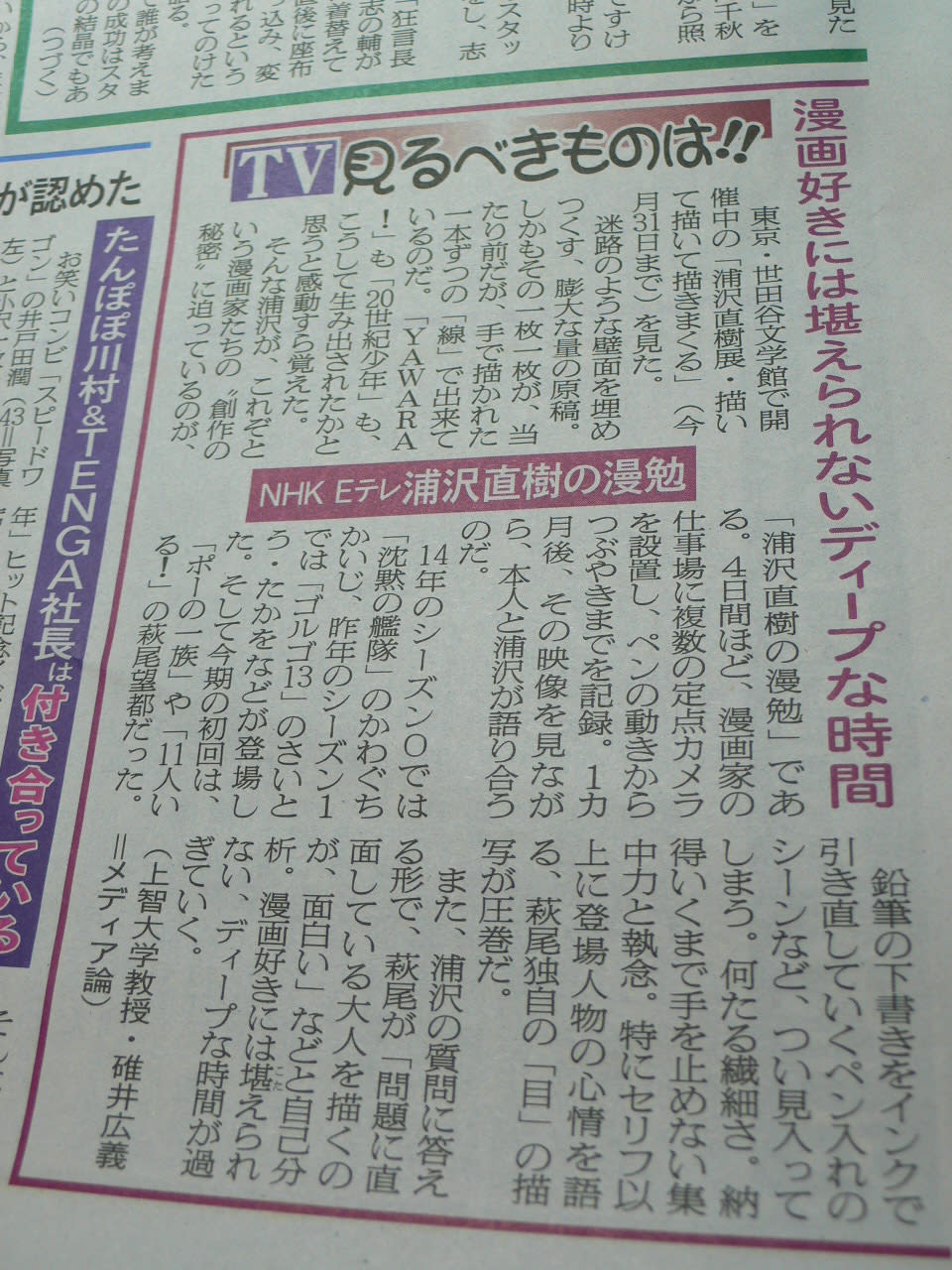2011年5月 仙台市荒浜で
11日午後2時46分、移動中のクルマを路肩に停め、1分間の黙とうをしました。
もう5年。
まだ5年。
日常の中で、私も含む個々人が、できることをする。それを続ける。
あらためて、そんなことを思いました。
合掌。
以下は、5年前に書いた文章です。
忘れないためにも、再録しておきます。
BS1の「被災者のための情報」は出色だ
「東北関東大震災」の緊急特番は、11日午後2時48分のNHKから始まった。
間もなく民放も続々と参入し、最も遅かった日本テレビでも57分には通常番組から切り替えられた。
その後、各局の大報道が続いているが、テレビ5波、ラジオ3波の全てを投入したNHKの総合力が目立つ。
中でもBS1が延々と行った「被災者のための情報」は出色だ。
ここでは岩手県、福島県など被災地にいる人たちに向けて、まさに具体的な「知りたい情報」を流し続けた。
たとえば、どこの町の何世帯が「断水」となっているか。また停電が続くとその範囲は広がる恐れがあること。そして「給水所」は何か所に設置されているか等々だ。
画面には女性アナが一人だけ。冷静な声と表情で正確な情報を伝える様子は、見ている側をも落ち着かせる効果があった。
一方の民放は「被災地以外の所にいる人たち」に向けた内容という印象が強い。
津波で家屋が押し流される衝撃映像の繰り返しと、死者や行方不明者の数など統計情報が中心で、どこか傍観者的・野次馬的・優越的な興味に迎合する報道になってはいないだろうか。
「取材団」と呼ばれる人員を現地に送るのはいい。しかし、時には現地の系列局と“競合”しているように見えるのが気になるのだ。
余震はまだ続いている。報道する側の姿勢も問われ続ける。
(日刊ゲンダイ 2011.03.14)
現地に立って知ったこと
震災報道に関する取材で仙台市荒浜地区に行ってきた。道路はつながったものの、今もほとんど手つかずの被災地だ。あえて高校生の息子も同行させた。
仙台駅から乗ったタクシーの運転手さんに言われた。「親子で来てくれたんだ。嬉しいねえ」。そして、「ボランティアとかじゃなくてもいいから、みんなに見てもらいたいよ」。
海岸方面へ向かう途中まではごく普通の町並みが続く。それがあるラインから一変するのだ。
住宅が立ち並んでいたはずの地域全体が瓦礫を残して消滅していた。それは九十年代に訪れたサラエボの、内戦で傷ついた街の風景とも異質のものだった。
どうすれば、こんなふうになるのか。見渡す限りのあらゆる建物を破壊し尽くす力とは、いったいどれほどのものなのか。
律儀ともいえる均等さで、広い範囲を一気になぎ倒していった容赦のなさに、二人とも言葉が出ない。
原形をとどめているのは小学校の建物だ。しかし、その教室の中には押しつぶされた自動車が三台も入り込んでいた。
この二ヶ月間、テレビや新聞などメディアを通じて大量の映像・画像を見てきた。
恥ずかしいことに、それで被災地の様子を知っているような、わかっているような気になっていた。
けれど、現地に立ってみると全然違っていた。何もわかってなどいなかった。それを知ったことが一番の収穫だ。
(東京新聞 2011.05.18)