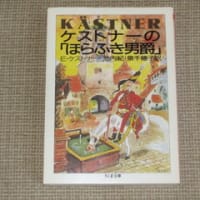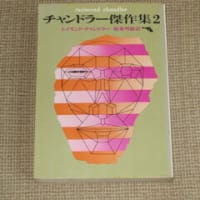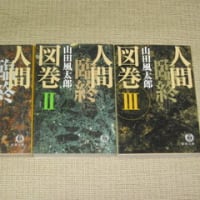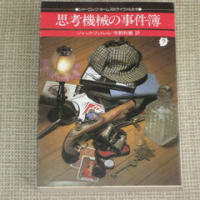高島俊男 2007年 文春文庫版
これは先月に買い求めた古本の文庫、「お言葉ですが…(8)」ということで、前に読んだ『漢字語源の筋ちがい』につづくもの、「週刊文春」の2002年から2003年が初出、単行本のときのタイトルは「百年のことば」だったそうで。
タイトルの「同期の桜」ってのは何のことかっていうと、軍歌の「貴様と俺とは同期の桜」ってのは、もとは西條八十作詞で「君と僕とは二輪の桜」だったのを、海軍兵学校で改作したもんだ、っていう話なんだけどね。
軍隊ぢゃあ、僕とか君ってのは禁止で、必ず俺、貴様と言わなきゃなんなかったそうな、そうなると二輪の桜なんて可憐ぽいのぢゃなくて同期の桜ってなったんでしょうと。そんな特段おもしろい話でもないな。
歌の話だったら、「六甲おろしに颯爽と」の颯爽ってのは、この歌ができた昭和11年ころにはやり出した言葉だったんだが、もとは1200年くらい前に唐の詩人杜甫が作ったってのが、意外でおどろかされて、いいと思った。ちなみに昭和15年時点では斎藤茂吉が、颯爽なんて言葉は陳腐だ、こんな語を使った歌は落選させるとか言ってるらしい。
ほかに、おもしろかったのは、2002年時点で「バカ」って言葉を大っぴらに使いにくく感じてきたんだけど、堂々と使っているひとがいるって、生物学者の池田清彦氏の文章を紹介しているところ。
山梨大学教授なんだけど、自分のとこの学生をバカだバカだと言ってるとして、
>日本の大学生の大半は知への憧れも畏れも皆無である。さらに言うならば、自分がものを知らないことを恥じる気配がまるでない。しかし、エゴだけは肥大しているから、意見は一応エラそうに言う。こういう人たちを指して、バカというコトバ以外に言うべきコトバをさしあたって私は知らない。はっきり言って、現在の日本の大学生の八割は、大学に来てはいけなかった人たちなのである。(p.27)
なんてとこを引用してる。さらに、
>この数年、学生たちのバカ化はさらに進んだように思われる。インターネットとケータイの普及に原因の一端はありそうだ。(p.28)
っていう意見を紹介して、そのことを小谷野敦氏というひとが、
>現在の「大衆社会」が、それまでのものと異なるのは、以前は「バカが大学へ入っている」程度で済んでいたものが、「バカが意見を言うようになった」点である。(p.29)
と表現しているって注をつけて、「バカが意見を言う」ってのはすごいなと感銘して、自身はネットわかんないけど新聞読んでもそう思うことあるなんて言っている。
2002年時点で、いわゆる不適切とおもわれる表現についてどんな社会状況だったか私は憶えちゃいないけど、加藤秀俊氏の著書のなかから、「浮浪者」って言葉を使うなって話から、
>広大なことばの大地を自由に行動することをゆるされていたわれわれは、いまでは地雷原のなかを細心の注意であゆむ兵士のごとき存在になってしまった。(略)
>あることばが不愉快だ、とある団体なり個人なりが判定することによって、そのことばが禁句になるのも雑菌排除のごときものなのだろう。そのことによって社会は清潔になる、という信仰のようなものさえ、そこには感じられる。(p.53)
みたいなことを引用している。社会的清潔趣味ってのは、なんだかいやだねえってことだ。
似たようなもんで、新聞に岸田秀氏が、現代日本の教育の崩壊を招いている固定観念の一つとして、「みんな潜在的には平等な能力を持っているという観念」をあげているのに賛成して、
>これは、おなじ年齢の子をあつめて正しい教えかたで野球を教えたらみんなじょうずになる、ということである。そんなことのあるはずがないのは、野球だけでなく、碁将棋でもピアノでも細工でも何でもわかりきったことなのだが、学校の勉強にかぎって、「だれも土台はおなじ、あとは先生の教えかたと当人の努力」ということになっていて、迷惑するのはもともと学校の勉強に適性のない子である。ところがそれを言うとたちまち「人権」だとか「差別」だとかいうコワイ弾劾がふりかかってきて、その背後には「民主主義」という不可侵の正義がそびえている。岸田先生はおっしゃっていないが、根本の問題は民主主義なのである。(p.196-197)
って社会に文句を言ってるとこがあったりする。こりゃあ、もう言葉の問題ぢゃあないね。
あと、どうでもいいけど、桜田門外の変の例をあげて改元について解説してる段があったとこに、興味をもった。
桜田門外の変は、安政七年三月三日なんだけど、三月十八日に改元があって年号が万延となった、それで大概の辞書とかには桜田門外の変は万延元年三月三日って書いてあるというんだけど。
>このことについて、岡田芳朗・阿久根末忠『現代こよみ読み解き事典』(柏書房)の「改元の儀式」の項にこうある。
>〈改元は普通「某々年をもって某(新年号)元年とする」というように改元の詔に記載される。したがって、新年号宣布以前に遡って新年号が適用されるのである。たとえば慶応四年という年はなく、この年はすべて明治元年と称すべきである。しかし、この考え方には異論があって、日本では古くは、やはり改元の日からが新年号であるというのである。〉
>右の文、「しかし」までのところはきわめて明快である。「遡って適用」だから、安政七年は改元の詔によって取消しになり、年初から万延元年ということになる。(略)
>ところが「しかし」のところで急に風向きが変って、とどのつまりは「どっちもありよ」みたいなことになっている。(p.36-37)
ということなんだが、私は「昭和六十四年・平成元年」って併記した書類をたくさん見た経験から、1月7日まで昭和で8日から平成ってのが正しいと思ってたんだけど、年初に遡るとは知らなかった。
どうしてこの話が引っ掛かったかっていうと、以前先祖の戸籍を調べたときに、万延元年一月生まれって表記があって、万延って三月からぢゃないのって疑問もったことがあったからっていう、きわめて個人的な経緯から。
本書のコンテンツは以下のとおり。
われら神州清潔の民
ピン助とキシャゴ
大統領夫人の靴とわが本と
バカが増殖しつつある?
瞼の母
桜田門外雪の朝
ムトウハップは生きていた
われら神州清潔の民
百年のことば
百年のことば
ワンワンキャンキャン
愁ひつゝ岡にのぼれば花いばら
アリャーターンシタア
大学の略称むかしと今
きら星のような御経歴
女碁打ちと探偵作家
「おはようございます」と「こんにちは」
証拠インメツ
正露丸式
稲垣先生の合併字のあつかい
文徴明か文征明か
あとみよそわか
劉宗周の絶食
天下分け目のホウチン合戦
証拠インメツ
関西はどこまでや
中山道笠取峠
本島の大火
僭称――パクリ地名
関西はどこまでや
土佐日記なはのとまり
森の都江戸
尻のつむじ……?
定刻ホテルの一夜
川上さんの引退の弁
名監督たち
六甲おろしに颯爽と
帝国ホテルの一夜
六目勝ってもまだ負けだ
ははァの三年忌
妖しい若武者
活字と整版
覆刻はかぶせぼり
ムマヤシテチウ???
からたちの花が咲いたよ
赤い靴はいてた女の子
妖しい若武者
少年の理想主義
同期の桜
同期の桜
嗚呼玉杯に花うけて
「玉杯」補遺
春のうららの隅田川
左のポッケにゃチュウインガム
「あなた」と「わたし」
キューキュータルブーブー
黄なる帽子は師団兵

これは先月に買い求めた古本の文庫、「お言葉ですが…(8)」ということで、前に読んだ『漢字語源の筋ちがい』につづくもの、「週刊文春」の2002年から2003年が初出、単行本のときのタイトルは「百年のことば」だったそうで。
タイトルの「同期の桜」ってのは何のことかっていうと、軍歌の「貴様と俺とは同期の桜」ってのは、もとは西條八十作詞で「君と僕とは二輪の桜」だったのを、海軍兵学校で改作したもんだ、っていう話なんだけどね。
軍隊ぢゃあ、僕とか君ってのは禁止で、必ず俺、貴様と言わなきゃなんなかったそうな、そうなると二輪の桜なんて可憐ぽいのぢゃなくて同期の桜ってなったんでしょうと。そんな特段おもしろい話でもないな。
歌の話だったら、「六甲おろしに颯爽と」の颯爽ってのは、この歌ができた昭和11年ころにはやり出した言葉だったんだが、もとは1200年くらい前に唐の詩人杜甫が作ったってのが、意外でおどろかされて、いいと思った。ちなみに昭和15年時点では斎藤茂吉が、颯爽なんて言葉は陳腐だ、こんな語を使った歌は落選させるとか言ってるらしい。
ほかに、おもしろかったのは、2002年時点で「バカ」って言葉を大っぴらに使いにくく感じてきたんだけど、堂々と使っているひとがいるって、生物学者の池田清彦氏の文章を紹介しているところ。
山梨大学教授なんだけど、自分のとこの学生をバカだバカだと言ってるとして、
>日本の大学生の大半は知への憧れも畏れも皆無である。さらに言うならば、自分がものを知らないことを恥じる気配がまるでない。しかし、エゴだけは肥大しているから、意見は一応エラそうに言う。こういう人たちを指して、バカというコトバ以外に言うべきコトバをさしあたって私は知らない。はっきり言って、現在の日本の大学生の八割は、大学に来てはいけなかった人たちなのである。(p.27)
なんてとこを引用してる。さらに、
>この数年、学生たちのバカ化はさらに進んだように思われる。インターネットとケータイの普及に原因の一端はありそうだ。(p.28)
っていう意見を紹介して、そのことを小谷野敦氏というひとが、
>現在の「大衆社会」が、それまでのものと異なるのは、以前は「バカが大学へ入っている」程度で済んでいたものが、「バカが意見を言うようになった」点である。(p.29)
と表現しているって注をつけて、「バカが意見を言う」ってのはすごいなと感銘して、自身はネットわかんないけど新聞読んでもそう思うことあるなんて言っている。
2002年時点で、いわゆる不適切とおもわれる表現についてどんな社会状況だったか私は憶えちゃいないけど、加藤秀俊氏の著書のなかから、「浮浪者」って言葉を使うなって話から、
>広大なことばの大地を自由に行動することをゆるされていたわれわれは、いまでは地雷原のなかを細心の注意であゆむ兵士のごとき存在になってしまった。(略)
>あることばが不愉快だ、とある団体なり個人なりが判定することによって、そのことばが禁句になるのも雑菌排除のごときものなのだろう。そのことによって社会は清潔になる、という信仰のようなものさえ、そこには感じられる。(p.53)
みたいなことを引用している。社会的清潔趣味ってのは、なんだかいやだねえってことだ。
似たようなもんで、新聞に岸田秀氏が、現代日本の教育の崩壊を招いている固定観念の一つとして、「みんな潜在的には平等な能力を持っているという観念」をあげているのに賛成して、
>これは、おなじ年齢の子をあつめて正しい教えかたで野球を教えたらみんなじょうずになる、ということである。そんなことのあるはずがないのは、野球だけでなく、碁将棋でもピアノでも細工でも何でもわかりきったことなのだが、学校の勉強にかぎって、「だれも土台はおなじ、あとは先生の教えかたと当人の努力」ということになっていて、迷惑するのはもともと学校の勉強に適性のない子である。ところがそれを言うとたちまち「人権」だとか「差別」だとかいうコワイ弾劾がふりかかってきて、その背後には「民主主義」という不可侵の正義がそびえている。岸田先生はおっしゃっていないが、根本の問題は民主主義なのである。(p.196-197)
って社会に文句を言ってるとこがあったりする。こりゃあ、もう言葉の問題ぢゃあないね。
あと、どうでもいいけど、桜田門外の変の例をあげて改元について解説してる段があったとこに、興味をもった。
桜田門外の変は、安政七年三月三日なんだけど、三月十八日に改元があって年号が万延となった、それで大概の辞書とかには桜田門外の変は万延元年三月三日って書いてあるというんだけど。
>このことについて、岡田芳朗・阿久根末忠『現代こよみ読み解き事典』(柏書房)の「改元の儀式」の項にこうある。
>〈改元は普通「某々年をもって某(新年号)元年とする」というように改元の詔に記載される。したがって、新年号宣布以前に遡って新年号が適用されるのである。たとえば慶応四年という年はなく、この年はすべて明治元年と称すべきである。しかし、この考え方には異論があって、日本では古くは、やはり改元の日からが新年号であるというのである。〉
>右の文、「しかし」までのところはきわめて明快である。「遡って適用」だから、安政七年は改元の詔によって取消しになり、年初から万延元年ということになる。(略)
>ところが「しかし」のところで急に風向きが変って、とどのつまりは「どっちもありよ」みたいなことになっている。(p.36-37)
ということなんだが、私は「昭和六十四年・平成元年」って併記した書類をたくさん見た経験から、1月7日まで昭和で8日から平成ってのが正しいと思ってたんだけど、年初に遡るとは知らなかった。
どうしてこの話が引っ掛かったかっていうと、以前先祖の戸籍を調べたときに、万延元年一月生まれって表記があって、万延って三月からぢゃないのって疑問もったことがあったからっていう、きわめて個人的な経緯から。
本書のコンテンツは以下のとおり。
われら神州清潔の民
ピン助とキシャゴ
大統領夫人の靴とわが本と
バカが増殖しつつある?
瞼の母
桜田門外雪の朝
ムトウハップは生きていた
われら神州清潔の民
百年のことば
百年のことば
ワンワンキャンキャン
愁ひつゝ岡にのぼれば花いばら
アリャーターンシタア
大学の略称むかしと今
きら星のような御経歴
女碁打ちと探偵作家
「おはようございます」と「こんにちは」
証拠インメツ
正露丸式
稲垣先生の合併字のあつかい
文徴明か文征明か
あとみよそわか
劉宗周の絶食
天下分け目のホウチン合戦
証拠インメツ
関西はどこまでや
中山道笠取峠
本島の大火
僭称――パクリ地名
関西はどこまでや
土佐日記なはのとまり
森の都江戸
尻のつむじ……?
定刻ホテルの一夜
川上さんの引退の弁
名監督たち
六甲おろしに颯爽と
帝国ホテルの一夜
六目勝ってもまだ負けだ
ははァの三年忌
妖しい若武者
活字と整版
覆刻はかぶせぼり
ムマヤシテチウ???
からたちの花が咲いたよ
赤い靴はいてた女の子
妖しい若武者
少年の理想主義
同期の桜
同期の桜
嗚呼玉杯に花うけて
「玉杯」補遺
春のうららの隅田川
左のポッケにゃチュウインガム
「あなた」と「わたし」
キューキュータルブーブー
黄なる帽子は師団兵