『くちびるに歌を』(2014)
監督:三木孝浩
新垣結衣
木村文乃
桐谷健太
恒松祐里
井川比佐志
【作品概要】
シンガー・ソングライター、アンジェラ・アキの名曲「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」を題材にしたテレビドキュメントから着想を得た中田永一の小説を実写化。輝かしい才能を持つピアニストだった臨時教員の女性が、生まれ故郷の中学校の合唱部顧問として生徒たちと心を通わせていく。オールロケを敢行した長崎の風景も見もの。(Yahoo!映画より)

【感想レビュー】
WOWOW放送の録画を何となく観ていたのですが、、少しずつ引き込まれていきました
なんといってもまず、舞台が長崎の離島というところが良かったです。土地柄、教会があって、生活に根付いた宗教があるわけで。聖歌隊が歌う賛美歌の響きはきっと、地元の人々の耳に、心に、全身に、自然に溶け込んでいるであろうその土壌が、説得力をもって物語に奥行きを感じさせてくれます。
そういう意味で、どこが舞台なのかはとても重要なのだなぁと改めて思いました 。そういえば、『ペコロスの母に会いに行く』も長崎が舞台でしたけど、その歴史的背景がとても生かされていて胸を打ちました
。そういえば、『ペコロスの母に会いに行く』も長崎が舞台でしたけど、その歴史的背景がとても生かされていて胸を打ちました
話しは戻って、『くちびるに歌を』ですが。
島という閉鎖的な社会の描写がとても繊細に、決して説明過多になることなく、断片的であるにも関わらず(‼)伝わってきて本当に素晴らしかったです
新垣結衣さん演じる先生のバックボーンは…正直ちょっと物足りなさを感じたけれど… 、そこはメインではないのでこんなものかなぁとも思います
、そこはメインではないのでこんなものかなぁとも思います
でも、歌うことで救われていく魂があるというのは実感をもって理解できます。
私も学生に合唱指導した経験や委託伴奏員で県大会の高校生合唱の伴奏をしたことがあります。
指導する方も受ける方も、それぞれの時間が流れていて、それぞれの気持ちがもちろんあるわけで。。でも、その瞬間瞬間に、一つのハーモニーを創りあげていくこと、それだけに専念する時間。合唱。音楽で繋がっているという実感。響き。エネルギー。
それを一緒に味わった仲間は、やはり特別なのだと思います。そういったことが、押し付けがましくなくほのかに香る映画でした
海に囲まれた島でのあれこれや歌の特訓。木下惠介監督の『二十四の瞳』を思い出しました。
閉鎖的な島の空気とそれを打ち破る真っ直ぐな歌声。希望。
心が洗われる映画でした

監督:三木孝浩
新垣結衣
木村文乃
桐谷健太
恒松祐里
井川比佐志
【作品概要】
シンガー・ソングライター、アンジェラ・アキの名曲「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」を題材にしたテレビドキュメントから着想を得た中田永一の小説を実写化。輝かしい才能を持つピアニストだった臨時教員の女性が、生まれ故郷の中学校の合唱部顧問として生徒たちと心を通わせていく。オールロケを敢行した長崎の風景も見もの。(Yahoo!映画より)

【感想レビュー】
WOWOW放送の録画を何となく観ていたのですが、、少しずつ引き込まれていきました

なんといってもまず、舞台が長崎の離島というところが良かったです。土地柄、教会があって、生活に根付いた宗教があるわけで。聖歌隊が歌う賛美歌の響きはきっと、地元の人々の耳に、心に、全身に、自然に溶け込んでいるであろうその土壌が、説得力をもって物語に奥行きを感じさせてくれます。
そういう意味で、どこが舞台なのかはとても重要なのだなぁと改めて思いました
 。そういえば、『ペコロスの母に会いに行く』も長崎が舞台でしたけど、その歴史的背景がとても生かされていて胸を打ちました
。そういえば、『ペコロスの母に会いに行く』も長崎が舞台でしたけど、その歴史的背景がとても生かされていて胸を打ちました
話しは戻って、『くちびるに歌を』ですが。
島という閉鎖的な社会の描写がとても繊細に、決して説明過多になることなく、断片的であるにも関わらず(‼)伝わってきて本当に素晴らしかったです

新垣結衣さん演じる先生のバックボーンは…正直ちょっと物足りなさを感じたけれど…
 、そこはメインではないのでこんなものかなぁとも思います
、そこはメインではないのでこんなものかなぁとも思います
でも、歌うことで救われていく魂があるというのは実感をもって理解できます。
私も学生に合唱指導した経験や委託伴奏員で県大会の高校生合唱の伴奏をしたことがあります。
指導する方も受ける方も、それぞれの時間が流れていて、それぞれの気持ちがもちろんあるわけで。。でも、その瞬間瞬間に、一つのハーモニーを創りあげていくこと、それだけに専念する時間。合唱。音楽で繋がっているという実感。響き。エネルギー。
それを一緒に味わった仲間は、やはり特別なのだと思います。そういったことが、押し付けがましくなくほのかに香る映画でした

海に囲まれた島でのあれこれや歌の特訓。木下惠介監督の『二十四の瞳』を思い出しました。
閉鎖的な島の空気とそれを打ち破る真っ直ぐな歌声。希望。
心が洗われる映画でした














 なんて幸運なんだ…‼
なんて幸運なんだ…‼

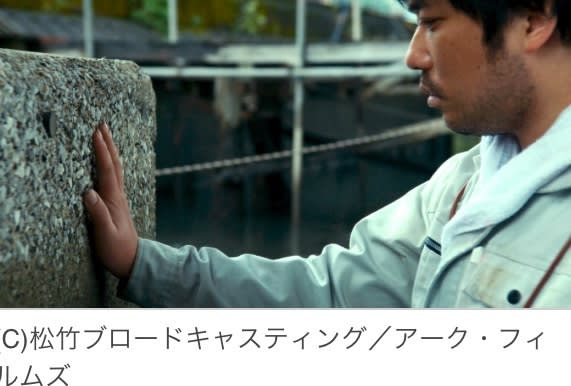
 )
)





