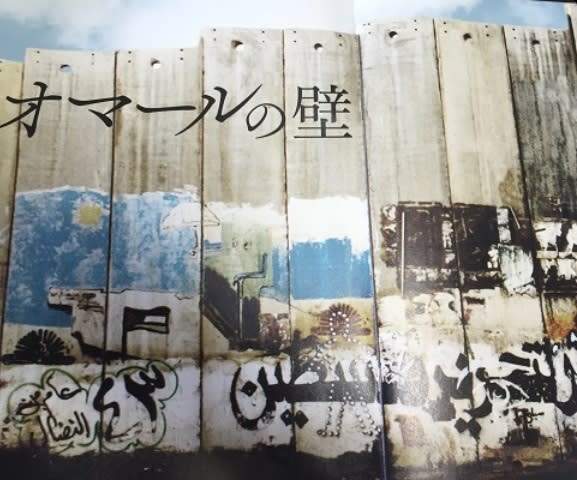『叫』(2006)
監督/脚本:黒沢清
音楽:配島邦明
出演者:役所広司、小西真奈美、葉月里緒奈
【作品概要】
『LOFT ロフト』などの黒沢清監督と『呪怨』シリーズの一瀬隆重プロデューサーが初めて手を組んだ本格派ミステリー。ある連続殺人をきっかけに、過去と現在が入り乱れる迷宮に足を踏み入れる刑事の苦悶をあぶり出す。(Yahoo!映画より)

【感想レビュー】
『叫』。未見だと思ってまた借りましたが観ていました
タイトルと内容が一致していないということをよくやってしまいます… 。それで、メモ代りにもなるしと映画ブログを始めたのもあるのですが
。それで、メモ代りにもなるしと映画ブログを始めたのもあるのですが
そして再び観てみると、これがもう!!…怖いっ
タイトルと一致はしていなくても、ずっっと脳裏に赤いワンピースがこびり付いていて、あの映画のタイトルなんだっけなぁ…と思っていたのでした
そして。この頃、奥貫薫さんはいつも幸薄い役どころだなぁ…などと思って、赤いワンピース=奥貫薫さんをなぜかセットで記憶していたにも関わらず、映画自体が怖くて思い出さないようにしていたのだった…ということも思い出しました
10年前の作品ですし、画像は荒いんです。全体的にグレーっぽい映像に虚ろに映える赤いワンピース…!
『シンドラーのリスト』を彷彿させます。療養所の写真の目を見開いた写真とかも、『夜と霧』が思い出されて細部まで不吉な感じで…。
黒沢清監督作品の『回路』は、昨年、特集上映で観たのですが、異界の住人がスクリーンから飛び出てくるんじゃないか!?という迫力で、黒沢監督ってこういう感じもあるのね…!ぶるぶる… と思っていたのでした。
と思っていたのでした。
それが『叫』にもそういう怖さがあります。異界の人の“叫”び!もう、耳につくいや〜な周波数の“叫”びです…。
自分を忘れた者を許さないと言う霊も怖いが、自分のことは忘れてくださいと言いながら現世に留まる霊も怖い…。
これは、成仏とかの問題ではなくて、恋愛とかでも同じことが言えそう…
執着。これ、怖いですよね…。
そして、場所も怖い…!
東京湾岸の埋立て地が舞台で、本当に忘れさられていたっぽい建物とか…、ちょっとぬかるんでいて、だだっ広い場所とか…、その虚ろさがもう怖いんです‼
そして風は不気味にバタバタと吹くし…。
役所広司さん演じる主人公の行動もいちいち不可思議だし…。
いまいち登場人物達の誰にも共感できない感じだし…。
そういう宙ぶらりんな感じと、場所の虚ろさが見事にマッチしています…
なにもかもが奇妙にズレていくことで生じる不安定さが、底知れない怖さを生んでいると思います。
ちょっと笑えるところもありつつの…でも、やっぱり怖い‼…な作品
監督/脚本:黒沢清
音楽:配島邦明
出演者:役所広司、小西真奈美、葉月里緒奈
【作品概要】
『LOFT ロフト』などの黒沢清監督と『呪怨』シリーズの一瀬隆重プロデューサーが初めて手を組んだ本格派ミステリー。ある連続殺人をきっかけに、過去と現在が入り乱れる迷宮に足を踏み入れる刑事の苦悶をあぶり出す。(Yahoo!映画より)

【感想レビュー】
『叫』。未見だと思ってまた借りましたが観ていました

タイトルと内容が一致していないということをよくやってしまいます…
 。それで、メモ代りにもなるしと映画ブログを始めたのもあるのですが
。それで、メモ代りにもなるしと映画ブログを始めたのもあるのですが
そして再び観てみると、これがもう!!…怖いっ

タイトルと一致はしていなくても、ずっっと脳裏に赤いワンピースがこびり付いていて、あの映画のタイトルなんだっけなぁ…と思っていたのでした

そして。この頃、奥貫薫さんはいつも幸薄い役どころだなぁ…などと思って、赤いワンピース=奥貫薫さんをなぜかセットで記憶していたにも関わらず、映画自体が怖くて思い出さないようにしていたのだった…ということも思い出しました

10年前の作品ですし、画像は荒いんです。全体的にグレーっぽい映像に虚ろに映える赤いワンピース…!

『シンドラーのリスト』を彷彿させます。療養所の写真の目を見開いた写真とかも、『夜と霧』が思い出されて細部まで不吉な感じで…。
黒沢清監督作品の『回路』は、昨年、特集上映で観たのですが、異界の住人がスクリーンから飛び出てくるんじゃないか!?という迫力で、黒沢監督ってこういう感じもあるのね…!ぶるぶる…
 と思っていたのでした。
と思っていたのでした。それが『叫』にもそういう怖さがあります。異界の人の“叫”び!もう、耳につくいや〜な周波数の“叫”びです…。
自分を忘れた者を許さないと言う霊も怖いが、自分のことは忘れてくださいと言いながら現世に留まる霊も怖い…。
これは、成仏とかの問題ではなくて、恋愛とかでも同じことが言えそう…

執着。これ、怖いですよね…。
そして、場所も怖い…!
東京湾岸の埋立て地が舞台で、本当に忘れさられていたっぽい建物とか…、ちょっとぬかるんでいて、だだっ広い場所とか…、その虚ろさがもう怖いんです‼
そして風は不気味にバタバタと吹くし…。
役所広司さん演じる主人公の行動もいちいち不可思議だし…。
いまいち登場人物達の誰にも共感できない感じだし…。
そういう宙ぶらりんな感じと、場所の虚ろさが見事にマッチしています…

なにもかもが奇妙にズレていくことで生じる不安定さが、底知れない怖さを生んでいると思います。
ちょっと笑えるところもありつつの…でも、やっぱり怖い‼…な作品